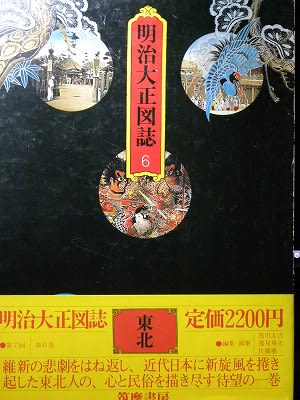ダニエル・コーエンさんは、フランスの経済学者。
高等師範学校教授という職業を持っている。
日本にもかつて師範学校があった。
すべて大学になった。
フランスでは高等師範は大学ではないのだろうか。
それはともかく、ダニエル・コーエンさんの考えはとても興味深い。
納得できることも多い。
朝日新聞1月15日のインタビュー記事を読みました。
「欧州は90年代の日本のような『失われた10年』に向かって出 . . . 本文を読む
京都高島屋で開催されていました。
1月23日まで開かれています。
犬塚勉さんは、1949年生まれですが1988年に谷川岳で遭難しています。
パンフには、「多摩に住み美術教師をしながら、多摩の山の風景を描き続け、早世したした画家、犬塚勉。没後20年の2009年にNHKの「日曜美術館」で紹介されると多くの感動の声が寄せられて注目を集めました」
「山に登り自然と一体となって描いた作品は、スーパー . . . 本文を読む
神戸新聞の「復興あしたへ 遺族が語る」を読んでいました。
当時を思い出します。
震災当日、京都の自宅から大阪の職場へやっとの思いでたどり着きました。
幸い大阪市では電力も電話も通じていました。
机の電話が鳴りました。
香港に出張している仲間からの電話でした。
香港のテレビで火に襲われる神戸が放送され続けているとのこと。
日本は壊滅したのではないかと、まさか繋がるとは思わず職場に電話をしてきたそ . . . 本文を読む
寒椿に菰を被せていますね。
長谷寺は20年ぶりですね。本堂も国宝指定になりました。三丈三尺(10m)の観音さんも光輝いていました。源氏物語の時代から初瀬詣は有名ですが、やはり一見に値する文化遺産ですね。
. . . 本文を読む
山の会の新年初登山です。
辰年に因んで竜のつく山に登りました。
竜がつく山はとても多く選ぶに困るほどです。
ご存知のように竜は雨を呼ぶ神の化身と信じられていたので、稲穂の国には至るところに竜の名がつけられている山があります。
12月には攝津の国にある竜王山。
今回は大和の国の竜王山です。
JR桜井線柳本駅から山之辺の道を竜王山へ向かう。
この辺りに巻向遺跡があります。
卑弥呼の宮殿跡 . . . 本文を読む
学費に関しては、保護者や受験生の立場に置かれないとあまり考えないものかもしれない。
私も他人事のように思っている。なんとも情けない。
群馬県の私立高校の教員である頼富雅博さんは、
「なぜ学費を抑えることができないのか。私は大学側に自助努力の意識が希薄だからと考える」と訴える。
私立の年間学費は130万円は必要という。それに生活費が必要だから平均的な所得の保護者には大変な負担だ。
「牛丼値 . . . 本文を読む
1月12日朝日新聞インタビュー記事「原発と司法」から。
記者がインタビューをしているのは海渡雄一弁護士。
原子力関連訴訟12件を担当している。
恥ずかしいことながら、原発裁判についてはほとんど知らない。
まことに情けない。
記者の質問。福島の原発事故が起きた時の気持は?
海渡雄一弁護士:「無念と公開の気持ちに襲われました。もんじゅ訴訟が最高裁で勝訴できていれば、もし浜岡原発訴訟の一審で . . . 本文を読む
このブログでもこの事故の直後から定期的に記事を書いてきました。
当時、JR西日本は営業を重視し安全面を軽視していました。
これは国鉄民営化以来の経営方針です。
そのことが事故の原因の一つであることは確かです。
ATSの設置が進まなかったことの理由は、利益に貢献できないことに投資はできないからです。
業務計画書をみても安全は軽視されていました。
なお、事故名については、新聞等ではJR宝塚線脱線事故 . . . 本文を読む
今朝から被災地の映像がテレビで映されている。
雪が降る寒そうな風景である。
本当に厳しい季節だ。
10ヶ月と言えば生活保護や雇用保険も打ち切りも考えられる。
温かさのある対応を行政に望みたい。
先月、岩手県を訪問した人の話をお聞きしたが津波の被害にあった沿岸部は瓦礫が撤去されただけの状況とのこと。
再開発の方針が決まらない段階ではいたし方がないのかもしれない。
しかし離れ離れになった人々の . . . 本文を読む
正月2日より母親が体調を崩し、正月らしさのなかった実家でしたが、やっと一息というところです。
今週末には父親をショートステイに送り、母親を実家に一人残し、京都に戻ります。
相撲取りは正月場所が終わって正月が来るといいます。
私の家族もそのような気分です。
写真は最上稲荷の奥の院です。
大石に南妙法蓮華経が彫られています。
競うように建てられた石塔。私には意味が分かりませんでした . . . 本文を読む
10年ほど前に、大阪中の島で古書販売会があり、数冊求めた中の一冊です。
長く本棚に眠っていた。昭和53年発行 編集・執筆 色川大吉、逸見英夫、佐藤憲一
昨年の東日本大震災以来、私自身の東北地方についての知識の欠如にあきれていた。
そこで本棚からこの本を出してきて読みだした。
明治大正図誌ということだから、戊辰戦争の敗北から中央政府から虐げられ再起を図る東北人を、素晴らしい図と写真で紹介する。
. . . 本文を読む
川久保玲さんの発言は、朝日新聞1月7日付の記事より。
「コムデギャルソン」ブランドで世界のファッションをリードし続けている川久保玲さん。
インタビュー記事が掲載されることは珍しい。
1942年生れ。この年に生まれたデザイナーでは、朝のドラマ「カーネーション」のモデルとなった小篠綾子さんの三女、ミチコさんがいる。
お二人とも現役バリバリですね。
かつてデザイナー35歳説というのがあったが、 . . . 本文を読む
本日のオバマ大統領の発言は世界の安全保障のターニングポイントかもしれない。
米国のアジアの一方からの撤退は大統領選挙のためにも必要なことであった。
そしてアジアのもう一方である東アジアは緊張が高まっている。
中国の軍事力の増強と北朝鮮の予期せぬ世代交代が主要因だ。
北朝鮮は、権力基盤が不安定だと言わざるをえない。
一人の独裁者による圧政下の安定は軸を失った。
新指導者を支える体制は軍部中心 . . . 本文を読む
「自分たちで動き、決める時が来た」には、「何十万人もの」がついているのです。
朝日新聞1月4日”新しい民主主義へ”インタビュー2012より。
アントニオ・ネグリさんは「帝国」「マルチチュ‐ド」を書いたイタリアの政治哲学者ですが、
どちらの本も読んでおりません。
欧州の危機について。
「この危機から脱したとしても、その時にはすべてが、あらゆるレベルで縮小してしまっている」
懸念すること。
. . . 本文を読む