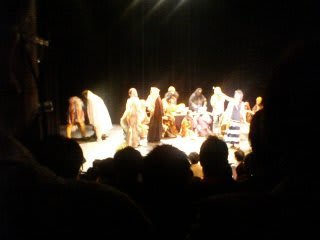いよいよ長かった連休も今日でお終いです。明日からの仕事に備えて、気を引き締めましょう。いつもの床屋さんへ行き、髪など整えて明日からは臨戦態勢です。
【床屋談義】
床屋さんでの話題はラーメン屋さんの店舗拡大についてでした。
札幌には人気のラーメン屋さんが実に多くあります。いわゆるチェーン店やフランチャイズ店であれば、どこでも大抵は同じくらいの味を出すものです。
道内であれば、そのようなお店でもかなりハイレベルの味を提供してくれますからある意味では安心できますが、一方では自分だけの贔屓(ひいき)とするのにはちょっと物足りない感じがします。
おやじさんの一代で築いた個店こそがラーメン屋探訪の醍醐味という方も多い事でしょう。
床屋さんと話をして盛り上がったのは、そんな大人気のラーメン屋が二店目、三点目と店舗を拡大するにつれて、なぜか元の味が出せない事が多いという共通の感覚でした。
「だって、あのおやじさんの息子が継いでいるんですよ。おやじさんだって気になってしょっちゅうチェックに行っているんでしょうけれど、それでも美味しくないんですよ」と床屋さん。
「そうなんです。私も何度もそういう目に遭っています。古いお店には駐車場がないので、新しくて大きくなった二号店に行ってみるのですが、そこで感じるのは『あれ?ここのラーメンってこんな感じだったかなぁ?美味しく感じないなあ』という感覚なんですよ」と私。
「以前大好きで、飲んだ後に必ず行ったラーメン屋さんがあったのですが、息子が店を変えて大きくしたんですよ。そこを久しぶりに訪ねてみたら、亡くなったのか引退したのか、おやじさんの姿がそこには無くて、お客さんが一人もいないということがありましたよ。別にお客の方で意地悪ができるわけはないでしょうし、『味が落ちた』という評判だけで客足が遠のくということはないと思うのですが、のれんの力だけではだめで、やはり味が落ちるとお客さんはいかなくなりますね。お客さんの目はそれほど厳しいし、商品を提供するという事はそれだけ厳しいということなんでしょうね」
「そうですね。現代日本人というのは、それだけ要求水準が高いということなのでしょうね。そういうハイレベルなお客さんに対して『贅沢言うなー!』と叫んでみても、客は文句も言わずただ離れて行くだけなのでしょうね」
社会で働く人たちが相手にするのは、世界でも最も目の肥えたハイレベルな目なのです。お客さんの満足を提供するということには、そういう事実から出発しなくてはならないのですね。
【コンカリーニョ再出発】
今日もまたまた琴似地区の話題ですが、今日はコンカリーニョについてです。
コンカリーニョとは、市民演劇を提供する団体として1988年に結成された「札幌ロマンチカシアター」魴鮄舎(ほうぼうしゃ)として始められた活動が発展して、1994年に琴似地区の石造り倉庫をベースにして活動を始めた演劇集団です。
その後、この石造り倉庫が琴似駅周辺の再開発事業によって撤去される事になり、活動を休止していたのですが、なんとしてもこの琴似地区へのこだわりが薄れる事は無かったのだと言います。
そこで2003年にはNPO法人として法人格を取得し、新しくできた再開発ビルの一階に演劇のためのフリースペースを取得するという行動に出て、なんと内装費約5千万円を自分たちで調達するという志を立てて、支援者を求めながら今日に至ったのでした。
今日はその新生コンカリーニョが今までの演劇活動の劇中歌を中心にしたレビューショーで、名付けて「コンカリーニョ生誕祭」の記念すべき初日でした。
会場は250名が入る椅子席でしたが、満員御礼どころか当日券を求めて来た人を階段にまでぎゅうぎゅうに押し込む盛況ぶりでした。
実はこのNPOの演劇活動をオリジナルの音楽面で支えてきたのが知人のH君であり、その表現者としての才能の一端を垣間見る事が出来ました。
会場には同じ地区に住む知人の姿もちらほらと見えて、地域が支える演劇活動という姿が良く伺えました。こういう活動を札幌の180万市民は支える事ができるのでしょうか。
週末に地域で演劇を観てから飲み屋の暖簾をくぐるという生活って素晴らしい事なのではないでしょうか。
コンカリーニョの復活をお祝いして、これからも機会を見つけて観劇に来ようと思います。こういうのが都会ならではの文化なんですねえ。
【床屋談義】
床屋さんでの話題はラーメン屋さんの店舗拡大についてでした。
札幌には人気のラーメン屋さんが実に多くあります。いわゆるチェーン店やフランチャイズ店であれば、どこでも大抵は同じくらいの味を出すものです。
道内であれば、そのようなお店でもかなりハイレベルの味を提供してくれますからある意味では安心できますが、一方では自分だけの贔屓(ひいき)とするのにはちょっと物足りない感じがします。
おやじさんの一代で築いた個店こそがラーメン屋探訪の醍醐味という方も多い事でしょう。
床屋さんと話をして盛り上がったのは、そんな大人気のラーメン屋が二店目、三点目と店舗を拡大するにつれて、なぜか元の味が出せない事が多いという共通の感覚でした。
「だって、あのおやじさんの息子が継いでいるんですよ。おやじさんだって気になってしょっちゅうチェックに行っているんでしょうけれど、それでも美味しくないんですよ」と床屋さん。
「そうなんです。私も何度もそういう目に遭っています。古いお店には駐車場がないので、新しくて大きくなった二号店に行ってみるのですが、そこで感じるのは『あれ?ここのラーメンってこんな感じだったかなぁ?美味しく感じないなあ』という感覚なんですよ」と私。
「以前大好きで、飲んだ後に必ず行ったラーメン屋さんがあったのですが、息子が店を変えて大きくしたんですよ。そこを久しぶりに訪ねてみたら、亡くなったのか引退したのか、おやじさんの姿がそこには無くて、お客さんが一人もいないということがありましたよ。別にお客の方で意地悪ができるわけはないでしょうし、『味が落ちた』という評判だけで客足が遠のくということはないと思うのですが、のれんの力だけではだめで、やはり味が落ちるとお客さんはいかなくなりますね。お客さんの目はそれほど厳しいし、商品を提供するという事はそれだけ厳しいということなんでしょうね」
「そうですね。現代日本人というのは、それだけ要求水準が高いということなのでしょうね。そういうハイレベルなお客さんに対して『贅沢言うなー!』と叫んでみても、客は文句も言わずただ離れて行くだけなのでしょうね」
社会で働く人たちが相手にするのは、世界でも最も目の肥えたハイレベルな目なのです。お客さんの満足を提供するということには、そういう事実から出発しなくてはならないのですね。
【コンカリーニョ再出発】
今日もまたまた琴似地区の話題ですが、今日はコンカリーニョについてです。
コンカリーニョとは、市民演劇を提供する団体として1988年に結成された「札幌ロマンチカシアター」魴鮄舎(ほうぼうしゃ)として始められた活動が発展して、1994年に琴似地区の石造り倉庫をベースにして活動を始めた演劇集団です。
その後、この石造り倉庫が琴似駅周辺の再開発事業によって撤去される事になり、活動を休止していたのですが、なんとしてもこの琴似地区へのこだわりが薄れる事は無かったのだと言います。
そこで2003年にはNPO法人として法人格を取得し、新しくできた再開発ビルの一階に演劇のためのフリースペースを取得するという行動に出て、なんと内装費約5千万円を自分たちで調達するという志を立てて、支援者を求めながら今日に至ったのでした。
今日はその新生コンカリーニョが今までの演劇活動の劇中歌を中心にしたレビューショーで、名付けて「コンカリーニョ生誕祭」の記念すべき初日でした。
会場は250名が入る椅子席でしたが、満員御礼どころか当日券を求めて来た人を階段にまでぎゅうぎゅうに押し込む盛況ぶりでした。
実はこのNPOの演劇活動をオリジナルの音楽面で支えてきたのが知人のH君であり、その表現者としての才能の一端を垣間見る事が出来ました。
会場には同じ地区に住む知人の姿もちらほらと見えて、地域が支える演劇活動という姿が良く伺えました。こういう活動を札幌の180万市民は支える事ができるのでしょうか。
週末に地域で演劇を観てから飲み屋の暖簾をくぐるという生活って素晴らしい事なのではないでしょうか。
コンカリーニョの復活をお祝いして、これからも機会を見つけて観劇に来ようと思います。こういうのが都会ならではの文化なんですねえ。