きょう、、 こんなニュース記事を読んだ。
鴎外「舞姫」モデルの晩年明らかに=ベルリン在住のライターが調査
『舞姫』のモデルとなったドイツ人女性は、 鴎外が日本に帰国した後を追って来日、、 しかし周囲の反対に遭って結局彼女は一人ドイツに戻ることになった、、 という話は知っていた。 その女性のその後の人生がわかったという記事。。 文学史的にすばらしい調査だし、 130年も経ってからわかる、、という歴史的時間があるからこそ、ロマンも感じる。
、、遠く離れ離れになった人でも、 フェイスブックなどを通じて、 どこで何をしているかわかる時代になってしまった現代となっては、、、
、、だから 私フェイスブックは使わない、、 昔の恋人のその後も しらべない、、(笑)
恋人でなくても、、 今どこで何しているのかなぁ、、とふと思う人はいるけれど。。 昔、英語を教えてもらったオーストラリア女性とか、、 一緒に飲み明かした北米男子とか、 北欧男子とか。。 でも思い出は思い出のままが良いかもと、、
***
ただ・・・
今でなくても、 いつかきっとまた会える、、 また会って話したい、、
そう思っているままで、 もう二度と顔を見ることができなくなってしまった人もいる。。 ここ数年、、 そんな悲しい経験を繰り返した。
思い出は断片的でも、、 家族や仕事の同僚みたいにずっと側にいなくても、、 ただほんの一時期を過ごした間柄でも、、 そして、 ある日を境に宙ぶらりんで終わってしまった思い出だとしても、
それらの思い出は全部、 その人と自分の間にだけ築かれた 人生の貴重な一部分だし、 その断片のパッチワークこそが、 人生そのものなんだと思える。
この小説を読みながら、 ずっとそういうことを考えていた。
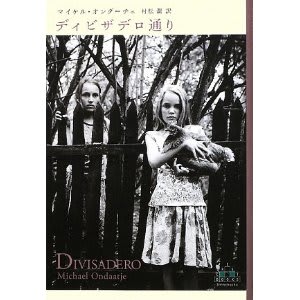
『ディビザデロ通り』 マイケル オンダーチェ著・村松潔 翻訳 (新潮クレスト・ブックス)
アンナとクレアと、 クープ。 互いに血のつながらない姉妹と兄のような、、 家族でもあり、幼馴染みでもあるような、、 そんな関係で生まれ育ち、 十代を共に成長していった3人が、 ある出来事を境に 互いの人生が離れてしまう。
『イギリス人の患者』のマイケル・オンダーチェの作品だけに、、 詩人の言葉で語られる物語は、 時間も 場所も 大きく飛んで語られるから、 読む者は、 写真の断片と向き合うような、 病人がたどたどしく語る記憶をつなぎ合わせるような、、 そんなもどかしい焦りを与えられる。
しかも、、 いつかはきっと、 ばらばらの3人の人生がどこかでまた交差したり、 それぞれに納得のいく結末を迎えるだろうと、 期待しながら読まざるを得ないので・・・
だけど、、 初めに書いたように、、 宙ぶらりんのように見える断片のパッチワークこそが、 人生を構成するかけがえのないパーツ。 それこそが「私」というもの。。。 実人生の中のやるせない悲しみと共鳴する部分が、 この本にはたくさんたくさんあるから、 だから一見 破たんしているような物語なのに、 ものすごく愛おしく感じられる。
物語の後半は、 ある作家に関わる三世代もの記憶に話が発展しているけれど、、 どの物語も魅力的だし、 どの人物も、 謎でありながら、 魅了される。。 もっと話したかった、、 もっともっと 会いたかった、、 きっとそんな気持ちにさせられる登場人物たち。
、、とはいえ、、 孤児の少年クープ。 ギャンブラーに成長したクープがとても魅力的でスリリングな展開だったので、、 あれからどうなるの? どうなるの? ・・・ 出来ることならハリウッド映画のように観客が納得する結末もあったらいいのにな、、 続編が読みたいな、、 などと オンダーチェ氏には有り得ないだろう期待も残ってしまうのでした。。
余韻、、 と呼ぶには 切なさのつのる読後感。。 でも、 きっと何年後かに読んでも名作だと思うでしょう。
そして
その頃にはまた心の中には新たな記憶の断片が増えているのでしょう。。 そのせつなさをひたすら束ねて 抱えて生きていくしかない、、 それが人生。。 そう思えるくらいには大人になった今日このごろ・・・
鴎外「舞姫」モデルの晩年明らかに=ベルリン在住のライターが調査
『舞姫』のモデルとなったドイツ人女性は、 鴎外が日本に帰国した後を追って来日、、 しかし周囲の反対に遭って結局彼女は一人ドイツに戻ることになった、、 という話は知っていた。 その女性のその後の人生がわかったという記事。。 文学史的にすばらしい調査だし、 130年も経ってからわかる、、という歴史的時間があるからこそ、ロマンも感じる。
、、遠く離れ離れになった人でも、 フェイスブックなどを通じて、 どこで何をしているかわかる時代になってしまった現代となっては、、、
、、だから 私フェイスブックは使わない、、 昔の恋人のその後も しらべない、、(笑)
恋人でなくても、、 今どこで何しているのかなぁ、、とふと思う人はいるけれど。。 昔、英語を教えてもらったオーストラリア女性とか、、 一緒に飲み明かした北米男子とか、 北欧男子とか。。 でも思い出は思い出のままが良いかもと、、
***
ただ・・・
今でなくても、 いつかきっとまた会える、、 また会って話したい、、
そう思っているままで、 もう二度と顔を見ることができなくなってしまった人もいる。。 ここ数年、、 そんな悲しい経験を繰り返した。
思い出は断片的でも、、 家族や仕事の同僚みたいにずっと側にいなくても、、 ただほんの一時期を過ごした間柄でも、、 そして、 ある日を境に宙ぶらりんで終わってしまった思い出だとしても、
それらの思い出は全部、 その人と自分の間にだけ築かれた 人生の貴重な一部分だし、 その断片のパッチワークこそが、 人生そのものなんだと思える。
この小説を読みながら、 ずっとそういうことを考えていた。
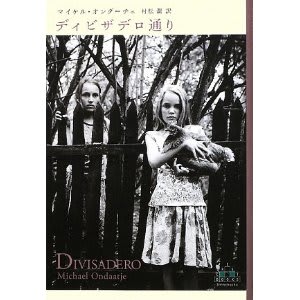
『ディビザデロ通り』 マイケル オンダーチェ著・村松潔 翻訳 (新潮クレスト・ブックス)
アンナとクレアと、 クープ。 互いに血のつながらない姉妹と兄のような、、 家族でもあり、幼馴染みでもあるような、、 そんな関係で生まれ育ち、 十代を共に成長していった3人が、 ある出来事を境に 互いの人生が離れてしまう。
『イギリス人の患者』のマイケル・オンダーチェの作品だけに、、 詩人の言葉で語られる物語は、 時間も 場所も 大きく飛んで語られるから、 読む者は、 写真の断片と向き合うような、 病人がたどたどしく語る記憶をつなぎ合わせるような、、 そんなもどかしい焦りを与えられる。
しかも、、 いつかはきっと、 ばらばらの3人の人生がどこかでまた交差したり、 それぞれに納得のいく結末を迎えるだろうと、 期待しながら読まざるを得ないので・・・
だけど、、 初めに書いたように、、 宙ぶらりんのように見える断片のパッチワークこそが、 人生を構成するかけがえのないパーツ。 それこそが「私」というもの。。。 実人生の中のやるせない悲しみと共鳴する部分が、 この本にはたくさんたくさんあるから、 だから一見 破たんしているような物語なのに、 ものすごく愛おしく感じられる。
物語の後半は、 ある作家に関わる三世代もの記憶に話が発展しているけれど、、 どの物語も魅力的だし、 どの人物も、 謎でありながら、 魅了される。。 もっと話したかった、、 もっともっと 会いたかった、、 きっとそんな気持ちにさせられる登場人物たち。
、、とはいえ、、 孤児の少年クープ。 ギャンブラーに成長したクープがとても魅力的でスリリングな展開だったので、、 あれからどうなるの? どうなるの? ・・・ 出来ることならハリウッド映画のように観客が納得する結末もあったらいいのにな、、 続編が読みたいな、、 などと オンダーチェ氏には有り得ないだろう期待も残ってしまうのでした。。
余韻、、 と呼ぶには 切なさのつのる読後感。。 でも、 きっと何年後かに読んでも名作だと思うでしょう。
そして
その頃にはまた心の中には新たな記憶の断片が増えているのでしょう。。 そのせつなさをひたすら束ねて 抱えて生きていくしかない、、 それが人生。。 そう思えるくらいには大人になった今日このごろ・・・

























