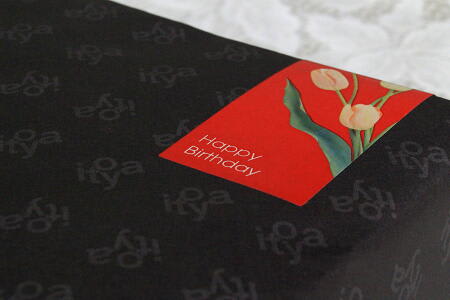長らく、桜便りをご覧いただき、ありがとうございました。
さて、2012年の桜便り、最後を飾るのは、この桜です
やはりこれを外しては、「浪速の春」は、語れないでしょう。

今日のフォト。 大阪造幣局・桜の通り抜け。
今年の桜は、「小手毬」です。
2012年4月17日(火)~23日(月)まで開催中。












今日の1曲。 「さくら」 森山良子&森山直太朗
最後の桜便りは、この曲を聴きながら、ご覧くださいませ。

春日井(かすがい)
大阪の春の風物詩、大阪造幣局の桜の通り抜けが、17日から始まりました。
初日の17日は、開門の10時には、2800人もの花見客が列をなしたそうです。

一葉(いちよう)
そして開門2時間後の正午には、2万6600人の来場者があったそうです。
期間中は、60万人~70万人の人出を見込んでいます。

紅笠(べにがさ)
昨年は東日本大震災を受け、桜の横に立てられたぼんぼりも外され
1951年から始まった夜間のライトアップが初めて中止となりましたが
今年は2年ぶりに、夜桜見物を楽しめることになりました。。

平野撫子(ひらのなでしこ)
今年は、129品種、354本の桜を楽しむことができます。

麒麟(きりん)
東京荒川堤にあった里桜で、花は、濃紅紫色で、花弁数は30~35枚ある。

高台寺(こうだいじ)
京都・高台寺の玄関口にある桜で
花は淡紅白色、花弁数は10~15枚の優雅な大輪の桜です。

祇王子祇女桜(ぎおうじぎじょざくら)
誰もが美しい桜の写真を 撮りたくなりますね。

簪桜(かんざしざくら)
女性が髪に飾るかんざしに似ていることから、この名前が付けられました。

数珠掛桜(じゅずかけざくら)
造幣局の桜の通り抜けには、特選、入選句に選ばれた
俳句・川柳が、短冊に記されて、ぶら下げてあります。

六高菊(ろっこうぎく)
旧制第六高等学校(現在の岡山大学)の校庭にあつたところから、この名が付けられた。

幸福(こうふく)
造幣局の局内には、「幸福」という桜が、2本あります。
花は、淡紅色で、花弁数は15~20枚あります。

松月(しょうげつ)
最初、花は淡紅色で、次第に白色に変化してくる。
花弁数は25枚ほどで、葉化雌しべがあります。

世のカメラ女子さん、絶対に真似しないでください。(笑)

大提灯(おおぢょうちん)
大輪の花が提灯のようにぶら下がって咲き、花は淡紅色です。

雨宿(あまやどり)
東京荒川堤にあった桜で、葉かげに垂れて咲く形が
あたかも葉かげに、雨をよけているように見えるので、この名前が付けられました。

めがね橋
明治4年(1871年)に完成したこの橋は、中央部分に
膨らみがあったことからこの名前がつけられ
昭和32年(1957年)に、現在の赤い橋に改装されました。

雨情枝垂(うじょうしだれ)
詩人の野口雨情氏邸内にあったことから、この名前が付けられました。
お嬢さん、倒れそうなほど、傾いて写真撮っています。(笑)

須磨浦普賢象(すまうらふげんぞう)
造幣局の桜、1本1本に、このような名札が付けられています。

福禄寿(ふくろくじゅ)
花弁には、波打つようなしわがあり、花弁数は15~20枚。

パパに肩車、よく桜が見えますね。

紅手毬(べにてまり)
咲きそろうと、花が紅い手毬のようになる

笹部桜(ささべざくら)
水上勉の小説「桜守」のモデルとなった、笹部新太郎が育てた桜で
花は淡紅色で、花弁数は14枚程の中輪です。
太い幹に、花のレイを巻いたように、幹にたくさんの花が咲いていました。

鬱金(うこん)
古くから知られた桜で、江戸時代に京都知恩院に植えられていたといわれ
樹姿は直立高木で、花は淡黄緑色のショウガ科のうこんの根の色に似ていることから、
この名前が付けられ、花弁数は10~15枚ある。

紅豊(べにゆたか)
携帯電話で写真を撮って、誰かに写メ送りたくなりますね。

帆立(ほたて)
造幣局旧正門。
明治4年に造幣局が創業した当時の正門です。

パート11まで続いたマドンナの「桜便り」は、如何でしたか?
大阪のソメイヨシノは散ってしまい、造幣局の桜の通り抜けも、23日には終わります。
桜前線は北上し、4月19日、福島県富岡町
(原発事故のため全域が立ち入り禁止の警戒区域)で、桜満開を迎えたという。
そして東北三県、東日本大震災の被災地は、間もなく桜色に包まれることでしょう。
少しの間だけ、辛いことも悲しいことも忘れて、桜に身をゆだねてほしいと思う。