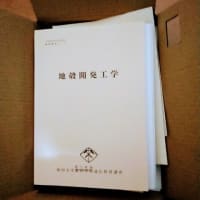| 発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ |
| クリエーター情報なし | |
| 木楽舎 |
・小倉ヒラク
発酵文化人類学というのは著者の造語のようだが、人類は昔から発酵という現象を利用してきた。だからこのような視点からの文化人類学があってもいいと思う。社会学や心理学などは頭に適当な文字をつけると新しい学問分野ができるような気がする。
例えばいま目の前にある我が本棚に鎮座している書籍のタイトルから適当に文字を拾うと、まぐれの社会学、まぐれの心理学、放課後社会学、放課後心理学、相対性社会学、相対性心理学。う~ん、ちょっと苦しいか。でもこんなものは絶対出てこないとは言い切れないような(笑)。だから文化人類学も頭に適当な文字をつければ新分野の一丁上がり。「発酵文化人類学」という分野があってもいいじゃないか。
発酵に関して一番多くの種類があるのはやはり酒だろう。本書にも酒に関する話が多いが、その他、味噌、醤油、漬物、発酵茶などの話もある。世界にはいろいろな発酵文化があるのだ。確かに本書にも記されているように、本書から発酵や文化人類学などを体系的に学ぶのは難しいかもしれない。しかし、発酵文化の多彩さ面白さ、奥深さは感じ取れるのではないだろうか。
ところで、本書にも載っているクサヤだが、これを最初に食べようとした人は勇気があるなあ。食べられるものだと知っていないと、臭いを嗅いだだけで腰が引けてしまうかもしれない。しかし世界にはもっと臭い発酵食品がある。本書では触れていないが例えば世界一臭いたべもとのとして有名なスゥエーデンのシュールストレミング。こういった臭さの観点から、発酵食品を語ると面白いんじゃないかな。
あえて言わせてもらえば、山口県出身者としては、柳井の甘露醤油が入っていなかったのがちょっと残念かな(笑)。
☆☆☆☆