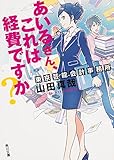「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」などのビジネス書や、楽しみながら会計の仕組みが分かる会計ミステリー「女子大生会計士の事件簿」シリーズでお馴染みの山田真哉氏の最新作、
「あいるさん、これは経費ですか?」(角川文庫)。
主人公は、顔がいいと言うことだけが取り柄の竜ヶ水隼人と言う青年。母が亡くなったために、モデルになろうと、はるばる鹿児島から上京してきた。ところが、憧れのアイドル烏山千歳が入ったオフィスをてっきり「芸能事務所」だと思って、働きたいと飛び込んだところ、そこはなんと芸能人専門の「会計事務所」だったというオチ。
結局、そこで働くことになった隼人だが、美人だが暴走気味の所長・天王洲あいるの、人使いの荒いこと、荒いこと。意外なことに、彼女の正体は、なんと烏山千歳と人気を二分していたアイドル桜上水芦花だった。しかし、今は、ちょっと変な人。そして、守銭奴(隼人評)。
本書は、連作短編の形で、税務に関係する4つの事件が描かれている税務ミステリーだ。ミステリーといっても、山田氏の他の作品と同じように、楽しみながら、会計や税務に関する知識を身につけようというものなので、殺人事件のような荒事は起こらない。これらの事件は、舞台が芸能界専門の会計事務所らしく、1曲目から4曲目という章建てとなっている。
1曲目で扱われるのは、芸能人の家賃に対する必要経費算入額。この事件では、隼人が、業務命令で、あこがれの烏山千歳とデートすることに。ところが、これには意外な事情が。
2曲目は、税務調査に関する話だ。毒舌タレントが、顧問税理士を替えたいと、あいるの会計事務所にやってくる。隼人は、理由を探るように特命を受けるのだが、成功すれば、雑用係の卵の殻から、卵に昇格してもらえるそうだ。しかし、この男、何も考えず突撃精神のみで調査を行うので、どんどん所長のあいるの評判が悪くなっている。これまた、最後には、「ええっ!」と驚くようなオチが。
3曲目は、賞金にかかる税金について。「アルピコ=シンシマーシマ=松本」と名乗る変な男が、賞金には税金がかかるのかと電話してくる。文学賞でも事業所得になる場合と一時所得になる場合があるということや、出版業界の裏事情も分かり、なかなか興味深い。
そして4曲目は、ゴーストライターと税金のこと。あいるが、税理士になった経緯とアイドル時代に同期生だった聖蹟桜のあいるに対する逆恨み。この事件を解決して、隼人は、やっと雑用係の卵から、雑用係に昇格したようである。
あいるの暴走ぶり、隼人の今後の成長など、これからどう展開していくのか、なかなか期待値の高い作品である。とかく税務というのは分かりにくく親しみにくいものだが、この作品は、税務のことは2割くらいに押さえて、事件の方の割合を大きくしたということもあり、難しさというようなものは感じさせない。そればかりか、税金って、案外と楽しいものなんだなあという勘違いまでさせてくれそうな感じがする(笑)。同じ税務を扱った「フラン学園会計探偵クラブ」の方も、連載が2巻目が出せるくらい進んでいるようなので、こちらも早く出して欲しいものだ。
☆☆☆☆☆
※本記事は、
姉妹ブログと同時掲載です。