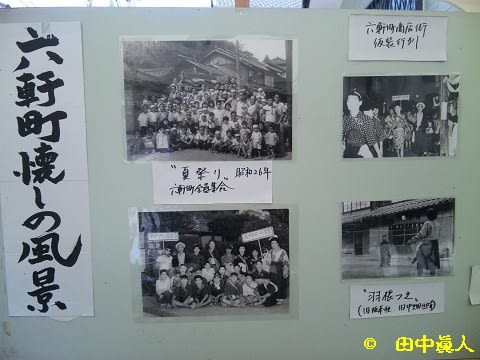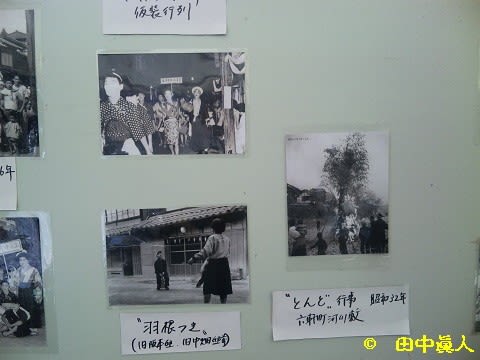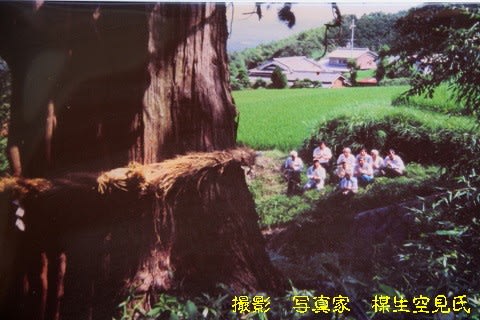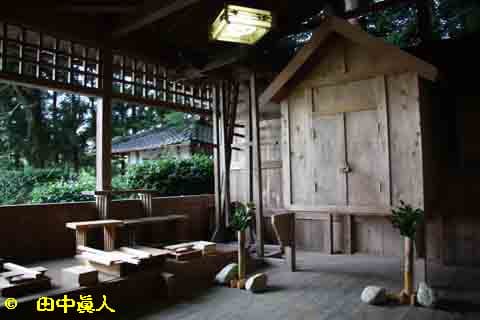桜井市瀧倉の取材を終えて食事処を探す。
向かう先は都祁の針テラスだ。
県道を東に向かい旧都祁村へ。
吐山の信号を左折れして北上する。
吐山の信号の次に信号が現われるのは白石の地である。
その信号地にあるお店は入店したことはない。
入店してもないから何を売っているのか存知しない。
ところがだ、ここの商店が作ったパック詰めの御膳をよばれたことがある。
箸袋に書いてあった商店の名は辻村商店。
よばれた大字は忘れもしない。
山添村の的野である。
平成25年の10月14日の宵宮と翌日15日のマツリを取材させてもらった。
その宵宮に当家もてなしの昼の膳をよばれた。
とても美味しかったことを覚えている。
それだけのことだが、よばれた味の印象は今でも記憶に残っている。
その店の表を流し目した。
えっと思った文字が飛び込んできた。
その文字は「刺しさば」。
再び、えっである。
特撰生鮎とか大阪西瓜など、空箱を店前に積んでいた処にあった。
行く人たちに気がつくように貼っていた「刺しさば」の文字。
これまで何度も通っているお店に「刺しさば」を売っていたとは・・。
初めて知った事実に思わずお店に飛び込んだ。
「刺しさば」を売っている店はこれまで民俗取材でお世話になった山添村の北野・津越のOさんが経営する商店がある。
お盆の家の風習にサシサバのイタダキサンがある。
お店で売っているし、家で行われるイタダキサンも撮らせてもらった。
売っていたサシサバを始めて見たのはその商店だった。
売っているのはそこだけと思っていた。
だから、えっというわけだ。
時間は午後2時前。
ぺこぺこに減ったお腹を満たすことが先決だ。
そう思って食事後に立ち寄った。
まずはお店の人に「刺しさば」話を聞け、である。
店主は白石の神社行事に出かけている。
お相手してくださったのは奥さんだ。

「刺しさば」はお店の自家製。作って売るようになって40年。
塩をいっぱい振って梅雨の晴れ間に干す。
売りもんの「刺しさば」は百尾も造る。
つい先日から売りに出した「刺しさば」はお盆の季節もん。
前述したサシサバのイタダキサンに捧げて家人が食べる。
以前、私も津越の大矢商店で買って食べたことがある。
とにかく堅いサシサバ。
カチカチに干した身をほぐすのはなかなかのもんである。
堅い身は箸で突いてもほぐれない。
ぐいぐい力を入れてなんとかほぐれだす。
一口食べて・・・。
仰天する味につい口にでたのがしょっぱぁ、である。
奥さんが説明してくださっている間はお客さんもいた。
その男性は3尾も買っていった。
話しを聞けば常連さんでもなく、私と同じように通りがかり。
「刺しさば」の表示に釣られて入店したという。
詳しくは聞けなかったが、かつて食べていたことのあるような雰囲気だった。
サシサバのイタダキサンはしていたかどうかわからないが、「刺しさば」の味を思い出されて買ったようだ。
奥さん曰く、お盆には広げたハスの葉に「刺しさば」を並べる。
両親が揃っておれば供えた「刺しさば」を食べるが、片親なら食べられないと云う。
と、いうことはご近所かどうかわからないがイタダキサンの風習をしているかも知れない。
予約の「刺しさば」に五枚、七枚の纏め買いの注文もある。
梅雨明けのころは屋外で干しているかも知れない。
塩をたっぷり入れて干すところを取材してみたいと思ったのは云うまでもない。
ちなみにお聞きした食べ方である。
一尾を6個に切って焼く。
塩辛くもなくなった刺しサバは茶粥に入れて食べていた。
冷たい茶粥は夏に最適。
サバに身をほぐして食べたら美味しいという。
(H28. 8. 1 EOS40D撮影)
向かう先は都祁の針テラスだ。
県道を東に向かい旧都祁村へ。
吐山の信号を左折れして北上する。
吐山の信号の次に信号が現われるのは白石の地である。
その信号地にあるお店は入店したことはない。
入店してもないから何を売っているのか存知しない。
ところがだ、ここの商店が作ったパック詰めの御膳をよばれたことがある。
箸袋に書いてあった商店の名は辻村商店。
よばれた大字は忘れもしない。
山添村の的野である。
平成25年の10月14日の宵宮と翌日15日のマツリを取材させてもらった。
その宵宮に当家もてなしの昼の膳をよばれた。
とても美味しかったことを覚えている。
それだけのことだが、よばれた味の印象は今でも記憶に残っている。
その店の表を流し目した。
えっと思った文字が飛び込んできた。
その文字は「刺しさば」。
再び、えっである。
特撰生鮎とか大阪西瓜など、空箱を店前に積んでいた処にあった。
行く人たちに気がつくように貼っていた「刺しさば」の文字。
これまで何度も通っているお店に「刺しさば」を売っていたとは・・。
初めて知った事実に思わずお店に飛び込んだ。
「刺しさば」を売っている店はこれまで民俗取材でお世話になった山添村の北野・津越のOさんが経営する商店がある。
お盆の家の風習にサシサバのイタダキサンがある。
お店で売っているし、家で行われるイタダキサンも撮らせてもらった。
売っていたサシサバを始めて見たのはその商店だった。
売っているのはそこだけと思っていた。
だから、えっというわけだ。
時間は午後2時前。
ぺこぺこに減ったお腹を満たすことが先決だ。
そう思って食事後に立ち寄った。
まずはお店の人に「刺しさば」話を聞け、である。
店主は白石の神社行事に出かけている。
お相手してくださったのは奥さんだ。

「刺しさば」はお店の自家製。作って売るようになって40年。
塩をいっぱい振って梅雨の晴れ間に干す。
売りもんの「刺しさば」は百尾も造る。
つい先日から売りに出した「刺しさば」はお盆の季節もん。
前述したサシサバのイタダキサンに捧げて家人が食べる。
以前、私も津越の大矢商店で買って食べたことがある。
とにかく堅いサシサバ。
カチカチに干した身をほぐすのはなかなかのもんである。
堅い身は箸で突いてもほぐれない。
ぐいぐい力を入れてなんとかほぐれだす。
一口食べて・・・。
仰天する味につい口にでたのがしょっぱぁ、である。
奥さんが説明してくださっている間はお客さんもいた。
その男性は3尾も買っていった。
話しを聞けば常連さんでもなく、私と同じように通りがかり。
「刺しさば」の表示に釣られて入店したという。
詳しくは聞けなかったが、かつて食べていたことのあるような雰囲気だった。
サシサバのイタダキサンはしていたかどうかわからないが、「刺しさば」の味を思い出されて買ったようだ。
奥さん曰く、お盆には広げたハスの葉に「刺しさば」を並べる。
両親が揃っておれば供えた「刺しさば」を食べるが、片親なら食べられないと云う。
と、いうことはご近所かどうかわからないがイタダキサンの風習をしているかも知れない。
予約の「刺しさば」に五枚、七枚の纏め買いの注文もある。
梅雨明けのころは屋外で干しているかも知れない。
塩をたっぷり入れて干すところを取材してみたいと思ったのは云うまでもない。
ちなみにお聞きした食べ方である。
一尾を6個に切って焼く。
塩辛くもなくなった刺しサバは茶粥に入れて食べていた。
冷たい茶粥は夏に最適。
サバに身をほぐして食べたら美味しいという。
(H28. 8. 1 EOS40D撮影)