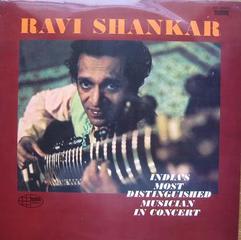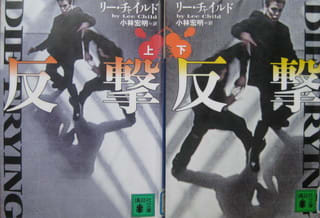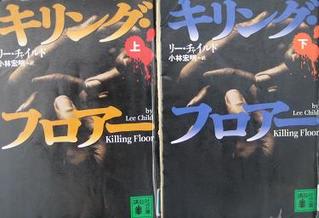[ L P ]
オーネット・コールマンもジャズを聴き始めた頃にはそれこそ、理解する目標の一人でありました。ところがさかのぼってアトランテックの初期を聞いてもいまいち心に触れません。
オーネットの場合ニュージャズといっても破壊とか凶暴とか関係なく、土着のブルースの展開というか、充分にJAZZを楽しんだ後でしか解らない独自の世界があるのです。
あまり聴かないオーネットをすんなりと理解できたのがこのアルバム。
アナウスの後始まる音楽のなんとも素直で歌心に満ちた演奏でしょうか。
2曲目のアルトでのリズム取りからのソロフレーズ、この頃のBlue Noteって余裕があります。次に行こうかと思うD・チェリーにしても、C・テイラーにしても良くアルバム発売したものです。
デヴィッド・アイゼンソンのベースとチャーレス・モフェットのベースとのトリオ演奏にしたおかげで、オーネットのフレーズに掛ける緊張がとても良く伝わってきます。
B面1曲目、アイゼンソンとモフェットは4ビートを刻みますから、その中でのコールマンのアルトは一人自由に歌うがごとき、もしくは自己の主張をしているのです。そしてこのように歌うことが出来るのはやはりアメリカにいる人々なのかと思ったものでした。ここで流れるメロディをすべてギターに置き換えてみると、まさにアメリカの黒人ブルースに行くのでないでしょうか。
それが解るとB面2曲目もなんとも暖かい心が伝わってきます。
At the "Golden Circle" in Stockholm, Vol. (1965)
Ornette Coleman (as,violin,tp)
David Izenzon (b)
Charles Moffet (ds)
1.Announcement
2.Faces And Places
3.European Echoes
4.Dee Dee
5.Dawn

[ L P ]
とても気に入った次に買ったのがこのアルバム。
フィアデルフィア・オーケストラの木管5重奏と室内4重奏との共演のアルバムです。
これは現代音楽で、それはそれなりにわかるのですが、特に現代音楽を選んで聴いて楽しみたいと思いはなく、そして一番のショックはオーネット・コールマンがトランペットを吹いていること、バイオリンより良いかとおもいますが、そして凄いのはB面、作曲だけで演奏なし。
そんなこともあり、オーネット・コールマンとはあまり近い部分に行きませんでした。
The Music Of Ornette Coleman
Ornette Coleman (tp, comp)
Mason Jones (frh)
Murray Panitz (fl, picc)
John DeLancre (ob, ehr)
Barnard Garfield (basn)
Anthony Gigliotti (cl, bcl)
"Village Theatre", NYC, March 17, 1967
Stuart Canin, William Steck (vln)
Carlton Cooley (vla)
William Stokking (vlc)
Ornette Coleman (comp)
NYC, March 31, 1967
1 Form And Sounds
2 Space Flight
3 Saints And Soldiers