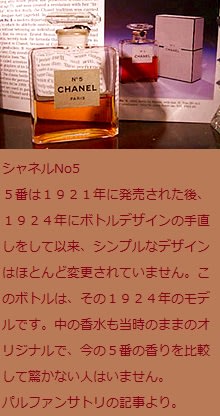飛行機の墜落事故。その飛行機に乗り合わせた人々の運命とはどんな糸で操られているのだろうか。
2014年7月26日午前11時銀座の歩道。梅雨明け10日と言われるように、梅雨が明けて10日間は快晴が続くと言われている。その通りの青空に浮かぶ雲は、まだ春の名残を引きずって薄ぼんやりとしたものだった。それでも降り注ぐ陽射しは思わず手をかざして光を遮りたくなるほど強く暑い。
この暑さの中、歩道は人の行き来で途切れることはない。その中にひときわ目に付く女性が銀座四丁目に向かって歩いていた。Tシャツにジーンズや短パンというスタイルが普通という時代にあって、つば広のブルーのサマーハットに薄いブルーのサマー・ドレス、足元は白のサンダル。足首にはプラチナのアンクレットが時折陽射しを反射していた。色白で肉感的な体つきに横顔の美しい女性三十代後半に見える45歳の川路美穂という。
行きかう人々のうち男性は目を離せなくなるようで彼女をずーっと眺めている。女性でも振り向く人も多い。そういう彼女は、女優でもファッション・モデルでもない。ごく普通の下町の娘だった。しかも、夫がいる。
新橋方面から銀座の方へ歩いている平凡な四十六歳の男神城健一は、ぴったりと体に合った鮮やかな紺色のスーツと真っ白なボタン・ダウン、シャツを着こなして平凡さを隠していた。馬子にも衣装とはよく言ったものだ。体つきは華奢でむしろ細い体躯だった。
銀座四丁目の人ごみを俯瞰すれば、まるで蟻が右往左往している様とそっくりだろう。それぞれが目的地へ急いでいる。
川路美穂は三越前で友人の加奈子と待ち合わせて、近くのホテルでランチ・バイキングを楽しむ予定だった。久しぶりの友人との食事とおしゃべりの期待が自然に歩みを速めている。
神城健一は新橋の取引先に寄って妻から頼まれた買い物に伊東屋へ急いでいるところだった。三越前の信号が赤になっていて歩行者が群がっていた。健一はポケットから妻がよこした買い物リストを取り出して眺めた。信号が青に変わって群衆が動き出した。眼をリストに落としていた健一は、前の男が何か光るものを取り出したのを気配で感じた。
眼を上げたとたん男は異様な叫びと共に前を歩く人々をなぎ倒しながら一点を見つめて三越前の群衆に迫った。健一はいつもとは違いとっさに男を追っていた。その男はブルーのサマーハットを被った川路美穂に迫った。「今日も俺を裏切るつもりか?」と言いざまレターマン・スパーツールの鋭利な刃をむき出したナイフを振り上げた。
健一はそのナイフしか眼に入らなかった。その腕に飛びついて全体重をかけぶら下がった。男は力強かった。男が振りほどこうとしたとき健一の腕につめたい感触が走った。数人の男が暴れる男を取り押さえていた。
まもなく救急車とパトカーが勢いよく停止した。一帯は通行止めになった。行き場を失った車と人で混乱状態になった。パトカーは犯人を連れ去った。神城健一は、救急車で病院へ搬送された。
青ざめた川路美穂に警官が近づいた。
「あなたの知り合いですか?」
「いえ、まったく知らない人です」
「近くにいた人の証言では、俺を裏切るつもりかというのを聞いたと言っていますが?」
「ええ、でも知らない人です」警官は美穂の身上調書をとった。途中から友人の加奈子も加わって美穂の言葉の裏づけとした。
最後に美穂は聞いた。
「怪我をなさった方はどちらの病院へ送られたのですか?」
警官は事務的だった。「それはお伝えできません。事件発生直後ですから」
「そうですか。犯人は私に向かってきて、犯人の手を止めさせたのが怪我をした人ですからお見舞いにあがりたいと思っているんです」
「ええ、よく分かりますよ。じゃあ、こうしましょう。捜査が一段落すればすべてお話できるかもしれません。ここに私の所属と電話番号を書いておきますから、二・三日したら電話をください。よろしいですか?」
「ええ、結構です。お手数かけますがよろしくお願いいたします」
それを眺めていた造物主つまり神は、あごに手をやって「うん、どうしたものかな! 二人ともパートナーのいる身だし、女が見舞いに行ったとたん二人は電気に討たれた様に離れられなくなるのは確かだ。神としても考えどころじゃのう」見えない神の手は、今日も忙しそうだ。