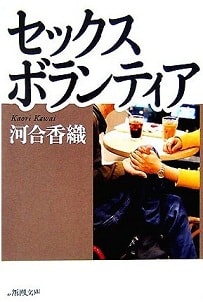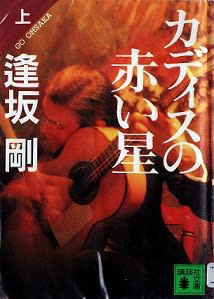
禿鷹シリーズに引き続き読んだ。著者の最高傑作と評される。第96回(1986年下半期)の直木賞、第40回(1987年)日本推理作家協会賞をダブル受賞した作品。
逢坂剛は、1943年生まれでこの作品が講談社から刊行されたのは1986年、著者の42~3歳の頃になる。執筆がそれよりも数年前とすれば30代後半ぐらいか。
かなりの長編であるが、飽きることなく読めた。「カディスの赤い星」と言うフラメンコ・ギターにまつわる運命に、人間模様が彩りを添える。
物語の中で偶然を嫌う私としては、自然な流れを阻害するものを見つけたときはチョット嫌な気分になる。だからといってこの作品が大きく傷つけられることはない。ほとんどの人は気にもかけない事ではある。
年配者特有の意地悪な言い方をすれば、主人公の男(ハンサムらしい)が他社の美人社員とのセックスだ。(またまた下半身かい、と言わないで欲しい)しかも処女だった。
これの描写が、最初は脚を閉じてなかなか開かないというそれらいき記述であったが、ことが進むにつれてまるで結婚1年を経た若妻のような反応になる。
それに、男は二週間のスペイン冒険行のあと再び交わる。その時は、もうベテランの女になっていた。例外はあるにしても、そんなに早く女が成熟するのが不自然に思われた。
また、会話の中に気の利いた冗談を散りばめてちょっとした遊びを織り込んでいる。ただ、ユーモアのある比喩という点では、欧米の作家には叶わない。
このユーモア・センスは、生まれ育った環境がかなり影響しているように思う。日本ではユーモア・センスを評価する度合いが低いせいかもしれない。それを無視すれば楽しめる作品だった。