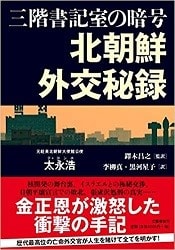36年前、13歳の淡い記憶を辿って、同級生だった美貌の塔屋米花(よねか)の今を確かめたいと願う男の軌跡を描く。男の名前は、杉井純造。
それは19年前、30歳の杉井純造の結婚式当日、一通の電報が届いた。発信人の名前のない「ワタシヲオイカケテ」という文面だった。一体誰だろう。瞬時に杉井の頭に浮かんだのは、塔屋よねかという名前だった。
中学1年生の秋、転校していって音信不通になった塔屋よねかが、どうして結婚式の日取りが分かったのか。ある筈もないこととはいっても、十五夜の月見の夜、「私を追いかけて。ねェ、月光の東まで私を追いかけて」と言いながら橋を渡っていったよねかを思い出す。
同級生で親交が続いている商社員の加古愼二郎の勤め先、シンガポール支店に問い合わせたが、よねかのことは分からないという返事。
この件は、やがて忘れ去られた。月日は足早に通り過ぎて、杉井純造も塔屋よねかも加古愼二郎も48歳か49歳になった。人生で一番脂がのる時期と言うのに、加古愼二郎はパキスタンのカラチのホテルで首を吊った。自殺だった。
その年の末に加古愼二郎の妻、美須寿(みすず)の突然の来訪を受けた。そして、美須寿夫人から驚くべき事実を告げられた。それは、ホテルのチェックインが塔屋よねか同伴だったことだ。美須寿夫人の動揺は、顔色・挙措すべてに表れていた。杉井とて同じでかつて恋心を抱いた塔屋よねかが加古と……嫉妬心が心の平穏を乱した。
冷静になった時、杉井の心にぜひ塔屋よねかの足跡を辿りたいという思いが膨らんだ。絡んだ糸を解きほぐすように、ミステリアスな展開を伴ってほろ苦く甘酸っぱい青春の追憶が投げかけられる。
塔屋よねかという女は、いったいどんな女なのか。謎の言葉、月光の東。それらを追ってページが進む。一人称形式で杉井純造のパートと加古美須寿の日記形式で語られる。
その中で、杉井純造は中学生の頃を懐かしく思い出しながら「米花ちゃんは、とびぬけて美人で学校中の男子生徒の垂涎の的だった。他校の生徒もわざわざ見学に訪れていた。米花ちゃんは、漢字の米花がきらいで「よねか」と言ったり書いたりした。ただ、家庭環境が複雑で本当のところは誰も知らない。
引っ越しが多く高校生のころには北海道の合田牧場でアルバイトをしていた」
ちょっと寄り道すると、他を圧倒する美貌の持ち主は滅多に見かけないが、私の1960年代、当時サントリーのトリス・ウィスキーのアンテナ・ショップともいうべきトリス・バーが出来ていた。大阪・梅田にその店があった。ハイ・ボールがセールス・ポイント。
今でいう店長が一目見ただけで言葉が出ない超美人なのだ。足しげく通う男どもで、カウンターはいつも満員。まるで電線に並んで止まる雀のようなのだ。そして誰もその美人にモーションをかけようとしない。男どもは身の程を知っていたのだ。どうせブ男で大金持ちの男の愛人だろうと誰もが思ったに違いない。真実は分からない。
この店にはテーブル席もあったが、いつもガラガラだった。当時はアベックと言い、こんにちのカップルだが、来てもカウンターにいる美人に男は釘付け。女の方がこの店を敬遠するのは当たり前。超美人だけでは商売が成り立たない。しばらくして閉店した。
塔屋よねかも他を圧倒する美貌を持っていて、その美貌を最大限に利用した。合田牧場で競走馬を買う美術商の津田富之に身を売った。「私を自由にしてもらっていいから、大学と留学の費用を出して欲しい」それが条件だった。その時、よねか高校三年生18歳。
そして塔屋よねかを最も端的に語るのは、バーのオーナー柏木邦光なのだ。よねかと肉体関係を持った男の一人。
よねかも50歳になった。成田空港のファースト・クラスのラウンジで柏木邦光がよねかを見かけた。読んでいる新聞の陰から見ると「よねかは今日も相変わらずキレイだった。ただやはり年齢は隠しようがなかったが……」
そんなよねかではあるが、登場人物全てが角が取れて丸くなり、まるで仏様のようになるのだ。よねか効果と言っていいかも。ただ、語られる塔屋よねかは傍証にすぎず、自身が語ることはない。そのせいか、この物語で判然としないものが三つある。一つは、杉井純造の結婚式をどうして知ったのか。二つ目、加古愼二郎の自殺のいきさつ。三つ目に、よねかの謎の言葉、月光の東。
その月光に東について考えてみた。人は誰でも届かない夢を見ている。しっかりした目的とか目標と言ったものでなく、ただあんな風になりたいとかあそこへ行きたいというもの、いうなればシャングリラ(理想郷とかユートピア)を求める。私は月光の東は、このシャングリラではないかと思う。
シャングリラは、「イギリスの作家ジェームズ・ヒルトンが1933年に出版した小説「失われた地平線」に登場する理想郷の名称という。この小説により「シャングリラ」という言葉は有名になり1930年代後半以後、ヒマラヤ奥地のミステリアスな永遠の楽園と見られるようになった。方角から見るとパキスタン北部やインド北部から中国西部、とりわけチベットやヒマラヤの高原では、観光用のキャッチフレーズにシャングリラという名が頻繁に登場する」とウィキペディアにある。
この小説でも、よねかと津田の共通の友人古彩斎と三人でヒマラヤ・トレッキングに出かけている。それらを考えると、ヒマラヤ周辺ということでシャングリラに思える。ただ、このシャングリラをヒマラヤ周辺に限定することもない。広く大きく捉えれば理想郷なので、それぞれの到達点ということもできる。
私がこのシャングリラという言葉に出会ったのは、マーク・ノップラーとエミルー・ハリスのデュエットで「Our Shangri-La」という曲。この曲はサーファーが落日を見ながら今日一日を振り返り、まさにここがシャングリラ(理想郷)だと思うというもの。それではこの曲を聴いていただきましょう。