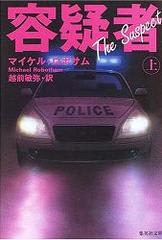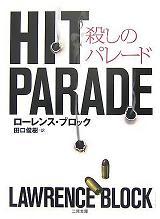ナマの犯罪者の体臭が漂う犯罪小説を書き続けている作家の、1977年度の作品。
かなり前に読んだこの作家の「野獣の街」がえらく印象的だったのを覚えている。この本も魅力的なワルが、ぞろぞろと出てくる。
令状送達人のジャック・ライアンは、仕事のマンネリ化が人生の行く末にふと寂しさを感じるときがある。仕事は気に入っていて自分にぴったりだと思っているが、すでに三十六歳。
「もしかしたら自分は世間のおちこぼれなのではないか、世間と少しずれてしまっているのではないのか、退屈な九時から五時までに縛り付けられている人たちのほうが正しく、自分のほうが間違っているのではないのか」と気になり始めていた。
そんな時仲間のジェイ・ウォルトからある男を捜してほしいという。報酬は百五十ドルから三百ドルに吊り上げた。そして調査が進むさなか、捜していた男が殺されて死体安置所で眠っていた。足のタグには、「身元不明者89号」とある。身元確認が済むまでは、この仮の名前になる。
ここからがだんだん複雑な展開になっていく。こういう本を読んでいると、映画化するとすればどんな配役にするかあれこれ考えるのも面白い。ライアンをジョン・トラヴォルタ、ジェイ・ウォルトにダニー・デビート、ライアンと親密な関係になる女デニーズには、知的な女優がいい。「プラダを着た悪魔」に出ていたアン・ハサウェイなどを思い浮かべていた。
エルモア・レナードは、1925年10月生まれというから今年八十三歳になる。執筆活動は衰えないようで、2007年にも新作を発表している。2005年の「ホット・キッド」が訳出されているので読んでみたい。


三島由紀夫の文体になかなか馴染めない。こちらの力不足ももちろんあるが、同類意識や同胞意識を「人種的親和感」なんて言われると「何だって?」と言いたくなる。
この世におおよそ存在しない男女の悲しい物語。石のように無反応な不感症の美しい人妻顕子(あきこ)と若くハンサムで育ちがよく金に不自由しない男城所(きどころ)昇の取り合わせだ。
作家は読者を選べない。読者は作家を選択できる。たまたま、三島由紀夫を選んで読み始めて、「何だ、もって廻った言い方で自己満足のために書いてるのか」と感じても読者を責めることは出来ない。読者自身のレベルはどうすることも出来ないからだ。まあそんな弁解染みた言い訳にぶらさがって、自分のレベルに合う部分を見つめるしかない。
そういう視点で読んでみると、三島由紀夫の自然や街中の描写には独特の観察と視点が見て取れる。
“古い樹々は芽吹き、おそるおそる、しなやかな若枝をさしのべた。樹という樹は、なにか予感に充ちていた。それらの粉っぽい芽が、童心といった感じがするのに比べて、若い枝々には、ふしぎな艶やかさがあった。
南向きの、雪のあらかた消えた斜面に、昇は葉の少しもない枝々から、白い鮮やかな花を一せいに咲かせている辛夷(こぶし)を見た。大きく広げた梢の先々に花をつけたさまは、枝附燭台(えだつきしょくだい)のようである。冬の間黒い幹の中に蓄えられていた燈油が、急に点火されて、白い焔(ほのお)を上げて、一せいに燃え出したように見えるのである”
“昇は午前のK町を歩いた。(このK町というのが気に喰わない。地図を見れば小出町と分かるのに、なぜ小出町としないのか。K町にする理由が分からない)田舎町の女たちは目にしみた。(そりゃ禁欲生活を半年以上続けたからだろう)
赤銅(しゃくどう)に金色の樽をはめ込んだ酒屋の看板を、永いこと立ち止まって眺めた。日あたりのよい裏の空き地には鶏が飼ってある。鶏を追う声がする。時ならぬ鶏鳴(けいめい)。
かたわらを疾駆する自転車のベルの音。道の上のトラックの大きな轍(わだち)。ひっそりとした洋装店の奥で、いつまでもなり続ける電話のベル。……
昇はまたとある仕舞屋(しもたや)の縁先で、ミシンを踏んでいる女を見た。生垣がまだ葉が乏しく、まばらに透いて見えたのである。家の奥深くは暗く、文色(あいろ)がはっきりしない。それで却(かえ)って、女の姿が明瞭に浮かんで見える。
女は小太りしている。若い。けんめいにミシンの上へかがみこんで、何か白い布を、両手で押さえて、ずらしている。ミシンのあらわな金属の部分が光る。女は空色のスウェータアを着、共色のスカアトを穿いている。ミシンの下部に、踏み板を小刻み踏みたてている太い健康な素足が見える。その動きがあまり激しいので、膝の上ではいつも空色のスカアトがはためいているのである。北国の女らしいその白い脚の肉は、たえず動いていたために、昇がそこを離れたのちも、目の中にちかちかする幻覚を残した”昇の立場だったら、白い脚の肉にエロチックな感情を抱いても不思議ではない。
全体に不足しているのはユーモア、それも上質のユーモアだ。日本人のもって生まれた生真面目さは、普段の日常生活においてもこのユーモアがないので、作家といえども付け焼刃のユーモアですら、生み出すことは出来ないのだろう。あの洒落者の三島でも……
あともう一つ。昇が越冬から解放されて顕子を再び抱いたとき、かつての石のような無反応な女ではなかった。そのセックス・シーンは奥床しく美しくしかもみだらな妄想を誘う。
“この髪、この額、この耳、と思いながら、昇の唇は確かめた。それらの物質的な細部はそのままだったが、顕子は少しも似ていなかった。美しい細身の体はつつましくしていたが、昇の項(うなじ)にまわしているその指には、おぼれかけて救われた人の手のような、怖ろしい力があった。
顕子のつぶっていた目がかすかに見ひらくその眼差しが、昇を戦慄させた。その目は決して昇を見ず、彼女自身の中に生まれた歓びをしか見ていなかった。その眼尻(まなじり)の繊細な溝を伝わる涙を昇は飲んだ。顕子は昇の名を呼んだが、こんな深い呼声は、昇の手のとどかない遠方から、呼びかけてくるとしか思われなかった”
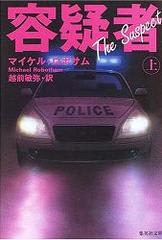
警察の捜査に協力しているつもりが、気がついたらなんと容疑者になっていた。臨床心理士のジョーゼフ・オローリンは、母でさえハンサムだと言わなかったし、茶色い髪は癖が強く、鼻は洋梨型で、日差しを少しでも浴びるとそばかすが出来るという四十二歳の男だった。
家族は大学時代に見初めたジュリアンと一人娘のチャーリーの三人。ジョーゼフは、配偶者が無料で尋ねる質問を、金をもらって尋ねる専門家というジョークの定義はともかく、患者の問題に耳を傾け、そこにひそむ意味を見つけ、本人の自尊心を打ちたて、あるがままの自分を受け入れるように導くことに専心していた。
いろんな症状の患者が来る。渡橋恐怖症や砂漠恐怖症など、高所恐怖症に閉所恐怖症は誰にでも少しはあるだろう。わたしの場合、それに踏切恐怖症と首都高恐怖症に橋上恐怖症が加わる。だからといって冷や汗が出るわけでもない。
踏切での事故や大地震で高速道路の橋脚が崩れたり橋が落ちたりしたのが軽い恐怖症として残っている。
ジョーゼフの身に起こることの発端は、元患者のキャサリンが殺されたことから始まる。身の潔白を証明するために調査を進めると意外な事実が浮かび上がってくる。前半は少し退屈気味だったが、後半はテンポよく展開もスピーディーで、適度のユーモアに彩られた文章と会話による人物造型が印象に残る。
一人娘のチャーリーの可愛さ、可愛いという言葉を使わずに表現している。妻ジュリアのたくましさ友人のジョック、父・母などが鮮やかに描かれる。
著者は、シドニー、カリフォルニア、ロンドンでジャーナリストとして活動。1993年から著述活動に専念し、ゴーストライターとして各界の著名人の自伝10作を手がけベストセラーとなる。初の小説である本書は10数ヶ国語に翻訳され、すでに30ヶ国以上で刊行されている。
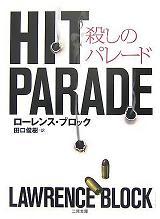
「ケラーは片手にビール、もう一方の手にホットドッグを持って……」という書き出しを読んだとき、この間食べたホットドッグの味が忘れられないことに気がついた。自作のホットドッグだが。時たま昼食にホットドッグを作って食べるが、いまひとつの感があった。たまたまキャンプをした日の朝、昼食用にホットドッグを作った。そして周辺をドライブの途中、そのホットドッグを食べた。まさにビールとともに(このときわたしは運転していない)。これが美味しかった。
なぜかと考えてみると、一つには素材のパンにもあるのではないかと思う。このパンはキャンプに行く朝、千葉幕張の「コストコ」で買ったもので、パンそのものは大して美味しくない。しかし、ソーセージに酸味のあるザワークラフトかピクルスをはさみ、ケチャップとマスタードあるいは辛子で味付けするとホットでなくても断然美味しい。
そんなことを思い出しながら殺し屋ケラーの仕事振りを読み進む。仲介者のドットとケラーの絶妙の会話を楽しみ、ケラーのクールな殺しに堪能する。ドットは女性でケラーとほぼ同年代なのだろう。このコンビは息がぴったり合っている。ケラーは、ブロックに言わせると四十代後半ということらしい。短編、中篇でなるそれぞれの章は完結するが、何らかの形でつながっている。
この仕事で厄介なのは、社会変質者でない限りターゲットになった人間を鮮明に記憶することだ。ケラーはそれもメンタルトレーニングで忘れることが出来る。
というが最後の「ケラーとうさぎ」というわずか約二千字の章を読むと社会変質者ではないかと思えてならない。
要約は「レンタカーでターゲットの女の家に向かった。ラジオのスイッチを入れたつもりが、CDプレイヤーが作動した。ケラーの前に借りた人物がCDを取り出すのを忘れたのだろう。
うさぎの寓話で人間に見立てたたとえ話でありうさぎの物語でもあった。ケラーは物語に引き込まれ、うさぎたちの無事を祈っていた。女の家を見張る位置に車を停めて待機に入った。子供が二人玄関から飛び出しガレージに走りこんだ。後からその女もガレージに入りSUVがバックで出てきて走り去った。子供を学校に送っていったのだろうと推測したケラーはガレージの中の影に潜んだ。
戻ってきて驚愕の表情で見つめる女を、ケラーは指に力を込めて彼女のみぞおちを突いて気絶させてから、その体を抱えて首の骨を折った。あまりいい気分ではなかった。エンジンをかけるとCDが作動した。
殺したばかりの女の顔の残像や、彼女の体を床に横たえて人目につかないようにSUVの下に押し込んだときの感覚的な記憶が邪魔になるだろうと思っていたのだが、三ブロックも行かないうちに物語に引き込まれた。女のイメージは早くも記憶から消え始めた。可哀そうなうさぎたち。彼らの身には何も起こらないように。ケラーはそんなことを思った」
わたしにとってこの章が一番印象に残った。

人を殺していないのに「お前がやったんだ」と、裁判で有罪しかも量刑は死刑。一体どうしてこんなことになるのだろうか。その詳細がジョン・グリシャムの手によってノンフィクションとして語られる。
抜群のエンタテイメント性で読者をひきつけたグリシャムも、最近ではその勢いがやや衰えたかに見えた。この本が起死回生の役割を担っているとは思えないが、事実の強みが淡々とした文章にも読み手の熱い感情が緊迫感と感涙を誘う。
とりわけ、犯人とされるロン・ウィリアムソンとデニス・フリッツをサポートする弁護団のDNA鑑定の結果にいたる記述は、適度のインターバルで、読者を少しじらすという小憎らしいところがあるが(わたしはそう思う)、緊張させられそしてほっとする。
題名からして行き先は分かっているが、それでも「どうなるのだろう?」という期待感は抑えがたい。1982年12月8日オクラホマ州オクラホマシティの南東にある小さな町エイダで、二十一歳のデビー・カーターが自宅アパートでレイプされ絞殺される。
捜査は難航して事件発生から五年後の1987年、ロン・ウィリアムソンとデニス・フリッツの二人が逮捕される。これがこの恐るべき冤罪事件の発端だった。デニス・フリッツは終身刑、ロン・ウィリアムソンは死刑で、死刑執行五日前に再審決定で無期限の延期になり、最終的には無罪になる。
証拠の分析にDNA鑑定が決定的な役割を果たした。日本でも1990年代はじめに導入されたDNA鑑定は、二億人の中の一人を識別するという精度を誇る。それにしてもずさんな捜査の行き先は、無実の人間を殺してしまうという悲劇が待ち受ける。
この無罪放免のあとにも興味が尽きない。日本でも冤罪事件で損害賠償を請求するが、アメリカの場合かなり難しいようだ。というのも、この本によれば「冤罪による不当な有罪判決にかかわる民事訴訟は、勝つのが極端に難しく、無罪が確定したもののほとんどが裁判所から締め出されているのが現状だ。不当な判決を下されたからといって、それだけで自動的に訴訟を起こす権利が得られるわけではない。原告として訴訟を起こそうというものは、おのれの人権が侵害され、憲法が認める人権保障が履行されず、その結果として不当な有罪判決が下されたと主張し、かつそれを証明しなければならない。
さらに難関が待っている――不当な有罪判決につながる訴訟手続きにかかわった人間は、そのほぼ全員が免責特権で守られているのだ。公判指揮がどれほどお粗末でも、判事は不当な有罪判決がらみの訴訟から免責される。ただし捜査に深く関与しすぎていれば、責任を問われる可能性がある。
警察官も免責されるが、道理をわきまえた捜査当局者の目から見て憲法違反だと判定されるほど不当な行為だったと示せるのなら話は違ってくる。こうした訴訟の維持には巨額な費用が必要で、原告弁護団は数万ドル――多ければ数十万ドル――の訴訟費用を前払いすることを強いられる。その費用を回収できる見込みもほとんどないため、提訴自体が無視できないリスクを伴っているのだ。不当な有罪判決を受けた大半は、一セントの金も受けとっていない」
これをどう考えればいいのだろうか。判事や検事、警察官、弁護士など免責がなければ嫌がらせの不当判決訴訟で身動きできない事態も予想される。それも困ったことだし善良な市民がいわれのない罪をかぶせられるのも困ったことだ。これをどうすればいいのか、わたしには判らない。
日本では憲法第40条「何人も、拘留または拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることが出来る」とある。
ふと思ったのは、裁判官や検事、警官にしても犯罪のランク付けをしているのではないかと思わないでもない。残忍な殺人事件、特に幼児が含まれる事件などには、世間の関心も強く気合を入れた捜査が行われるが、こそ泥事件などは日常業務の一環に過ぎないとばかり一丁上がりで済ませているのでは……ということ。それを非難するつもりは毛頭ないが、この事件のように、いい加減な捜査や証言の信憑性を損なうような扱いには心底怒りがこみ上げる。