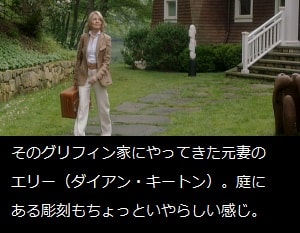この題名を見たとき、2004年の「サイドウェイ」を連想した。中年男がアメリカの西海岸のワイナリーを訪れるという話で、ワインのうん蓄はもとよりワインと女性という男にとっては究極の贅沢を味わえた。
この映画もその類かと期待した。期待に応えてくれたかと言うとやや不満。まず邦題が問題。グルメを表に出しすぎ。原題は単にトリップだけ。トリップには小旅行の意味もあるから適切な題名だ。
ロンドンに住むスティーヴ(スティーヴ・クーガン)は、オブザーバー誌の企画、イギリス北部のレストラン巡りの仕事が入りガール・フレンドのミッシャと同道を計画したが、ミッシャの都合が悪く友人のロブ(ロブ・ブライトン)を口説き落とした。
イギリスの四輪駆動車レンジ・ローバーを駆って北部へ。スティーヴのロード・プランは「M1とM6を走って高速をJ31で降りる。それからA59をちょっとドライブしてクリズローへ、そこからホワイトウェルはすぐだ」
レストラン「ランクリム」での食事。小袋の底には角切りの野ウサギのくん製と刻んだラディッシュ、カモのフォアグラ・ムースで覆いを」ウェイターの説明。
スティーヴとロブは「うーん、うまい」と言うが、ロブは時々皮肉を利かす。
「これは二枚貝(シェルフィッシュ)のスープで、素材自体のエキスで調理し海草の彩を」とウェイター。
ロブは「セルフィッシュ(身勝手な)スープだ」と混ぜかえす。
ロブの物まね、マイケル・ケインやロバート・デ・ニーロなどいろいろに、なにやら落ち着かないスティーヴ。ミッシャとうまくいかない腹いせとも思えるいく先々で女性とベッドを共にする。朝密かに女性がドアから出て行く、残ったスティーヴは片目をあけて無言で別れを告げる。
そして言うことに「歳をとるにつれてより熟女に魅力を感じないか? そして若い女にも。 若い女には命の輝きが魅力だが、熟女は、その人間性のほうにもっと魅力を感じる」だと。
次の目的地までの道順を運転中にロブに言う。「ナビにすれば?」
スティーヴ「ナビには地理的な感覚が欠けている」
「でも効率がいいぞ!」
「効率よりも過程が大事だ」とスティーヴ。
女性観とか道路地図にするかナビにするかの価値観は、監督の信念なのだろう。おおむね同感だ。レストランめぐりをする中年男二人の背景には、家族があり恋人があり別れた妻と子供がいる。合間にそれらが描かれ、女性関係が派手なわりに家庭的にはさびしいスティーヴだし、逆に幸せなロブという人それぞれの人生がある。
それにしてもイギリスの北部へのドライブは、日本ほど人家が密集していないから冷たくさびしい風景に映った。道路も狭いから日本の田舎道を走っている感覚に落ちた。





監督
マイケル・ウィンターボトム1961年3月イギリス、イングランド ランカシャー州ブラックバーン生まれ。イギリス映画界をリードする実力派の映画監督。
キャスト
スティーヴ・クーガン1965年10月イギリス、イングランド マンチェスター生まれ。
ロブ・ブライトン1965年5月イギリス、ウェールズ生まれ。