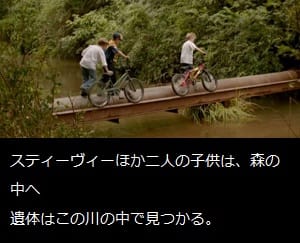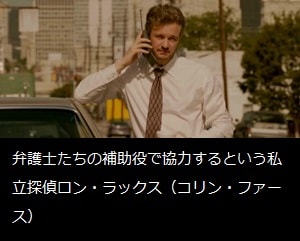私にはどうしても記憶から消し去れない映像がある。それは米軍撮影の記録映画だったと思うが、沖縄の断崖の上にモンペを穿いた中年の女性がおどおどしていて、手前の米兵がなにやら言っている。(モンペは今の人に通用するんだろうか?)しかし、女性は身を翻して断崖に飛び降りた。女性は死を選んだ。これはやりきれない映像だった。日本の軍部が盛んに言っていた「鬼畜米英」が刷り込まれた悲劇と言える。
そして目にした新聞のこの本の案内。沖縄戦記が気になった。著者のユージン・B・スレッジは、大学を中退してまで海兵隊に入隊した愛国者。
アメリカ第一海兵師団第五連隊第三大隊K中隊所属の歩兵として六十ミリ迫撃砲手となった。戦場の最前線で見聞した日本兵への憎悪や戦友への思いやりに加えアメリカ兵の残虐性も合わせて記述してある。
スレッジが体験した日本兵(ジャップやニップの蔑称がある)への憎悪はどこから来るのか。ガダルカナル上陸作戦後、海兵隊は一人の日本兵を捕虜にした。この捕虜は、自分の部隊は飢えに苦しんでいる。海兵隊が「解放」してくれれば投降するという。
情報将校のゲッチイ大佐と兵25名が現地に向かった。ところが着いてみると待ち伏せ襲撃にあい3名が脱出したという。このだまし討ちが海兵隊に憎悪を植えつけるきっかけになったらしい。
そればかりではない。死んだ振りして手榴弾を投げつける。負傷したふりをしてアメリカ軍衛生兵に救いを求め、近づいてきた衛生兵をナイフで刺し殺す。それに加え真珠湾奇襲攻撃。(当時はこの認識で仕方がない)おかげで海兵隊員たちは日本兵を激しく憎み、捕虜にとる気にもなれなかったと書いている。
さらに、日本兵もまた、われわれアメリカ兵に対しても同様の憎悪を抱いていたに違いない。ペリリュー島と沖縄での戦場体験を通じて、私はそう確信した。彼らは狂信的な敵愾心を抱いていた。つまり、日本兵たちは、現代の人々には理解できないほど強烈に、自分たちの大儀を信じていたのだ。
憎悪と大儀の間に容赦のない残忍で凶暴な戦闘をもたらした。そういう狂信的な戦場で一人ひとりの兵士がどのように耐え抜いたかを理解するためには、海兵隊が戦った戦場の実相を十分考慮すべきだ。 という配慮を見せる。
日本兵の常軌を逸した行動を書いたが、アメリカ兵もそれに劣らず目を覆う行為がある。「ふとそばにいた海兵隊員の動きが気になった。われわれの迫撃砲班の仲間でなく、通りかかりの戦利品のおこぼれにあずかろうしたようだ。
死体らしきものを引きずって近づいてくる。しかし、よく見るとその日本兵はまだ息があった。背中にひどい傷を負って、手が動かせないのだ。さもなければ最後の息が絶えるまで抵抗したに違いない。その日本兵の口元には大きな金歯が光っていた。
問題の海兵隊員は、なんとしてもその金歯が欲しいらしかった。ケイバー・ナイフの切っ先を歯茎に当てて、ナイフの柄を平手で叩いた。日本兵が足をばたつかせて暴れたので、切っ先が歯の沿って滑り、口中深く突き刺さった。
海兵隊員は罵声を浴びせ、左右の頬を耳元まで切り裂いた。日本兵の下顎を片足で押さえ、もう一度金歯をはずそうとする。日本兵の口から血があふれ、喉にからんだうめき声をあげて、のたうち回る。私は、そいつを楽にしてやれよ! と叫んだ。が、返事の代わりに罵声が飛んできただけだった。
別の海兵隊員が駆け寄ってきて、敵兵の頭に弾を一発うち込みとどめを刺した。金歯をあさっている海兵隊員は何か呟いて、平然と戦利品外しの作業を続けた。歩兵にとっての戦争はむごたらしい死と恐怖、緊張、疲労、不潔さの連続だ。そんな野蛮な状況で生き延びるために戦っていれば、良識ある人間も信じられないほど残忍な行動がとれるようになる。われわれの敵に対する行動規範は、後方の師団司令部で良しとされているものと雲泥の差があった」
著者は、パラオ諸島ペリリュー島の戦闘、沖縄の戦闘、共に激戦といわれる地獄を潜り抜けて生還した。しかし、絶えずまとわり着いたのが「恐怖」だった。出撃命令を待つ間、今度の戦闘で命を落とすかもしれない。 という恐怖は何度経験しても払拭できないという。
それでも著者のむすびの言葉は『やがて「至福の千年期」が訪れれば、強国が他国を奴隷化することもなくなるだろう。しかしそれまでは、自己の責任を受け入れ、母国のために進んで犠牲を払うことも必要となる―私の戦友たちのように。
われわれはよくこう言ったものだ。「住むに値する良い国ならば、その国を守るために戦う価値がある」特権は責任を伴うということだ』
最後にノンフクション作家の保坂正康さんの解説によせた言葉が印象的だった。「日本軍の将校、下士官、兵士からこのような内省的な作品が書かれなかったことに、私は改めて複雑な思いを持ったのである」