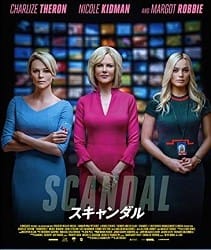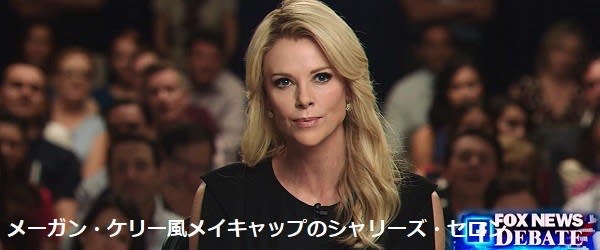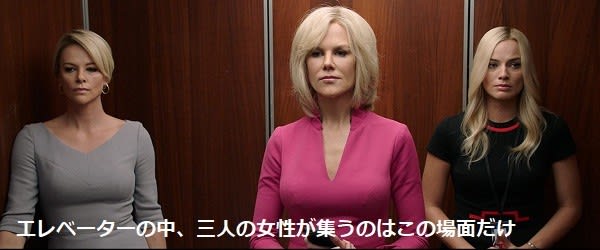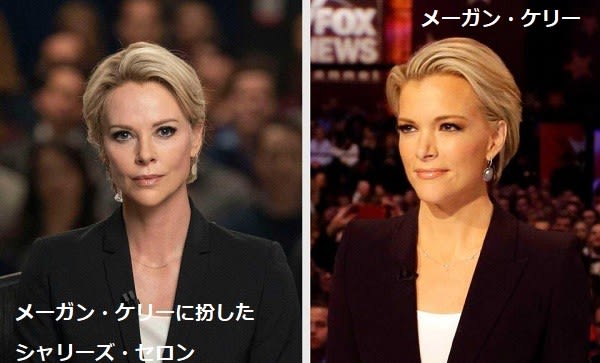1998年、スティーヴン・グリーンリーフの作品を最初に読んだのは「血の痕跡」だった。以来読み続けていて、本作は2002年12月に読了している。
主人公は、私立探偵ジョン・マーシャル・タナーでシリーズとして14編がある。今回再読ということになるが、タナーの実直さや優しさに加え正義感をスティーヴン・グリーンリーフ独特の比喩とユーモアで浮き彫りにする。
タナーにはジルという検事補の恋人がいる。そのジルは「背が高く肌は浅黒くほとんど可愛いといっていい顔立ちだ。瞳は朝顔のように青く輝き、髪はクルミ材の節のように艶やか。鼻筋はサーベルのように優雅なそりを持ち、口は生意気な表情から一瞬にして魅惑の表情に変わる。彼女と一緒にいると私は大男を倒したり、詩を書いたりできる気分になる。離れているときは、一緒にいたいと思う。愛を交わしているときは、彼女の温かみと潤みにまみれたいと願い、それから自分の存在をすべて投げ出して、彼女の肉体と心の密やかな部分に触れられたことへの感謝を示したい」と思う女性なのだ。こんな女性ならタナーに限らず、男はみんな虜になるだろう。
そのジルとの会話。『呼び出し音になかなかでないジルを「仕事中」と思いやって受話器を置こうとしたとき、いら立ちを含んだ声が応答した。
「はい、コッペリア」とジル・コッペリア。
「自宅にいるときは愛想よくしてもいいんじゃないですか、先生」とタナー。「
愛想よくする気分じゃないの」
「話し方にも現れてるね」
「有名人のパーティはどうだった?」
「素晴らしかった。俺はボディガードに向いてるみたいだな」
「皮肉っぽく聞こえるけど」
「作家先生はおれが立っている場所から十フィートほどのところで殺すと脅迫された」
「まさか」
「本当だ」
「どうしてそんなことが?」
「わかったら教えるよ」この逃げ口上にジルは腹を立てた。
「そう。そんならいい。で、何の用なの?」
「ちょっと無愛想すぎないか?」
「無愛想(グラッフ)な気分なのよ。グラッフ、グラッフ」
「よしよし、ファイドー(犬の名前)、電話したのは、今日の《エクザミナー》の記事についてコメントを貰うためなんだ。地元警察の腐敗に関する大陪審の捜査は頓挫しかけている(ファウンダリング)とある。それとも難航している(フラウンダリング)だったか。違いがあるかどうかは分からないけど」
「私のコメントはこうよ。平目(フラウンダー)は魚で、ファウンダーはそうじゃない」
「じゃ、ファウンダーってなんだい?」
「リーランド・スタンフォードみたいな人。スタンフォード大学を創立(ファウンド)したでしょ。スティーヴ・ジョブズもそう。アップル社を創立した」
「ビル・クリントンもだな」
「彼はなんの創立者(ファウンダー)?」
「大統領執務室で彼女を見つけた(ファウンド・ハー)」
大統領執務室で桃色遊戯に耽ったクリントン大統領、相手がモニカ・ルインスキーという実習生。
ジルは「ああ、駄洒落なの。勘弁してほしいわ」
「申し訳ない」
「世の中には赦せないものもあるのよ」
冗談ともいいきれない口調とともに、柳の葉越しにわたる風のようなため息をついた。』という一節がある。
タナーは掛け合い漫才のような会話を、強面の男にも投げかけるという男なのだ。上記の会話の中で作家先生とあるが、それはタナーが依頼を受けた女流人気作家シャンデリア・ウェルズを指す。彼女の身辺警護を受け持っていたが、何者かに仕掛けられた爆弾でシャンデリア・ウェルズは重傷を負う。未然に防止できなかったことで、タナーは責任を感じている。作家のシャンデリアが警察の暗部に肉薄しつつあったこともわかり、それが遠因となって命を狙われた。恋人の検事補ジルと協力して悪徳警官グループを逮捕できた。
日ごろタナーが親身に世話をした老婦人がこの世を去った。その老婦人がタナーに莫大な遺産を残した。恋人ジルと遺産で「最終章」にふさわしいエンディングだった。
人生70歳を過ぎると死が身近に迫り、過去がやたらと思い出されるのもだ。この本もある日のある時突然浮上した。図書館で借りた中まで黄変したハヤカワ・ポケット・ミステリー「最終章」であるが、記憶の中の「最終章」は色褪せていなかった。