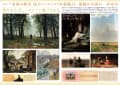ルーベンスの作品は、その躍動感が命だと思う。動きのある人間の姿態は時に劇的にあまりに誇張しすぎるきらいもある。「キリスト昇架」、「キリスト降下」「聖母被昇天」などはどちらかというと抑え気味にした躍動が見るものを感動させる好例だと思う。結構誇張のあまり、危うい均衡を保ってもいるのもあるのではないか。
1604年頃の「パエトンの墜落」(ワシントン・ナショナルギャラリー)は、人も馬も極めて劇的で現実離れした描き方をしている。しかし現実感が保たれた作品である。
日本では「イカロスの墜落」としてブリューゲルに帰せられる作品がある。私はこのイカロスとパエトンとの関係はよくわからない。
図録の解説では、同じくオウィディウスの返信物語に基づいた話として、太陽神アポロの戦車を暴走させたために、太陽の熱で地上が焼き払われ、ジュピターが雷でパエトンを撃ち殺し、戦車の暴走を止める、というもの。
パエトンと馬車の馬が図の右下側に真っ逆さまに墜落している様子が描かれている。雷が右上から中央をとおって左下に貫いている。馬は墜落しつつ遁走し、女神たちは驚愕している。
図録の解説によると闘いの場面を想定しながら描いた可能性があり、イタリアでの学習成果のひとつということになっている。この初期のころからルーベンスの躍動的で劇的な作品の特徴が発揮されたのであろうか。
右下の焼かれた地上よりも雷の光の方が明るくそれで照らし出された光が、劇的な要素をさらに強調しているようだ。その光から外れて一番暗い場面に、雷に打たれたパエトンを配置するという効果が魅力的であると思う。

1638年頃の「聖アンデレの殉教」(カルロス・デ・アンパレス財団)は今回の展示でいちばん印象に残った作品であった。ルーベンスの死の前年の完成で、ルーベンスが60歳を過ぎた頃の作品である。
十二使徒のひとりのアンデレがローマ総督によって十字架に磔にされ、取り巻いた群衆がアンデレの教えに教化され総督を脅したため、総督がアンデレを十字架から下すように命じた。しかしアンデレは降りることを拒否し、天から光が射し、昇天したという言い伝えを描いた作品。
宗教画や神話というのは、信仰しないものには理解が困難な筋も多い。しかし信仰を糧に多くの芸術家がさまざまな解釈を独自に加え、人間的要素、劇的要素を加えて抱負かしたこともまた事実であろう。逆に信仰ゆえに普遍性を喪失したもの、他の信仰を持つものからは敵意を増幅させたものもある。
ルーベンスなどの作品が現代にまで残るのは、信仰に基づく説話や神話に普遍的な人間の要素を加えものが、現代のわれわれに通じる何かをもたらしたということであると理解している。その普遍性に惹かれるものや、現代性を垣間見ることで、私たちは鑑賞している。
アンデレという理想や信念に生きようとした人間の意思のありよう、それをとりまく人間の表情、アンデレの思想に共鳴してしまった総督の妻の存在が右端の総督の表情を困惑と逡巡とで目がうつろである。またアンデレは「聖人であること」にこだわり、その矛盾したともいえる生き様に恍惚としている。
生きて教えを広めるのではなく、死によって思想の正しさを達成せざるを得ない生き方、というのは残念ながら私の選択するところとは違う。総督の右手の力の無さも「どうしてたら良いのか」という逡巡を表わしているようだ。乗っている馬すら戸惑いを見せているようだ。
左端の女性を除いた人物全員が、この劇的な物語の語り部としてどこかでモヤモヤとしたものを語っているようだ。綱とを解いてアンデレを下ろそうとする人物もその行為が完結しないものかしさにいらだち、総督の妻も助けたい意志と助けられない現実、釈放を決断した夫に対する評価とそれが報われない苛立ち、赤子を抱いて傍観しているような女性の不思議そうな表情、さまざまな人物が描きこまれている。
なお、左端の青い布をまとった女性は聖母マリアではないだろうか。あらゆる人間の困惑や戸惑いや悩みを引受けるマリア信仰がここに収斂していると思う。天の光と地上の対極に位置しており、その視線は天の神に向いているというよりも、総督を見ているようでもある。総督が救いの対象であるかのようだ。

ルーベンスの師であるオットー・ファン・フェーンにも「聖アンデレの殉教」(1594-99、シント・アンドリース聖堂)という作品がある。この作品の影響を受けていると解説には記されている。しかし師の作品はあまりに静的で、ドラマ性の感じられない。いかにも中世的な作品である。信仰の場での作品としては成立するのであったろう。しかしルーベンスは、人間としてのドラマを描きたかったのであろう。この作品が現在も生き続ける根拠がわかる。