松本城を散策したあとは、旧制松本高校校舎が保存されている「あがたの森公園」へ。中町通りから周遊バス(グリーンコース)で「旧松本高校」へ。ほんの10分程度だが、歩くにはちょっときつい。4つのコースの周遊バスが20~30分程度の間隔で運用されている松本の交通網は便利でありがたい。
旧制松本高等学校の校舎は、ごく一部が保存されているに過ぎない。昭和40年代まで、松本高校の校舎、学寮などの建築物は解体されたまま、見棄てられた状態だった。廃材として処分される寸前に、保存運動が起こり、教室棟の一部が当時のまま修復、再現され、旧校地を引き継いだ「あがたの森公園」に保存されている。その隣には新たに建てられた「旧制高等学校記念館」があり、たまたま「旧制高校有名教授展」が開催中で、新渡戸稲造、猪木正道などのよく知られた名前が見られた。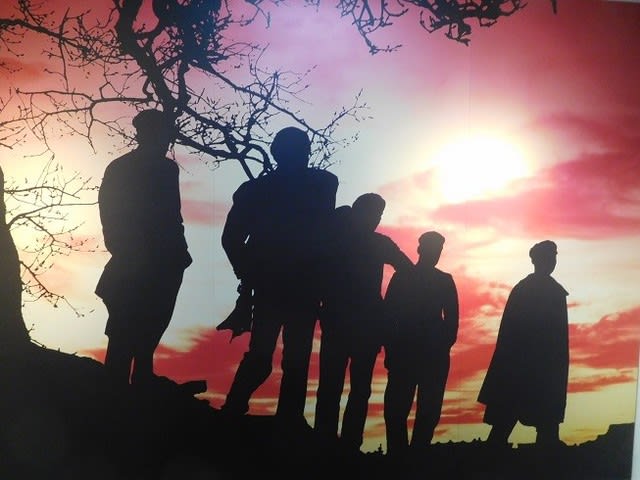
もう30年も前になるだろうか、旧制高等学校卒業生が毎年開く「日本寮歌祭」がTVで放送されていて、それを見た私は「アナクロ(時代錯誤)でおぞましい」と思った。だが、旧制高校体験者がほぼいなくなったいま、この跡地を訪れてみると、全く別の感慨を覚えた。それは月並みなのだが、旧制高校制度の廃止は、日本の弱体化を至上命題とするGHQの占領政策のひとつだったに違いないということだ。
昨今、TVのバラエティ番組などを見ると、早慶程度の卒業者を「高学歴」「名門校」と囃し立てる。国立一期校、国立二期校そして私立大学という明白な序列を知る私のような世代では、かつて二期校だった横浜国立大学経済学部や東京外国語大学が早慶などの私立大学よりも下位にあるなどとは、今でも到底信じられない。その伝で言えば、旧制高校出身者は「大学」と言えば帝国大学であり、私立大学などは「大学のようなもの」としか見ていなかったはずだ。不幸にして旧制高校に入れなかった当時の優秀な学生は、私立大学よりも東京外国語学校などの官立専門学校に進んだ。それらは「大学」とは名付けられていなかったものの、私立大学よりはその質と内容において上位にあったからだ。
そのことを物語るデータを「旧制高等学校記念館」の展示の中に見つけた。

これは各旧制高校の卒業生の進学先(1922-1945年)を示したデータ。これを見て明らかなのは、卒業生の進路は、ほぼ次の官立20大学に限られている。
《帝国大学》8大学
東京、京都、北海道、東北、大阪、名古屋、京城、台北
《医科大学》6大学
新潟医科大学、岡山医科大学、千葉医科大学、金沢医科大学、長崎医科大学、熊本医科大学
《工科大学》2大学
東京工業大学、旅順工科大学
《文理科大学》2大学
東京文理科大学、広島文理科大学
《商科大学》2大学
東京商科大学、神戸商業大学
戦後、旧制高校は廃絶され、その組織は新制国立大学に吸収された。その際、上記の旧制官立大学はすべて国立大学一期校に、そして旧制高校→帝国大学・旧制官立大学(上記の20大学)のライン外にあった官立専門学校は国立大学二期校とされた。
旧制高校は平均して200名程度の少人数で、全寮生活に特色があった。学生たちは、人生や天下国家を論じるとともに、青春の火を燃やした。現在の大衆化社会においては、もはや望むべくもない少人数エリート教育だった。GHQは、このような「古き良き日本」を根絶やしにしたかったのだと思い至る。
名ばかりの大学、羊頭狗肉の大学しか知らない私には眩しいばかりだったが…。























