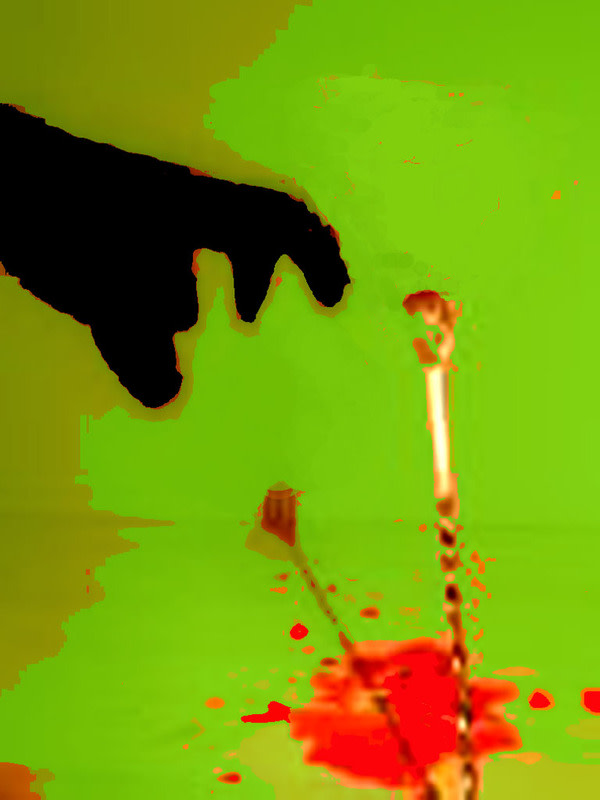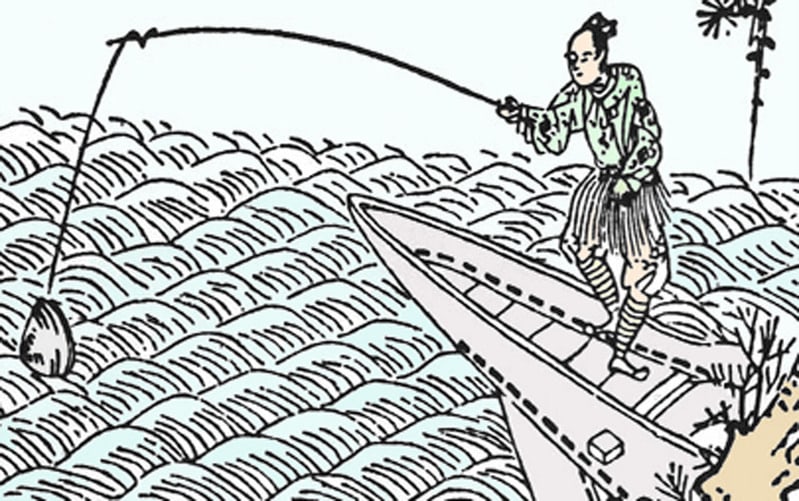都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」

12月22日~23日ごろは、太陽が冬至線の真上に直射する時です。今年は今日です。太陽が一番南に来て低い位置になる為、一年の中で昼の長さが最も短く夜が長くなります。
この頃から寒さもいっそう厳しくなり、いよいよ本格的な冬になるのです。日差しはこの日をさかいに『畳の目一目ずつ』『米粒一粒ずつ』長くなっていくといわれています。
作物だけでなく人や動物達にとっても暖かい太陽の復活はとてもうれしいことです。
西洋のサンタクロースの訪問と同じように、日本でも冬至の日には、「お大師様(おだいしさま)」という人が訪ねて来るという伝承は、全国的にあるそうです。このお大師様は、足が不自由であるとか、子だくさんで貧乏な神であるとか、いろいろな性格を持ったなぞの「客人神(まろうどがみ)」です。
冬至の翌朝は風が吹くそうです。足が悪い「お大師様」の足跡を消すために・・・。
北海道では、そういう話は聞いたことがありません。
まろうど‐がみ〔まらうど‐〕【▽客神/▽客▽人神】
他の地域から来訪し、その土地で信仰されるようになった神。きゃくじん。
大辞泉
この日には皆さんのお家でも「かぼちゃ」を食べたり、夜はお風呂にゆずをたくさん浮かべて「ゆず湯」を楽しんだりしますか?
この時期になぜ「かぼちゃ」や「ゆず湯」なのでしょう。
もともと「かぼちゃ」は夏の野菜です。今では季節を問わず、どのような野菜でも簡単に手に入れることが出来ますが、昔は冬の寒い季節の野菜不足を補うものとして保存が利き、体内でビタミンに変化するカロチンの豊富に含まれている「かぼちゃ」はとても貴重な栄養源だったのです。
『冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない(中風にならない)』と言われるのもこのような理由があるのです。
そのほかにも、「皮膚」や「粘膜」、「視力」、「骨」や「歯」にも効果があるそうです
また、この頃を過ぎると「かぼちゃ」が腐りだすので食べきろうという意味もあったようです。
また、「ゆず」にはビタミンCの他にリモネンという成分が含まれているので、お肌もすべすべになるだけでなく新陳代謝を活発にするので、体も温まり風邪も引きにくくなるのです。
寒い冬を元気に過ごすために、昔の人の知恵がつまった行事なのですね。
北海道十勝では、「かぼちゃ汁粉」というものを食べます。十勝は「赤いダイヤ」といわれた豆の国、小豆の産地ですから・・・。これは、汁粉の餅を塩茹でのかぼちゃに置き換えたものです。
小豆の主成分はデンプンとタンパク質で、ビタミンはB1を多く含んでいます。
また、ビタミンB2、ニコチン酸、カルシウム、リン、鉄なども含有しています。なので。「かっけ」、「はれもの」、「低血圧」、「疲労回復」、「二日酔い」、「筋肉痛」、「肩こり」などに効果があります。
みなさんの地域の「冬至」には、何か特徴がありますか?
したっけ。
「徐福」は秦始皇帝の命令で不老長寿の妙薬を求めて日本に渡り、各地に地名や伝説などが残っているものの結局は見つけられなかったといわれています。
また、「徐福」が捜し求めた不老長寿の妙薬は「天台烏薬」ではないかとも言われています。
テンダイウヤク
和名:天台鳥薬/別名:ウヤク/生薬名:鳥薬(うやく)/天台鳥薬(てんだいうやく)
学名:Lindera strychnifolia
中国中部原産:日本に渡来したのは享保年間(1716~1736)
冬から初春にかけて、根を掘り取り塊根(かいこん)部を水洗いしてから日干しにして乾燥させます。
テンダイウヤクの根は、棒状のものと塊根(かいこん)のものがあり、棒状より塊根の方が芳香(ほうこう)成分が多く良品とされています。
この塊根を乾燥したものを、生薬(しょうやく)で鳥薬(うやく)、天台鳥薬(てんだいうやく)といいます。
天台鳥薬(てんだいうやく)は、中国の天台山で産出されるものが一番効き目があり貴重ということで、天台鳥薬(てんだいうやく)と言われています。
鳥薬(うやく)は、神経性胃腸炎、腸管癒着(ゆちゃく)による軽度の通過障害などに見られる、臍(へそ)周辺の疼痛(とうつう)、腹鳴、泥状便などの症状がある場合に適しています。
また、月経痛にも用いていて、月経の後半に疼痛(とうつう)がある場合には、沈香、延胡索(えんごさく)、当帰(とうき)、肉桂(にくけい)を配合して、月経前の腹痛には、木香(もっこう)、縮砂(しゅくしゃ)、香附子(こうぶし)を配合します。
芳香(ほうこう)性健胃薬、鎮痛薬として1日量5~10グラムを水0.5リットルで煎じて、約2分の1量まで煮詰めて服用します。
健胃(けんい)整腸、腸蠕動(ぜんどう)の促進作用は木香(もっこう)の作用より効果があります。
何故、「天台烏薬」が不老不死の薬と言われたか定かではないそうです。
不老長寿の霊薬が「天台烏薬」だとしたら、原産国は中国で、日本には後世・江戸時代になって移入されています。辻褄が合いません。
不老長寿薬その他の候補
カンアオイ
和名:寒葵/生薬名:土細辛(どさいしん)
学名:Asarum kooyanum var. nipponicum
本州の関東と中部地方の山地の樹下。日本、中国中部以東に分布。
秋から冬の開花期に、地下の根茎と根を掘り取って水洗いして、陰干しにします。
これを、生薬名の土細辛(どさいしん)といいます。
土細辛(どさいしん)は、咳止めに1回5~10グラムの土細辛に、水0.3グラムを加えて、煎じながら約半量まで煮詰めたものをこして服用します。
これは、根茎(こんけい)および根に含まれる、精油(せいゆ)とアミノ酸のピペコール酸によって鎮咳(ちんがい)作用があることが証明されています。
佐賀市金立地区では徐福が探した不老不死薬は「クロフキ」、「フロフキ」と呼称される「カンアオイ」と言い伝えられているそうです。徐福長寿館中央ホールの徐福像を囲むようにして十数種250鉢が、展示された。(2005.4.17徐福長寿館)
今から2200年前、中国が秦(紀元前778年 - 紀元前206年)の時代に「徐福(じょふく)」という人物がいました。
 まだ、日本が縄文時代から弥生時代へと変わろうとしていた頃の話です。
まだ、日本が縄文時代から弥生時代へと変わろうとしていた頃の話です。
司馬遷(紀元前145~86年)の『史記』によると、「徐福」は「斉の国(始皇帝によって滅ぼされた国で現在の山東省あたりにあつた)」の「方士(ほうし」という身分だということです。
「方士」とは、呪術師であり、医薬、天文、他の学問にも精通していたもののことらしいのです。
紀元前210年のことです。「徐福」(前259~前208?) は「始皇帝」(前259~前210)に、はるか東の海に「蓬莱(ほうらい)」・「方丈(ほうじょう)」・「瀛洲(えいしゅう)」という「三神山」があって仙人が住んでいるので不老不死の薬を求めに行きたいと申し出ました。この願いが叶い、莫大な資金を費やして一度旅立ちました。
しかし、数年経っても仙薬を手に入れることはできませんでした。このまま帰れば皇帝は怒り、殺されてしまうかもしれません。そこで、徐福は偽りの報告をします。
「出航したものの大鯨に苦しめられ、行き着くことができませんでした。」(台風を大鯨にたとえたのかもしれない)
さらに、「徐福」は言いました。
「私は海上で海神と出会いました。海神に不老不死の仙薬を探していると話したところ、海神はこう申されました。『おまえの主君の礼が足りないから仙薬を手に入れることができないのだ』。そのあと私は海神に蓬莱山にある宮殿に連れて行かれました。そこで、海神に仙薬を手に入れるにはどうしたらいいかと尋ねました。すると、海神は『童男童女(若い男女)と道具や技術を献上しなさい』と言われました。」
これを聞いた始皇帝は、「そんなことであったか・・・」と大変喜びました。
紀元前219年、始皇帝は「徐福」に「童男童女(若い男女)3、000人」、「米・麦・粟・キビ・豆」などの五穀の種、農具、武具や造船、航海、養蚕などの技術者をつけて、再度航海に出しました。これを「五穀百工」といいます。
佐賀県に伝わる『金立山物語』によると、男女500人となっています。(中国人は大袈裟に言う傾向があるので、どちらが本当かは分かりません)
そして、何日もの航海の末にどこかの島に到達しました。実際、「徐福」がどこにたどり着いたかは不明ですが、「平原広沢(へいげんこうたく/広い平野と湿地)」の王となって中国には戻らなかった」と中国の歴史書に書かれているそうです。
この「平原広沢」が日本であるともいわれています。
実は中国を船で出た「徐福」が日本にたどり着いて永住し、その子孫は「秦(はた)」と称したとする「徐福伝説」が日本各地(佐賀県、鹿児島県、宮崎県、三重県熊野市、和歌山県新宮市、山梨県富士吉田市、京都府与謝郡、愛知県など)に存在するそうです。
秦氏(はたうじ)
『日本書紀』で応神天皇14年(283年)に百済より百二十県の人を率いて帰化したと記される弓月君を秦氏の祖とする。『新撰姓氏録』によれば秦の始皇帝の末裔とされるが、その真実性には疑問が呈せられており、その出自は明らかではない。
Feペディア
もともと「徐福」は不老不死の薬を持って帰国する気持ちなどなかったかもしれません。「万里の長城」の建設で多くの民を苦しめる「始皇帝」の政治に不満をいだき、東方の島、新たな地への脱出を考えていたかもしれません。
「徐福」らの大船団での旅立ちは一種の民族大移動かもしれないのです。
後に「徐福」に騙されたと知った始皇帝が、中国に残った徐福の親族を迫害したのは言うまでもありません。
「徐福」は中国を出るとき、「稲など五穀の種子と金銀・農耕機具・技術(五穀百工)」も持って出たと言われます。一般的に稲作は弥生時代初期(徐福以前)に大陸や朝鮮半島から日本に伝わったとされますが、実は徐福が伝えたのではないかとも考えられるそうです。
「徐福」が日本の国つくりに深く関わる人物だったのかもしれません。中国には、「徐福」が「神武天皇」だとする説もあるそうです。
だとしたら、「徐福」は日本人のルーツかも知れないのです。
どうです。弥生時代に文明を持った人間がやってきたとしたら、彼らを神だと思っても不思議はありません。日本神話の神々は彼らだったのかもしれません。
しかし、「徐福」という名は歴史の教科書にも登場しないので日本人には馴染みがありません。
実在したかどうかもわからない人物が歴史に登場しないのは当然かもしれません。
今から2000年以上も前のことなのに、江戸時代にあったことかと思ってしまうような話として伝わっているものもあるそうです。
このように、徐福は長い間中国でも伝説上の人物でした。
しかし、1982年、江蘇省において徐福が住んでいたと伝わる徐阜村(徐福村)が存在することがわかり、実在した人物だとされました。
「斉の国 琅邪 (現在は山東省) 江蘇省 連雲港市かん楡(ゆい)県金山郷徐阜村」
そして、徐阜村には石碑が建てられました。驚くことに、その村には現在も徐福の子孫が住んでいるそうです。代々、先祖の徐福について語り継がれてきたそうです。大切に保存されていた系図には徐福が不老不死の薬を求めて東方に行って帰ってこなかったことが書かれていたそうです。
又使徐福入海求神異物、還為偽辭曰:『臣見海中大神、言曰:「汝西皇之使邪?」臣答曰:「然。」「汝何求?」曰:「願請延年益壽藥。」神曰:「汝秦王之禮薄、得觀而不得取。」即從臣東南至蓬萊山、見芝成宮闕、有使者銅色而龍形、光上照天。於是臣再拜問曰:「宜何資以獻?」海神曰:「以令名男子若振女與百工之事、即得之矣。」』秦皇帝大?、遣振男女三千人、資之五穀種種百工而行。徐福得平原廣澤、止王不來。
? 司馬遷 「淮南衝山列伝」『史記』巻118。
この壮大な話は聖書の「ノアの方舟」のようで、歴史ロマンを感じます。
「徐福」という名前は“haruさん”に教えていただいて初めて知りました。面白いのでまだ続きます。
したっけ。
「おむすびころりん」は、日本のおとぎ話の一。「鼠の餠つき」「鼠浄土」「団子浄土」などともいう。
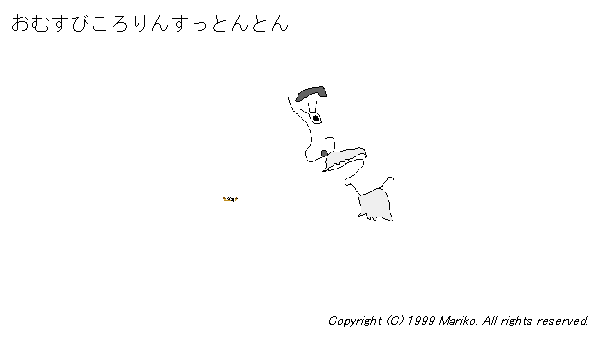 山でおむすびを穴に落としてしまったおじいさん。穴に入るとネズミたちがいて、帰りに宝物を持ち帰ります。
山でおむすびを穴に落としてしまったおじいさん。穴に入るとネズミたちがいて、帰りに宝物を持ち帰ります。
そのことを知った隣のおじいさんは、同じように山に行ってネズミの穴に入りますが、ネズミたちを驚かしたため、闇の世界に閉じ込められてしまいます。
※動画は「Welcome to Mriko Home」さんからお借りしました。クリックすると動きます。
「おむすび ころりん すっとんとん」 のフレーズで御馴染の噺です。
「おむすびころりん」の話は様々なバリエーションが存在します。
・ネズミはおじいさんに噛み付いたので、おじいさんは降参した。
・ネズミが浄土の明かりを消してしまったために、そのままおじいさんが3年3ヶ月のあいだ行方が知れなくなった。
・そのままおじいさんがねずみもち(もぐら)となった話などがみられる。
また、「ねずみ浄土」と「おむすびころりん」は別々の昔話として区分している書籍もあるのだそうです。
話にこのようなバージョンが存在するのは、今日みられる暴力的表現を排斥しようとする運動の影響が強い。
古くからある口承文芸で室町時代に『御伽草子』として成立したと見られる。あらすじの特徴は「こぶとり爺さん」と同じく、無欲な老人と強欲な老人の対比であり、因果応報など仏教的要素も併せ持つが、『グリム童話』にある「ホレ婆さん」との類似性も指摘されているとおり、筋立てはありふれたもので独自性は見られない。特徴的なのは異界の住人であるネズミが善人に福をもたらすという筋立てであり、ネズミは「根の国の住人」(根住み)とも見られており、米倉などにあるネズミの巣穴は黄泉の国、浄土への入り口と言い伝えられる地方がある。
またこの話は鼠を神の使い、あるいは富をもたらす者とする民間の観念が反映されている。この昔話のような鼠の世界が地中にあるとする観念は、古くからあり室町時代物語の『鼠の草子』や『かくれ里』にも克明に描写されている。
この話の中で歌われる鼠の餅搗き歌は地方によって変化があり、土地によっては<鼠とこびきは引かねば食んね、十七八なるども、猫の声は聞かないしちょはちょちょ>(新潟県)のように実際の民謡が盛り込まれている例もある。
一般的に「ねずみ浄土」・「おむすびころりん」の名でよく知られているこの話は、異郷訪問譚に分類されます。地下にあるネズミの楽園を訪ねて財宝をもらってくる昔話で、全国に分布し、特に東北と中国地方に多くの類話がみられます。東北地方では豆が、関西以西(南)では団子がころがり落ちる話の方が多く、九州地方では団子が穴に落ちていく音が強調されています。(例だだごろ、だだごろ、すってんとん)
 この話が全国的に巾広く分布している背景(・ネズミは神にかかわる動物(俗信)・生活苦のない豊かな浄土への憧れとものを貯えるネズミの習性との結合)「地蔵浄土」は「鬼の博打」とも呼ばれ、主人公が地下の地蔵の所へ導かれ、金や宝を得て帰ってくる昔話で、地蔵は現実と冥界の境に立つ人を救うといわれています。
この話が全国的に巾広く分布している背景(・ネズミは神にかかわる動物(俗信)・生活苦のない豊かな浄土への憧れとものを貯えるネズミの習性との結合)「地蔵浄土」は「鬼の博打」とも呼ばれ、主人公が地下の地蔵の所へ導かれ、金や宝を得て帰ってくる昔話で、地蔵は現実と冥界の境に立つ人を救うといわれています。
全国的に分布する「ねずみ浄土」の方が古いと考えられますが、異質の秩序の支配する異郷へ、そこの住人の案内、あるいは無邪気にまよいこんだ結果、不思議が起こるというモチーフは共通でどちらの話にも、まねをして無理やり異郷を訪問して失敗する隣の爺婆型(舌きり雀・こぶとり爺さん等)の話がついています。
では、「ねずみ浄土」のお話を紹介しましょう。
「ねずみの浄土.」
ある所に与兵衛とお房という仲の良い老夫婦がおりました。
与兵衛さんは、朝、目を覚ますと、「ほい、ほっほっ、ほい、ほっほっ。」と体を動かし、お房さんとあさげをとりました。与兵衛さんは箱膳に箸をしまうと、
「ではら、お房、いってくらぁ。」
といいます。するとお房さんは
「はい、いってくらせ。」
とおにぎりを三つ渡します。
こうして毎日、与兵衛さんは、お房さんの握ったおにぎりをもって山や畑に出かけました。
春、彼岸の日、与兵衛さんは山菜を取りに山に入りました。背負い籠の中に、ぜんまいやら蕨(わらび)やら、たくさんとれたので、ちょうど良いあんばいの石に腰掛けて、お弁当をひろげました。
するとおにぎりがひとつ、与兵衛さんのひざから転がり落ちました。
「ああっ、お房のおにぎり…。」
おにぎりはコロコロコロところがっていき、与兵衛さんは慌てて追いかけていきました。
「おにぎり 待て待て ほいほっほ。」
「コロコロ コロリン コロコロリン。」
「待て待て おにぎり ほいほっほ、待て待てほっほ 待てほっほ。」
「コロリン コロコロ コロコロリン。」
おにぎりはコロコロと草むらをころがり、木の枝をピョ~ンとはね、切り株の下にある穴に転がり落ちました。
与兵衛さんは切り株の穴に手を入れて、おにぎりを探しました。穴の中は広く、与兵衛さんの手はどこにも届きませんでした。与兵衛さんが不思議に思っていると、
「コロコロ コロコロ おにぎりっこ。もっとくれろ、もっとくれ。」
と穴の中から聞こえてきました。
不思議に思った与兵衛さんは、おにぎりをもう一つ、穴の中に入れました。するとおにぎりは、コロコロと転がって、穴の中に消えていきました。
しばらくすると、また穴の中から声が聞こえてきました。
「コロコロ コロコロ おにぎりっこ。 うんめぇかった、うめかった。じじさ、こっちにおいでなさい。」
与兵衛さんは、どこから声がしたのかと、穴の中を覗きました。しかしあたりは真っ暗で何も見えません。与兵衛さんはもっとよく見ようとぐいっと身をのり出しました。
その瞬間、与兵衛さんは穴の中へコロコロコロと転がり込んでしまいました。
しばらくすると与兵衛さんは、穴の底にいました。そこにはお地蔵様がおられました。
「ほへっ? お地蔵様がおらを呼ばれたのかな? なら、おにぎりを転がして失礼しました。ここにもうひとつ、泥のついてないおにぎりがあるすけ、どうぞ、許してくらせ。」
与兵衛さんは残っていたおにぎりをお地蔵様に供えました。すると、穴の奥からもう一度、与兵衛さんを呼ぶ声がしました。
「じじさ じじさ うめかった。 こっちにおいで、おいでなさい。じじさ、じじさ、おいでなさい。」
与兵衛さんはびっくりしてお地蔵様を見ました。するとお地蔵様は目を開けられると、
「与兵衛さん、与兵衛さんを呼んだのは私ではない。この穴の奥に住むものがよんだのじゃ。」
「お地蔵様。」
与兵衛さんはお地蔵様が話されたのできょとんとしました。
「よいか、与兵衛さん。この奥に行きなされ。しかし、けっして猫の鳴きまねをしてはいけませんよ。」
お地蔵様はそう言うとまた目を閉じられました。
与兵衛さんはしばらくぼんやりしていましたが、「わかりました、お地蔵様。」と言うと奥の方へ向かって歩いていきました。
しばらく歩くと穴の中が薄ぼんやりと明るくなってきました。するとまた、声が聞こえてきました。
「じじさ、よくおいでくださいました。」
与兵衛さんは声のする足下を見ると、ネズミが三匹頭を下げていました。
「わしを呼んだのは、お前さま達かね?」
「はい、わたすたちです。 おにぎりっこ、うめかった。ちょど、まま焚くひまもなくて困っておりました。ありがたくいただきました。」
与兵衛さんが耳をすますと。チュチュチュ、チュチュチュと、ちいさな泣き声がします。
「おらとこのムスメッコが三人。」
「おらとこのムスメッコも二人。」
「おらとこなぞ五人もムスメッコが産気づいてしまって、今、やっと、産み終えたばっかりさ。」
「・・・それは難儀な事でした。」
与兵衛さんはネズミ達の話にすこしびっくりしました。
「で、じじさ、これからお祝いのお餅つきをしますさ。じじさも一緒にお祝いしてもらえないだろかね?」
与兵衛さんは、目を細めて答えました。するとあたりにぽつぽつちいさな明かりがつきました。それはネズミのぼんぼりでした。穴の中にはたくさんのネズミの家があり、のきが幾重にも重なって、京の都がすっぽり穴の中にはいっているようでした。そこからゾロゾロたくさんのネズミが出てきて、お祝いの餅つきがはじまりました。
「にゃんごおらねば、ネズミの世ざかり、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。 鈴の音ならねば、ネズミの天下、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。 百になっても、二百になっても、にゃんごの声などきぎだくね。 ほいほいポポポン、ほいポポポン。」
つき終わったおもちは姉御かぶりのネズミ達が、小豆餅だの麦こがしだの、いろんなおもちをポコポコと、次々に作っていきました。
与兵衛さんはネズミのあまりの数の多さに目をぱちくりし、次々につきあがるおもちに、またまたびっくりしました。しばらくすると、ムスメッコのネズミ達が赤ちゃんを連れて与兵衛さんに挨拶に来ました。赤ちゃんネズミは、「ちゅ。」と鳴きました。一匹、二匹、三匹と、「ちゅ。」「ちゅ。」「ちゅ。」と鳴きました。 十人のムスメッコの赤ちゃんたちは、全部で二百四十八おりました。与兵衛さんは、ネズミ達と一緒に、小さなお餅を食べ、赤ちゃんネズミのお祝いをしました。
さっきの親ネズミが三匹、大判やら小判やら金銀の大粒小粒を持ってきました。
「じさま、これは面白くて引いては来たものの、わしらには使い道の無いものです。持って帰って使ってくだされ。」
そう言ってネズミ達は与兵衛さんを家まで送りました。家に帰ると与兵衛さんはお房さんに、ネズミのお産の話をしました。するとお房さんは、次の日からおにぎりをおじいさんの分と、赤ちゃんネズミの分を作って、与兵衛さんに渡しました。
それから与兵衛さんは毎日穴の前におにぎりを置いておくようになりました。与兵衛さんがおにぎりを切り株の穴の前に置いておくのを見て、隣の弦蔵おじいさんは不思議に思いました。そして婆さまに、与兵衛さんは、なんしてあんな事をするのか、隣へ行って聞いてこいと言いました。
そしてお房さんからネズミのお産の事を聞くと、自分もちょっと真似してみようかと、婆様におにぎりこさえてもろうて、穴の前に行きました。
弦蔵さんは与兵衛さんの置いたおにぎりをはねのけると、自分の持ってきたおにぎりを穴の中に転がしました。するとおにぎりは入り口の所に、グシャリとつぶれてしまいました。
腹を立てた弦蔵さんはつぶれたおにぎりを穴の中にけり入れました。弦蔵さんはしばらく耳をすませていましたが、何も聞こえて来ません。弦蔵さんはおにぎりをもう一つとりだすと穴の中に蹴り入れました。すると足下が崩れ弦蔵さんは穴の中にどどどどっと落ち、何かにゴツンと頭をぶつけました。
「あたたたたたた。」
弦蔵さんは頭をかかえていました。見るとぶつかったのはお地蔵様でした。
「なしてこんなところに、お地蔵さんがおる?」
弦蔵さんは頭をかきかき、残ったおにぎりを自分で食べてしまいました。すると、弦蔵さんの後ろで、お地蔵様が目を開けられ、
「弦蔵さん、けっして猫の鳴きまねをしてはいけませんよ。」
と言ってまた目を閉じられました。弦蔵さんは誰が何を言ったのかわからず、きょとんとしていました。
すると穴の奥の方から声が聞こえてきました。
「にゃんごおらねば、ネズミの世ざかり、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。」
話に聞いたネズミの餅つき歌でした。弦蔵さんは声のする方へ頭をゴンゴンぶつけながら進みました。弦蔵さんが穴の奥にいくと、たくさんのぼんぼりの下に、着飾った小さなネズミ達がたくさん、千歳飴を持って座っていました。
その前でネズミ達が大勢でおもちをついていました。どうやらネズミの七五三のようでした。
「鈴の音ならねば、ネズミの天下、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。 百になっても、二百になっても、にゃんごの声などきぎだくね。 ほいほいポポポン、ほいポポポン。」
弦蔵さんはここが与兵衛さんの来た所だと思いました。ここには小判や金銀の大粒小粒がたくさんある。弦蔵さんはハッとしました。そうだ猫の鳴き声をするんだ。
弦蔵さんは大きな声で猫の鳴きまねをしました。
「うにゃあぁあぁ~~~っごぉ。」
歌がぱたっとやみ、ぼんぼりの明かりが消えてあたりが突然真っ暗になってしまいました。
「・・・・・・・あっ。」
弦蔵さんがびっくりしていると、 暗やみの中に、ネズミ達がチュチュ~~~ッと、どこかへ走り去る声が聞こえました。
弦蔵さんは真っ暗な穴の中でぽつんと一人、もうどうにもなりませんでした。
弦蔵さんは次の日、おにぎりをもってきた与兵衛さんに助けだされました。
与兵衛さんは切り株の中に入って見ましたが、中は崩れていて、もう先には進めませんでした。お地蔵様もネズミ達もみつかりませんでした。
「ネズミ達はどこに行ったのかね?」
与兵衛さんはお房さんに聞きました。
お房さんはお茶をすすりながら、
「もしかすたら、また、どこかの切り株の下で、にゃんごの声などきぎだくね。と、お餅をつきながら、歌ってるかもしれねぇな。」と答えましたとさ。
したっけ。
 貧しい少女カーレンは、病気の母親と2人暮らしえした。ある日、靴を持たない彼女は足に怪我をしたところを靴屋のおかみさんに助けられ、赤い靴を作ってもらいます。
貧しい少女カーレンは、病気の母親と2人暮らしえした。ある日、靴を持たない彼女は足に怪我をしたところを靴屋のおかみさんに助けられ、赤い靴を作ってもらいます。
その直後、看病も虚しく母親は死んでしまったのです。カーレンは母親の葬儀に赤い靴を履いて出席し、それを見とがめた老婦人は彼女の境遇に同情して養女にました。
それからカーレンは、勉強をしたり、お裁縫(さいほう)を習ったりしながら、楽しく暮らしました。昔の貧乏な暮らしが、まるで嘘のような、すてきな毎日です。
それから、何年か経ちました。
カーレンも、そろそろ、大人の仲間入りをする年頃になりました。
裕福な老婦人のもとで育てられたカーレンは、町一番の美しい娘に成長していました。ある日、靴屋の店先に綺麗な赤い靴を見つけたカーレンは、老婦人の目を盗んで買ってしまいました。
「カーレン。教会は黒い靴をはいていくものです。赤い靴をはいていってはいけませんよ」
戒律上無彩色の服装で出席しなければならないはずの教会にも、その赤い靴を履いて行き、老婦人にたしなめられました。
それでもまたは教会に赤い靴を履いていきました。
教会では大勢の人たちが、羨ましそうに自分の靴を見ているように思えて、とても嬉しかったのです。
・・・みんな、わたしの靴を見ている。
皆は、赤い靴を穿いているカーレンを軽蔑していたのです。
ある日、カーレンは、ダンスパーティーに招かれました。
老婦人が死の床についているというのに、看病もしないで、カーレンはその靴を履いて舞踏会に出かけようとしたのです。
そして赤い靴をはいて、パーティーに出かけようとして歩き出したとたん、大変なことがおこりました。
「わあ、とまらない、とまらないわ!」
やめようと思っても、自分ではどうにもなりません。
まるで靴のいうなりになってしまったように、外へ踊り出したのです。
カーレンは、踊りながら町を出て、とうとう暗い森の中へ入っていきました。
すると木陰に、赤いひげをはやした気味の悪い魔法使いの老人がたっていて、
「ほほう、なんときれいなダンス靴だ」
と、いうと、カーレンの踊りは、いよいよ激しくなりました。
カーレンは死ぬまで踊り続ける呪いをかけられたのでした。そしてそれから、カーレンは昼も夜も、晴れた日も雨の日も、森や野原を踊り続けました。
何日過ぎたでしょうか。
もうフラフラになって、もといた家のそばまで踊りながらきた時、カーレンは、お婆さんのお葬式にであいました。
カーレンは、胸が張り裂けそうになって、泣きだしました。
あの優しかった老婦人が死んでしまったのは、自分のせいだと思ったからです。
「ああ、お婆さん、ごめんなさい。・・・神さま、どうか、どうかこの愚かな私を、お許し下さい」
身も心も疲弊してしまう。
 カーレンは、とうとう呪いを免れるため首斬り役人に依頼して両足首を切断してもらいました。すると切り離された両足と赤い靴はカーレンを置いて、踊りながら遠くへ去ってしまったのです。
カーレンは、とうとう呪いを免れるため首斬り役人に依頼して両足首を切断してもらいました。すると切り離された両足と赤い靴はカーレンを置いて、踊りながら遠くへ去ってしまったのです。
心を入れ替えたカーレンは不自由な体で教会のボランティアに励む毎日を送りました。ある日、あたりにサーッと、まばゆい光がさしてきました。
そして光の中に、まっ白な服をきた天使(てんし)がたっていて、カーレンにほほえみました罪を赦されたことを知ったカーレンは、法悦のうちに天へ召されていったのです。
アンデルセンは何故、カーレンに両足を切断するという、非常に惨い終焉を用いたのでしょう。踊り続けなければならないという仕打ちから逃れるため、もっと酷い両足切断という仕打ちをこれでもかと与えたのでしょうか。
教会のボランティアとは両足と交換するほど大切な事なのでしょうか。とても子供向けとは思いません。これも大人向けの話なのだと思います。
したっけ。
「眠れる森の美女(仏語La Belle au bois dormant)」のタイトルで有名ですが、グリム童話では「茨姫」となっています。
よく姫が眠っていると誤解されますが、dormantは男性系の形容詞なので眠っているのは美女でなく、森だそうです。
 あるところに子どもを欲しがっている国王夫妻がいた。ようやく女の子を授かり、祝宴に一
あるところに子どもを欲しがっている国王夫妻がいた。ようやく女の子を授かり、祝宴に一 人を除き国中の12人の魔法使いが呼ばれた(13は不吉な数字であった為と見られる、またメインディッシュのため賓客に供する金の皿が12枚しかなかった為とも)。魔法使いは一人ず つ贈り物をする。宴の途中に、一人だけ呼ばれなかった13人目の魔法使いが現れ、11人目の魔法使いが贈り物をした 直後に“王女は錘(つむ:糸を紡ぐ機械の付属具)が
人を除き国中の12人の魔法使いが呼ばれた(13は不吉な数字であった為と見られる、またメインディッシュのため賓客に供する金の皿が12枚しかなかった為とも)。魔法使いは一人ず つ贈り物をする。宴の途中に、一人だけ呼ばれなかった13人目の魔法使いが現れ、11人目の魔法使いが贈り物をした 直後に“王女は錘(つむ:糸を紡ぐ機械の付属具)が 刺さって死ぬ”という呪いをかける。まだ魔法をかけていなかった12人目の魔法使いが、先の魔法を修正し「王女は錘が刺さっても百年の間眠るだけ」という呪いに変える。
刺さって死ぬ”という呪いをかける。まだ魔法をかけていなかった12人目の魔法使いが、先の魔法を修正し「王女は錘が刺さっても百年の間眠るだけ」という呪いに変える。
王女を心配した王は、国中の紡ぎ車を燃やさせてしまう。王女は順調に育っていくが、15歳の時に一人で城の中を歩いていて、城の塔の一番上で老婆が紡いでいた錘で手を刺し、眠りに落ちる。呪いは城中に波及し、そのうちに茨が繁茂して誰も入れなくなった。侵入を試みた者もいたが、鉄条網のように絡み合った茨に阻まれ、入ったはいいが突破出来ずに皆落命した。
100年後。近くの国の王子が噂を聞きつけ、城を訪れる。王女は目を覚まし、2人はその日のうちに結婚、幸せな生活を送った。(115歳の老婆と?)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
以上がみなさんの良く知っている物語ですが、この物語の元になったとされる民話を紹介しましょう。この物語の残酷な場面は削除され「茨姫」が生まれたのです。
ジャンバティスタ・バジーレ(Giambattista Basile, 1575年? - 1632年2月23日)は、イタリアの詩人・軍人である。説話集『ペンタメローネ(五日物語、Pentamerone)』の作者として知られている。『ペンタメローネ』はヨーロッパにおける童話集のさきがけとなった。「太陽と月のターリア」は『ペンタメローネ』の中の一つで、ナポリ地方に昔から伝わる説話です。
太陽と月のターリア

 昔、一人の王がありました。娘のターリアが生まれた時、王は国中の賢者や占い師を呼び集めて娘の未来を予測させました。占い師たちは何度も相談を重ねてから、「亜麻の繊維に混じったトゲがこの子に大きな災いをもたらすでしょう」と告げました。そこで王は何とか災難を免れようと思い、「亜麻も大麻も麻の類は一切 我が館に持ち込んではならぬ」と厳しい命令を下したのです。
昔、一人の王がありました。娘のターリアが生まれた時、王は国中の賢者や占い師を呼び集めて娘の未来を予測させました。占い師たちは何度も相談を重ねてから、「亜麻の繊維に混じったトゲがこの子に大きな災いをもたらすでしょう」と告げました。そこで王は何とか災難を免れようと思い、「亜麻も大麻も麻の類は一切 我が館に持ち込んではならぬ」と厳しい命令を下したのです。
 ところが、ターリアが大きくなったある日、窓辺に立っていると、外を糸紡ぎのお婆さんが通っていきました。ターリアはそれまで糸巻き竿や紡錘(つむ)を見たことがありませんでしたし、くるくる踊っているところがとても面白そうでしたので、好奇心に駆られておばあさんを呼び入れ、糸巻き竿を手にとって糸を縒り始めました。
ところが、ターリアが大きくなったある日、窓辺に立っていると、外を糸紡ぎのお婆さんが通っていきました。ターリアはそれまで糸巻き竿や紡錘(つむ)を見たことがありませんでしたし、くるくる踊っているところがとても面白そうでしたので、好奇心に駆られておばあさんを呼び入れ、糸巻き竿を手にとって糸を縒り始めました。
その途端、麻に混じっていたトゲが爪の間に突き刺さり、たちまちターリアは床に倒れて死んでしまいました。これを見るとお婆さんは階段を駆け下りて逃げていきました。
哀れな王は、この苦い悲しみを樽いっぱいの涙で飲み干しました。それから死んだ娘を別荘の安楽椅子に座らせましたが、その椅子にはビロードが張ってあり、金襴で作った天蓋がついていました。やがて戸という戸を閉め切ると、忌まわしい記憶を二度と思い出さないよう、永遠に、この森の中の館から立ち去ったのです。
さて、それからしばらく経ったある日のこと。この辺りに別の王が鷹狩りにやって来ましたが、王の鷹が例の館の窓から中へ飛び込んでしまいました。いくら笛を吹いても呼んでも出てこないので、王は館の門を叩かせました。しかし、誰も出てきません。王はぶどう摘みの梯子を持ってこさせて門を乗り越え、中の様子を自分で調べ始めました。全く人気がないのに驚きましたが、とうとうターリアの眠っている部屋にたどり着いたのです。
 王はターリアが眠っているのだと思い、声をかけました。ところが、いくら呼んでも揺すっても目を覚ましません。
王はターリアが眠っているのだと思い、声をかけました。ところが、いくら呼んでも揺すっても目を覚ましません。
眠っているターリアを見るうち、王の胸に恋の炎が燃え上がりました。王はターリアを腕に抱いてベッドに運ぶと、存分に愛の果実を味わいました。それから、ターリアをベッドに寝かせたまま自分の国に帰り、それっきりこの出来事を忘れてしまったのです。
※ この場面も白雪姫同様、屍姦を想像させます。
九ヶ月経って、ターリアは双子を産み落としました。とはいっても、相変わらず眠ったままでした。双子は男の子と女の子で、光り輝く二個の宝石のようでした。屋敷に現れた二人の仙女の手で、子ども達はターリアの乳房にあてがわれ、そのほか細々とした世話を受けたりました。
そんなある日のこと。子供たちはまた乳が飲みたくなって母の乳房にあてがわれましたが、その一方がなかなか乳首を見つけられず、代わりに母の 指をつかんでチュウチュウ吸っているうち、とうとうあの麻のトゲを吸いだしてしまいました。その途端にターリアは深い眠りから覚めました。そして自分の側にいる二人の可愛い赤ん坊に気づくと、しっかり抱きしめて、乳を飲ませて自分の命と同じくらい大切にしましたけれど、どうしてそんなことになったのかさっぱり解りませんでした。というのも、屋敷の中には自分と赤ん坊しかいませんし、食べ物などを運んできてくれる仙女の姿はまるで目に見えなかったからです。
指をつかんでチュウチュウ吸っているうち、とうとうあの麻のトゲを吸いだしてしまいました。その途端にターリアは深い眠りから覚めました。そして自分の側にいる二人の可愛い赤ん坊に気づくと、しっかり抱きしめて、乳を飲ませて自分の命と同じくらい大切にしましたけれど、どうしてそんなことになったのかさっぱり解りませんでした。というのも、屋敷の中には自分と赤ん坊しかいませんし、食べ物などを運んできてくれる仙女の姿はまるで目に見えなかったからです。
時が過ぎて、王はふと、森の館で眠っていた美しい娘との情事を思い出しました。そうして久しぶりに訪ねてみますと、ターリアが目覚めていて、男の子の太陽(ソーレ)と女の子の月(ルーナ)、可愛らしい二人の子供まで生まれているではありませんか。
王は有頂天になり、ターリアに事の次第を説明しました。ターリアもすっかり王が気に入って、二人は数日の間、館で一緒に過ごしました。そして王が立ち去るときには、今度来るときは国に連れて帰る、と約束したのです。
それ以来、王は美しい愛人と可愛い双子にメロメロになってしまいました。国に帰っても、起きて寝るまでターリア、ソーレ、ルーナばかり口にします。
この状況に はらわたを煮えくり返らせたのは王妃でした。前々から、王が狩りと言っては数日間留守をするのを怪しいと思っていたのですが……。
「お前は門柱と扉のように《対になるもの》なのだから、私か王か、どちらに仕えるのか選ばなくてはなりません。王の愛人がどこの誰なのか、教えてくれたなら金持ちにしてあげましょう。けれど隠しだてするなら、この先、日の目は見られなくなるものと心得なさい」
大臣はすっかり王妃に教えました。そこで王妃は大臣を王の名においてターリアの館に遣わし、
「王が子供たちに会いたがっておられます」
と伝えさせました。嘘とも知らないターリアは大喜びし、早速子供たちを送り出しました。
王妃は子供たちを手に入れるやいなや、嫉妬のあまりに鬼女の心になりました。
「子供たちの喉を掻き切って、細切れにして、ソースで煮て、王の食卓に載せておくれ!」
けれども、料理人は心の優しい男でした。彼は金のリンゴのように愛らしい双子を見ると可哀想でたまらなくなり、双子を自分の妻に匿わせてから、山羊を二頭殺して、それで百種もの料理を作りました。
王はこの料理を食べると、
「美味い、我が母の命にかけて、我が祖母の魂にかけて、実に美味い!」
と絶賛しました。
王妃は「どんどんおあがりなさいませ、あなた自身のものを食べておいでなのですから」
と言いました。あんまり何度もそう言うので、しまいに王は不機嫌になり、
「自分の(稼いで得た)ものだということは分かっている、大体、そなたは何一つ獲ってはこないのだしな」
と言って、別邸に行ってしまいました。
※この場面も白雪姫同様、カニバリズム(英: Cannibalism)、人間が人間の肉を食べる行動、あるいは宗教儀礼としてのそのような習慣を思い起こさせる。
王妃は自分がしたと思っていることに まだ満足せず、もう一度大臣を呼びつけると、今度はターリアを呼び寄せました。ターリアは目に入れても痛くない子供たちに会いたい一心で、恐ろしい目論見のことも知らずに城にやって来ました。ターリアが目の前に連れ出されると、王妃は憤怒の表情で言いました。
「ようこそ、でしゃばりの奥様。なるほど、そなたが私の夫の気に入りの花というわけですね。……このメス犬! 地獄に堕ちて、私の苦しみを味わうがいい!」
ターリアは弁解しました。
「私が誘惑したのではありません、眠っている間に王様の方から押し入ってこられて……」と。
「城の中庭に大きな焚き火をして、この女を放り込め!」と命じたのです。
哀れなターリアは、王妃の前にひざまずいて懇願しました。せめて、着ているものを脱ぐだけの時間をください、と。王妃は承知しました。というのも、タ ーリアは燃やしてしまうには惜しいような、金と真珠で刺繍した素晴らしいドレスを着ていたからです。ターリアは脱ぎ始めましたが、一枚脱ぐたびに叫び声をあげました。服を脱ぎ、スカートを脱ぎ、胴着を脱ぎ、ペチコートを脱ぎかけたとき、とうとう地獄の灰汁の大鍋に投げ込むべく、家来たちに引きずられはじめました。
ーリアは燃やしてしまうには惜しいような、金と真珠で刺繍した素晴らしいドレスを着ていたからです。ターリアは脱ぎ始めましたが、一枚脱ぐたびに叫び声をあげました。服を脱ぎ、スカートを脱ぎ、胴着を脱ぎ、ペチコートを脱ぎかけたとき、とうとう地獄の灰汁の大鍋に投げ込むべく、家来たちに引きずられはじめました。
※ この場面は、まるでストリップです。
 その時でした。騒ぎを聞きつけて、王がやってきたのです。王はこの有様を見、子供たちはどうなったのか、と王妃に尋ねました。王妃は王の裏切りをなじって言い放ちました。
その時でした。騒ぎを聞きつけて、王がやってきたのです。王はこの有様を見、子供たちはどうなったのか、と王妃に尋ねました。王妃は王の裏切りをなじって言い放ちました。
「あなたに、あの子達の肉を食べさせて差し上げたのよ!」
「なんだと! 我が子羊を食った狼がこの私だと! おお、なぜ我が血は我こそ子供たちの血の源だと自覚しなかったのか。おお、残酷な裏切り者め、お前がこのような野蛮な行いをしたというのか。さあ、行け、罪の報いを受けるのだ。お前のような醜い嫉妬顔の女は闘技場でライオンに食わせるまでもないわ!」
王の命により、王妃と大臣は、ターリアを投げ込むための焚き火に投げ込まれました。それから、王は子供たちを料理した料理人をも同じ目に遭わせようとしましたが、料理人は王の足元に身を投げ出して言いました。
 「確かに、そのような仕業の報いには相応しい処罰です。私のような身分の者には王妃様の灰と混ざることも光栄かと思われます。けれども、忌まわしい企みからお子様方をお救い申し上げた私なのですから、そんな褒美はまっぴら御免ですわい」
「確かに、そのような仕業の報いには相応しい処罰です。私のような身分の者には王妃様の灰と混ざることも光栄かと思われます。けれども、忌まわしい企みからお子様方をお救い申し上げた私なのですから、そんな褒美はまっぴら御免ですわい」
これを聞いた王は狂喜し、それが本当なら、もう台所仕事などさせず、存分に褒美をやろうと言いました。その時には、夫の苦境を見て取った料理人の妻が、もう子供たちを連れてきていました。王は子供たちとターリアに一人ずつキスをして、 料理人にたっぷりの褒美をやり、御寝所番の頭に取り立ててやりました。
料理人にたっぷりの褒美をやり、御寝所番の頭に取り立ててやりました。
ターリアは王妃となり、子供たちと共に末永く幸せに暮らしました。
諺にもあるように、幸運児は眠ったまま運命の女神の祝福を受けるものなのです。
日本でも「果報は寝て待て」いう諺があるとはいうものの、とても子供に話せる内容ではありません。
したっけ。
『白雪姫』(しらゆきひめ、Schneewittchen、Schneeweißchen標準ドイツ語)とは、ドイツのヘッセン州地方の民話。後にグリム兄弟(ヤーコプ・ルートヴィヒ・カルル・グリム、ヴィルヘルム・カール・グリム)の『グリム童話』("Kinder und Hausmärchen" (KHM))に収載された。KHM 53番目の童話。
昔々、ヨーロッパのあるお城に住んでいた王と王妃がいました。夫婦は大変仲が良く皆がうらやむような美男美女でした。しかし、結婚して10年以上がたつというのに、いっこうに子供ができる気配がありませんでした。
そのまま3年がたったある雪の日、王妃がとうとう子供を身篭りました。その日の夜、王妃は嬉しさのあまり眠ることができなかったので、自分の部屋で刺子(さしこ)をする事にしました。2時間ほどたったその時、
誤って針を自分の指に刺してしまいました。やがて傷口から少しずつ血がにじんでいました。そこでお妃様は思ったのです。
「この空に降る真っ白な雪のような肌をして傷口から出た血のように赤い唇、そして窓の外に広がる黒闇のような黒髪を持った子供が欲しい。」
そしてうまれた子供は色が雪のように白かったので、白雪姫という名前を付けることにしました。
白雪姫はとても美しい王女になりました。彼女の継母(グリム童話初版本では実母)である王妃は、自分が世界で一番美しいと信じており、彼女の持つ魔法の鏡もそれに同意したため、満足な日々を送っていました。
白雪姫が7歳になったある日、王妃が魔法の鏡に
「世界で一番美しい女性は?」
と聞くと、白雪姫だという答えが返ってきたのです。
王妃は怒りのあまり、猟師に白雪姫を森に連れて行き、白雪姫を殺し肝臓(※作品によっては心臓、となっている)をとってくるように命じました。
※当時のヨーロッパは全体的に貧しかったせいか、実際に実の親による 子殺しや子捨てという「口減らし」が行なわれていたのです。
猟師はいわれるままに、白雪姫を森の奥へ連れていって殺そうとしましたが、美しい白雪姫に泣いて命乞いされるとかわいそうになりました。そこで、お城へ戻らないと約束させて、白雪姫を逃がすと、猟師は代わりにいのししを殺してその肺と肝を持ち帰ったのです。
 お妃は、猟師の持ち帰った血が滴る肺と肝を見ると喜んで、料理番を呼びました。
お妃は、猟師の持ち帰った血が滴る肺と肝を見ると喜んで、料理番を呼びました。
「すぐに、調理にとりかかるんだよ。血を一滴でもこぼさないようにね。」
料理番が肺と肝を塩ゆでにして持ってくると、お妃は我を忘れ、美しい顔がゆがむのもかまわず、かぶりつきました。
そして、白雪姫への憎しみをのみくだすように、白いきれいな歯で食いちぎりながら、ひとかけも残さずぺろりとたいらげたのです。
「白雪姫の美貌はこれで私のものだわ……。」
こうして奇妙な食事を終えた妃の頬には、満足そうに笑みが浮かびました。
※19世紀のドイツには「その人の肉を食べれば、その人の持つ特性を身につけることができる」という古い民間信仰があったそうです。
そのため現実の社会でも、「汚れを知らない若い娘の肉を食べれば、この世でどんなことをしてもその責任を問われない」と信じて、幼い娘を殺してその肉を食べたという事件の記録も残っているのだそうです。
白雪姫は、森の中で7人の小人(sieben Zwerge、英訳ではドワーフ)たちと出会い、ご飯を作り、寝床をしつらえて、洗濯をして、縫い物や編み物をして、どこもかしこもきれいにする」という条件付きで暮らすようになります。
※初版では白雪姫を助けるのは7人の人殺しだったが、二版以降は7人の小人に変わりました。
しかし、王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しいのは?」と聞いたため、白雪姫がまだ生きている事が露見したのです。
 王妃は物売りに化け、小人の留守を狙って腰紐を白雪姫に売りつけ、その腰紐を締め上げて息を絶えさせたのです。
王妃は物売りに化け、小人の留守を狙って腰紐を白雪姫に売りつけ、その腰紐を締め上げて息を絶えさせたのです。
帰ってきた7人の小人が腰紐を切って白雪姫を助け出すと、再び魔法の鏡により生きている事が露見します。
王妃は毒つきのくしを作り、白雪姫の頭にくしを突き刺して白雪姫は倒れました。しかしまた、7人の小人がくしを抜き蘇生させました。
 王妃は、白雪姫を殺そうと毒リンゴを作り、リンゴ売りに化けて白雪姫に食べさせたのです。白雪姫は小人たちから「家の扉は開けてはいけないよ」と言われていたため、はじめは抵抗したが、王妃が「わたしはただのリンゴ売りです。」と言ったために信じてしまい、その毒りんごを食べて息絶えたのです。
王妃は、白雪姫を殺そうと毒リンゴを作り、リンゴ売りに化けて白雪姫に食べさせたのです。白雪姫は小人たちから「家の扉は開けてはいけないよ」と言われていたため、はじめは抵抗したが、王妃が「わたしはただのリンゴ売りです。」と言ったために信じてしまい、その毒りんごを食べて息絶えたのです。
白雪姫は帰ってきた小人たちに発見されるが、小人たちは白雪姫が倒れた原因を見つける事が出来ませんでした。白雪姫は死んでしまった、と悲しみに暮れた小人たちは、白雪姫をガラスの棺に入れるのです。
そこに王子が通りかかり、毒リンゴを食べて亡くなったと思われた白雪姫を一目見るなり、死体でもいいからと白雪姫をもらい受ける。
※ 初版のグリム童話では死体を買い受ける死体愛好家とされている。
※ 死体愛好家(したいあいこうか)とは死体に欲情する性的嗜好をも指し、屍体性愛(したいせいあい)や、ネクロフィリア(necrophilia)とも呼ばれるものである。性的倒錯の一つでもある。屍姦 (しかん) とは、死体を姦する (犯す) ことを言う。
※ 18世紀フランスの売春宿では、女が棺桶の中で死体のふりをし、男性が牧師の姿になり交わるという屍姦的なサービスを行っている所もあり、一部の人間にはかなりの人気があったようである。
家来に棺を運ばせるが、家来のひとりが木にツマヅキ、棺が揺れた拍子に白雪姫は喉に詰まっていたリンゴのかけらを吐き出し、息を吹き返します。(※王子のキスによって目を覚ましたのではありません。たとえ、そうだとしても、どんな美女であろうが、死体を抱きしめ、キスまでしてしまうなど、どう考えても死体愛好家でしかありえない。この物語は死体愛好家の猟奇物語であり、白雪姫の話は前振りに過ぎないというのです。)
無事に王子と結婚して幸せに暮らしました。めでたし、めでたし・・・。
 ・・・では終わりません。とんでもない血も凍るようなエンディングがまっているのです。
・・・では終わりません。とんでもない血も凍るようなエンディングがまっているのです。 
白雪姫を殺そうとした王妃に白雪姫の結婚式の招待状が届きます。で、この王妃はのこのこと結婚式に出かけていって、そこで世にも残酷な方法で処刑されてしまうのです。その結婚披露宴で、王妃は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、死ぬまで踊らされたのです。
いずれにしても、この物語は子供向けの童話ではなかったこ とは間違いありません。
とは間違いありません。
したっけ。
青ひげ(Barbe-Bleue:バルブ・ブルー[仏語])は、フランスのシャルル・ペローの『がちょうおばさんの話』(1697年)に収められている童話、およびその主人公の呼び名です。グリム童話の初版にも収録されていたが、二版以降では削除されたそうです。
むかしむかし、町と田舎に、大きな屋敷をかまえて、金の盆(ぼん)と銀のお皿(さら)をも って、きれいなお飾りと縫箔(ぬいはく)※のある、椅子、机と、それに、総金ぬりの馬車までも持っている男がありました。
って、きれいなお飾りと縫箔(ぬいはく)※のある、椅子、机と、それに、総金ぬりの馬車までも持っている男がありました。
※ 縫箔(ぬいはく):刺繍(ししゅう)と摺箔(すりはく)を併用して布地に模様を表すこと
こんな恵まれた身分でしたけれど、ただひとつの欠点は、恐ろしい青ひげをはやしていることでした。それはどこの奥さんでも、娘さんでも、この男の顔を見て、あっといって、逃げ出さないものはありませんでした。
さて、この男の屋敷近くに、身分のいい奥さんがいて、二人の美しい娘さんをもっていました。この男は、この娘さんのうちどちらでもいいから、一人、お嫁さんにもらいたいといって、度々、この奥さんを困らせました。けれど、二人が二人とも、娘たちは、この男を、とても嫌っていて、逃げまわってばかりいました。
なにしろ青ひげをはやした男なんか、考えただけでも、ぞっとするくらいです。それに、気持ちが悪いほど嫌なことには、この男は、前からも、幾人か奥さまをもっていて、しかもそれが一人残らず、どこへどう行ってしまったか、行方が分からなくなっているのでした。
そこで、青ひげは、これは、この娘さん親子のご機嫌をとって、自分が好きになるように仕向けることが、なによりの近道だと考えました。そこで、あるとき、親子と、そのほか近所で知りあいの若い人たちを大勢、田舎の屋敷に招いて、一週間あまりも泊めて、ありったけの持て成し振りを見せました。
それは、毎日、毎日、野遊びに出る、狩に行く、釣をする、ダンスの会だの、夜会(やかい)だの、お茶の会だのと、目の回るようなせわしさでした。夜になっても、誰も寝床に入ろうとするものもありません。宵(よい)が過ぎても、夜中が過ぎても、皆そこでもここでも、おしゃべりをして、笑いさざめいて、ふざけっこしたり、歌をうたいあったり、それは、それは賑やかなことでした。
何もかも、とんとん拍子にうまく運んで、末の娘のほうがまず、この屋敷の主人のひげを、もうそんなに青くは思わないようになり、おまけに、りっぱな、礼儀ただしい紳士だとまで思うようになりました。
そして、家へ帰ると間もなく、末の娘は男と結婚しました。
それから、ひと月ばかり経った後のことでした。
青ひげは、ある日、奥方に向かって、これから、ある大切な用むきで、どうしても六週間、田舎へ旅をしてこなければならない。そのかわり、留守の間の気晴らしに、お友だちや知りあいの人たちを、屋敷に呼んで、里の家にいた頃と同じように、面白おかしく遊んで、暮らしてもかまわないから、と言いました。
「これはふたつとも、私の一番大事な道具の入っている大戸棚の鍵だ。これは普段使わない金銀の皿を入れた戸棚の鍵だ。これは金貨と銀貨をいっぱい入れた金庫の鍵だ。これは宝石箱の鍵だ。これは部屋全部の合鍵だ。さて、ここにもうひとつ、小さな鍵があるが、これは地下室の大廊下の、いちばん奥にある、小部屋を開ける鍵だ。戸棚という戸棚、部屋という部屋は、どれを開けてみることも、中に入ってみることも、おまえの勝手だが、ただひとつ、この小部屋だけは、けっして開けてみることも、まして、入ってみることはならないぞ。これはかたく止めておく。万一にもそれにそむけば、おれは怒って、なにをするか分からないぞ。」
奥方は、お言いつけの通り、必ず守りますと、約束しました。やがて青ひげは、奥方に優しく接吻して、四輪馬車に乗って旅だって行きました。
すると、奥方の知りあいや、お友だちは、お使を待つ間も、もどかしがって、われさきに集まって来ました。お嫁入り先の、立派な住まいの様子が、どんなものなのか、どのくらい立派なのか、みんなは見たがっていたでしょう。ただ主人が家にいるときは、あの青ひげが恐くて、誰も寄りつけなかったのです。
 皆は、居間、客間、大広間から、小部屋、衣裳部屋と、片っ端から見てあるきましたが、いよいよ奥深く見て行くほど、だんだん立派にも、綺麗にもなっていくようでした。
皆は、居間、客間、大広間から、小部屋、衣裳部屋と、片っ端から見てあるきましたが、いよいよ奥深く見て行くほど、だんだん立派にも、綺麗にもなっていくようでした。
とうとう最後に、いっぱい家具のつまった、大きな部屋に来ました。そのなかの道具や洋服は、この屋敷のうちでも、一番立派なものでした。壁掛けでも、寝台でも、長椅子でも、タンスでも、机や、椅子でも、頭のてっぺんから、足の爪さきまで写る姿見でも、それはむやみに沢山あって、むやみにぴかぴか光って、綺麗なので、誰も彼も、ただもう、感心して、ため息をつくばかりでした。
姿見のなかには、水晶の縁のついたものもありました。金銀めっきの縁のついたものもありました。何もかも、この上もなく立派なものばかりでした。
お客たちは、まさかこれほどまでとも思わなかった、お友だちの運のよさに、いまさら感心したり、羨ましがったり、羨望の眼差しは消えることがありませんでした。
しかし、ご主人の奥方は、いくら立派なお部屋や、飾りつけを見てあるいても、じれったいばかりで、いっこうに面白くも楽しくもありませんでした。それというのが、夫が出がけに厳しく言い付けて置いていった、地下室の秘密の小部屋というのが、始終、どうも気になって気になって、ならなかったのです。
いけないというものは、とかく見たいのが、人間の癖ですから、そのうちとうとう、我慢がしきれなくなってきた奥がたは、もうお客に対して、失礼のなんのということを、思ってはいられなくなって、ひとりそっと裏梯子を降りていきました。二度も三度も、首の骨が折れたかと思うほど、激しく、柱や梁(はり)にぶつかりながら、夢中で駆けだして行きました。
でも、いよいよ小部屋の戸の前に立ってみると、さすがに夫の厳しい言いつけを、はっと思い出しました。それにそむいたら、どんな不幸せな目にあうかしれない、そう思って、しばらくためらいました。でも、誘いの手が、ぐんぐん強くひっぱるので、それを払いきることは、できませんでした。そこで、小さい鍵を手にとって、ぶるぶる、震えながら、小部屋の戸を開けました。
 窓が閉まっているので、始めはなんにも見えませんでした。そのうち、だんだん、暗闇に目がなれてきました。すると、その床いっぱいに、血のかたまりがこびりついていました。血のかたまりには五、六人の女の死骸を、並べて壁に立てかけたのが、写って見えていました。これは、みんな青ひげが、ひとりひとり、結婚したあとで殺してしまった女たちの死骸違いありません。
窓が閉まっているので、始めはなんにも見えませんでした。そのうち、だんだん、暗闇に目がなれてきました。すると、その床いっぱいに、血のかたまりがこびりついていました。血のかたまりには五、六人の女の死骸を、並べて壁に立てかけたのが、写って見えていました。これは、みんな青ひげが、ひとりひとり、結婚したあとで殺してしまった女たちの死骸違いありません。
これを見たとたん、奥方は、あっと言ったなり、息がとまって、身体がすくんで動けなくなりました。そうして、戸の鍵穴から抜いて、手に持っていた鍵が、いつか、すべり落ちたのも知らずにいたくらいです。
しばらくして、やっとわれにかえると、奥がたは慌てて、鍵を拾いあげて、戸を閉めて、急いで二階の居間に駆けて帰ると、ほっと息をつきました。でも、いつまでも胸がどきどきして、正気がつかないようでした。
見ると、鍵に血がついているので、二、三度、それを拭いてとろうとしましたが、どうしても血がとれません。水につけて洗ってみても、石鹸と磨き砂をつけて、砥石(といし)で、ごしごし、擦ってみても、いっこうに印(しるし)が見えません。血の着いた跡は、いよいよ、濃くなるばかりでした。それもそのはず、この鍵は魔法の鍵だったのです。
ですから、表側のほうの血を落したかとおもうと、それは裏側に、いつか、よけい濃く、滲み出していました。
すると、その日の夕方、青ひげが、ひょっこり、家へ帰って来ました。それは、まだ向こうまで行かないうち、途中で、用むきが、都合よく片づいた、という知らせを聞いたからだと、青ひげは話しました。出し抜けに帰ってこられたとき、奥方は、ぎょっとしましたが、一生懸命、嬉しそうな顔をして見せていました。
さて、そのあくる朝、青ひげは、さっそく、奥方に、預けた鍵をお出しと言いました。そういわれて、奥方が鍵を出したとき、その手の震えようといったらありませんでしたから、青ひげは、すぐと感づいてしまいました。
「おや。」と、青ひげは言いました。
「小部屋の鍵がひとつないぞ。」
「じゃあ、きっと、あちらの机の上に置き忘れたのでしょう。」と、奥方は答えました。
「すぐ持ってこい。」と、青ひげは、怒った声を出しました。
五、六度、あちらへ行ったり、こちらへ行ったり、まごまごした後で、奥方は、しぶしぶ鍵を出しました。青ひげは、鍵を受けとると、恐い目をして、じっと眺めていましたが、
「このかぎの血はどうしたのだ。」と言いました。
「知りません。」と、泣くような声でこたえた奥方の顔は、死人よりも青ざめていました。
「なに、知りませんだと。」
と、青ひげは言いました。
「おれはよく知っているよ。おまえはよくも思い切って、小部屋の中に入ったな。えらい度胸だ。よし、そんなに入りたければ、あそこへ入れ、入れてやる。そこにいる妻たちの仲間になれ。」
こういわれると、奥方は、いきなり夫の足もとに突っ伏して、いかにも真心から、悔い改めた様子で、もうけっして、お言いつけには背きませんから、と言って、詫びました。
このうえもなく美しい人の、このうえもなく悲しい姿を見ては、岩でもとろけ出したでしょう。けれど、この青ひげの心は、岩よりも、鉄よりも固かったのです。
「妻よ、おまえをもう生かしておくわけにはいかない。今すぐに死んでもらう。」
と、青ひげはいいました。
「わたくし、どうしても死ななければならないのでしたら。」
と、奥方は答えて、目にいっぱい涙をうかべて、夫の顔を見ました。
「せめて暫く、お祈りをする間だけ、待ってくださいませんか。」
「しかたがない、七分半だけ待ってやる。だがそれから、一秒も遅れることはならないぞ。」と、青ひげは言いました。
ひとりになると、奥方は、お姉さまの名を呼びました。
「アンヌお姉さま。アンヌお姉さま、後生です、塔のてっぺんまで上がって、お兄さまたちが、まだおいでにならないか見てください。お兄さまたちは、今日、訪ねて下さる約束になっているのです。見えたら、大急ぎで来るように、合図をしてください。」
アンヌお姉さまは、すぐ塔のてっぺんまで上がって行きました。半分気が狂ったようになった奥方は、可哀想に、始終怯えて叫び続けていました。
「アンヌお姉さま、アンヌお姉さま、まだ何も来ないの。」
すると、アンヌお姉さまは言いました。
「日が照って、埃が立っているだけですよ。草が青く光っているだけですよ。」
そのうちに青ひげが、大きな剣を抜いて手に持って、ありったけの割れ鐘声(濁った太い大声)を出して、怒鳴りたてました。
「すぐ降りて来い。降りて来ないと、おれのほうから上がって行くぞ。」
「もうちょっと待ってください、後生ですから。」
と、奥方は言いました。そうして、極低い声で、
「アンヌお姉さま、アンヌお姉さま、まだ何も見えないの。」
と、叫びました。
アンヌお姉さまは答えました。
「日が照って、埃が立っているだけですよ。草が青く光っているだけですよ。」
「早く降りて来い。」
と、青ひげは叫びました。
「降りて来ないと、上がって行くぞ。」
「今まいります。」
と、奥がたは答えました。
そうして、その後で、
「アンヌお姉さま、まだなにも見えないの。」と、叫びました。
「ああ。でも、大きな砂煙が、こちらのほうに向かって、立っていますよ。」
と、アンヌお姉さまは答えました。
「それはきっと、お兄さまたちでしょう。」
「おやおや、そうではない。羊の群ですよ。」
「こら、さっさと降りてこないか。」
と、青ひげは叫びました。
「今すぐに。」
と、奥方は言いました。そうして、そのあとで、
「アンヌお姉さま、アンヌお姉さま、まだ、誰も来なくって・・・。」
「ああ、二人馬に乗った人がやって来るわ。けれど、まだずいぶん遠いのよ。」
「ああ、ありがたい。」
と、奥方は、嬉しそうに言いました。
「それこそ、お兄さまたちですよ。わたし、お兄さまたちに、急いで来るように合図しましょう。」
そのとき、青ひげは、家ごと震えるほどの大声で怒鳴りました。奥方は、しぶしぶ、下へ降りて行きました。涙をいっぱい目にためて、髪の毛を肩にたらして、夫の足もとに突っ伏しました。
「今さらそのようなことをしても、どうなるものか。」
と、青ひげはあざ笑いました。
「はやく死ね。」
こういって、片手に、奥方の髪の毛を掴みながら、片手で、剣を振り上げて、首をはねようとしました。奥方は、夫のほうを振り向いて、今にもたえ入りそうな目つきで、ほんのしばらく、身づくろいする間、待ってくださいと、頼みました。
青ひげはこう言って、剣を振り上げました。
「ならん、ならん。神さまにまかせてしまえ。」
そのとたん、表の戸に、ドンと、激しくぶつかる音がしたので、青ひげはおもわず、ぎょっとして手をとめました。とたんに、戸が開いたとおもうと、すぐ騎兵が二人入って来て、いきなり、青ひげに向かって来ました。これは奥方の兄弟で、ひとりは竜騎兵(りゅうきへい:騎兵の一種でドラゴンという名の小銃で武装していた)、ひとりは近衛騎兵(このえきへい:君主を警衛する君主直属の軍人)だということを、青ひげはすぐに知りました。そこで、慌てて逃げ出そうとしましたが、兄弟はもう、後から追いついて、青ひげが、くつぬぎの石に足を掛けようとするところを、胴中(どうなか)を一突き刺して、殺してしまいました。
でもそのときには、もう奥方も気が遠くなって、死んだようになっていましたから、とても立ちあがって、兄弟たちを迎える気力はありませんでした。
さて、青ひげには、跡継ぎの子がありませんでしたから、その財産は残らず、奥方のものになりました。奥方はそれを、姉さまやお兄さまたちに分けてあげました。
物珍しがり、それはいつでも心をひく、軽い楽しみですが、いちど、それが満たされると、もうすぐ後悔が、代ってやってきて、そのため高い代価を払わなくてはなりません。
当時ヨーロッパに広く知られていた妻殺しを題材にした民謡からヒントを得て、ペローが御伽話にしたものと考えられている。現在では口伝えの昔話として、各地で記録されている。
私は「青ひげ」の中に死体愛好(したいあいこう)の臭いを感じるのです。
なぜなら、青ひげは娘のどちらでもいいといっています。結婚する相手をどちらでもいいとは不自然です。それに、死体を飾ってあるかのような状態は、尋常ではありません。
死体愛好とは死体に欲情する性的嗜好をも指し、これはまた、屍体性愛(したいせいあい)や、ネクロフィリア(necrophilia)とも呼ばれるものである。性的倒錯の一つでもある。屍を姦するので「屍姦」といわれるものです。
これは、エジプトのミイラまで遡ります。死体はミイラ職人に屍姦されないよう数日間たった後、渡したといいます。屍姦の歴史はとても古いということです。
18世紀フランスでは、屍姦プレーを提供する売春宿が人気だったようです。もちろん、売春婦は死体のふりをするだけですが。
しかし、いくら殺人者だからといっても、殺して全財産を得るというのは、如何なものでしょうか。私には略奪としか思えないのですが。
民話の類型としては禁室型(きんしつがた)、開けるなのタブー、鶴の恩返し等の話に分類されます。
また、一説にはヘンリー八世と6人の妃たちの死を題材にしたともいわれています。
したっけ。
人類が誕生して間もない頃のことであった。奈良県の天理市あたり翁(おきな)と媼(おうな)がいた。契りを交わして三十年が過ぎても子供を授からずにいた。前世は人間ではなかったであろうが、きっと、悪行を重ねていたに違いない。だからこのような報いを受けるのだと、嘆き悲しんでした。
ただただ、毎日瓜をせっせと育てるばかりであった。
 ある日、畑に行くと食べてしまうには惜しいほどの美しい瓜を見つけました。翁(おきな)は家に持って帰ると媼(おうな)に言いましたた。
ある日、畑に行くと食べてしまうには惜しいほどの美しい瓜を見つけました。翁(おきな)は家に持って帰ると媼(おうな)に言いましたた。
「この玉のように美しい幼子がいたらどれだけうれしいだろうか」
「ほんにまぁ、食べるのが惜しいわい」
「同じことを考えておるわ」
ふたりはもいだ瓜を戸棚にしまっておくことにしました。
その晩、寝ていると戸棚から物音がしたのです。どうしたものかと、翁(おきな)が戸を開けると、なんともかわいらしい姫君がいました。
「ばあさん、これはいったい」
「瓜から生まれたんですよ。わたしたちが子供のように大事に瓜を育てたから、前世の悪行をお許し下さったのでしょう」
姫君は日が経てば経つほどに美しくなりました。姿顔立ちのみならず、人柄も文才も知恵もこの世にないほど優れていました。
噂を聞きつけた国の守護代は后にしたいと、手紙で申し立てました。翁(おきな)と媼(おうな)は大変喜び、支度をはじめました。
「いいかい、人さらいにあったら困ったことになる。扉は開けてはならないよ」
翁(おきな)と媼(おうな)はたっぷりと念を押して出かけました。
近所に住む世にも醜い女・天探女(あまのさぐめ)がいました。同じ貧しい家の者でありながら、美しい女だけが幸福になれるのは不公平に思ったのです。それに、あの女は瓜から生まれたというではないか。天探女は他人の、特に美しい女の、幸せは我慢ならなかったのです。
 天探女(あまのさぐめ)が来て、「美しい花の枝を差し上げよう」と言うので、瓜姫は戸を開けました。天探女は瓜姫をつかまえて遠方の高い木の上に縛り付けたのです。そして瓜姫の着物を着て、自分が守護代の嫁になろうと企みました。
天探女(あまのさぐめ)が来て、「美しい花の枝を差し上げよう」と言うので、瓜姫は戸を開けました。天探女は瓜姫をつかまえて遠方の高い木の上に縛り付けたのです。そして瓜姫の着物を着て、自分が守護代の嫁になろうと企みました。
天探女(あまのさぐめ)は顔を隠して迎えの篭屋に乗りました。瓜姫を見つけないように、遠回りの道を教えたのですが、篭屋は間違った道を来ていたのです。上の方ですすり泣く声が聞こえてきました。篭屋が本物の瓜姫を見つけると、醜女の正体は天探女(あまのさぐめ)とばれたのです。 
「こんな女と間違えるなんてひどすぎますわ」
もっともだと、迎えの者は瓜姫にわび、このことを守護代に秘密にしてもらうようお願いしました。迎えの者達は話しあい、天探女(あまのさぐめ)を始末することにしたのです。あまりの理不尽さに天探女(あまのさぐめ)は、女の武器を使って泣きながら「許してほしい」とすがりついて謝罪しましたが、男達の胸をうつにはほど遠かったのです。
 男達は天探女(あまのさぐめ)を容赦なくずたずたに切り裂きました。この世に醜い女が存在してはいけないと言わんばかりに……。そして、栗(くり)と蕎麦(そば)と黍(きび)の根本に埋めたのです。
男達は天探女(あまのさぐめ)を容赦なくずたずたに切り裂きました。この世に醜い女が存在してはいけないと言わんばかりに……。そして、栗(くり)と蕎麦(そば)と黍(きび)の根本に埋めたのです。
それ以来、その三種の植物は根が赤くなるのだということです。
あまのさぐめ 【天探女】
記紀神話の神。天稚彦(あめのわかひこ)の従神。高天原(たかまのはら)から遣わされた雉(きじ)を天稚彦に射殺させた。一説に、後世の天の邪鬼(じやく)に関係づけられる。
三省堂 大辞林
古代人たちは、芽生え、生育し、実り、死に絶え、その屍体の中から再び芽生えるという、大自然の死と再生の営みそのものに、偉大なる大地母神の姿を見た。地母神は、殺害され、切り刻まれ、大地に撒き散らされることによって、人間の食べられる作物を芽生えさせた
この作物起源神話は、水田農耕を知らない世界の「古栽培民」の間に広く分布している。そして同じモティーフは、確かに日本の神話の中にも見出すことができるのである。
日本書紀では、一書に曰はくとしてツクヨミ(月夜見:月の神)とウケモチ(保食神:食物の神)との話を載せ、殺されたウケモチの頭から牛馬、額からアワ、眉から蚕、眼からヒエ、腹からイネ、陰部からムギと豆が化生した。アマテラスは、アワ・ヒエ・ムギ・マメを「陸田種子(はたけつもの)」、イネを「水田種子(たなつもの)」と区別し、この世の人間の「食ひて活くべきものなり」として、五殻の起源を説明している。
蛇足ながら、瓜は女性器の隠語であります。これもまた、寝所の御伽噺なのです。
したっけ。
昔々、あるところに大層蛤(はまぐり)をとるのが上手な男がいました。
あるとき茂吉は海で巨大な蛤をとりました。
「こいつはでけぇ。きっと高く売れるぞ。」
しかし、良く見ると貝柱に傷がついているではありませんか。
「これは、可愛そうだ。ここまで生きるのは大変だったに違いない。よし、逃がしてやろう。」
しばらく後、男のもとに美しい女が現われ、嫁にもらってほしいと言ったのです。
「わたしはお浜ともうします。あなたに一目ぼれをしたので、お嫁にしていただきたいのです。」
お浜の料理は大層おいしく、とりわけ味噌汁が最高でありました。
茂吉はお浜に
「何があっても私の料理中は台所を覗かないで下さい。」
と言われていた。でも、茂吉はどうしても見たくて仕様がない。とうとう我慢しきれなくなって覗いてしまったのです。茂吉が見たのは鍋にまたがり小便をするお浜でした。
茂吉は怒って女を家から追い出してしまいました。女は海辺でいつまでも泣いていましたたが、やがて元の姿の蛤となって海へ帰って行ったのです。そして、二度と帰っては来ませんでした。
一時の感情により茂吉は掛け替えの無い女房を失い後悔しました
実はこの女房昔、茂吉に助けられた蛤だったのです。
 その後、時折海底から浮かび上がり漁をする茂吉を見ては涙していたそうです。
その後、時折海底から浮かび上がり漁をする茂吉を見ては涙していたそうです。
子供向けのおとぎ話では料理の秘密の部分への配慮として、女が蛤となって鍋に身を浸していたと変更されている場合もあります。
類話として、御伽草子に収められている「蛤の草子」があります。
「見るな」のタブーは、各地の民話に見られるモチーフの一つである。何かをしている所を「見るな」とタブーが課せられたにもかかわらず、それを見てしまったために悲劇(多くは離別)が訪れるという話である。民話の類型としては禁室型(きんしつがた)とも言うそうです。
料理というものを例にとって、そこに込められた人の思い、気持ちを知ることの大切さ、それを説き明かしている話といえます。茂吉に恩を返すために訪れた蛤女房は、その美味もさることながら、その愛情いっぱいの料理を提供し、茂吉を感動させます。
しかし、茂吉はお浜との約束を破りました。
愛情の基礎である約束という信頼関係を裏切ったため、茂吉はお浜を失ってしまったというわけです。
貝が昔から女陰の隠語であることがわかれば、この話はいそうエロティックであることがわかる。蜆(しじみ)は幼児のそれ、蛤(はまぐり)は娘、赤貝(あかがい)は成熟した女のそれを言うのが、一般的である。
古事記
和銅5年(712年)太朝臣安萬侶(おほのあそみやすまろ)、太安万侶(おおのやすまろ)によって献上された日本最古の歴史書です。
古事記には、スサノヲがオホゲツヒメに食物を乞うたところ、女神は鼻・口・尻から種々のおいしい食べ物を取りだし、さまざまに料理し整えてさしあげた。これをのぞき見たスサノヲは、けがれた物を食べさせようとしたと怒って、女神を殺害してしまう。すると、殺された女神の頭から蚕が、二つの目から稲種が、二つの耳からアワが、鼻から小豆が、女陰から麦が、尻から大豆が化生したとある。
このことから、女性の体は食物を産む源であったことがわかる。
余談ですが、蜃気楼と見られる記述が初めて登場したのは、紀元前100年頃のインドの「大智度論」第六まで遡る。この書物の中に蜃気楼を示す「乾闥婆(けんだつば)城」という記述がある。また、中国では『史記』天官書の中に、蜃気楼の語源ともなる「蜃」あるいは「蛟(みずち:龍の古語)」が吐き出す吐息によって楼(高い建物)が形づくられる」という記述がある。中国では大蛤(おおはまぐり)を蜃(しん)と呼んでいました。
 鳥山石燕(とりやませきえん (1712年-1788年) の「今昔百鬼拾遺(こんじゃくひゃっきじゅうい)」1780年(安永10年)に刊行された妖怪画集、その「雲の巻」に面白いお話がのっています。
鳥山石燕(とりやませきえん (1712年-1788年) の「今昔百鬼拾遺(こんじゃくひゃっきじゅうい)」1780年(安永10年)に刊行された妖怪画集、その「雲の巻」に面白いお話がのっています。
史記の天官書にいはく、「海旁蜃気は楼台に象る」と云々。 蜃とは大蛤なり。海上に気をふきて、楼閣城市のかたちをなす。 これを蜃気楼と名づく。
又海市とも云。
つまり、歳経た大蛤が気を吐き、それが城郭を形作る。
よって「蛤の気の楼閣」から「蜃気楼」という言葉が生まれた、ということです。
したっけ。