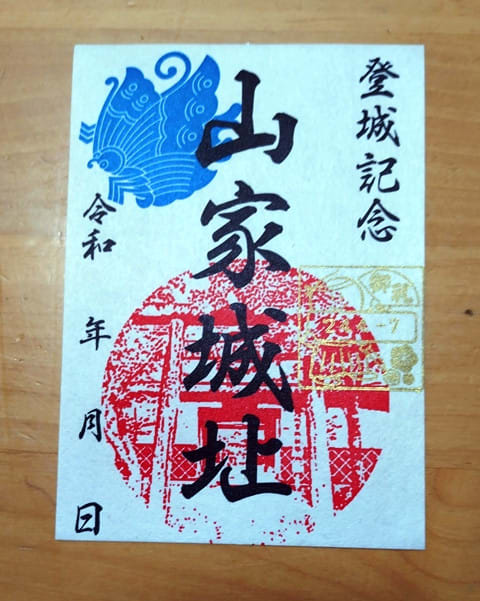22日㈯、先日、約20年という長い年月をかけて読み切った本がある。
それは「ソラからの真実の歴史」(白木妙子著、ブイツーソリューション、2006年2月)という本で、おそらく2006年の初版発行当時に、著者の白木さんのお仲間の尼崎の方からいただいたのではなかったかと思う。

2004年5月7日付の私のブログには下記の記述がある。
12時半に星原の星の宮神社で、尼崎から来られたソラの方に会い、少し話をした後、志賀郷の藤波神社、大江町の才の神にお送りした。
その帰りに、物部の諏訪神社と奈須波伎部神社と私市円山古墳に立ち寄った。やはり、綾部は重要な土地なんだなあと思っていた。
その方は、昨年の夏に初めて綾部に来られて以来、今日で4回目らしい。綾部に住みたいとおっしゃっていた。
同年6月18日付には下記を書いている。
14時に綾部駅で待ち合わせだったのだが、法務局に行っておられたようで、そこまで迎えに行った。ソラの読者の方で、尼崎から来ていただいた。
出口なお、王仁三郎のことを調べておられるそうで、今日は奥都城に行きたいということで、天王平にご案内した。僕も天王平に上がるのは、小学生の頃にくわがた採りに行って以来だった。古墳のようなお墓が6つ並んでいた。あと1つでいっぱいになるようだった。
帰りに大本に立ち寄り、両丹企画に来られた。アビちゃんのところに少し寄った。高本さんの店にも寄った。
今回の台風は綾部で呼んでいるそうだ。でも、良いことをしている人には被害がないので、心配しなくていいらしい。綾部市教育委員会発行の古墳地図のコピーもくださった。綾部では約1000の古墳が見つかっているそうだ。
綾部は倭の国の都だったそうだ。倭の国は大和に滅ぼされ、以後、迫害され続けてきたそうだ。足利尊氏も明智光秀も「逆賊」と呼ばれ、大本は二度にわたる国家弾圧を受けた。
神を守護していた物部一族が敗れたため、そうなったそうだ。綾部には確かに物部町という地名が残っている。
2000年2月に綾部市はイスラエルのエルサレム市と友好都市締結を行い、2003年7月に第1回中東和平プロジェクトIN綾部が開催された。
その頃だったか、その後か「イスラエル、パレスチナの戦争孤児や綾部市長に本を何冊か渡してほしい」とその尼崎のソラの方(たしか酒井さんという女性)に頼まれたことがあったように記憶している。
しかし、チャネリングによって著者の白木さんにもたらされたという情報をまとめた本は、当時の私にはあまりよく理解ができず、「この本を綾部市役所に渡したら、市長の息子は頭がおかしくなったと思われてしまう」と遠回しに断わった。
著者の白木さんが10人程の仲間を連れられて綾部に来られたこともあり、その時もいろいろとお話をさせてもらったが「この子はダメだ」と思われたのだろう。パタッと連絡がなくなって、もう20年近く経ってしまっていた。
「地球の謎解き」というホームページの中の2007年7月の情報に「ケンタロウス」という名前が出てくる。そして、その「ケンタロウス」が(ソラの情報の流れを)止めていた「一番の悪者」と書かれている。
2012年8月10日には「いかにシリウスBCが悪いかというと、アヤベという言葉でわかります。アは先頭に立ちたい、ヤは槍=ヘビ使い座で、ヘビ使い座の上に立つということで、アカンベーという意味です」以前の綾部市長の四方八洲男はヘビ使い座の長老で、大本教とつながり、ソラの友達物語の冊子をパレスチナに贈ったら、わざわざ違う冊子を創って贈っていました。(もっともイスラエルからクレームが来ていましたが)その息子は「ケンタロウス」で国会議員の谷垣専一とつながっています。
「ケンタロウス」はおそらく私のことで、消極的な態度が白木さんらの不興を買い、2007年頃に連絡がパタッと途絶えたのだろうと思う。
最近、「ニギハヤヒと『先代旧事本記』物部氏の祖神」(戸矢学著、河出文庫、2020年3月)という本を読み、昨年暮れに「縄文の世界を旅した初代スサノオ 九鬼文書と古代出雲王朝でわかる ハツクニシラス【裏/表】の仕組み」(表博耀著、ヒカルランド、2024年)という本を読んだことで、自分の意識が「ソラからの真実の歴史」を読みたくなっていた。
※参考:2025年2月24日付blog『いかるが』という地名
※参考:2024年12月26日付blog「スサノオノミコト」
ずっと気になりながら置いてあった「ソラからの真実の歴史」に手をつけたのは上記の2冊の本の内容と一致する点があったからだ。
「綾部が人類の歴史の初めのところに大きく関与している」という本の内容を信じたいという気持ちがありながらも、「さすがにそんなこと言っても、誰にも信じてもらえないどころか、非難されるのではないか?」という怖れもあったが「いや待てよ」と思ってしまった。
「ソラからの真実の歴史」は10章から構成されており、その第7章「出雲と倭の国」の一節をご紹介する。
【イシカミの巨人トヨウケは丹波の由良川沿いの私市円山古墳になった】
射手座のイシカミの君山(綾部市城山)は、丹波の由良川近くのホシノミナが降りたかたわらに降り、君山のお供のイシカミは君の尾山(綾部市上林)として近くに降りました。そして君の尾山は君山の身代わりになって人目をひくことにより、君山はヤマトから狙われることなく星述べの者たちを見守ることができました。君山は257mほどの小さな山ですが、日室が岳(加佐郡大江町)、鶴山(綾部市内の本宮山)、トヨウケ(私市円山古墳)の巨人を作りました。
イシカミの巨人トヨウケはいろいろな食べ物をソラのものと協力して作り出し、そのことを他の巨人に連絡したので食べ物の神様(豊受の神。食べ物の神で真名井神社、伊勢神宮の外宮の神様です)として伝えられました。そしてトヨウケは死んだ後に私市円山古墳(京都府最大の古墳で高速道路の工事中に見つかりました。この古墳の記録が全く残っていないのは、ヤマトの権力者にとって都合が悪かったからです)のある丘になったのです。…
【ヤマトに協力する丹後とヤマトの両方に攻められて倭の国は滅びた】
倭の国の物部氏一族は、支配星に支配されて仏教を推進するヤマトと、その仲間になった丹後の両方から攻められて滅ぼされ、倭の国はヤマトの支配下になってしまいました。倭の国の一部の人はヤマトに支配されるのを嫌がり、石を信じる人たちに匿われて倭の国を去って散り散りになっていきました。(中略)
倭の国は滅ぼされましたが、それまで海外との交流があり倭の国という名前は有名だったので、海外では日本のことを倭の国と呼ぶようになっていました。平和で平等な倭の国が何処にあったかが隠されたのは、民衆から搾取した富で巨大な仏教建築などを作るヤマトにとって都合が悪かったためです。(後略)
「ソラからの真実の歴史」の「はじめに」に「見えない存在である【ソラの意識体】からの情報を、そのようなことはありえないと思われる方はフィクションとして読まれても、人間だけに意識があるのではないと思われる方はノンフィクションとして読まれても、それは読者の全くのご自由です」と書かれている。
時が経ち、様々な経験と情報を受け入れて、今はノンフィクションとして読めた自分に、少しの驚きと新たな発見があった。
【本の紹介】
謎解き本=ソラからの真実の歴史
宇宙の始まりから日本の隠された歴史まで、ソラ(宇宙)の意識体によって、初めて人類に知らされた、衝撃の情報をまとめたのが「ソラからの真実の歴史」です。
その情報を7年前から、インターネットや本で公開していましたが、この度、星雲社様を通して発売することができました。
情報は、想像をはるかに超え、整合性をもって、あらゆる謎を解き明かしてくれます。
現在も、これまでの内容を補足する情報が与えられ、一部の情報は、パレスチナなどへ届いています。
イスラムの教え「目には目を。歯には歯を」は復讐の教えでなく、目は、見る物を、歯は、食べ物をあらわし、もらった人は誰かにお返しをして、富の独占を防ぐ教えが、本当の意味と伝えられました。
超古代、巨石遺跡、穀物模様、オーパーツ、などの地球のあらゆる不思議、
ヤマタイコク、倭の国、カタカナの意味、百人一首の隠された意味などの謎の答えが、全てつながって解き明かされていきます。