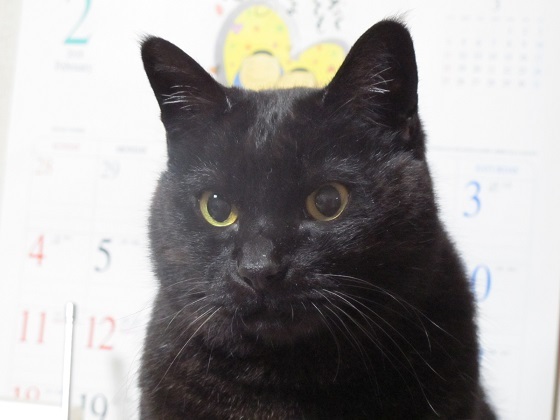菰野の「茶茶」の駐車場で
青空市をしていて、買った柿。
帰りの車の中で思い出した。
以前、これに似た柿を買って、食べたら渋かったのを。
帰って少し食べてみた やっぱり渋柿。
やっぱり渋柿。
熟したのが混ざっていたので、食べてみたら、これはOK。
熟すと渋が抜けるのかな。
ケースで買ったので、
18個も入っていて、さて、困った。
蜂屋柿ってあんぽ柿という干し柿にする柿なのだそう。
そこで、10個干し柿にした。
皮を剥いて、干せばいいだけかと思ったら、
殺菌のために皮を剥いたら10秒ぐらい熱湯にくぐらせるのだそう。
知らなくてそのまま干した。
うまくできるといいな
剥いた皮は干して、漬物の彩りにするといいらしい。
これも知らなかったので、ゴミ処理機にかけてしまった。
残りは熟すのを待って
パラミタガーデンで見かけ、
面白い名前だなと・・・・・
帰ったら、名前
パソコンで探し幕って、やっと名前がわかった!
年取るとメモしとかんといけんネ。
野草かなと思ったら、
高さ50~100cmの落葉小低木だそうです。
漢字で書くと「高野箒」。
写真のように、その年に伸びた枝先に
花を咲かせるのだそうです。
名前の「高野」は高野山と関係があって、
高野山の開祖空海が、
敷地内に人の心を惑わす※ようなものを植えることを禁じたため、
竹がなくて、竹箒を作ることができず、
代わりに、高野山ではこの植物の枝で箒を作ったのだそうです。
そこから「コウヤボウキ」と名づけられたのだと。
奈良時代から箒としては使われていたようです。
正倉院御物の中にも
「子日目利箒(ねのひのめとぎほうき)」として残っているそうです。
いろいろ調べていたら
近場にもそれらしきものが展示してあるのを発見!
稲沢市の祖父江町郷土資料館に同じものがありました。
ここでは、次のような説明
「正月の初子の日に養蚕の神を祭って皇后が目利草
マメ科の多年草(耆草)を使って作った箒で蚕室を掃くことが
奈良時代以来年中行事として行われていた」と。
実際にはコウヤボウキだったそうです。
ちなみに「耆草」は薬草で
解毒消腫・止血・止痛作用があるらしい。
耆草(薬膳情報から写真を拝借)
「初春の 初子の今日の玉箒
手に執るからに 揺らく玉の緒」 大伴家持
万葉集にも歌われています。
植物一つの名前にも
いろいろな情報が詰まっているんだと
※惑わすとは竹は筍がとれ、また加工して篭、花器などが作られる。
これらのもので利益を得ることが出来る。
このことから、修行にさしつかえると空海は考えたらしい。