本日19時から21時30分まで、表題の説明会が開かれました。
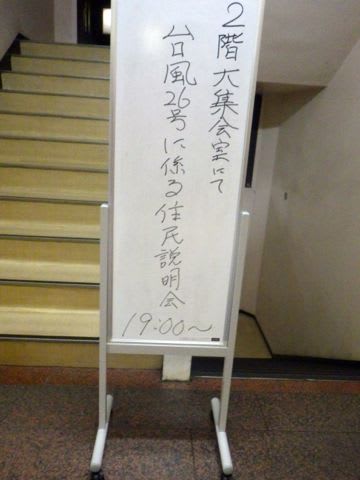
正確な参加人数はわかりませんが、たぶん100名以上が参加していたのではないかと思います。

説明内容は…
(1)復興計画策定に向けての今後の進め方
(2)平成26年度当初予算の概要
(3)伊豆大島土砂災害対策検討委員会の報告
(4)その他
(1)の今後の進め方では、50名規模の復興町民会議で町民の意見を聞いて行くとのことで、以下の図が示されました。

今年の9月までに復興計画案をまとめていくとのこと。
東京都からは応急、短期、中長期のハード対策案が示されました。

現在ある砂防施設の復旧と、導流堤の組み合わせで、流路の幅は広げない…この工事で100年に一度の雨には対応可能とのこと。
会場からは,途切れることなく次々に質問が出ました。
以下に出された質問を青で、回答を黒で、概略をまとめました。
今回の災害の被害原因のひとつに、橋に瓦礫が詰まったことがある。橋が架かっていなかったらこれほど被害はでなかった。狩野川台風でも橋が詰まって同じような被害があった。今回の都の対策では、橋のことが考えられていない。想定外の雨量で今回も砂防ダムを乗り越えたと言われるが、想定外が起こらないように何重もの対策をとるのが基本では?
砂防の施設の範囲内で、土砂を納めるのを基本に考えている。橋は下流の話し。上流の話しは今、急ぎで進めなければ。橋は町の防災の問題。大島町と一緒に今後決めて行く。
町づくり事業に6千万とある。ほとんどコンサルティング会社への委託料ではないか?
専門的ノウハウがいるので委託している。
最初に我が家に入って来たのは半透明の水で、家の中で泳いでいた。その数分後、泥が来た。泥の何倍もの水が流れて来た。東電周辺ゴミ詰まると冠水している。水をはけさせるための計画を考えてほしい。
情報を計画に活かしたい。
復興計画案になっているが、これでほぼ決まるのか?ダムの計画は、いつ誰がどういうふうに決めて行くのか?
土砂災害対策検討委員会で検討した。ハード対策選定、東京都砂防部局で立案。中長期については案だが、大きく変わることはない。
(町長)下流の対策、流路対策進めるときは,地元住民との調整を進める必要がある。どこまで何ができるかは、復興町民会議で練り上げて行きたい。
沢の側に住んでいて心配して来た。私が知りたいのは、被災した人がどういう思いでいるか。それを知るためには3月初めのアンケート、集約、公表をしてほしい。住んでいる人たちが感じていることを汲みとり、復興会議の中で練ってもらわないと安心できない。
アンケートでは被災者から97(被災者の44%)。町全体で551を回収。ヒアリングなどで意見を聞けるような工夫をしたい。
沢が屈曲している場所に住んでいる。土手、色々な部分で崩れている。その部分の復興に対しては話しがなかった。自宅の修理ができるのか?いつどうなるのかがわからない。アンケートを書きたくても何を書いたらいいのかわからない人が多いのをわかってほしい。個人個人の不安に対して近づいてほしい。大学生の娘が帰ってくる部屋もない状態なので、仮設住宅に入るのを断念した。もう少し歩み寄っていただきたい。
アンケートに対してはヒアリングなどをしていきたい。両親または片親がなくなった人の支援を町として考えている(町の事業として検討して行く)
(町長)インフラやハード対策だけを復興とは思っていない。子どもの養育支援もやっていく。策定委員会は専門の先生に入ってもらう。財政的裏付けつくる。行政の上からの計画では意味がない。被災者の人も現場を見ながら「この沢はどうした方がよい」などが議論され、策定委員会の先生と議論することをやりたい。復興町民会議と策定委員会以外に個別に被災者の方の意見をヒアリングして、要望を聞いていかないと解決しない。沢の流域に安全地帯を作るのか、再建して住むにはどうすれば住めるのか、コンサル会社に町職員と一緒に被災した人の中に入って行くよう、これから集中してやる。
復興町民会議のお知らせ届かない地区がある。手続きがおくれて参加がかなわない。社員のためにも参加して情報得たい、傍聴させてほしい。
配られない人の地区、再考する。
地下水のことについて京大グループの話しでは、1m前後に水を通す層があり、バランスが崩れてレス層(水の染みにくい層)と上の層を砂が動いた、ということだった。地下水のことも当然議論されているはず。表層地下水の影響を考慮して計画してほしい。
堆積物の透水性については、砂防工学的見地と地質学的見地からおおむね意見が一致している。砂防施設の地下水の流れを阻害したのではないかと言う話しがあったが、大金沢は地下深くまで構造物を打ち込んでいる所はない、今の所はそこまで阻害しないと思っている。
不安定な土砂が少しずつ崩れているのか、災害直後の姿と変わって来たと思っている。中長期計画は3~4年先、何が起きるかわからない。噴火や地震があるかも。中長期計画においては常に見直しを考えておいてほしい。今のままでは観光客は来ない。防災のとりくみを見に来て下さいと言うぐらいではないと観光客も来ないのでは?
大金沢の川幅広げるのか?いじらないのか?
今の状態でどのぐらい流れるのかの検証をしている。←
曲がっている所に関しては検討をする予定。
もう少し幅が広がって,もう少し安心できるようなものほしい。安心できる沢を作ってもらいたい。
住民アンケートを出さなかった、出したくない。なんで聞きに来ないのかと言う気がする。聞き取りの方が生の声が聞こえるはず。
沢広げないということだが流された人は住んで良いのか?弘法浜に下りる沢の手すり、脇や下りる道崩れたままのところもある。
社協は聞き取りに行っていたが、その声が町に伝わっているかわからない。町の職員に歩いてほしい。散歩しながらでも声聞けば色々な状況わかると思う。
父と兄弟被災、家をなおしていいのか、またそこの場所に住みたいのか。先々どうして良いものか?立ち退きなら線引きしてもらえれば踏ん切りが着くと思う。
今すぐできることは防災無線で避難指示的確に伝えること。昨日の避難勧告で岡田地区136名は自分が入っているのかわからなかったので、不安に思いながらも避難しなかった。避難指示きちんと出すのはそれほど時間がかからないと思うが?
(町長)昨日のようなことは今後連続して起こるから、周知徹底を努力したい。放送の仕方なども含めて考えたい。
以上、様々な質疑応答を聞きながら1000年に一度の大雨で被害にあった人たちが、100年に一度の雨対策で、安心して住めるのだろうかという疑問が拭いきれませんでした。
しかし1000年に1度の雨に基準をあわせたら、巨大な施設が日本中に必要で、それはできないのかも…。
どこにどう、納得して住むか…課題は山積みです。
でも…、頑張りましょう~。
(カナ)
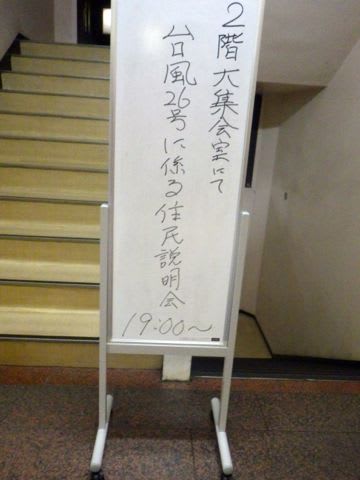
正確な参加人数はわかりませんが、たぶん100名以上が参加していたのではないかと思います。

説明内容は…
(1)復興計画策定に向けての今後の進め方
(2)平成26年度当初予算の概要
(3)伊豆大島土砂災害対策検討委員会の報告
(4)その他
(1)の今後の進め方では、50名規模の復興町民会議で町民の意見を聞いて行くとのことで、以下の図が示されました。

今年の9月までに復興計画案をまとめていくとのこと。
東京都からは応急、短期、中長期のハード対策案が示されました。

現在ある砂防施設の復旧と、導流堤の組み合わせで、流路の幅は広げない…この工事で100年に一度の雨には対応可能とのこと。
会場からは,途切れることなく次々に質問が出ました。
以下に出された質問を青で、回答を黒で、概略をまとめました。
今回の災害の被害原因のひとつに、橋に瓦礫が詰まったことがある。橋が架かっていなかったらこれほど被害はでなかった。狩野川台風でも橋が詰まって同じような被害があった。今回の都の対策では、橋のことが考えられていない。想定外の雨量で今回も砂防ダムを乗り越えたと言われるが、想定外が起こらないように何重もの対策をとるのが基本では?
砂防の施設の範囲内で、土砂を納めるのを基本に考えている。橋は下流の話し。上流の話しは今、急ぎで進めなければ。橋は町の防災の問題。大島町と一緒に今後決めて行く。
町づくり事業に6千万とある。ほとんどコンサルティング会社への委託料ではないか?
専門的ノウハウがいるので委託している。
最初に我が家に入って来たのは半透明の水で、家の中で泳いでいた。その数分後、泥が来た。泥の何倍もの水が流れて来た。東電周辺ゴミ詰まると冠水している。水をはけさせるための計画を考えてほしい。
情報を計画に活かしたい。
復興計画案になっているが、これでほぼ決まるのか?ダムの計画は、いつ誰がどういうふうに決めて行くのか?
土砂災害対策検討委員会で検討した。ハード対策選定、東京都砂防部局で立案。中長期については案だが、大きく変わることはない。
(町長)下流の対策、流路対策進めるときは,地元住民との調整を進める必要がある。どこまで何ができるかは、復興町民会議で練り上げて行きたい。
沢の側に住んでいて心配して来た。私が知りたいのは、被災した人がどういう思いでいるか。それを知るためには3月初めのアンケート、集約、公表をしてほしい。住んでいる人たちが感じていることを汲みとり、復興会議の中で練ってもらわないと安心できない。
アンケートでは被災者から97(被災者の44%)。町全体で551を回収。ヒアリングなどで意見を聞けるような工夫をしたい。
沢が屈曲している場所に住んでいる。土手、色々な部分で崩れている。その部分の復興に対しては話しがなかった。自宅の修理ができるのか?いつどうなるのかがわからない。アンケートを書きたくても何を書いたらいいのかわからない人が多いのをわかってほしい。個人個人の不安に対して近づいてほしい。大学生の娘が帰ってくる部屋もない状態なので、仮設住宅に入るのを断念した。もう少し歩み寄っていただきたい。
アンケートに対してはヒアリングなどをしていきたい。両親または片親がなくなった人の支援を町として考えている(町の事業として検討して行く)
(町長)インフラやハード対策だけを復興とは思っていない。子どもの養育支援もやっていく。策定委員会は専門の先生に入ってもらう。財政的裏付けつくる。行政の上からの計画では意味がない。被災者の人も現場を見ながら「この沢はどうした方がよい」などが議論され、策定委員会の先生と議論することをやりたい。復興町民会議と策定委員会以外に個別に被災者の方の意見をヒアリングして、要望を聞いていかないと解決しない。沢の流域に安全地帯を作るのか、再建して住むにはどうすれば住めるのか、コンサル会社に町職員と一緒に被災した人の中に入って行くよう、これから集中してやる。
復興町民会議のお知らせ届かない地区がある。手続きがおくれて参加がかなわない。社員のためにも参加して情報得たい、傍聴させてほしい。
配られない人の地区、再考する。
地下水のことについて京大グループの話しでは、1m前後に水を通す層があり、バランスが崩れてレス層(水の染みにくい層)と上の層を砂が動いた、ということだった。地下水のことも当然議論されているはず。表層地下水の影響を考慮して計画してほしい。
堆積物の透水性については、砂防工学的見地と地質学的見地からおおむね意見が一致している。砂防施設の地下水の流れを阻害したのではないかと言う話しがあったが、大金沢は地下深くまで構造物を打ち込んでいる所はない、今の所はそこまで阻害しないと思っている。
不安定な土砂が少しずつ崩れているのか、災害直後の姿と変わって来たと思っている。中長期計画は3~4年先、何が起きるかわからない。噴火や地震があるかも。中長期計画においては常に見直しを考えておいてほしい。今のままでは観光客は来ない。防災のとりくみを見に来て下さいと言うぐらいではないと観光客も来ないのでは?
大金沢の川幅広げるのか?いじらないのか?
今の状態でどのぐらい流れるのかの検証をしている。←
曲がっている所に関しては検討をする予定。
もう少し幅が広がって,もう少し安心できるようなものほしい。安心できる沢を作ってもらいたい。
住民アンケートを出さなかった、出したくない。なんで聞きに来ないのかと言う気がする。聞き取りの方が生の声が聞こえるはず。
沢広げないということだが流された人は住んで良いのか?弘法浜に下りる沢の手すり、脇や下りる道崩れたままのところもある。
社協は聞き取りに行っていたが、その声が町に伝わっているかわからない。町の職員に歩いてほしい。散歩しながらでも声聞けば色々な状況わかると思う。
父と兄弟被災、家をなおしていいのか、またそこの場所に住みたいのか。先々どうして良いものか?立ち退きなら線引きしてもらえれば踏ん切りが着くと思う。
今すぐできることは防災無線で避難指示的確に伝えること。昨日の避難勧告で岡田地区136名は自分が入っているのかわからなかったので、不安に思いながらも避難しなかった。避難指示きちんと出すのはそれほど時間がかからないと思うが?
(町長)昨日のようなことは今後連続して起こるから、周知徹底を努力したい。放送の仕方なども含めて考えたい。
以上、様々な質疑応答を聞きながら1000年に一度の大雨で被害にあった人たちが、100年に一度の雨対策で、安心して住めるのだろうかという疑問が拭いきれませんでした。
しかし1000年に1度の雨に基準をあわせたら、巨大な施設が日本中に必要で、それはできないのかも…。
どこにどう、納得して住むか…課題は山積みです。
でも…、頑張りましょう~。
(カナ)
















