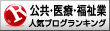日本における高齢者の大量にして急激に急増する事象への備えとして、高齢者への施策として創設したのが介護保険法にもとづく介護保険制度であり、両者の共通の利益を追求する介護支援専門員は介護保険法によって資格がつくられていることを認識した。
したがって介護支援専門員の行う業務は介護保険法等法令に規定されることになる。
高齢者の急激にして急増することの示すことは、高齢者のなかには介護を要する高齢者も急激に急増し大量の要介護状態の高齢者が存在することだ。
多くの要介護状態の高齢者の存在は、高齢者はもちろん若年層にとっても今以上に身近なこと、普通にあることといえる。
介護保険法によって資格が付与された介護支援専門員は介護保険法等の規定に基づく業務の執行が求められ、大量の要介護高齢者の支援を行う事情からも20世紀での困窮者を支援するためのスキルとは別の考えに基づいて業務を行うことになる。
たとえば、がんの病気はだれでもかかる可能性のある病気で、これが健康診断で胃がんが見つかったら医療を受けることになるだろう。そこにソーシャルワークは介在する場面はない。これが複数の疾患を抱えたり家族関係での問題があったりした場合には当事者である本人だけ受診など解決の決定が難しいかもしれない。そのような複合的課題を抱えた患者には専門的なソーシャルワークのかかわりは不可欠であるように、要介護高齢者の介護の解決には専門的なソーシャルワークのかかわりまでも求めずとも介護の支援と提供ができる仕組みを公的な制度であるゆえに介護保険法等の規定に基づく介護支援専門員の業務により解決を見る。
ただ、介護支援専門員の業務の行われている現状は法に基づくものとはいえない状態が散見され、介護支援専門員の役割に期待している研究者から介護支援専門員のより活躍を期待する見解からだろうが、介護支援専門員に対してソーシャルワークの浸透を訴える。
このソーシャルワークからの指摘は介護支援専門員が法に規定の業務内容の理解と法のもとめる業務の具体化とは別の理解と業務執行によるもので、ソーシャルワークを介護支援専門員に学習させることにことは、現今の大量のしかも急激な存在となっている高齢者の在り方とは別のことと理解できる。
ソーシャルワークではケースの発見を挙げるが、介護を要する高齢者の発見は介護保険法における医療機関からの勧めや近隣住民や家族からの相談といった一連の流れでなされる。
ケースの発見を担当している利用者に係りの始めの問題とは別の問題が含まれていたとき、そのケースを発見ということでればケースの発見はある。
要介護居宅高齢者が日々の支援を訪問介護の利用によって生活をしているときに訪問販売による不要な高額商品を購入といったケースは新たな問題を示しており高額商品の購入は日常生活の支援を行う訪問介護サービスでは埋めることができなかったその人の寂しさへの解消を販売員が埋めていたことの表れだとしたら看過できない。
別の例で要介護居宅高齢者の介護に訪問介護サービスの職員が訪れるといつも高齢の親と同居している子供が在宅していることを伝えられた介護支援専門員は、この家族に子供の問題を発見する。これはケースの発見だが解決に介護支援専門員が対応できなければ行政に相談を持ちかけることになる。介護支援専門員が対応できるとしても、将来の不安に備えるためにあえて行政に持ち込むという選択もとられるように、このようなケースの発見はある。
介護支援専門員によって要介護状態の高齢者自体を発見することは、その介護支援専門員がかかわっている利用者からの近隣のもしくは友人の相談によって知りえるが、介護支援専門員がソーシャルワークでいう発見を行うことは稀だ。
社会資源の発掘、開発も介護支援専門員が行うのはその業務から難しい。特に開発に係ることは困難で、介護保険制度の範疇で介護に係るサービスが提供されることから、既存のサービスにない新しいものを設けるようにするためには行政への働きかけと理解により実現するので、その任を介護支援専門員に求めるには介護支援専門員の法的な改定が前提になる。
ディサービスに機能訓練的なサービスでないディサービス事業者に導入を働きかけるといった既存の介護サービスに別の機能を求めるようなことは介護支援専門員が行っているかもしれない。そのときにサービスの変更がディ―サービスの利用者すべてが望む内容となるか、変更した機能訓練を求める利用者をそのディサービスが集めることができるならばよいが、利用者が充足しないことになったらサービスの変更を求めた介護支援専門員の関与に問題が生じることはないだろうと危惧される。
ディサービスの利用者の状態に応じてディサービス利用時に食事の盛り付けや温め直しを手伝うように依頼し、また、片づけや食器洗いをしてもらうようにするという開発はできる。
これらを太田義弘、小榮住まゆ子はその小論で「主な先行研究を概観したが、多少の差があるもののケアマネジメントが介護保険制度に付随した形で機能するために、全体的に介護保険制度の枠組み以外のケアマネジメント業務の達成率は概ね低い結果となっている。また、社会資源に対するアセスメントをはじめとするケアマネジメント展開過程における基本的実践ですらあまりできていない現状が明らかになった」と指摘したうえで「地域における連携や地域資源の利用・開発といった機能に関してもできていない状況に」あるので、その解決には「ソーシャルワークの領域で重視される機能についても取り組む必要性」を述べている。
先にみたように高齢者の急激にして大量の増加の解決に保険制度を選択し、介護保険法によって創設された資格という事情から介護支援専門員の業務は介護保険法の求める内容と規定される。介護保険制度上、介護支援専門員がソーシャルワークを行うことに対する対価が設けられていないことも考慮されるとさらに法の求める業務を行うにとどまる。
したがってソーシャルワークを行うための介護保険制度とみることはなく、介護支援専門員が行うのは介護保険法の範疇であり、その過程で必要に応じソーシャルワークを援用すると理解される。