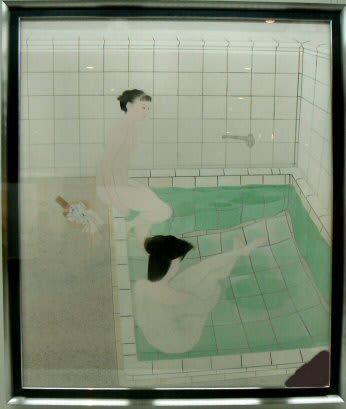前回の国立近代美術館の続きで、2階テラスに面した壁にかけられていた絵には驚いた。川面がキラキラと動いているし、橋を渡る車も走っている。日本画風の形や色合いだったのでだまされたが、ディスプレイだったのだ。

テラスに出て見ると、代官町通りが竹橋を渡って内堀通りになり、毎日新聞社本社があるパレスサイドビルが見える。

テラスにあるレストラン「アクアH2」から見ると、黄色と黒の美術館の2本のオブジェ(?)の間にパレスサイドビルの白い円筒コアが見えた。レストランのテーブルには人なれした肥満体のスズメがいた。


テーブルから皇居東御苑へ入る北桔橋門(きたはねばしもん)が見えたので、行ってみることにした。歩道橋脇に鮮やかな紅葉が見えた。


北桔橋門(皇居東御苑)は月曜、金曜は休園日で、その他の曜日の9時から4時ごろまで入園できる。入園は無料だが、入口で入園票を受取り、退園時に返却する。
江戸城本丸が近いので防御の為に、橋をはねあげて遮断できるようになっていたし、堀も深くなっている。ちなみに、「桔」という字は「ききょう」と入力すると「桔梗」と出てくる字だが、桔梗は「けっこう」とも読むらしい。「「けっこう」とはおもりの反動で井戸水をくみあげる「はねつるべ」のこと」と辞書にある。

門の手前で西の乾濠、吹上大宮御所の向こうに気球が見えた。

門を入ると江戸城天守閣跡の石組みがある。左の八角形の建物は、昭和天皇の皇后だった香淳(こうじゅん)皇后の還暦を記念して建てられた音楽堂だ。

江戸城の天守閣跡は高さ20mほどの石組み(天守台)が残るだけだ。

「天守台」の説明看板には、
「最初の天守閣は、1607年、二代将軍秀忠の代に完成しましたが、その後大修築され、1638年、三代将軍家光の代に、江戸幕府の権威を象徴する国内で最も大きな天守閣が完成しました。外観5層、内部6階で、地上からの高さは58メートルありました。しかし、わずか19年後の1657年、明暦の大火(振り袖火事)で、飛び火により全焼し、以後は再建されませんでした。」とある。
織田信長が建てたが、20年たらずで焼失あるいは倒壊した壮大な安土城天守閣を思い出す。
天守台からは丸の内の高層ビル群が見える。

それにしてもこんな巨大な石をどこから、どのように運んだのか?また、自然の石をぴたりと組み上げる技術は大変なものだ。


テラスに出て見ると、代官町通りが竹橋を渡って内堀通りになり、毎日新聞社本社があるパレスサイドビルが見える。

テラスにあるレストラン「アクアH2」から見ると、黄色と黒の美術館の2本のオブジェ(?)の間にパレスサイドビルの白い円筒コアが見えた。レストランのテーブルには人なれした肥満体のスズメがいた。


テーブルから皇居東御苑へ入る北桔橋門(きたはねばしもん)が見えたので、行ってみることにした。歩道橋脇に鮮やかな紅葉が見えた。


北桔橋門(皇居東御苑)は月曜、金曜は休園日で、その他の曜日の9時から4時ごろまで入園できる。入園は無料だが、入口で入園票を受取り、退園時に返却する。
江戸城本丸が近いので防御の為に、橋をはねあげて遮断できるようになっていたし、堀も深くなっている。ちなみに、「桔」という字は「ききょう」と入力すると「桔梗」と出てくる字だが、桔梗は「けっこう」とも読むらしい。「「けっこう」とはおもりの反動で井戸水をくみあげる「はねつるべ」のこと」と辞書にある。

門の手前で西の乾濠、吹上大宮御所の向こうに気球が見えた。

門を入ると江戸城天守閣跡の石組みがある。左の八角形の建物は、昭和天皇の皇后だった香淳(こうじゅん)皇后の還暦を記念して建てられた音楽堂だ。

江戸城の天守閣跡は高さ20mほどの石組み(天守台)が残るだけだ。

「天守台」の説明看板には、
「最初の天守閣は、1607年、二代将軍秀忠の代に完成しましたが、その後大修築され、1638年、三代将軍家光の代に、江戸幕府の権威を象徴する国内で最も大きな天守閣が完成しました。外観5層、内部6階で、地上からの高さは58メートルありました。しかし、わずか19年後の1657年、明暦の大火(振り袖火事)で、飛び火により全焼し、以後は再建されませんでした。」とある。
織田信長が建てたが、20年たらずで焼失あるいは倒壊した壮大な安土城天守閣を思い出す。
天守台からは丸の内の高層ビル群が見える。

それにしてもこんな巨大な石をどこから、どのように運んだのか?また、自然の石をぴたりと組み上げる技術は大変なものだ。