瀬谷ルミ子 2011年9月 朝日新聞出版
著者の瀬谷さんは、認定NPO法人・日本紛争予防センター(JCCP)事務局長。
それって何をする人かっていうと、専門は紛争後の復興、平和構築、治安改善、兵士の武装解除・動員解除・社会再統合など。
いままで行った場所は、ルワンダ、シエラレオネ、アフガニスタン、コートジボワール、ソマリア、ケニア、南スーダン、バルカン地域。
私がこの本を読もうと思ったのは、著者がラジオ(J-WAVE)に出ていたのを、たまたま聴いたとこから始まっている。
車の運転中に最初は何気に聴いてただけなんだけど、うわっスゴイ人がいるんだな、って途中から引き込まれた。そう思うと、本を読まないわけにはいかなくなる。
武装解除っていうと、なんか、戦争して、負けたほうが白旗あげて出てきて、武器を捨てて丸腰になる、って絵柄を想像してたんだけど、彼女の語るのを聴いてたらちょっと違った。
紛争地域で、和平合意が結ばれて紛争が終わったら、兵士の武装解除(Disarmament)、動員解除(Demobilization)、社会復帰(Reintegration)=DDRが問題になると。
>兵士・戦闘員から武器を回収し、除隊させたうえで、一般市民として生きて行けるように手に職をつける職業訓練や教育を与える取り組みが、DDR。
紛争が終わったら、兵士は仕事がなくなるんだから、それを社会復帰させるにはどうしたらいいか、なんて考えたこともなかった。
世界中のそういう紛争地域には、子ども兵士もいる。物心ついてから(つく前から?)人を殺すことしか教えられてないような子どもをどう社会に入れてくか。
社会復帰させると言ったって、内部紛争してたとこでは、肉親を殺されたような被害者と、殺した元兵士である加害者が、一緒にならざるをえないようなとこもある。武器とりあげたからって、すぐ仲良くなれるはずもない。
そういうとこへ出かけてっては、最終的には人々が自立できるように手助けをする。ただカネを出して、物を贈ったりハードを建てたりするだけぢゃない、社会を立て直すのが仕事。って言うのは簡単だけど、大変。
著者は、高校三年生のときに、ルワンダの難民キャンプの写真を見て、衝撃を受けて、進む道を決めたという。
紛争地域で死と直面している子どもたちに比べたら、自分には何かをする自由があり、自分でやろうとすればその悲惨な状況を変えられる立場にいるって意識が、行動を起こすもとになっている。
特に、ラジオでも言ってたんだけど、「やらない言い訳をしない」ってポリシーをもって物事にあたっているというとこに、私はえらく感銘をうけた。(私のような他人に無関心な人間にしては、めずらしく…)
うーん、シエラレオネという国名をみたとき、私はすぐに、やっぱりやがて国連ではたらくことになった、吉田真紀さん=FMヨコハマ「THE VOICE」のDJを思い出した。
あのひとも、このままでいいのか、自分には何ができるのかと考えてるひとで、私は、とても、とーっても、尊敬してた。
そういう人たちの言うことを聞いたり、本を読んだりして、ぢゃあ私もって行動を起こしはしないんですけどね、私の場合は。
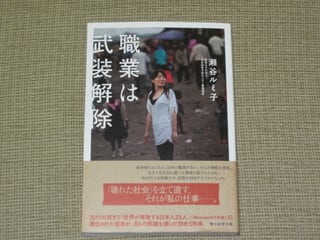
著者の瀬谷さんは、認定NPO法人・日本紛争予防センター(JCCP)事務局長。
それって何をする人かっていうと、専門は紛争後の復興、平和構築、治安改善、兵士の武装解除・動員解除・社会再統合など。
いままで行った場所は、ルワンダ、シエラレオネ、アフガニスタン、コートジボワール、ソマリア、ケニア、南スーダン、バルカン地域。
私がこの本を読もうと思ったのは、著者がラジオ(J-WAVE)に出ていたのを、たまたま聴いたとこから始まっている。
車の運転中に最初は何気に聴いてただけなんだけど、うわっスゴイ人がいるんだな、って途中から引き込まれた。そう思うと、本を読まないわけにはいかなくなる。
武装解除っていうと、なんか、戦争して、負けたほうが白旗あげて出てきて、武器を捨てて丸腰になる、って絵柄を想像してたんだけど、彼女の語るのを聴いてたらちょっと違った。
紛争地域で、和平合意が結ばれて紛争が終わったら、兵士の武装解除(Disarmament)、動員解除(Demobilization)、社会復帰(Reintegration)=DDRが問題になると。
>兵士・戦闘員から武器を回収し、除隊させたうえで、一般市民として生きて行けるように手に職をつける職業訓練や教育を与える取り組みが、DDR。
紛争が終わったら、兵士は仕事がなくなるんだから、それを社会復帰させるにはどうしたらいいか、なんて考えたこともなかった。
世界中のそういう紛争地域には、子ども兵士もいる。物心ついてから(つく前から?)人を殺すことしか教えられてないような子どもをどう社会に入れてくか。
社会復帰させると言ったって、内部紛争してたとこでは、肉親を殺されたような被害者と、殺した元兵士である加害者が、一緒にならざるをえないようなとこもある。武器とりあげたからって、すぐ仲良くなれるはずもない。
そういうとこへ出かけてっては、最終的には人々が自立できるように手助けをする。ただカネを出して、物を贈ったりハードを建てたりするだけぢゃない、社会を立て直すのが仕事。って言うのは簡単だけど、大変。
著者は、高校三年生のときに、ルワンダの難民キャンプの写真を見て、衝撃を受けて、進む道を決めたという。
紛争地域で死と直面している子どもたちに比べたら、自分には何かをする自由があり、自分でやろうとすればその悲惨な状況を変えられる立場にいるって意識が、行動を起こすもとになっている。
特に、ラジオでも言ってたんだけど、「やらない言い訳をしない」ってポリシーをもって物事にあたっているというとこに、私はえらく感銘をうけた。(私のような他人に無関心な人間にしては、めずらしく…)
うーん、シエラレオネという国名をみたとき、私はすぐに、やっぱりやがて国連ではたらくことになった、吉田真紀さん=FMヨコハマ「THE VOICE」のDJを思い出した。
あのひとも、このままでいいのか、自分には何ができるのかと考えてるひとで、私は、とても、とーっても、尊敬してた。
そういう人たちの言うことを聞いたり、本を読んだりして、ぢゃあ私もって行動を起こしはしないんですけどね、私の場合は。
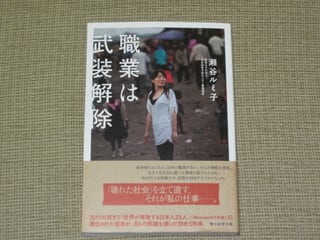













 )
)















