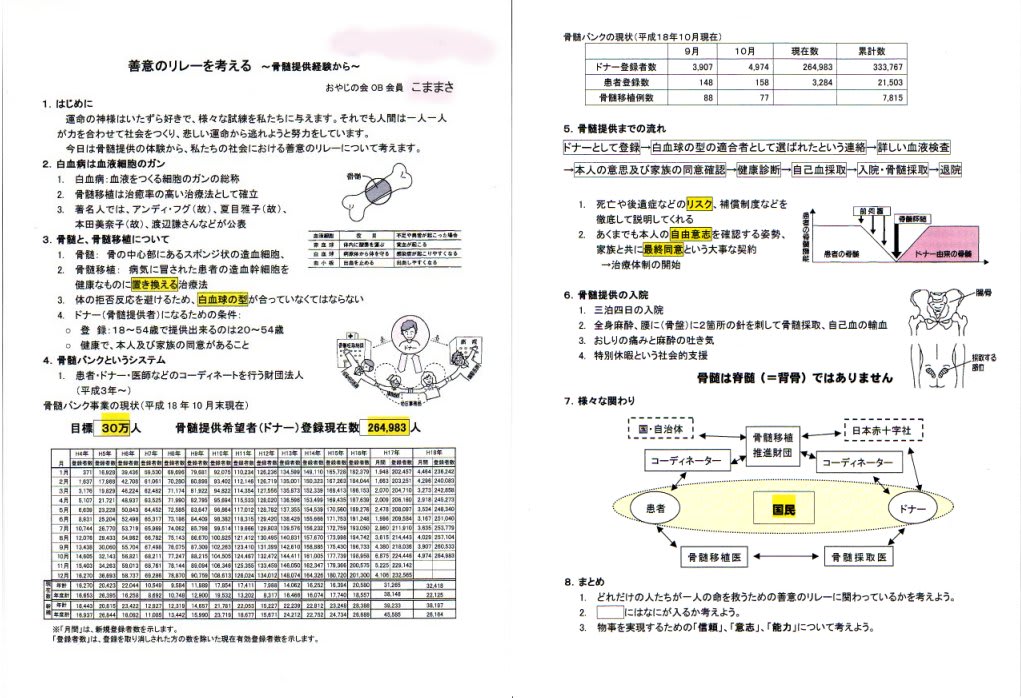11月も末だというのに今日は雨。天気予報では、明日からは雨が雪に変わるとのことですが、どうかな。
【発言の仕方】
一昨日中学校で「おやじの一言」をさせていただきました。
幸い子供達はそれなりに感じてくれたようですが、壇上から「質問はありませんか?」と訊ねてもあまり反応はありませんでした。
先生とは違う、普段見慣れない大人が来て、突然話を始めたのですから慣れるのに時間がかかると言うこともあるのかも知れませんが、それにしてもおとなしく感じました。
こちらが話をしている最中は、真剣な眼差しを向けて聞き入ってくれていた様子が伺えていただけに、質問や意見がないのは少々残念に思ったのです。
さて、所は変わって今日は職場で市役所の景観行政担当の方をお招きしての景観勉強会が開かれました。我が職場から約50人が参加して景観行政の最前線についてお話を聴いたのです。
私も最後まで聴きたかったのですが、別の会議がぶつかっていたために中座せざるを得ず、残念の極みでした。
そこで夜になってから、会議の様子を参加していた職員に尋ねました。
「会議の後で質問は出たかな?」
「はい、建築関係の方が一人質問をされていました」
「たった一人か…。それは情けないなあ、せっかくの機会なのになあ」
「そうですねえ」
私自身は、①講義や講演を聴くときは出来るだけ前で聴きなさい、②講師の許しがあれば一問だけでも良い質問をして帰ってきなさい、ということを職場でいつも言っています。またそう言っている以上、自らも実践に心がけています。
講演の後に質問の手が誰も上がらないときは「あれ?今日はこままささんは来ていないのかな、と思いますよ」と言ってくれる人もいますが、講演の後に会場から質問が来ないというのは、講師としてはいたたまれなくなる、という気持ちもあるのです。
会場からの反応がないと言うことは、話が難しすぎたか、あまりに易しすぎたか、またはあまりにつまらなかったか、のどれかに違いないからです。
音楽の演奏の後に「アンコール!」の声が挙がることが、演奏者に対する礼儀である、ということは多くの聴衆が常識として感じていることでしょう。
講演や講義でも、質問をすると言うことは「アンコール!」と同じくらいの、講師に対する礼儀であるという常識や良識が育っていないことを感じないわけにはいきません。
しかし考えてみると、自分自身も義務教育から高等教育を受けたなかで、そういう価値観について教えてもらった記憶がないのです。
もしかしたら一度や二度は先生が言ったのかも知れませんが、そういう価値観を育て上げずに大人になってしまっていたのです。
もしかしたらこれは学校における義務教育と家庭教育の責任なのかも知れません。しかし、今からでも遅くありません、気づいたときにこういう価値観を子供達に植え付けることに消極的であるべきではないと思うのです。
* * * *
日本では意見を述べたり質問をしたりする事への体系立ったスキルを教えることがありません。それもまた問題です。
発言には幾つかの種類があることを知らなくてはなりません。
私の経験としては、発言には「質問」と「意見」の二つがあるのですが、これらの区別がついていない人が案外多いものです。
「質問」は自分の疑問を相手にぶつけて、相手に対して回答を求めるものです。
これに対して「意見」は、要望や感想も含めて自分の主張を述べるもので、相手には必ずしも回答を求めないものです。
良い講師の良いお話に出会ったときには、「この人なら、この私の疑問にどう答えるだろうか?」というような、わくわくするような楽しみを覚えることもありますが、会場の雰囲気や講演の内容に合致させつつ、さらにお話の興味の深いところを引き出すような良い質問をするには、質問を作るだけの「質問力」も必要になってきます。
しかしそれはその必要性を理解した上で練習することで身に付いてくるものだと思っています。
日本人は奥ゆかしいとか消極的と言われますが、どんなときでも自分の意見を述べるものだ、という価値観を幼いときから育て上げていないことが最大の原因ではないでしょうか。
気づいたことは気づいたときから改善を始めるべきです。
読者の皆さんはどう思いますか?特に読者の中に学校の先生がいらっしゃったら意見を訊いてみたいものです。
いかがですか?
【発言の仕方】
一昨日中学校で「おやじの一言」をさせていただきました。
幸い子供達はそれなりに感じてくれたようですが、壇上から「質問はありませんか?」と訊ねてもあまり反応はありませんでした。
先生とは違う、普段見慣れない大人が来て、突然話を始めたのですから慣れるのに時間がかかると言うこともあるのかも知れませんが、それにしてもおとなしく感じました。
こちらが話をしている最中は、真剣な眼差しを向けて聞き入ってくれていた様子が伺えていただけに、質問や意見がないのは少々残念に思ったのです。
さて、所は変わって今日は職場で市役所の景観行政担当の方をお招きしての景観勉強会が開かれました。我が職場から約50人が参加して景観行政の最前線についてお話を聴いたのです。
私も最後まで聴きたかったのですが、別の会議がぶつかっていたために中座せざるを得ず、残念の極みでした。
そこで夜になってから、会議の様子を参加していた職員に尋ねました。
「会議の後で質問は出たかな?」
「はい、建築関係の方が一人質問をされていました」
「たった一人か…。それは情けないなあ、せっかくの機会なのになあ」
「そうですねえ」
私自身は、①講義や講演を聴くときは出来るだけ前で聴きなさい、②講師の許しがあれば一問だけでも良い質問をして帰ってきなさい、ということを職場でいつも言っています。またそう言っている以上、自らも実践に心がけています。
講演の後に質問の手が誰も上がらないときは「あれ?今日はこままささんは来ていないのかな、と思いますよ」と言ってくれる人もいますが、講演の後に会場から質問が来ないというのは、講師としてはいたたまれなくなる、という気持ちもあるのです。
会場からの反応がないと言うことは、話が難しすぎたか、あまりに易しすぎたか、またはあまりにつまらなかったか、のどれかに違いないからです。
音楽の演奏の後に「アンコール!」の声が挙がることが、演奏者に対する礼儀である、ということは多くの聴衆が常識として感じていることでしょう。
講演や講義でも、質問をすると言うことは「アンコール!」と同じくらいの、講師に対する礼儀であるという常識や良識が育っていないことを感じないわけにはいきません。
しかし考えてみると、自分自身も義務教育から高等教育を受けたなかで、そういう価値観について教えてもらった記憶がないのです。
もしかしたら一度や二度は先生が言ったのかも知れませんが、そういう価値観を育て上げずに大人になってしまっていたのです。
もしかしたらこれは学校における義務教育と家庭教育の責任なのかも知れません。しかし、今からでも遅くありません、気づいたときにこういう価値観を子供達に植え付けることに消極的であるべきではないと思うのです。
* * * *
日本では意見を述べたり質問をしたりする事への体系立ったスキルを教えることがありません。それもまた問題です。
発言には幾つかの種類があることを知らなくてはなりません。
私の経験としては、発言には「質問」と「意見」の二つがあるのですが、これらの区別がついていない人が案外多いものです。
「質問」は自分の疑問を相手にぶつけて、相手に対して回答を求めるものです。
これに対して「意見」は、要望や感想も含めて自分の主張を述べるもので、相手には必ずしも回答を求めないものです。
良い講師の良いお話に出会ったときには、「この人なら、この私の疑問にどう答えるだろうか?」というような、わくわくするような楽しみを覚えることもありますが、会場の雰囲気や講演の内容に合致させつつ、さらにお話の興味の深いところを引き出すような良い質問をするには、質問を作るだけの「質問力」も必要になってきます。
しかしそれはその必要性を理解した上で練習することで身に付いてくるものだと思っています。
日本人は奥ゆかしいとか消極的と言われますが、どんなときでも自分の意見を述べるものだ、という価値観を幼いときから育て上げていないことが最大の原因ではないでしょうか。
気づいたことは気づいたときから改善を始めるべきです。
読者の皆さんはどう思いますか?特に読者の中に学校の先生がいらっしゃったら意見を訊いてみたいものです。
いかがですか?