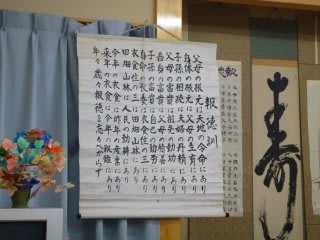生来の転勤族のこの私。
就職してから13回の転勤、物心ついた子供の時からの引っ越し回数は17回を数えます。
転勤というとなにか辛そうなイメージですが、新しい場所へ行けるというのは一つの冒険であり可能性を開くチャンスでもあります。
そのような経験を踏まえて、地方へ転勤した時に地域に受け入れられるためには、どのような心がけと姿勢でいると良いかをいろいろと考えました。
歳をとってくると所長だとか支所長など、ある程度の地位や立場も得られるでしょうけれど、そういう立場をもちながら、地域の中で仕事をうまくやってのけるにはどうしたらよいでしょうか。
特にまた転勤でそのマチからもいなくなってしまう宿命を背負っている転勤族にとっての、たった2年や3年のマチに対してどういう姿勢で臨むべきでしょうか。
そうしたことを今回は、「地域で求められる6つの人材像」として私なりにまとめてみました。
皆さんはどのようにお考えでしょうか。
◆
まず始めは、「1.旺盛な好奇心(よそ者ならではの切迫感)をもつべき」を挙げましょう。
どうせ地域に2、3年しかいないのだとしたら、その間に見られるものは全部見た方が良いでしょう。その際には、「誘われたら何でも話にノってみよう」という姿勢が良いと思います。
(その先はどうなっているのかな)という、知らないことの先を知るように努力していると、いつしかとても多くのことが分かるようになるものです。
私がハマっているフライフィッシングで言えば、2年しかいなければ夏のフライは2度しか楽しめないと言うことです。もったいないと思いませんか。
次は「2.該博な知識欲(現場、歴史、地理、出来事、人)を持とう」を挙げます。
1の旺盛な好奇心と似ているところもありますが、好奇心の赴くままという出会いだけではなく、その地域の歴史や地理、様々な現場など、ちゃんと勉強した方が良いに決まっています。
行ったことのない場所がない、というくらいに徹底して掘り下げる気持ちがあると良いでしょう。
もちろん、情報を得るためには多くの人に会うことが一番手っ取り早いでしょう。こうしたある程度勉強をして知識を増やすという姿勢もほしいところです。
続いて「3.地域に共感し、好感を持ち面白がる心をもとう」ということを挙げましょう。
どのマチへ行っても、地域には誇りとプライドがあります。それに対して否定的な言葉を投げかけると住民は怒ったりしょげたりします。
逆に正当に評価をしてあげるとうれしくなるのは当然です。せっかくこのマチに縁ができた人が、その縁を喜んでいる姿を見るのは住民としてとてもうれしいことでしょう。
かつて私が長野県の松本で勤務をした時に、(ここの人たちの自慢と誇りは何だろうなあ)と考えました。そしてその答えは「蕎麦と北アルプスにある」と思いました。
そこで手打ち蕎麦屋を百軒巡ってリストを作り、また北アルプスへも登り、最後は槍ヶ岳の山頂まで行くことができました。
そういうことに心がけていると、やがて地元の人よりも多くの蕎麦屋へ行っている自分になり、蕎麦談義に重みが増して行きました。
地元の人が「小松さんは本当に蕎麦が好きなんですね」と言う時はとても嬉しそうなのです。おかげで今でも私は松本、そして安曇野が大好きでいられるのです。
次ぎに、「4.地域に参加し、貢献する姿勢」を挙げましょう。
転勤してきた人によく見られる姿が、「なんで自分はこんなところに来たのか」と不平不満に思っていたり、職場の職員として転勤してきたけれど、このマチの市民だという自覚はない、という残念なものです。
職場の職員はそうだとしても、ある一時期、このマチの住民となったのだということを自覚して、地域のイベントや奉仕活動、あるいはNPOなどに参加すると良いでしょう。
何かに参加することできっと人生の思い出だって増えるはずですし、職場以外の友達だって増えるでしょう。
さて五番目は、「5.茶目っ気と意外な人間性を多様に持つ」ということです。
真面目な人だと思いきや実はいろいろな趣味があって独特の世界がある、というのはやはり地域に溶け込むには有力な武器になるでしょう。
私は釧路で釣りを始めて、それそのものは素人でしたが、下手くそな釣りを見て市役所の先輩釣り師たちには大分笑われました。
こちらは真剣なのですが、なにしろ基礎ができていなかったりして大いに失敗もします。
しかしそういう笑い話が酒の肴になったりして、職場の関係以外での同僚の皆さんに意外な一面を見ることもできました。
やはり何でもやってみることです。
最後に、「6.一目置かれる何かの達人である」ということを挙げましょう。
私はもう十数年にわたって蕎麦打ちをしていますが、それが面白く伝わると、あちこちから「蕎麦打ちを教えて欲しい」という依頼が来たりします。
掛川にいた時は「蕎麦研究会」を作って、蕎麦打ちの指導を行って若手(当時)の蕎麦打ちを育てました。
今でもそのとき一緒に蕎麦を打った人たちが地域で引っ張りだこになっている姿を見るとこんなに嬉しいことはありません。
また、本当に良いお店や人は見極めができるので、達人の目から見て「あの人はすごいですね」とか「あのお店は本当に美味しいですね」という評価が重みをもって語られるようになります。
私の知人にはマラソンを得意にしている人だとか、とにかく全国の花火を見て回っている人だとか、釣り名人…などなど異色な人たちがたくさんいます。
何かの達人であるということは世渡りの上でやはり強い武器になるモノです。
そうして、これらのような生き方を貫いてみると、再び転勤でそのマチを離れるような時には最後に寂しいと思ってくれるような仲間が増えてきます。そういう別れこそ最高ではないでしょうか。
◆
さて、最近は転勤を嫌って地方自治体に就職をする若者も増えているようです。
転勤や引っ越しや煩わしいものですが、その先にはすてきな出会いの可能性もたくさんあるのです。
たった一度の人生をどう生きるか。
人生の価値って、結局自分と一緒にいたことを嬉しく思ってくれる友達の数で決まるのではないでしょうか。




















 ある会合の懇親会で、本当に久しぶりに苗穂のサッポロビール園でジンギスカンの食べ放題に挑みました。
ある会合の懇親会で、本当に久しぶりに苗穂のサッポロビール園でジンギスカンの食べ放題に挑みました。