しばらく、所用により家をあけていたが、帰ってきたら、Bobbyさんからたくさんコメントをいただいていたが、あまりにも長くなりそうなので、新たな記事の形で、私なりの見解を示しておこう。
【bobbyさんからのコメント1】
コメント表題と同じタイトルのTBを入れさせて頂きました。要点は、労働者の流動性を高めるには、解雇規制緩和で労働者を「押す」よりも、企業自ら転職市場を作って「引っ張る」方が、労働者へ与える心理的な安心感が高いので、流動性を高めやすいという事です。
【私の見解】
私も、新卒偏重は改める方が、企業の中に多様性を与え、成長のための活力になるのではないかと思います。しかし、問題となるのは、労働市場での重要です。需要超過の場合はうまくいくでしょうが、需要のないところに市場だけあっても、それは、既卒者と新卒者が同じパイを奪いあうだけなので、需要と供給の関係により、より悪い条件での再就職となることでしょう。
【bobbyさんからのコメント2】
>仮に雇用規制を撤廃するとすると、経営者は一種のモラルハザードにより、経営努力をするより、安易なリストラで短期的な利益の確保に走る可能性があります。
これを経営者のモラルハザードと言うのは、資本主義の理念からいってどうかと思います。株主が企業の短期的な利益向上を求め、経営者が株主の期待に沿って、即効性の高い利益改善策として不採算部門でのレイオフを行う事は、経営者として合理的行動だと理解します。
逆に労働者が自分の生存する責任を企業に取らせよううとする現在の慣習も、香港で生活する私から見ると大変無責任に見えます。
【私の見解】
私がここで述べているのは、自分の在任中に財務諸表の数字を良くするために、将来の企業の活力を奪うような行為です。色々な思惑を持つ株主がいるのは事実ですが、株主の多くは、会社が安定的に発展して株価が上昇することを望んでいるのではないでしょうか。しかし、株主と経営者の情報の非対称性のために、経営者は必ずしも株主の意に染まないことを行う。これは、経済学で言うモラルハザードの典型的な例です。
【bobbyさんからのコメント2】
>日本の製造業では、現場レベルまで巻き込んでTQCやTPM活動の行えることが強みの一つだろうと考えます。「3年から5年」で転職しては、このような強みは構築できないのではないでしょうか。
沈没中のタイタニック号の船室で、レストランのウェイトレスのマナーを叱っても、1時間後にみんな死んでいるのなら意味がありません。
おそらく21世紀中ずっとグローバリゼーションが進行するであろう世界的環境の中で、TQCやTPM活動といっても意味があるとは思えません。企業は生き残る為に、可能で合法で合理的な事は何でもするでしょう。20年後の国内工場の作業が、ほとんどはロボットが行われていたとしても私は驚きません。
私のブログに「官僚達の夏」の教訓として書きましたが、駄目だとわかっている事は、抵抗するよりも早めに手を打つ事です。行政に何かできるとすれば、いま工場労働者を守る事よりも、工場労働者をどのように将来性のある業種へ転換させるかを、問題が深刻化する前に手を打つべきです。
【私の見解】
工場でロボットが使われているのは、今に始まったことではありません。しかし、ロボットでもほっておけばすべてやってくれる訳ではなく、それが、十分な性能を発揮し続けていくようにメンテナンスをしながら動かしていくというのが現場技術者の腕の見せ所です。
グローバル化する世界こそ、他の国と同じことをやっていては、存在価値がありません。我が国の強みはものづくりにあります。この強みを活かすことが、他の国と差別化を進めていくことに繋がります。必ずしもすべての工業がそういうわけではありませんが、ものづくりを支えているところをいかに守っていくかということも重要なことだと考えます。
○ついでにbobbyさんのブログの記事に関する見解も
【bobbyさんのブログの記事「押してもだめなら引いてみな」より】
日本では終身雇用という幻想が広く社会全体(経営者、労働者、家庭の中、裁判官、政府の官僚、政治家など)に深く浸透しています。雇用問題は、理論や制度の問題ではなく、風竜胆さんを含む多くの日本人のエモーショナルな問題になっています。こういう問題の解決は、制度を変えただけでは解決しないと思われます。この状況を改善するには、「みえざる手」に任せるのではなく、「誰か」が適当な戦略を持って雇用・労働改革を進める事が必要と思われます。
【私の見解】
まず、私が「エモーショナル」であると書かれていることは心外です。解雇規制をなくすことが、論理的におかしいと言っているつもりなのですが。自分と違う意見を「エモーショナル」と決めつけるのは単なるレッテル貼りではないでしょうか。
また、私は転職しやすい環境をつくることに対して異論を述べているわけではありません。パイの少なくなっているときに、解雇が容易にできれば、ダメな経営者は努力するより先に、安易な道を選びかねず、それが益々経済の悪化を招くだろうという極めて論理的な理屈を言っているだけなのですが、理解していただけないのは残念です。
(ぽちっとお願いします。) ⇒
「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら
「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら
【bobbyさんからのコメント1】
コメント表題と同じタイトルのTBを入れさせて頂きました。要点は、労働者の流動性を高めるには、解雇規制緩和で労働者を「押す」よりも、企業自ら転職市場を作って「引っ張る」方が、労働者へ与える心理的な安心感が高いので、流動性を高めやすいという事です。
【私の見解】
私も、新卒偏重は改める方が、企業の中に多様性を与え、成長のための活力になるのではないかと思います。しかし、問題となるのは、労働市場での重要です。需要超過の場合はうまくいくでしょうが、需要のないところに市場だけあっても、それは、既卒者と新卒者が同じパイを奪いあうだけなので、需要と供給の関係により、より悪い条件での再就職となることでしょう。
【bobbyさんからのコメント2】
>仮に雇用規制を撤廃するとすると、経営者は一種のモラルハザードにより、経営努力をするより、安易なリストラで短期的な利益の確保に走る可能性があります。
これを経営者のモラルハザードと言うのは、資本主義の理念からいってどうかと思います。株主が企業の短期的な利益向上を求め、経営者が株主の期待に沿って、即効性の高い利益改善策として不採算部門でのレイオフを行う事は、経営者として合理的行動だと理解します。
逆に労働者が自分の生存する責任を企業に取らせよううとする現在の慣習も、香港で生活する私から見ると大変無責任に見えます。
【私の見解】
私がここで述べているのは、自分の在任中に財務諸表の数字を良くするために、将来の企業の活力を奪うような行為です。色々な思惑を持つ株主がいるのは事実ですが、株主の多くは、会社が安定的に発展して株価が上昇することを望んでいるのではないでしょうか。しかし、株主と経営者の情報の非対称性のために、経営者は必ずしも株主の意に染まないことを行う。これは、経済学で言うモラルハザードの典型的な例です。
【bobbyさんからのコメント2】
>日本の製造業では、現場レベルまで巻き込んでTQCやTPM活動の行えることが強みの一つだろうと考えます。「3年から5年」で転職しては、このような強みは構築できないのではないでしょうか。
沈没中のタイタニック号の船室で、レストランのウェイトレスのマナーを叱っても、1時間後にみんな死んでいるのなら意味がありません。
おそらく21世紀中ずっとグローバリゼーションが進行するであろう世界的環境の中で、TQCやTPM活動といっても意味があるとは思えません。企業は生き残る為に、可能で合法で合理的な事は何でもするでしょう。20年後の国内工場の作業が、ほとんどはロボットが行われていたとしても私は驚きません。
私のブログに「官僚達の夏」の教訓として書きましたが、駄目だとわかっている事は、抵抗するよりも早めに手を打つ事です。行政に何かできるとすれば、いま工場労働者を守る事よりも、工場労働者をどのように将来性のある業種へ転換させるかを、問題が深刻化する前に手を打つべきです。
【私の見解】
工場でロボットが使われているのは、今に始まったことではありません。しかし、ロボットでもほっておけばすべてやってくれる訳ではなく、それが、十分な性能を発揮し続けていくようにメンテナンスをしながら動かしていくというのが現場技術者の腕の見せ所です。
グローバル化する世界こそ、他の国と同じことをやっていては、存在価値がありません。我が国の強みはものづくりにあります。この強みを活かすことが、他の国と差別化を進めていくことに繋がります。必ずしもすべての工業がそういうわけではありませんが、ものづくりを支えているところをいかに守っていくかということも重要なことだと考えます。
○ついでにbobbyさんのブログの記事に関する見解も
【bobbyさんのブログの記事「押してもだめなら引いてみな」より】
日本では終身雇用という幻想が広く社会全体(経営者、労働者、家庭の中、裁判官、政府の官僚、政治家など)に深く浸透しています。雇用問題は、理論や制度の問題ではなく、風竜胆さんを含む多くの日本人のエモーショナルな問題になっています。こういう問題の解決は、制度を変えただけでは解決しないと思われます。この状況を改善するには、「みえざる手」に任せるのではなく、「誰か」が適当な戦略を持って雇用・労働改革を進める事が必要と思われます。
【私の見解】
まず、私が「エモーショナル」であると書かれていることは心外です。解雇規制をなくすことが、論理的におかしいと言っているつもりなのですが。自分と違う意見を「エモーショナル」と決めつけるのは単なるレッテル貼りではないでしょうか。
また、私は転職しやすい環境をつくることに対して異論を述べているわけではありません。パイの少なくなっているときに、解雇が容易にできれば、ダメな経営者は努力するより先に、安易な道を選びかねず、それが益々経済の悪化を招くだろうという極めて論理的な理屈を言っているだけなのですが、理解していただけないのは残念です。
(ぽちっとお願いします。) ⇒
「時空の流離人(風と雲の郷 本館)」はこちら

「本の宇宙(そら)」(風と雲の郷 貴賓館)はこちら













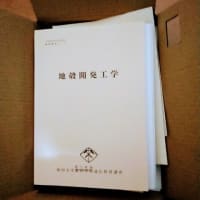













【トヨタに学ぶ「日本型雇用の守り方」】
http://blog.goo.ne.jp/jyoshige/e/f7ac59d3183d49717393dc468ef463cc
上記の記事は「一時的な応援要員として」という事ですが、これからは「一時」が何年も続く人も出てくるでしょう。トヨタの社員でさえいられれば、どんな業務でも甘んじて受け入れるという事。こういう人事を行わなければいけない企業側も、受け入れる社員側も、ともに不幸ですね。
http://blog.goo.ne.jp/magicgirl/e/8d224def8bc8c0d67cf883974909bb11
ただ、「上場企業において株主が経営者(代表取締役社長とか役員とか)を選任する目的は、四半期毎に公開が義務付けられている決算発表で企業の業績を向上させ、株価を上げて、株式市場における企業価値を高める事です。これは誤解の無いようにしておく必要があります。」と書かれていたbobbyさんが、それは経営者として当たり前の行動であると言われないのは、少し意外な気がしました。
ここの部分は、しばしば多くの方が「感情的」になるようですので、慎重な表現方法に致しました。
ところでJoさんの下記の「なぜ、日本人は世界一長い労働時間をぬってまで、自己のプライヴェートを書くのか」から下の内容も興味深い意見です。
http://blog.goo.ne.jp/jyoshige/e/926e0fa7c62bcebbfb2aa37de3872d19
子供が未来の職業の夢を語る時、○○会社に入りたいと考える人は少ないでしょう。大学で就活をする時も、やはり特定の職種(技術者、研究職、営業職など)を考えていると思います。しかし実際に入社すると、特に大企業では、職種と配属と勤務地は会社側がほぼ一方的に決め、それも定期的に、配置転換という名のもとに、辞令によって変え続けられます。職業選択の自由は、雇用維持の名のもとに、日本の大企業では有名無実化しています。日本のサラリーマンから労働のモチベーションを奪い、生産性を低下させている大きな原因のひとつではないかと思います。