まだ「リスク管理」という言葉がなかった時代にも、成功を収める人々は、トラブルや失敗を巧みに回避する策を講じてきました。しかし、リスクを恐れすぎるとかえって……。私たちにリスクと向き合う術を解説する『
リスク、不確実性、人類の不覚』から一部を抜粋、加筆のうえお届けします。
不確実性のもとで暮らす時代の意思決定
歴史とは本当に難しいと思います。同時代に作成された文書である「一次資料」や遺跡の新たな発見や研究で、これまで考えられてきた「史実」が覆ることがよくあります。この点では、「将来のことはわからない」という意味で使う「不確実性」が、過去にも適用されます。
例えば、これまでの関ケ原の戦いというと、そのイメージは、「東西両軍の伯仲した戦いだったのに、日和見(ひよりみ)していた小早川秀秋が家康の(東軍方での参戦を促す)『問い鉄砲』で裏切ることにより決着した」というものでした。
ところが最近の研究では、「開戦の前には、すでに勝敗の趨勢(すうせい)は決していた」など、そのイメージも大きく変わりつつあり、今後の映画や大河ドラマはどう扱うのだろうと心配になります。
イメージといえば、2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、三谷幸喜さんによる脚本の妙味から、源頼朝や義経、北条時政や義時らのイメージが変わったり、新たに作られたりして、ネット上でも話題になっています。
「史実と違うのでは」といったコメントも見かけますが、そこはドラマですから面白ければいいのでは、と私などは思ってしまいます。ここが歴史物の難しいところです。
「鎌倉殿の13人」を観て改めて思うのは、昔の人は、将来のことが一切わからない不確実性のもとで暮らし、その不安はいかばかりであったろうかということです。おそらく当時は、同時代のこともすぐにはわからない、また、あとになっても正確にはわからないような状況だったでしょう。
「不確実性」のもとで生き、武家政権を確立した源頼朝(鎌倉市・源氏山公園の銅像)(写真/shutterstock)
[画像のクリックで拡大表示]
そうした中で、例えば頼朝が、平家打倒の旗揚げ(1180年)や木曽義仲の追討といった重要な意思決定をするには、神仏のご加護を願いつつ、周囲のアドバイスを参考にしながら、あとは「直感」に任せるしかありません。
頼朝が願文を捧(ささ)げたり寄進したりした寺社は、関東地方(当時は坂東)を中心に数多くあります。鎌倉の鶴岡八幡宮はあまりにも有名です。また、北条氏や三浦氏などの有力武将に加え、鎌倉を本拠地にして以降、大江広元や三善康信など京都から下ってきた文官たちにも支えられます。










 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture> </picture>
</picture>





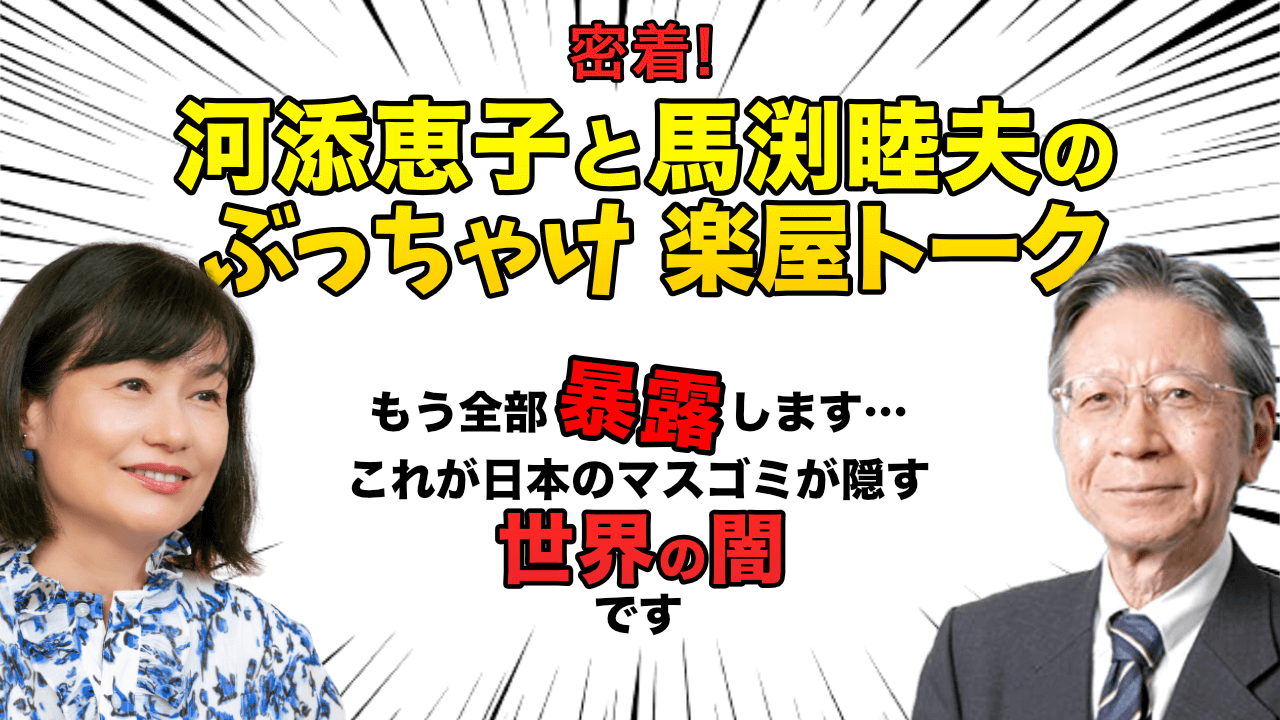









時代遅れのバリウム透視何故?
1. 単価が安いから。 2. いっぺんに沢山捌けるから。 3