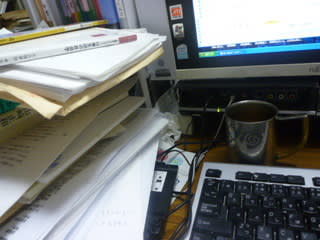9時、起床。ハム、チーズ、レタス、トースト、牛乳の朝食。メールで提出されてくる演習のレポートをチェックし、PDFファイルに変換する(コースナビ上にアップして全員が全員のレポートを読めるようにする)。明日の講義「日常生活の社会学」の試験問題を作成する。う~ん、これは難しいかも・・・というのは嘘で、ちゃんと授業に出ていればお茶の子さいさいの問題である。

昼食にざる蕎麦を食べて、午後から大学へ。
4限は大学院の演習(最終回)。小倉康嗣の博士論文『高齢化社会と日本人の生き方 岐路に立つ現代中年のライフストーリー』(慶応義塾大学出版会)を読了。大部の本だったが、前期で切りよく読み終えることができた。「補論一」の「社会学を生きる―私に刺さった「棘」と社会学―」は短い文章だが、実存的な内容で読み応えがあった。
「人は追い詰められ苦しんでいるとき、じつはとても小さな固定化された枠の中でもがいたりする。だがちょっと視点をずらして見てみると、その枠の外にはさまざまな隙間や居場所があり、大海原が広がっている。社会学はそれを気づかせてくれる学問である。だから自分自身の身体(経験)をそこに入れ込んでみよう。たんなる「知識」ではなく、自分自身が生きていくための「知恵」として考えていこう。他者や社会への想像力も、案外そこから生まれてくるはずだ。」(498頁)
彼にとっての「棘」、それは自分がゲイであることだった。
「ふと思い出しただけでもいろんな記憶がよみがえってくる。ある日、親友とテレビを見ていたとき、同性愛のタレントが出てきた。そのとき親友は、「こいつゲイボーイって言うとばい。気色悪かぁ!」―すかさずそう言った。そのとき私は、親友からも抹殺される存在なんだなぁと思った。当時、本当はなんでも話せる悪ガキ仲間がほしかったが、シモネタで仲間意識をつくれない自分がいた。嫌悪感を抱きつつ優等生を演じることで、かろうじて学校のなかでの自分の居場所を確保していた私は、毎日吐き気をもよおしながらも「勤勉に」学校に通っていた。その一方で、そんな自分をさとられたくなくて、いつもつくり笑いをしているような少年だった。
(中略)
家族という親密性の城塞にも自分の居場所を見出すことはできなかった。サラリーマンの父、専業主婦の母という典型的な近代家族のなかで育った私は、結婚して子どもを持って一人前という会社社会の価値観に染まっていた。だが将来、父のようなサラリーマンというライフスタイルを生きていくことはできない。かといって、それ以外の生き方を当時の私は知らなかった。自分には家族を形成する機会を持つことも許されず、もはや大人社会のなかで生きていくすべはないと思った。むろん、親に自分のセクシュアリティを明かすことなど到底できない。親を絶望に追い込むであろうことが、十代の少年にも痛いほどわかっていたからである。
自分の名前に対しても葛藤があった。私の名前は「康嗣」(やすつぐ)という。康嗣の「嗣」は、「世継ぎ」の「嗣」である。長男である私に、祖父が付けてくれた名前だ。孫思いの立派な祖父の、私が小さいころからの口癖は、「しっかり勉強して、立派な大人になって、いい嫁さんをもらって、小倉家の跡をしっかり継いでくれよ」だった。だが祖父の期待にこたえて結婚するのであれば、自分を偽りつづけて生きていかなければならない。そんな将来に希望を持てない私は、「あぁ、結婚できない自分は小倉家を途絶えさせてしまう。生まれてきちゃいけない人間だったんだ」と思えた。名前が重かった。」(499-500頁)
十代の少年が、誰にも悩みを打ち明けられずに、自分のことを「生まれてきちゃいけない人間だったんだ」と思っている。いたましいとしか言いようがない。しかし、時代は動いていった。ゲイであることを自ら語る人々の存在をメディアを通して彼は知るようになる。
「自分に刺さった「棘」にフタをせず、その「棘」を一生懸命に生きると、社会を相対化する眼が見開かれてくる。みずからの人生、そしてみずからが生きる社会は、わが身でつくっていくだとうい深い了解が生まれる。そこから新たな生き方づくり・社会づくりへの模索が始まる。そしてさらにそれは、試行錯誤しながらの下からの社会生成ことが力を持つ時代状況とシンクロすることがわかってくる。
この一連の過程のなかで、生きてちゃいけない人間だと思っていた自分が、生きてていいんだと思えるようになった。そして現在は、生かされているという感覚が強く私のなかに生成している。それは、私自身のひとつのエイジング・プロセスであると言えるが、同時にそれは私の社会学人生の底流でもある。」(501-502頁)
演習の唯一の受講生であるSさんが、私に質問した。「先生にとっての「棘」は何ですか?」―予想された質問である。「それはね」、と私は一呼吸置いて、観念したように言った、「自分が地球人ではないということなんだ」。Sさんはケタケタと笑った。予想された反応だった。やはり告白すべきではなかったな、と私は思った。「BOSS」の缶コーヒーが飲みたくなった。

「maruharu」でハムカツとタマゴのサンドウィッチ、アイスカフェオレ。今日は私を入れて男ばかり5人がカウンターに並んだ。きわめて珍しい光景である。穴八幡の境内を通って大学に戻る。

あ

うん
6限は演習「現代人と家族」(最終回)。プリントアウトしたレポートを提出してもらいながら、自分のレポートのテーマの説明そして宣伝をしてもらう。レポートというのは、とにかく所定の字数を埋めて出せばいいというものではなく、読者を想定して、読者をいかに説得するか、いかに面白がらせるか、そのために構成を考え、論理やレトリックを駆使して書くものである。だから書き上げたレポートは「ぜひ読んでみてください」と人に言えるものでなくてはならない。そういう気構えでレポートに取り組んでいけば、必ず腕は上がるものである。
この演習のテーマは「現代家族」であったが、一番相対化の難しいのが家族である。一番身近なものが実は一番手ごわいのである。家族とはそれぞれの人にとっての「棘」のようなものであるからだ。
石黒先生と「メーヤウ」で夕食。タイ風カントリーカリー(★3つ)を初めて注文したが、辛かった。同じ★3つのインド風ポークカリーと同じレベルとは思えなかった。★3.5ではなかろうか。ラッシーの力を借りて完食。

あゆみ書房で以下の本を購入。電車の中で読み、蒲田に着いてから、「シャノアール」でも読む。
吉田篤弘『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(中公文庫)
エンツォ・トラヴェルソン『全体主義』(平凡社新書)
『シリーズ日本の近現代史⑩ 日本の近現代史をどう見るか』(岩波新書)
山口謡司『ん』(新潮新書)

カントリーカリーの辛さをアイスココアで払拭する