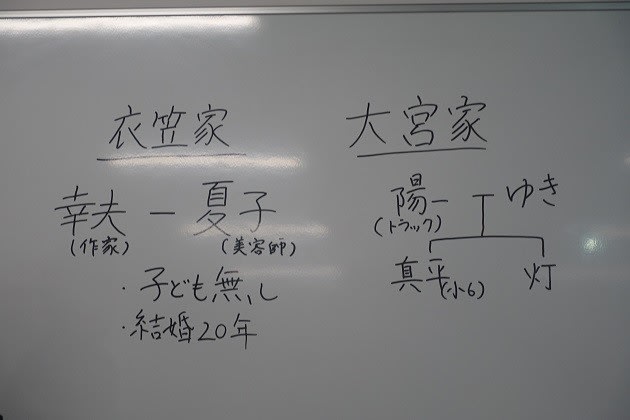7時半、起床。
朝飯前に一仕事終える。もしかしたら今日は一日、これにかかりきりなるかもしれないと思っていたのだが、案ずるより産むがやすしで、ホッとする。
トースト、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

午後、昼食をとりがてら散歩に出る。今日も冬曇りの一日だが、風はなく、それほど寒くもない。

「テラス・ドルチェ」で食べることにする。

アラビアータを注文。カップスープとミニサラダが付いて来る。

アラビアータとナポリタンは見た目が似ているが、アラビアータの方はピリ辛である。

サイホンで淹れたコーヒーがついて980円なり。

木曜日の大学院の演習でYさんが報告する予定の資料に目を通しておく。

川本三郎「モダン都市東京と私娼―永井荷風の作品を中心に」。
私は永井荷風の小説の熱心な読者ではないが、彼の日記(断腸亭日乗)には大いに関心をもっている。出版されている日本の作家の日記では、荷風のものと高見順のものが双璧である。2人とも書いているときから刊行されることを意識して日記を書いていた。読者を想定した日記であり、その意味では、ブログに通じるものがある。

資料に目を通し終えて、店を出る。サンカマタ商店街の「ちよだ鮨」は、先日見たときは、閉店するのかと思ったが、看板を含めてリニューアルしているようである。

資料の中で言及されていた荷風の作品で参照したいものがあって、駅ビル東館の「くまざわ書店」に行ってみる。


お目当てのものはなかったが、代わりに、加藤郁乎編『荷風俳句集』(岩波文庫)を見つけて購入。ちょうど今頃の時期で荷風らしい句を二三選んでみる。
下駄買うて箪笥の上や年の暮
雪になる小降りの雨や暮の鐘
用もなく銭もなき身の師走かな
先ほどの資料の中で川本は荷風の日記の中に登場する娼婦たちが公娼から私娼に代わって行く過程をモダン都市東京の形成と関連させて論じていたれども、たしかにそれはそうだろうと思う一方で、荷風の懐具合がしだいに貧しくなっていくこととも関連しているのではないかと、私は考えた。

家路を辿る。

書庫で荷風の作品を捜しているときに、西崎憲編訳『短編小説日和―英国異色作家傑作選』(ちくま文庫)をつい手に取ってしまい、「短編だから時間はとらないだろう」と言い訳をしながら、しばし読み耽る。こういうときの読書が面白いのは誰もが経験的に知っていることである。

最近の文庫本は字が大きくなってきているけれども、昔の文庫本(とくに新潮文庫)は本当に字が小さくて、裸眼ではつらい。老眼鏡(くっきり)+ハズキルーペ(大きく)の併用で対応するしかない。

今夜は娘が仕事終わりに顔を出した。娘のリクエストで夕食は餃子である。

餃子の美味しさのポイントは、皮の焼き加減と中身のジューシーさであると思うが、餃子の大きさ(皮と中身の比率)も重要である。大きすぎても小さすぎてもいけない(大きすぎる方が罪が重い)。その点、食べなれていることもあるだろうが、我が家の餃子はこのバランスがいい。二口で食べられる大きさということだろうか。三口では大きすぎるし、一口では小さすぎる。
3人で2皿(40個ほど)を食べた。

デザートは杏仁豆腐。

12月22日(金)から24日(日)の3日間、吉祥寺の「櫂スタジオ」で、娘が主宰をしている劇団「獣の仕業」の公演(第13回)がある。
タイトルは「THE BEAST」
(チラシから引用)十周年、「獣」の名の付く作品です。これまでの公演でマイナーチェンジを重ねながら積み上げてきた歴代の演劇言語を総動員しました。そして作品のテーマはずばり「演劇」です。個人的に節目であるからなのか、近頃、「演劇が終わる日」ということについてよく考えます。どんなに身を捧げようと、演劇はいつか終わります。「私」が演劇ができなくなる日、「私」が演劇を見られなくなる日、もしくは演劇そのものが消えてなくなる日・・・・。それは一体どんな日なのでしょう。まったく想像もつきません。しかしくっきりとしていることが一つ。「その日」は必ずやってきます。
いつか来るその日よりも早く「演劇のための作品」を作りたいと思いました。今から千年後の、演劇が終わろうとしている世界を舞台にした「THE BEAST」。私自身も皆様と一緒に、見届けたいと思っています。(代表 立夏)

「THE BEAST」はこんなストーリー(チラシから)
かつて地球に多く生息していた“エンゲキジン”という動物が滅びようとしていた。あるものは子供ができたため、あるものは演劇で食っていけず、あるものは・・・・そして千年後。とうとう地球上のエンゲキジンはある男ひとりになってしまった。男はかつて十年続いたある劇団のメンバーだったが、昔の仲間との思い出を忘れることができずに、滅んだ仲間を泥で作り稽古を繰り返していた。そんな彼の元にひとりの女がやってくる。女は言う。「私の名はシュジンコウ。月からやってきた“カンキャク”最後の生き残りです」 千年の時を越え、エンゲキジンとカンキャクが出会う。そして再び演劇が始まる――
現在あるいはかつて演劇に身を捧げたすべての演劇人へ、そして演劇を愛するすべての観客へ贈る獣の仕業流、全身全霊“演劇賛歌”

吉祥寺櫂スタジオ(吉祥寺駅から徒歩12分)
12月22日(金) 15:00 19:00
12月23日(土) 14:00 19:00
12月24日(日) 14:00 18:00
上演時間は80分から85分
料金 2000円(前売・当日ともに)
予約は→こちらへ