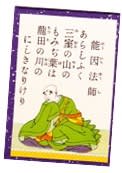すっかりお正月気分も抜けきっている時に、なぜまた百人一首かということですが、
たまたま、JAFの新年号(月刊情報誌)に取り上げられていて、JAFのことだから京都・奈良を巡る企画の記事でした。
そんなわけで・・・。
普通、百人一首といえば、小倉百人一首のことで、何で小倉・・というのか?
またまた、無粋な質問で申し訳ありませんが,ちょっとおさらいしておこうと思います。
“小倉百人一首は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した公家・藤原定家が選んだとされる
私撰和歌集である。 その原型は、鎌倉幕府の御家人で歌人でもある宇都宮蓮生(宇都宮頼綱)の求めに応じて、
定家が作成した色紙である。 蓮生は、京都嵯峨野(現・京都府京都市右京区嵯峨)に建築した別荘・
小倉山荘の襖の装飾のため、定家に色紙の作成を依頼した。
定家は、飛鳥時代の天智天皇から鎌倉時代の順徳院まで、100人の歌人の優れた和歌を一首ずつ選び、
年代順に色紙にしたためた。
小倉百人一首が成立した年代は確定されていないが、13世紀の前半と推定される。成立当時には、
この百人一首に一定の呼び名はなく、「小倉山荘色紙和歌」「嵯峨山荘色紙和歌」「小倉色紙」などと呼ばれた。
後に、定家が小倉山で編纂したという由来から、「小倉百人一首」という通称が定着した。”
(ウイキペディアから)
なるほど・・。
小倉山は、京都の嵐山にある標高295mのこんもりとした実在の山なんですね。
ここに山荘があった・・・。
 右手の低いこんもりとした山ですね。
右手の低いこんもりとした山ですね。
これをカルタとして、いろいろな楽しみ方や競技に発展させたのは何時ごろかわかりませんが、
上の句と下の句をうまい具合に読み札と取り札に配置した、そこに文学的な和歌に加えて、競技てきな面白さ、
さらにいえば武士、僧侶、姫などの絵柄も楽しめるなかなかのものといつも感心しています。
ちょっとだけですが、お正月に遊んだ札をスキャナーで読んでここにアップして見ます。




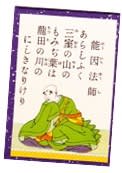
たまたま、JAFの新年号(月刊情報誌)に取り上げられていて、JAFのことだから京都・奈良を巡る企画の記事でした。
そんなわけで・・・。
普通、百人一首といえば、小倉百人一首のことで、何で小倉・・というのか?
またまた、無粋な質問で申し訳ありませんが,ちょっとおさらいしておこうと思います。
“小倉百人一首は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活動した公家・藤原定家が選んだとされる
私撰和歌集である。 その原型は、鎌倉幕府の御家人で歌人でもある宇都宮蓮生(宇都宮頼綱)の求めに応じて、
定家が作成した色紙である。 蓮生は、京都嵯峨野(現・京都府京都市右京区嵯峨)に建築した別荘・
小倉山荘の襖の装飾のため、定家に色紙の作成を依頼した。
定家は、飛鳥時代の天智天皇から鎌倉時代の順徳院まで、100人の歌人の優れた和歌を一首ずつ選び、
年代順に色紙にしたためた。
小倉百人一首が成立した年代は確定されていないが、13世紀の前半と推定される。成立当時には、
この百人一首に一定の呼び名はなく、「小倉山荘色紙和歌」「嵯峨山荘色紙和歌」「小倉色紙」などと呼ばれた。
後に、定家が小倉山で編纂したという由来から、「小倉百人一首」という通称が定着した。”
(ウイキペディアから)
なるほど・・。
小倉山は、京都の嵐山にある標高295mのこんもりとした実在の山なんですね。
ここに山荘があった・・・。
 右手の低いこんもりとした山ですね。
右手の低いこんもりとした山ですね。これをカルタとして、いろいろな楽しみ方や競技に発展させたのは何時ごろかわかりませんが、
上の句と下の句をうまい具合に読み札と取り札に配置した、そこに文学的な和歌に加えて、競技てきな面白さ、
さらにいえば武士、僧侶、姫などの絵柄も楽しめるなかなかのものといつも感心しています。
ちょっとだけですが、お正月に遊んだ札をスキャナーで読んでここにアップして見ます。