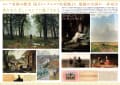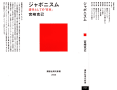私が見に行きたかった作品は、以前にも観たことがある作品ばかりであると思う。特に前回のトレチャコフ美術館展で観た記憶があるが、定かではない。当時は図録を購入していなかった。
今回の展示で新たに惹かれた作品は、3点あった。

まずはフィリップ・アンドレーエヴィチ・マリャーヴィンの「本を手に」(1895)。これは女性の肖像画のコーナーにあった。私としては「忘れえぬ女」(イワン・ニコラエヴィチ・クラムスコイ、1883)よりも惹かれた。
むろん美術史的にも、技術的な面でも、さらに影響力からも「忘れえぬ女」の価値は高いのだろうが。決して上流な家庭の人でもないが、本を読むだけの知識もあり、だが着飾ることもない女性の像は、社会が大きく胎動している当時のロシアの女性のある側面を描き切っているように思えてならない。根拠は何かと問われるとこれを示すことはできない。解説では画家の妹で、28歳という若さで亡くなった女性であるらしい。
顔の皮膚の艶などから早世したにしては、たくましさすら感じられる。意志の強さも感じられる。知的な印象を強く受ける。背景の白い壁とそこに写った濃い影が人物の存在感を強くしている。白い壁と白い服、それをきわだたせている暗い椅子の後ろの闇、そして手にする書物が物語を感じさせる。現実の生活に裏打ちされた存在感のある女性像である。

「忘れえぬ女」(イワン・クラムスコイ、1883)は、チラシの面を飾っている。わたしにはこの女性の視線はとても冷たく、馬車の上にいて人を見下す位置にいる自分の位置に無自覚である、と感じる。この時代の新しい女性像のような解説にいまひとつピンとこないところがある。トルストイの「アンナ・カレーニナ」の主人公、ドストエフスキーの「白痴」のナスターシャ・フィリッポヴナなどのヒロインになぞらえたりしているらしい。解説では貴族ではないが豊かな女性でもあるとされているが、どこか意志を持たない表情に思える。その割には高い位置から画家を見おろすことで、見るわれわれを見下している視線である。画家とモデルの関係が近代的ではない何かに支配されている。
「本を手に」の女性と比べるとどこか架空の、存在感の薄い女性である。

グリゴーリー・クリゴーリエヴィチ・ミャソエードフの「秋の朝」(1883)を見たとき、どこか病的に執拗な執念を感じた。
この細部にまだ異様にこだわった写生の根拠は何処にあるのか、中心のない一面の黄葉の森のせせらぎの一場面へのこだわりは何か。疑問が湧いて来た。その答えを見つけるだけの情報はない。
解説では、皮肉屋であり美術界の周囲とも打ち解けず、孤独感を深めていたという記述がある。それがこの作品に反映しているのかは私は断定はできない。だが、このように執拗な写生へのこだわりに、当時の美術界のありように対する違和感をぶつけたような気迫を感じることも確かにできる。

ロシアの大地では白樺が思い出される。この白樺を描いた作品ではエフィーム・エフィーモヴィチ・ヴォルコフの「10月」(1883)に惹かれた。川に向って拡がる白樺の疎林は、岸辺に立つ人物に向って開かれているようだ。手前から人物に向かう踏み跡でてきた道が、白樺の年輪よりも長い時間の経過を暗示している。人の営みの長さを暗示している。このような景色に私はいつも惹かれる。描かれた肖像画よりも人の営みについて多く語ってくれるのが、このような風景画ではないだろうか。