
この暗くどんよりしたロシアの自然と一体化したかのような現実感。荒涼たる写真群は人間の生きることの苦悩を写し出す。
人は土地でさえ、家族でさえ権力の思いのままに奪われ、もはや神の不在を問うことさえ愚直に思えるほどだ。このペシミズムは現代のロシアを提起しているのか、それとも人類の普遍的な営みの危機を訴えているのか。
2時間強、観客はこの苦痛に耐えている。その時間は映画の登場人物と共有する。けれど、映画館を出るとそこには秋の明るい日差しが見える。このギャップは何だろうかと訝う。
あいかわらずのズビャギンツェフの、出し惜しみに近い説明不足は、苛々感を超えて壮大な世界のペシミズムに辿り着く。彼の個性なんだろうが、どこか明るさが見える視点がないのだろうか、、。後味もよくないネ。
けれど、この徹底したペシミズムからはこのような映画芸術が誕生する。好きではないが、秀作であることも事実。










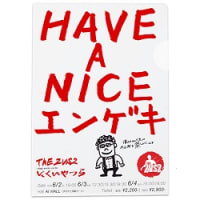






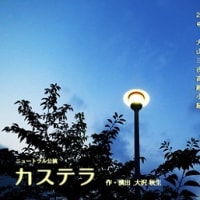







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます