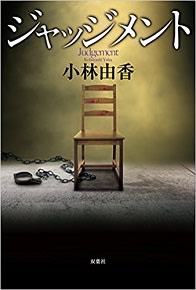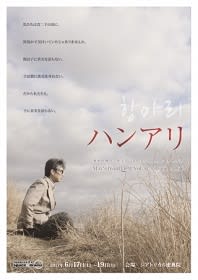巨匠の遺作とやらを随分見てきた。恐らく作家は遺作なんて考えずに映画を撮っていたのであろうから、遺作なんてという括りで映画を語ることは意味のないとは分かっている。でも語りたい、のである。
90歳。体力の衰えも顕著なはず。でも映像への衰えは全く感じられない。冒頭の、丘の上に立つ教授とその教え子たちの牧歌的な美しさはみずみずしく美しい。ワイダが映像を作品の中心に据えていたことが分かる。
光と影を意識 . . . 本文を読む
結構好きな石持の新作だ。これが何と、殺し屋家業の話なんです。けれど暗くない。明るいわあ。人を殺して何の罪の呵責もないのが不思議ですが、まあこれは小説ですから、、。
短編集で、読みやすい。最後の章は何と自分が殺しの標的になってしまう。まあ、なかなか面白い。こんな殺し屋に彼女がいるのが不思議だ。もちろん彼女は彼氏の職業を知っている。
それほどミステリー的に過ぎれているかといえばそうでもないが、まあ . . . 本文を読む
僕にとっては初めての劇団だけど、名前は知っていた。中川氏も対談等では見知っていた。前作も(見てはいないが)難しい新左翼劇だったし、期待するところ大であった。
主人公はケースワーカという立派な仕事をする非正規雇用の男性である。実際舞台では、ケースワーカーの業務内容を見せているが、あんな高度な仕事を非正規の人間にさせているのだろうか、非正規雇用の人間には事務ワークぐらいしかさせていないのではないか、 . . . 本文を読む
目には目を歯には歯を、という復讐法に焦点を持ってきたのがまずこの小説の成功の秘訣だろう。このプロットはとても面白いし、そして否が応でも考えさせられる。つまり読者が他人事と言ってられない何かが、常に残滓となって自分に乗りかかって来るからである。
これをテーマに5編の短編。
すべて一気読み。読むのが厭でも、本を離せなくなるから不思議である。これは作者の力量がそうさせるのか、それともこの深淵たるテー . . . 本文を読む
自前の劇場を持つ劇団である。そこそこ立派な劇場で、天井までの高さもある。出し物は地方の中小スーパーの話である。隣町に大型商業ゾーンが出来るという。さて、このスーパーは生き残ることができるのか。
店員さん、新米店長などの日常がじっくり描かれる。スーパーという親近感のある話なので、とても他人事と思えない何かがずっと存在する。このスーパーもこの街に乗り込んできた時には、今の商店街に同じ思いをさせたらし . . . 本文を読む
いつも厭なざわざわ不安感をあおるファルハディの映画。今回は多少ましだったかな。意外とシンプルで、分かりやすい作品でした。その分ちょっと彼らしき毒性が薄まった感もする。「セールスマンの死」との対比は作家風色付けが見え見えで少々鼻白むが、、。
この映画で何点か分からないことがあります。
1.彼女は本当に強姦に遭ったのかどうか。
怪我はしたようだが、その怪我も何故そうなったのか分からない。強姦でな . . . 本文を読む
力作である。登場人物も多い。なのに一人何役も掛け持ちもある。それだけボリューム感も豊富な、深く掘り下げられた一在日韓国人の人生が語られる。
日本に来るときは船に乗り、それこそ苦渋の難旅である。そしてたまたま住み着いたぼろ屋に前の住人の表札か掲げられている。それが太田という名であり、すなわちそれが彼らの日本名となる。そんなものか。僕はかなり驚くが、そういうことが淡々と語られる。
そして祖国では政 . . . 本文を読む
「今時」って、こんな言い方をするのは失礼だろうか。オーソドックスで、演劇の魅力をいやがおうに知りつつ、されど周りに目もかけず、おのれの信じる演劇だけを創作し、演じることに最高の喜びを感じる劇団がここにいる。
そんな感じがします。この劇団は。
小説の朗読から始まる不思議な劇だ。世間から断然感をもって隠遁したはずの主人公。けれど彼女の周囲では不思議なことが続く、、。
面白い。何かわからないが、こ . . . 本文を読む
うーん、このどんな法律でも通ってしまう忌まわしい世の中に、颯爽とさわやかに吹く一陣の風。素敵なミステリー小説です。
けれど、ミステリーの本筋から言うと、どう考えてもああはならないと、多少は苛々するけれども、それでもぐんぐん読ませる作者の青春への息吹が並大抵ではない。なんだかんだ言って、一気読みでしたね。
この小説をミステリーとして評価するには僕はまだまだ年寄りだ。ミステリー的小説だということで . . . 本文を読む
やはり読ませる作家である。内容はどう考えてもありえない警察小説だが、一気読みである。
人間が書かれている。この作家の一番の読みどころである。ぐいぐい引き込まれる。
冒頭、愛妻が殺戮されるところから始まる。しかし、ポツンと、その後が書かれない。通常の警察での出来事が普通に語られる。あれ、あの事件はどうなったんだろうと誰もが思う、、。
それがこの作家のうまい手である。徐々に小出しする。そしてこの . . . 本文を読む
今回はいつもより大きな劇場での公演だ。というか、あのアイホールが巨大に見える。これが美術のすごさだろう。まずそのことに驚く。
この劇団の特性は日本人に忘れられかけている作家の復権を題材にしているということだろう。
横光利一の「機械」、倉田百三の「出家とその弟子」、そして今回の梅崎春生の「侵入者」「桜島」、これらの作品は今やよほどの愛読者でない限り読むことのかなわない作品群であります。これらを現 . . . 本文を読む
トリイホールの出し物ではかなりまともでハートフルな演劇であると思う。5人の女性たちの、花香る高校生時代から70歳ぐらいまでの、ある意味現代版女の一生である。
この林龍吾という人は女性の機微をかなりお分かりだと思います。想像だけでは描けない5人の女性の実像をさらりとエッセンスを詰め込んで色濃く描いています。
それぞれの話が語られるのだが、やはり主軸の、ことねさんと川田恵三さんのカップルの話が後々 . . . 本文を読む
今回は前回から転じて小さな小屋での上演。客席をゆったり取っているので、舞台部分は超小さく狭い。おのずから今までのように思う存分暴れることはできない感じである。
そんな環境のもと、劇は始まる。林が演出を担当しているせいか、彼は出演していない。となると、おのずから都 美佳に負担がかかることになるのだが、、。
100分ぐらいのランタイムなんだが、意外と長く感じる。いつもはミステリータッチだが、今回は . . . 本文を読む
きれいないい映画ですね。でもこんな灯台守の映画で、自然描写も美しく、みんなキリスト教に目覚めて一度だけ赦しをなんていうテーマで、すこぶるきれいきれいな映画なんですけど、少々胡散臭いと思ったのは僕が胡散臭いから?
人生の大波をこんな波立ちのさざ波にして、人生ってこんなに美しいと思わせる映画って、どうなのと感じる僕はほんとにいやらしいと思います。ひねくれてます。
退屈はしなかったけれど、何かなあ、 . . . 本文を読む
名優5人、そしてオールロケ、俳優陣に重くのしかかる演技要求。そう、舞台を見ていると思えばこの作品、ぐっとくるんですが、これは映画なんだよなあ。映画だから、少なくともリアル感は必要だと思う。
主人公が認知症でほとんど一瞬しか理解できていない人間相手に、色濃く人生を殴り描いても、、。こういう言い方は好きではないんですが、リアルではなかったですね。小林の作家的思いは、観客の、少なくとも僕には伝わってこ . . . 本文を読む