「おむすびころりん」は、日本のおとぎ話の一。「鼠の餠つき」「鼠浄土」「団子浄土」などともいう。
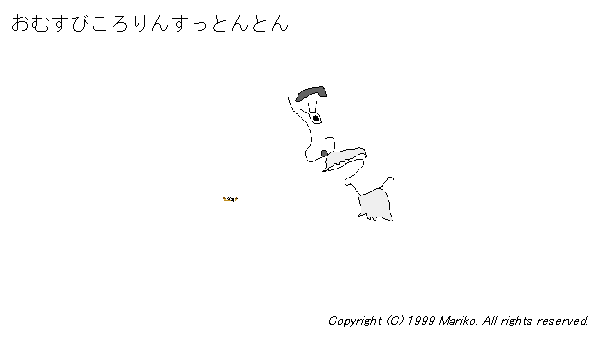 山でおむすびを穴に落としてしまったおじいさん。穴に入るとネズミたちがいて、帰りに宝物を持ち帰ります。
山でおむすびを穴に落としてしまったおじいさん。穴に入るとネズミたちがいて、帰りに宝物を持ち帰ります。
そのことを知った隣のおじいさんは、同じように山に行ってネズミの穴に入りますが、ネズミたちを驚かしたため、闇の世界に閉じ込められてしまいます。
※動画は「Welcome to Mriko Home」さんからお借りしました。クリックすると動きます。
「おむすび ころりん すっとんとん」 のフレーズで御馴染の噺です。
「おむすびころりん」の話は様々なバリエーションが存在します。
・ネズミはおじいさんに噛み付いたので、おじいさんは降参した。
・ネズミが浄土の明かりを消してしまったために、そのままおじいさんが3年3ヶ月のあいだ行方が知れなくなった。
・そのままおじいさんがねずみもち(もぐら)となった話などがみられる。
また、「ねずみ浄土」と「おむすびころりん」は別々の昔話として区分している書籍もあるのだそうです。
話にこのようなバージョンが存在するのは、今日みられる暴力的表現を排斥しようとする運動の影響が強い。
古くからある口承文芸で室町時代に『御伽草子』として成立したと見られる。あらすじの特徴は「こぶとり爺さん」と同じく、無欲な老人と強欲な老人の対比であり、因果応報など仏教的要素も併せ持つが、『グリム童話』にある「ホレ婆さん」との類似性も指摘されているとおり、筋立てはありふれたもので独自性は見られない。特徴的なのは異界の住人であるネズミが善人に福をもたらすという筋立てであり、ネズミは「根の国の住人」(根住み)とも見られており、米倉などにあるネズミの巣穴は黄泉の国、浄土への入り口と言い伝えられる地方がある。
またこの話は鼠を神の使い、あるいは富をもたらす者とする民間の観念が反映されている。この昔話のような鼠の世界が地中にあるとする観念は、古くからあり室町時代物語の『鼠の草子』や『かくれ里』にも克明に描写されている。
この話の中で歌われる鼠の餅搗き歌は地方によって変化があり、土地によっては<鼠とこびきは引かねば食んね、十七八なるども、猫の声は聞かないしちょはちょちょ>(新潟県)のように実際の民謡が盛り込まれている例もある。
一般的に「ねずみ浄土」・「おむすびころりん」の名でよく知られているこの話は、異郷訪問譚に分類されます。地下にあるネズミの楽園を訪ねて財宝をもらってくる昔話で、全国に分布し、特に東北と中国地方に多くの類話がみられます。東北地方では豆が、関西以西(南)では団子がころがり落ちる話の方が多く、九州地方では団子が穴に落ちていく音が強調されています。(例だだごろ、だだごろ、すってんとん)
 この話が全国的に巾広く分布している背景(・ネズミは神にかかわる動物(俗信)・生活苦のない豊かな浄土への憧れとものを貯えるネズミの習性との結合)「地蔵浄土」は「鬼の博打」とも呼ばれ、主人公が地下の地蔵の所へ導かれ、金や宝を得て帰ってくる昔話で、地蔵は現実と冥界の境に立つ人を救うといわれています。
この話が全国的に巾広く分布している背景(・ネズミは神にかかわる動物(俗信)・生活苦のない豊かな浄土への憧れとものを貯えるネズミの習性との結合)「地蔵浄土」は「鬼の博打」とも呼ばれ、主人公が地下の地蔵の所へ導かれ、金や宝を得て帰ってくる昔話で、地蔵は現実と冥界の境に立つ人を救うといわれています。
全国的に分布する「ねずみ浄土」の方が古いと考えられますが、異質の秩序の支配する異郷へ、そこの住人の案内、あるいは無邪気にまよいこんだ結果、不思議が起こるというモチーフは共通でどちらの話にも、まねをして無理やり異郷を訪問して失敗する隣の爺婆型(舌きり雀・こぶとり爺さん等)の話がついています。
では、「ねずみ浄土」のお話を紹介しましょう。
「ねずみの浄土.」
ある所に与兵衛とお房という仲の良い老夫婦がおりました。
与兵衛さんは、朝、目を覚ますと、「ほい、ほっほっ、ほい、ほっほっ。」と体を動かし、お房さんとあさげをとりました。与兵衛さんは箱膳に箸をしまうと、
「ではら、お房、いってくらぁ。」
といいます。するとお房さんは
「はい、いってくらせ。」
とおにぎりを三つ渡します。
こうして毎日、与兵衛さんは、お房さんの握ったおにぎりをもって山や畑に出かけました。
春、彼岸の日、与兵衛さんは山菜を取りに山に入りました。背負い籠の中に、ぜんまいやら蕨(わらび)やら、たくさんとれたので、ちょうど良いあんばいの石に腰掛けて、お弁当をひろげました。
するとおにぎりがひとつ、与兵衛さんのひざから転がり落ちました。
「ああっ、お房のおにぎり…。」
おにぎりはコロコロコロところがっていき、与兵衛さんは慌てて追いかけていきました。
「おにぎり 待て待て ほいほっほ。」
「コロコロ コロリン コロコロリン。」
「待て待て おにぎり ほいほっほ、待て待てほっほ 待てほっほ。」
「コロリン コロコロ コロコロリン。」
おにぎりはコロコロと草むらをころがり、木の枝をピョ~ンとはね、切り株の下にある穴に転がり落ちました。
与兵衛さんは切り株の穴に手を入れて、おにぎりを探しました。穴の中は広く、与兵衛さんの手はどこにも届きませんでした。与兵衛さんが不思議に思っていると、
「コロコロ コロコロ おにぎりっこ。もっとくれろ、もっとくれ。」
と穴の中から聞こえてきました。
不思議に思った与兵衛さんは、おにぎりをもう一つ、穴の中に入れました。するとおにぎりは、コロコロと転がって、穴の中に消えていきました。
しばらくすると、また穴の中から声が聞こえてきました。
「コロコロ コロコロ おにぎりっこ。 うんめぇかった、うめかった。じじさ、こっちにおいでなさい。」
与兵衛さんは、どこから声がしたのかと、穴の中を覗きました。しかしあたりは真っ暗で何も見えません。与兵衛さんはもっとよく見ようとぐいっと身をのり出しました。
その瞬間、与兵衛さんは穴の中へコロコロコロと転がり込んでしまいました。
しばらくすると与兵衛さんは、穴の底にいました。そこにはお地蔵様がおられました。
「ほへっ? お地蔵様がおらを呼ばれたのかな? なら、おにぎりを転がして失礼しました。ここにもうひとつ、泥のついてないおにぎりがあるすけ、どうぞ、許してくらせ。」
与兵衛さんは残っていたおにぎりをお地蔵様に供えました。すると、穴の奥からもう一度、与兵衛さんを呼ぶ声がしました。
「じじさ じじさ うめかった。 こっちにおいで、おいでなさい。じじさ、じじさ、おいでなさい。」
与兵衛さんはびっくりしてお地蔵様を見ました。するとお地蔵様は目を開けられると、
「与兵衛さん、与兵衛さんを呼んだのは私ではない。この穴の奥に住むものがよんだのじゃ。」
「お地蔵様。」
与兵衛さんはお地蔵様が話されたのできょとんとしました。
「よいか、与兵衛さん。この奥に行きなされ。しかし、けっして猫の鳴きまねをしてはいけませんよ。」
お地蔵様はそう言うとまた目を閉じられました。
与兵衛さんはしばらくぼんやりしていましたが、「わかりました、お地蔵様。」と言うと奥の方へ向かって歩いていきました。
しばらく歩くと穴の中が薄ぼんやりと明るくなってきました。するとまた、声が聞こえてきました。
「じじさ、よくおいでくださいました。」
与兵衛さんは声のする足下を見ると、ネズミが三匹頭を下げていました。
「わしを呼んだのは、お前さま達かね?」
「はい、わたすたちです。 おにぎりっこ、うめかった。ちょど、まま焚くひまもなくて困っておりました。ありがたくいただきました。」
与兵衛さんが耳をすますと。チュチュチュ、チュチュチュと、ちいさな泣き声がします。
「おらとこのムスメッコが三人。」
「おらとこのムスメッコも二人。」
「おらとこなぞ五人もムスメッコが産気づいてしまって、今、やっと、産み終えたばっかりさ。」
「・・・それは難儀な事でした。」
与兵衛さんはネズミ達の話にすこしびっくりしました。
「で、じじさ、これからお祝いのお餅つきをしますさ。じじさも一緒にお祝いしてもらえないだろかね?」
与兵衛さんは、目を細めて答えました。するとあたりにぽつぽつちいさな明かりがつきました。それはネズミのぼんぼりでした。穴の中にはたくさんのネズミの家があり、のきが幾重にも重なって、京の都がすっぽり穴の中にはいっているようでした。そこからゾロゾロたくさんのネズミが出てきて、お祝いの餅つきがはじまりました。
「にゃんごおらねば、ネズミの世ざかり、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。 鈴の音ならねば、ネズミの天下、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。 百になっても、二百になっても、にゃんごの声などきぎだくね。 ほいほいポポポン、ほいポポポン。」
つき終わったおもちは姉御かぶりのネズミ達が、小豆餅だの麦こがしだの、いろんなおもちをポコポコと、次々に作っていきました。
与兵衛さんはネズミのあまりの数の多さに目をぱちくりし、次々につきあがるおもちに、またまたびっくりしました。しばらくすると、ムスメッコのネズミ達が赤ちゃんを連れて与兵衛さんに挨拶に来ました。赤ちゃんネズミは、「ちゅ。」と鳴きました。一匹、二匹、三匹と、「ちゅ。」「ちゅ。」「ちゅ。」と鳴きました。 十人のムスメッコの赤ちゃんたちは、全部で二百四十八おりました。与兵衛さんは、ネズミ達と一緒に、小さなお餅を食べ、赤ちゃんネズミのお祝いをしました。
さっきの親ネズミが三匹、大判やら小判やら金銀の大粒小粒を持ってきました。
「じさま、これは面白くて引いては来たものの、わしらには使い道の無いものです。持って帰って使ってくだされ。」
そう言ってネズミ達は与兵衛さんを家まで送りました。家に帰ると与兵衛さんはお房さんに、ネズミのお産の話をしました。するとお房さんは、次の日からおにぎりをおじいさんの分と、赤ちゃんネズミの分を作って、与兵衛さんに渡しました。
それから与兵衛さんは毎日穴の前におにぎりを置いておくようになりました。与兵衛さんがおにぎりを切り株の穴の前に置いておくのを見て、隣の弦蔵おじいさんは不思議に思いました。そして婆さまに、与兵衛さんは、なんしてあんな事をするのか、隣へ行って聞いてこいと言いました。
そしてお房さんからネズミのお産の事を聞くと、自分もちょっと真似してみようかと、婆様におにぎりこさえてもろうて、穴の前に行きました。
弦蔵さんは与兵衛さんの置いたおにぎりをはねのけると、自分の持ってきたおにぎりを穴の中に転がしました。するとおにぎりは入り口の所に、グシャリとつぶれてしまいました。
腹を立てた弦蔵さんはつぶれたおにぎりを穴の中にけり入れました。弦蔵さんはしばらく耳をすませていましたが、何も聞こえて来ません。弦蔵さんはおにぎりをもう一つとりだすと穴の中に蹴り入れました。すると足下が崩れ弦蔵さんは穴の中にどどどどっと落ち、何かにゴツンと頭をぶつけました。
「あたたたたたた。」
弦蔵さんは頭をかかえていました。見るとぶつかったのはお地蔵様でした。
「なしてこんなところに、お地蔵さんがおる?」
弦蔵さんは頭をかきかき、残ったおにぎりを自分で食べてしまいました。すると、弦蔵さんの後ろで、お地蔵様が目を開けられ、
「弦蔵さん、けっして猫の鳴きまねをしてはいけませんよ。」
と言ってまた目を閉じられました。弦蔵さんは誰が何を言ったのかわからず、きょとんとしていました。
すると穴の奥の方から声が聞こえてきました。
「にゃんごおらねば、ネズミの世ざかり、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。」
話に聞いたネズミの餅つき歌でした。弦蔵さんは声のする方へ頭をゴンゴンぶつけながら進みました。弦蔵さんが穴の奥にいくと、たくさんのぼんぼりの下に、着飾った小さなネズミ達がたくさん、千歳飴を持って座っていました。
その前でネズミ達が大勢でおもちをついていました。どうやらネズミの七五三のようでした。
「鈴の音ならねば、ネズミの天下、 ほいほいポンポン、ほいポンポン。 百になっても、二百になっても、にゃんごの声などきぎだくね。 ほいほいポポポン、ほいポポポン。」
弦蔵さんはここが与兵衛さんの来た所だと思いました。ここには小判や金銀の大粒小粒がたくさんある。弦蔵さんはハッとしました。そうだ猫の鳴き声をするんだ。
弦蔵さんは大きな声で猫の鳴きまねをしました。
「うにゃあぁあぁ~~~っごぉ。」
歌がぱたっとやみ、ぼんぼりの明かりが消えてあたりが突然真っ暗になってしまいました。
「・・・・・・・あっ。」
弦蔵さんがびっくりしていると、 暗やみの中に、ネズミ達がチュチュ~~~ッと、どこかへ走り去る声が聞こえました。
弦蔵さんは真っ暗な穴の中でぽつんと一人、もうどうにもなりませんでした。
弦蔵さんは次の日、おにぎりをもってきた与兵衛さんに助けだされました。
与兵衛さんは切り株の中に入って見ましたが、中は崩れていて、もう先には進めませんでした。お地蔵様もネズミ達もみつかりませんでした。
「ネズミ達はどこに行ったのかね?」
与兵衛さんはお房さんに聞きました。
お房さんはお茶をすすりながら、
「もしかすたら、また、どこかの切り株の下で、にゃんごの声などきぎだくね。と、お餅をつきながら、歌ってるかもしれねぇな。」と答えましたとさ。
したっけ。





























