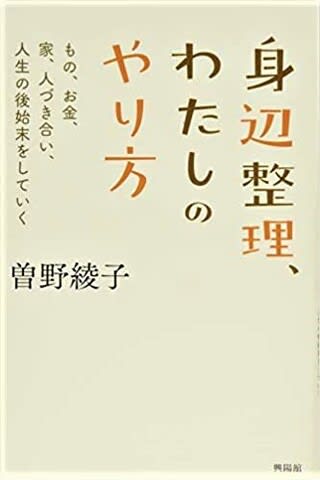先月は、箱根駅伝で岸本大紀選手、都道府県対抗駅伝では女子の小海遥選手、男子の山本唯翔選手が、それぞれ快走を見せてくれた。
新潟県出身選手のロードでの活躍はうれしいと思っていたが、今日の別府大分毎日マラソンでも、またすばらしい走りを見ることができた。
その走りを披露した選手は、青山学院大4年の横田俊吾選手。

別大マラソンでは、順位が日本人選手2位、全体でも4位という好成績だったが、それ以上に素晴らしかったのが、記録。
フルマラソンを、2時間7分47秒でゴールし、学生のマラソンの日本最高記録をたたき出した。
従来の記録が2時間8分12秒であり、それは2003年3月のびわ湖毎日マラソンで中大4年の藤原正和(現中央大監督)が打ち立てたものだった。
この20年間破ることができなかった記録を、横田選手が破ったのだ。
横田選手の出身中学校は、五泉市の山王中学校。
丘の上にある中学校だったが、その後旧村松町にあった2校(山王中学校と愛宕中学校)が統合となり、村松桜中学校となっている。
ただ、現在の村松桜中は横田選手が通った山王中の場所ではなく、かつて愛宕中学校があった場所にある。
そこは、私が昨年11月に走ったごせん紅葉マラソンの主会場となった村松公園の隣に位置している。
そんな縁があって、五泉市出身の横田選手に肩入れして応援したい気満々だったのである。
横田選手は、1年前の別大マラソンでもフルマラソンを走り、2時間12分41秒で16位。
初マラソンとしては、実に立派な成績だった。
ところが、そんな彼なのに、今年4年生になるまで箱根駅伝を走ったことはなかったのである。
ようやく走った今年の箱根駅伝は、3区を担当し、青学大の3位はキープしたものの、区間8位と目立った成績はおさめられなかった。
彼が走っているときの右腕の振りは、卓球のフォアハンドの素振りによく似ているのだ。
それで「よこたっきゅう」と名付けられた特徴のあるフォームの走りは、卓球もRUNも好きな私にとって、とても魅力的なのであった。
その彼が、今日のマラソンでどんな走りを見せてくれるのか、とても楽しみだった。
スタートから先頭集団に付けていた横田選手の走りは、とても冷静に見えた。
いつもどおりの特徴的なランニングフォームで、大集団の中でも、無理をせずよい位置を取っているように見えた。
名のある社会人の選手が一人一人脱落していく中でも、彼はちゃんと先頭集団の中位についていた。
30kmでペースメーカーが離れ、先頭の2名の外国人選手が抜け出した時も、決して無理をしないで日本人選手の集団に入って後を追った。
やがて、社会人の日本人選手が3名、彼よりも先にスパートして3位争いを始め先行していったが、冷静にあきらめずに追っていった。
やがて、残りの距離が5kmより少なくなって行った辺りで、3位集団を追い始め、やがて残り1kmあたりで追いついたようだ。
前の3人のうちの1人は抜けなかったが、2人を抜いて、堂々の4位となった。

記録は、2時間7分47秒という立派なもの。
前回大会の優勝記録と同じタイムであった。
かつて、北京マラソンで児玉泰輔選手が、2時間7分35秒が一時期ながらく日本記録だった時があったが、それに近いタイムで走れるなんて、すごいじゃないか。
その快走に、拍手


同じ新潟県出身ながら、青学大で同級生だった岸本大紀選手の後塵を拝してきたように思えた横田俊吾選手だったが、4年生の最後のレースで見事な走りを披露した。
大学を卒業後、岸本選手はGMOインターネットで、横田選手はJR東日本で、それぞれ競技を続けると聞いている。
2人とも、駅伝やマラソンでこのような活躍を見せてきた。
競い合って、これからのさらなる活躍をしてくれることだろう。
新潟県人として、それが楽しみでしようがない。
横田選手、大学生としてのマラソン、歴代最高記録、本当におめでとうございます



今後も、大活躍を期待しています!!