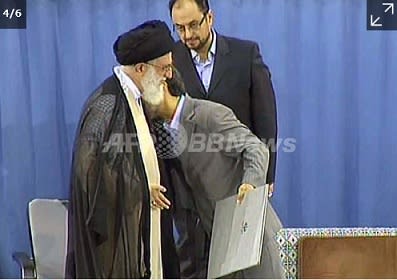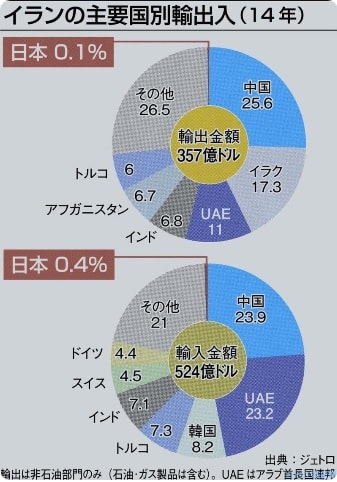(イランの首都テヘランで12日、大統領選のテレビ討論会を見るロハニ大統領の支持者たち=AP【5月13日 朝日】)
【イランの選挙風景】
先日の韓国大統領選挙では、選挙集会でのダンスチームのパフォーマンスが話題にもなりましたが、それぞれの国で独特の選挙風景があります。日本の名前をひたすら連呼する、うるさいだけの選挙カーなどもそのひとつでしょう。馬鹿々々しさでは韓国に負けていません。
日本の場合、選挙ポスターの掲示は場所、枚数等は厳しく制約されていますが、(規則があるのか、ないのかは知りませんが)町中いたるところに膨大な枚数が貼られる選挙風景が見られる国はあちこちにあります。
イランも、そうした国のひとつのようです。
****選挙ポスターの「無法地帯」 イラン、標識や銅像にも*****
19日に大統領選挙が行われるイランで、同時に行われる市議会選挙の候補者ポスターであふれかえる街がある。激戦区で、昔から候補者らがルールを顧みずにあらゆるところに貼りまくっているという。
市民は「街をきれいにする市政と言っているが、選挙でやっていることは逆」(タクシー運転手のムハンマド・オリヤイーさん)とあきれている。
首都テヘランから南に車で約1時間半。人口約22万人のバラミン市はいま候補者のポスター一色だ。電線にのれんのようにつるされたり、ポストや交通標識にも貼られたり。クリスマスツリーの飾りのようなものもあり、イスラム教聖職者の銅像までも「犠牲」になっている。
取材中には、通りがかった人から「車を止めたままだと、戻ったときには貼られまくっているぞ」と忠告された。
住民によると、市議会議員選挙のたびに街中がポスターだらけになる。同市議会は、164人が9議席を争う激戦で、アピールのために様々な場所に貼り付けるのだという。
地元メディアによると、同市選挙本部は「許可なく壁や公共の場所に貼るのは違法」としているが、昔からの「悪習」が改まる気配はない。「こんな無法地帯は他にない」と住民は声をそろえる。
たまりかねた一部の市民がネット上で「選挙運動に反対する運動」という住民運動まで始まったが、陣営はお構いなしだ。【5月15日 朝日】
********************
“イスラム教聖職者の銅像までも「犠牲」になっている”・・・宗教的な制約が大きいというイメージもあるイランでそんなことして大丈夫なのか・・・と、他人事ながら心配にもなりますが、宗教による社会的制約というのは、よそ者にはなかなかわかりにくいものでもあります。(前大統領が最高指導者の警告を無視して立候補申請したりもしています)
それにしても、“同市議会は、164人が9議席を争う激戦”とのことですが、大統領選挙の方も“定員1”に対し1636人が届け出ています。(「護憲評議会」の資格審査で6名に絞り込まれてはいますが)
以前のブログでも触れたように、イラン国民は選挙が大好きなのでしょうか?
あるいは、普段は政治的制約が厳しいため、その分、選挙になると一気に溜まったエネルギーが噴き出す・・・といったことでしょうか?
あるいは、当局も“ガス抜き”のために、そうした選挙のお祭り騒ぎを黙認しているということでしょうか?
【核合意でも「経済は好転していない」】
それはともかく、注目されるのは19日の大統領選挙の行方です。
選挙戦の概況、保守強硬派の有力候補ライシ師の問題などについては、5月1日ブログ“イラン大統領選挙 争点は核合意評価と「自由」 対抗馬ライシ前検事総長の深い「闇」”http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20170501でも取り上げました。
*****核合意で経済好転したか? イラン大統領選で最大の争点****
19日投票のイラン大統領選まで1週間となった12日、候補者6人による最後のテレビ討論会がテヘランで行われた。
国際社会の対イラン経済制裁を解除させた2015年7月の核合意をめぐり、「雇用増につなげた」とアピールする現職のロハニ大統領(68)に対し、他候補は「経済は好転していない」と反論。核合意が経済的な利益をもたらしたかどうかが最大の争点となっている。
今回の大統領選は、国際協調路線を志向する保守穏健派のロハニ師に対し、反米を基調とする保守強硬派の最高指導者ハメネイ師に近い前検事総長のライシ師(56)、同派のガリバフ・テヘラン市長(55)が挑む構図が軸となっている。
討論会でロハニ師は、1期目の成果として「核合意で輸出増へ道を切り開いた」とし、「雇用増のためには新たな(外国からの)投資が必要だ」と強調。イラン経済の発展のため、国際協調路線を堅持すべきだと訴えた。
これに対し、ライシ師は「現政権は不況などの経済問題を解決できていない。この4年で貧困層の比率は23%から33%に増えた」とし、核合意は経済の好転につながっていないと批判した。
ガリバフ氏も「国内の企業家は外国からの過剰な輸入という圧力にさらされている」とし、外国からの投資に頼らず雇用増を達成すべきだと主張した。
大統領選のテレビ討論会はイラン国内で数千万人が視聴し、勝敗を左右するとされる。13年の前回大統領選では、ほぼ無名だったロハニ師が「私は自由の体現者だ」と発言して注目を集め、初当選につなげた。イランメディアは今回の討論会について、「どの候補も浮動票を引きつける発言はできなかった」と評した。
今回の大統領選は当初、ロハニ師が優勢で、現政権への信任投票の色合いが濃いとみられていた。だが、対立候補から「核合意後も経済は好転していない」と繰り返し批判され、ロハニ師に逆風が吹き始めた様子だ。直近の世論調査によると、ロハニ師は41・6%でトップだが、ライシ師が26・7%、ガリバフ氏が24・6%で追い上げている。
イラン大統領選は18歳以上の有権者による直接選挙で、過半数の投票を得た候補が当選。1回目の投票で過半数を得た候補が出なければ、上位2人の決選投票で決める。他にも保守強硬派のミルサリム元文化イスラム指導相、保守穏健派のハシェミタバ元副大統領らが立候補している。【5月13日 朝日】
*****************
核開発というイランの主権を大きく制約しながらまとめた核合意であったにもかかわらず、「経済は好転していない」ではないか・・・という、ロウハニ大統領の対立候補の言い分はもっともでもあります。
****海外勢はイラン投資に及び腰、再選目指すロウハニ師は誘致に躍起****
19日のイラン大統領選で再選を目指す現職の保守穏健派ロウハニ師は、核合意を受けた経済制裁の一部解除と、それに伴う海外からの投資増を有権者に訴えたいところだが、海外投資家たちは今のところ口約束をするのみで、実際の投資にはほとんどつながっていないのが現状だ。(中略)
対イラン制裁の解除を受けて、海外のエネルギー会社は昨年、10件以上の石油・ガス田の探査に関する契約をイランと締結。ただ、今のところ、実際の投資につながる契約にこぎつけたものは1件もない。
油田サービスのシュルンベルジェは先月、油田探査の合意の終了を発表。取引で得られる恩恵はリスクに見合わない、と判断したためだ。
こうした状況の中、イラン政府は、海外からの投資を思うように誘致できない原因は「宿敵の」米国にあるとして、苛立ちを強めている。
米政府は、イランが核合意を守っているかどうか90日ごとに確認することを議会に義務付けられている。米国はまた金融制裁の一部を残しており、このためイランの銀行は国際金融システムに参加できない。
さらに、トランプ米大統領は核合意について「これまでに調印された合意の中でも最悪のもの」と宣言。外国企業は、トランプ大統領が突然、核合意を破棄することもあり得るとして、及び腰になっている。
イランのザンギャネ石油相は、欧州の石油メジャーからの投資がまだない主な理由として「米国での政治的要因と圧力」と指摘した。
<イランの投資環境にも問題>
海外投資家はイランでの投資をためらう理由として、イラン自身が抱える問題も挙げる。例えば、透明性の欠如、ぜい弱な銀行システム、官僚主義などだ。
また、ロウハニ師が今回の大統領選で、ロウハニ師の対外開放政策に懐疑的な保守強硬派に敗北する可能性も警戒している。【5月12日 ロイター】
******************
“ロウハニ師の対外開放政策に懐疑的な保守強硬派に敗北する可能性”を警戒して海外からの投資が進まない、その結果、経済は好転せず、国際協調路線を志向する保守穏健派のロハニ師の立場は悪化する・・・という悪循環でもあります。
【トランプリスク】
再選を目指すロウハニ大統領にとって、その足を引っ張る形になっているのがイランに厳しい姿勢をとるアメリカ・トランプ大統領の存在です。
そのあたりの話は、4月16日ブログ“イラン大統領選挙 再選を目指す穏健派ロウハニ大統領 核合意を嫌うトランプ大統領は?”http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20170416でも触れたところです。
そのトランプ大統領は、今月後半、イランの宿敵サウジアラビア、更にイスラエルを訪問します。
****<イラン大統領選>米の強硬姿勢、ロウハニ師再選に影響も****
トランプ米大統領は今月下旬に行う就任後初の外遊で、イスラム教スンニ派の大国サウジアラビアを最初に訪問する。
サウジと敵対し、訪問時期の19日に大統領選を控えるシーア派国家イランでは、選挙戦への影響が注視されている。トランプ氏が親米アラブ諸国の結束を強調し、「反イラン」姿勢を明確にした場合、再選が有力視されるロウハニ大統領の対外融和路線を批判する保守強硬派が勢いづく可能性もある。
サウジは昨年1月にイランと断交。シリアやイエメンの内戦でもそれぞれ別の勢力を支援し、敵対する。
サウジのジュベイル外相はトランプ氏来訪について「米国がアラブ・イスラム諸国と協力関係を結べるという明確なメッセージ」と歓迎。イスラム教の聖地メッカを擁するスンニ派の盟主として、米国や周辺諸国と過激派組織「イスラム国」(IS)などに対抗する姿勢を強調し、イランへの圧力も示す考えだ。
サウジではイラン非難が熱を帯びる。中東メディアによると、2日には国防相も務めるムハンマド副皇太子が「イランはイスラム世界を乗っ取ろうとしている」と主張した。
投票まで1週間となったイランでは、主要争点は雇用や所得格差など経済問題だが、トランプ氏がイランを露骨に刺激すれば、ロウハニ師が優勢とされる選挙戦に影響が出る可能性もある。
中東政治に詳しいカイロ大学のアマル・ハマーダ助教は「米国による過度な強硬姿勢は、ロウハニ師に対外融和路線の変更を強いかねない」と指摘。選挙戦でライシ前検事総長ら反米強硬派の候補が勢いづき、緊張が高まる可能性もあると見ている。【5月11日 毎日】
*******************
“イラン憎し”のサウジアラビアの思惑は上記のとおりですが、国内でFBI長官“クビ”問題で大きな騒動を抱えて苛立っているトランプ大統領が、外遊先で対イランで何か騒ぎを起こすということは十分に考えられます。
もともとトランプ氏自身がイランとの合意を非常に不満に思っていますし、国内の騒動を鎮めるためにも、注目される対外的な問題を提起した方が得策・・・という判断もあります。(北朝鮮問題を抱えて、更に中東・イランでも問題を起こすか?ということはありますが)
【イランにおける世論調査の信頼性】
ロウハニ大統領にとっての救いは、トランプ大統領のサウジアラビア訪問は5月21日とされていますので、第1回投票の19日で決めてしまえば“トランプリスク”を避けられることです。
もし、第1回で過半数を取れなければ、1週間後(ということは26日でしょうか)に決選投票となります。
そうなると、保守強硬派が一人に絞られてロウハニ批判票が集中するうえに、ひょっとしたら“トランプリスク”が・・・という話にもなります。
そうしたことからも、現在の支持率が注目されます。
前出【朝日】には“直近の世論調査によると、ロハニ師は41・6%でトップだが、ライシ師が26・7%、ガリバフ氏が24・6%で追い上げている。”とあります。
ただ、イランでは信頼に足る世論調査などないとも言われていますので、上記数字がどこまで信用できるのか?
そんな関心から、前回(2013年6月14日投票)選挙時の事前世論調査による支持率と結果を見てみると・・・
下記は前回大統領選挙の投票日前日の記事です。
********************
iPOSは5月31日から毎日、約1000人のイラン在住の有権者(18歳以上の男女)に電話で「今日投票するなら誰か」と質問。最高指導者ハメネイ師に近い保守強硬派ガリバフ氏が10日まで首位だったが、11日に保守穏健派ロウハニ師が26.6%の支持を受け、ガリバフ氏を1.8ポイントリードした。
唯一の改革派候補だったアレフ元副大統領(61)が10日夜に出馬を辞退し、改革派や保守穏健派ラフサンジャニ元大統領がロウハニ師支持を正式表明したことで、勢いが増したとみられる。
調査では、独立系候補とされるレザイ元革命防衛隊最高司令官(58)が16.3%、有力視されていた保守強硬派ジャリリ最高安全保障委員会事務局長(47)は13.7%と厳しい情勢。
一方、イランの保守系ウェブサイト「アレフ」は12日、アレフ氏が離脱した後の世論調査結果を掲載。ガリバフ氏(21.5%)をロウハニ師(19.1%)が猛追し、ジャリリ氏(12.5%)とレザイ氏(12.1%)が続く情勢を伝えている。【2013年6月13日 毎日】
*********************
投票結果は、“ロウハニ師は有効投票3546万票の52.5%に当たる1861万票を獲得。2位の保守強硬派、ガリバフ・テヘラン市長(51)が獲得した608万票の3倍以上の得票で、圧勝した。選挙戦開始当初、有力視されていた保守強硬派のジャリリ最高安全保障委員会事務局長(47)は3位で、419万票にとどまった。”
唯一の改革派候補だったアレフ元副大統領が10日夜、選挙戦からの離脱を表明して保守穏健派ロウハニ師との“一本化”をはかったという変動要素があるものの、19~26%でガリバフ氏と競り合っているとされたロウハニ師が3倍以上の得票で過半数を制するという具合に、事前の支持率と結果は全く異なっています。
そうした“実績”からすると、前出【朝日】に紹介されている数字はほとんど信用できない・・・とも思われ、「ふたを開けてみないとわからない」と言えます。
(前回選挙では、ふたを開けてもロウハニ師が過半数を制したかどうかがわかるまで、しばらく時間を要しました)
先述のように、ロウハニ師は第1回投票で決めないと、決選投票では苦しい戦いが待っています。
なお、トランプ大統領は22~23日にはイスラエルを訪問しますが、こちらも在イスラエル米大使館のエルサレム移転問題など、何が飛び出すか・・・。
【追加】
****保守強硬派候補が撤退=現職ロウハニ師に逆風―イラン大統領選****
イラン国営メディアによると、19日投票の大統領選で有力候補の一人だった保守強硬派ガリバフ・テヘラン市長が15日、選挙戦から撤退した。ガリバフ氏は、同じ保守強硬派で最高指導者ハメネイ師に近いライシ前検事総長への支持を表明。現職の保守穏健派ロウハニ大統領と事実上の一騎打ちとなる。
ガリバフ氏は声明で「国民と国の利益を守るには、現状を変えることが必要だ」と訴えた。再選を目指すロウハニ大統領は、2015年に欧米など主要6カ国と結んだ核合意に伴う制裁解除の恩恵が国民に行き届いていないとの批判にさらされている。強硬派の候補が一本化されたことで、一層厳しい戦いを迫られそうだ。【5月15日 時事】
***************
前回選挙では、改革派・保守穏健派が投票日直前に一本化して成功しましたが、今回は保守強硬派が同様の戦略のようです。