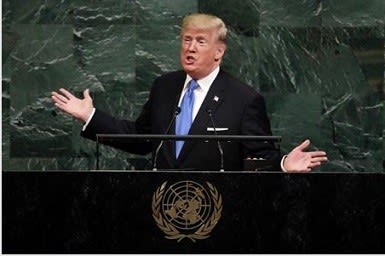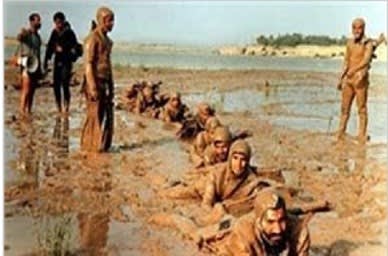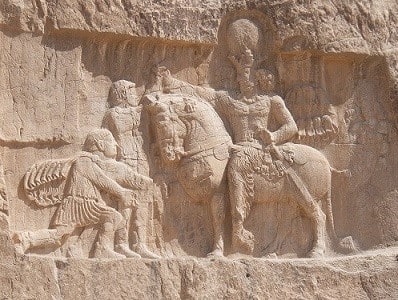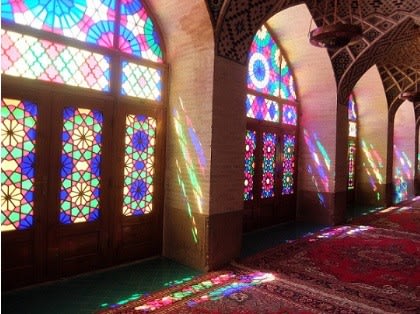(保守強硬派の牙城、イスラム聖職者の街コムでもデモが【12月30日 BBC】)
【ロウハニ大統領 国民に対し、自らの権利を主張するよう呼びかける】
このところあまりイラン発のニュースは多くなかったのですが(サウジアラビアなどによるイラン包囲網の話は多々ありますが)、先日“奇妙”と言うか、何を意図してしているのかよくわからない穏健派ロウハニ大統領の発言が報じられました。
****イラン大統領、国民に権利主張するよう訴え 治安組織の締め付け批判?****
イランのハッサン・ロウハニ統領は19日、市民の権利憲章を発表してから1年がたったのを機に演説を行い、国民に対し、自らの権利を主張するよう呼びかけた。
ロウハニ大統領は「権利は政府にではなく、国民にある」と強調した上で、「国民の権利を文化に変えなければならない」と述べ、若者やソーシャルメディアの利用者らに、権利が侵害されていると感じたらその不満を広く主張するべきだと訴えた。
また、「国民は政府に放っておいてほしいと思っている」と指摘し、国内の強力な治安組織を念頭に、市民生活への介入を減らし、干渉しないよう求めた。
ロウハニ氏が発表した画期的な権利憲章は、言論・抗議の自由、公正な裁判、プライバシーなどを保障するとしているが、改革派のメディアは、より自由な社会が実現していないと批判している。
イラン国内では司法界や革命防衛隊を含め多くの組織で保守強硬派が支配している状況で、ロウハニ氏の主張についても未だに沈黙を守ったままだ。【12月20日 AFP】
********************
イランでは、改革派からの支持も集める穏健派ロウハニ大統領の政権と、ハメネイ最高指導者周辺を固める保守強硬派の間で厳しいせめぎあいが続いていることは周知のところです。
自らの権利を主張するよう呼びかけ、「国民は政府に放っておいてほしいと思っている」・・・・文字どおり解釈すると、政治・社会を支配する議会・治安当局・革命防衛隊などの保守強硬派への国民決起を促すような、随分と過激な発言にも思えます。
「権利は政府にではなく、国民にある」・・・・現在の最高指導者を頂点とするイスラム主義イラン政治システムへの反旗ともとれる発言ですが、その真意は・・・。
単に、“市民の権利憲章を発表してから1年”という節目にあたっての啓蒙的な国民向けアピールなのか、保守強硬派との権力闘争があるなかで国民支持を引き寄せようという差し迫った事情があるのか・・・知りません。
【異例の抗議デモ “物価上昇への抗議が徐々に政治的スローガンに変わる”】
このロウハニ発言と関連があるのかどうかは知りませんが、発言から日を置かず、イランでは異例の反政府デモが行われ、治安当局との衝突も起きています。
****「大統領に死を」 イラン各地、禁令破り反政府デモ****
イラン各地で28~29日、物価高や政府の経済政策に抗議するデモがあった。
地元メディアによると、第2の都市・北東部マシュハドでは52人が逮捕され、他都市でも警官隊と衝突した。デモが事実上禁じられているイランでは極めて異例の事態だ。
10%を超える高い失業率や、遅々として進まない経済発展に市民がしびれを切らした形だ。
地元メディアによると、中部イスファハンや北西部タブリーズなど、少なくとも11都市で数百人規模のデモがあった。警官隊が催涙ガスや放水車で対応したという。
イランでは今月、卵の価格が約2倍に高騰したほか、通貨リアルの価値が下落傾向で、日常品の価格も上昇。市民の不満が高まっていた。
英BBCなどによると、参加者は「ロハニ大統領に死を」「パレスチナやシリアは放っておけ。国民のことを考えろ」などのスローガンを叫んだ。最高指導者ハメネイ師を示唆して「独裁者に死を」「イスラム体制はこりごりだ」との声も上がったという。
デモ参加者の多くは、インターネットのSNSを通じて集まったとみられる。2009年には、大統領選挙の結果などに不満を持った市民が大規模な反体制デモを行い、多数の逮捕者や負傷者が出た。首都テヘランでは30日、ネットを通じてデモが呼びかけられており、警察などが警戒している。
イランでは、核開発疑惑で原油禁輸を含む制裁を受け、経済が冷え込んだ。15年7月、イランが核開発を大幅に制限する見返りに国際社会が制裁を解除することで欧米などと合意。
16年の経済成長率は国際通貨基金(IMF)の調べでは12・5%だが、イラン統計局などによると、若年層の失業率は25%以上だという。ロハニ師は雇用拡大などを掲げて5月に再選されたが、国民は経済成長を実感できない状況が続いている。
イランと敵対する米国は素早く反応した。トランプ大統領はツイッターに「体制の腐敗と、国の財産をテロ支援に使う無駄遣いにうんざりした市民が、平和的なデモをしたとの多くの報道があった。イラン政府は国民の権利を尊重すべきだ。世界が注視しているぞ!」とつづった。
国務省も「平和的なデモ参加者の逮捕を非難する」との声明を出した。国内での自由が抑圧されているとして、イランが「ならず者国家」であるとのイメージを、国際社会に強く植え付けるという狙いがあるとみられる。【12月30日 朝日】
********************
「ロハニ大統領に死を」と「独裁者に死を」「イスラム体制はこりごりだ」では、その矛先・影響が全く異なります。
不満の核心が「ロハニ大統領に死を」ということであれば、約束してきた制裁解除による経済浮揚を実現できない穏健派政権への批判にとどまり、結果、保守強硬派の力が強化されることになります。
国民不満が「独裁者に死を」「イスラム体制はこりごりだ」というレベルに達しているのなら、ハメネイ最高指導者を頂点とするイスラム主義現行体制への批判となり、ロウハニ大統領などの穏健派や改革派はその不満の受け皿になります。
“報道によると、28日に北東部マシャドで始まったデモは、29日に首都テヘランなどに拡大。西部ケルマンシャーでは約300人が「イラン革命に反対」「政治犯を釈放せよ」などと訴えた。
物価上昇への抗議が徐々に政治的スローガンに変わり、イスラム教シーア派の聖地コムではハメネイ師を名指しして「国を去るべきだ」と抗議する市民もいたという。シリアやイラクなど中東各地の紛争に介入する政府の姿勢を批判し「シリアを離れ、私たちのことを考えて」との訴えもあった。”【12月30日 毎日】
一方、“イランのエリート集団、革命防衛隊に近いファルス通信は、経済的苦境に不満を唱えていたデモ参加者の多くは、政治スローガンが繰り返されるようになると、その場を離れたと伝えている。”【12月30日 BBC】とも。あくまでも革命防衛隊に近いメディアの報道です。
今回デモの性格については“今回のデモの広がりは、反ロウハニ強硬派が意図したわけではなく、強硬派が開いた集会がたちまち制御不能となり各地に飛び火したもののようだ。”【12月30日 BBC】とも。
保守強硬派は、先日のロウハニ大統領の発言を逆手にとって反政ロウハニ集会を開いたものの、イラン統治体制への不満にまで一気に拡大した・・・というところでしょうか?
“物価上昇への抗議が徐々に政治的スローガンに変わる”状況を、保守強硬派は座視しないでしょう。
徹底した治安当局により鎮圧が行われるとおもわれます。
そのとき、“国民に対し、自らの権利を主張するよう呼びかけた”ロウハニ大統領はどのように行動するのか?
自由な空気を求めている多くの国民は、どのように行動するのか?
【イラン国民の権利を危機にさらすトランプ大統領が「イラン政府は国民の権利を尊重すべきだ」】
“トランプ大統領はツイッターに「体制の腐敗と、国の財産をテロ支援に使う無駄遣いにうんざりした市民が、平和的なデモをしたとの多くの報道があった。イラン政府は国民の権利を尊重すべきだ。世界が注視しているぞ!」とつづった”【前出 朝日】
しかし、核合意による制裁解除の効果が十分に発揮されず、物価高・失業に国民が苦しむ困難な現状の元凶は、ミサイル開発などを理由に独自のイラン制裁を続け、欧州・日本の対イラン投資を手控えさせているトランプ政権自身です。
トランプ大統領は更に核合意そのものをも覆すような動きを見せており、その結果は、比較的国民の権利に寛容な現行ロウハニ政権を潰し、国民の権利をないがしろにする保守強硬派支配を強化するものと思われます。
自分自身がイランの経済を追い込み、イラン国民の権利を危機にさらしていながら“イラン政府は国民の権利を尊重すべきだ。世界が注視しているぞ!”というのは、はなはだ笑止・滑稽ですが、これが政治の現実でもあります。
****米イスラエルが対イランで秘密工作を検討****
米ニュースサイト「アクシオス」は28日、米国とイスラエルの政府高官が12日、イランによる核兵器開発の再開を阻止するための秘密工作検討などを含む「共同戦略作業計画」に合意したと報じた。
ホワイトハウス当局者は取材に対し、マクマスター大統領補佐官(国家安全保障問題担当)が12日にイスラエルと安全保障協力を協議したとし、報道を大筋で認めた。
トランプ米政権はエルサレムをイスラエルの首都と認定し、米大使館を移転する方針を決めて同国との同盟関係の強化に取り組み、同時にアラブ諸国とも連携して対イラン包囲網を形成しようとしている。
同サイトによると、米国とイスラエルは複数の作業部会を設置し、イランの弾道ミサイル開発、同国によるレバノンのシーア派組織ヒズボラやパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム原理主義組織ハマスの支援に対抗する方策を協議する。イランの核合意順守を監視、検証するための外交措置も話し合う。
ただ、トランプ大統領は10月、イランによる核合意の順守を認定せず、欠陥が解消されなければ合意を破棄できると強調し、合意の先行き自体が不透明だ。
米政府は90日ごとに議会に順守状況を通告するよう義務付けられている。次の期限は1月中旬で、大統領による制裁適用の免除期間120日の期限も同時期に訪れる。そのため、米メディアからはトランプ氏が合意破棄に踏み切る可能性があるとの指摘も出ている。
これに関連し、ティラーソン国務長官は28日付の米紙ニューヨーク・タイムズへの寄稿で「米国のイラン政策の焦点は欠陥のある核合意ではなくイランの脅威全体に立ち向かうことにあり、同盟関係の再構築が必要となる」と強調した。【12月29日 産経】
******************
イラン国内の抗議デモが、来年にかけて、これ以上の広がりをみせるのか?
トランプ大統領が1月中旬に核合意破棄に踏み込むのか?(ここまで、イスラエルやサウジアラビアなどとも対イラン包囲網を画策してきていますので、なんらかのアクションを起こすのではないでしょうか)
年明け早々、世界は新たな混乱の火種を抱えることになるかも。