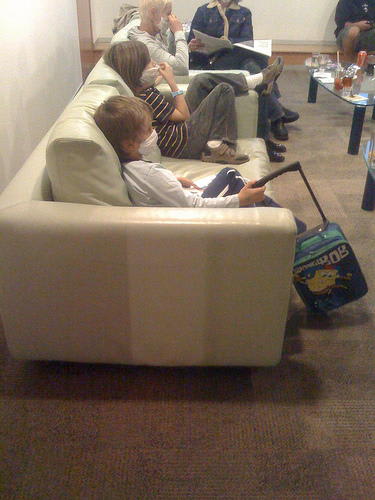(スワト渓谷は観光客が国外からも集まる美しいリゾートでしたが、今は・・・
“flickr”より By Farooq Nasir (Extremely busy but available soon)
http://www.flickr.com/photos/farooqnasir/3152537951/)
【和平協定】
パキスタン政府の対応は、国内のシャリフ派など野党や前最高裁長官復職を求めた弁護士グループなどへの対応、アフガニスタン国境隣接地域での武装組織への対応、どれをとってもその場しのぎというか一貫しないものがあります。
これは国内問題にあっては、ザルダリ大統領自身がかつての収賄容疑を引きずっていること、武装組織との関係では、国内治安改善への要求および国民の反米感情とアメリカからの強い要請の板ばさみになっていることが背景にあります。
北西辺境州スワト地域で活動するタリバン系イスラム原理主義武装組織との間で、今年2月、同地域でのイスラム法の施行を条件に和平協定が締結されましたが、その後、ザルダリ大統領は、アメリカの反発やイスラム法施行に対する国民の不安もあって、これに署名せず棚上げしていることが報じられていました。
しかし、結局は武装組織側の首都へ向けた進軍という実力行使、州政府与党の中央での連立解消への動きなどに押される形で、この和平協定に署名し発効することになったことは、4月15日ブログ「パキスタン イスラム法(シャリア)導入を認める和平協定で開く「タリバン化」への水門」でも取り上げたところです。
(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20090415)
【逡巡する政府 拡大するタリバン支配】
しかし、「ビンラディンは兄弟のようなもの。いつでもここに来ることができる」と豪語する武装組織側と、アメリカの圧力を受け、また、“タリバン化への水門を開く”ことをためらう政府側の関係はやはりうまくいきません。
イスラム法施行を逡巡する政府側に対し、武装組織側は首都まで100kmの北西辺境州ブネール地区へ支配を拡大する形で圧力をかけます。
この事態にクリントン米国務長官は22日、下院外交委員会の公聴会で、パキスタン北西部でイスラム武装勢力タリバンが支配圏を拡大、首都に迫っていることについて、国際社会に「致命的な脅威を突きつけている」と述べ、深刻な懸念を示しました。
武装組織の戦闘員数百名が乗り込んだブネール地区では、音楽を聴いたことへの懲罰として、男性4人が頭髪とひげを剃るような事件も。
“「3人の友人らと車に乗り、音楽を聴いていたところ、武装したタリバンのメンバーに車を止められた。カセットテープとプレーヤーを叩き壊された後、彼らは、ぼくらの頭髪を半分だけ丸刈りにして、ひげをそり落とした。殴られ、2度と音楽を聴かないようにと言われた」(被害にあった匿名の若者)
地元警察は、そういった事件の情報は無いとしている。
被害にあった若者と友人らは、「無駄なので」警察に届け出なかったと述べ、「タリバンをさらに怒らせることになるし、自分の命が惜しい」と語った。”【4月26日 AFP】
【掃討作戦】
こうした武装組織側の支配圏拡大に対し、パキスタン政府は26日、北西辺境州スワト地区に隣接するローワー・ディール地区で、検問所を設置した武装勢力を武装ヘリで攻撃し30人を殺害したと発表、タリバン掃討作戦を開始したことを明らかにしています。
更に、首都に100kmと迫るブネール地区でも、武装組織側は一旦撤収したとのことでしたが実際には戦闘員が残っているようで、政府側はこの掃討作戦に乗り出しました。
****タリバン掃討開始 パキスタン軍*****
パキスタン軍報道官は28日、同国北西辺境州ブネール地区で、イスラム原理主義勢力タリバンの掃討作戦を開始したことを明らかにした。タリバンは24日に同地区からの撤退を表明したが依然、約500人のタリバン兵がとどまっているという。報道官は「撤退はうそだった」と非難し、「作戦の目的はブネール地区から武装兵を根絶し、駆逐することだ」と述べた。
地元からの情報によると、軍はブネール地区とスワト地区の間の山岳地帯への空爆も開始。ブネール地区では軍車両の通行のため住民の外出禁止令が出されている。
軍報道官はまた、スワト地区西隣のローワー・ディール地区で26日から実施されていたタリバン掃討作戦は終わり、「タリバン兵は一掃された」と語った。この作戦で武装兵75人と兵士10人が死亡した。
タリバンは、今月に入りスワト地区周辺にも勢力を拡大。米政府の強い懸念表明などを背景に、パキスタン政府もこれまで慎重だったタリバン掃討作戦に踏み切ったとみられる。【4月29日 産経】
***********************
数日前の報道では、和平協定の成立しているスワト地区ではまだ戦闘は避けられているとも。
スワト地区での和平合意は昨年5月に続き2回目です。
前回は、米国の圧力を受けた政府がイスラム法導入の協定内容を守らなかったことなどから、同8月に破棄されています。
今回も、スワト地区に隣接するローワー・ディール地区、ブネール地区での掃討作戦によって、スワト地区での和平合意もかなり危うくなっています。
【難民3万人】
和平合意したり、掃討作戦を行ったり・・・一定しないパキスタン政府の対応ですが、そうした対応もやむを得ない苦しい事情があります。
****タリバーン掃討で難民3万人 パキスタン、拡大の恐れ****
パキスタン軍が同国北西辺境州で26日から開始した反政府武装勢力タリバーンへの掃討作戦で、28日までに約3万人の避難民が出ている模様だ。政府は首都イスラマバードに最も近いタリバーンの勢力範囲での新たな掃討作戦を示唆しており、今後、難民が増える可能性がある。
同州のフサイン情報相は28日の記者会見で、軍がタリバーンを攻撃している同州下ディール地区からの避難民が約3万人に上っている、と述べた。地元紙は同地区で軍による攻撃に巻き込まれて女性1人が死亡したと報じ、民間人の被害が懸念されている。
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は「難民の規模や移動状況を確認し、できるだけ早く救済したい」としている。 (中略)
国連によると、昨秋から今年初めにかけて北西部バジョール地区で行われたタリバーン掃討作戦などで、今年1月下旬時点で20万人以上の国内難民が難民キャンプなどで生活している。うち約1万6千人は、今回の作戦が始まった下ディール地区の四つの難民キャンプに収容され、難民の増加が懸念されている。【4月28日 朝日】
***********************
武装組織側と和平合意すればアメリカが怒り、国内ではタリバン化が進行する。
戦闘状態になると、地域住民の生活は破壊され大量の難民が発生する。更に、国内各地で自爆テロが頻発する。
ザルダリ大統領ならずとも対応に苦慮するところです。
【アメリカの懸念】
ところで、アメリカはこうした“ブレる”パキスタン政府への不信感を募らせています。
万一、パキスタンの支配権がイスラム原理主義勢力の手に落ちることになると、それはパキスタンが保有する核兵器がアルカイダとも通じる彼等の手に渡ることを意味します。
****オバマ米大統領、パキスタン政府は「ぜい弱」と懸念表明****
バラク・オバマ米大統領は29日、パキスタン政府のぜい弱性に懸念を表明し、さらに同国の核兵器がイスラム教原理主義者たちの手に落ちた場合、米国が介入する可能性を排除しないことを示唆した。
就任100日目にあたりゴールデンタイムに行った記者会見でオバマ大統領は、イスラム系武装勢力との戦いにパキスタンが真剣であり、同国が保有する核兵器は守られている点は確信していると語った。
しかし一方で、次週ワシントンを訪問するパキスタンのアシフ・アリ・ザルダリ(大統領率いる文民政権に関しては、同国国民の忠誠心を確保するための基本的機能を提供できていないと指摘し、「パキスタンの状況には非常に懸念を覚える。それは今すぐに政権が覆され、パキスタンがタリバンに支配にされると思うからではなく、現在の文民政権があまりにぜい弱なことから不安を感じる」と述べた。
その上でオバマ大統領は「もとより、わが国はパキスタンの主権を尊重したい。しかし、同時にわれわれは、米国の戦略、すなわち国家安全保障は、パキスタンが安定していること、パキスタンを核武装勢力の国にしないことに、極めて大きな関わりを持っていることを認識している」と語った。この発言を受け、パキスタンの保有する核兵器が脅威にさらされた場合に米国の介入はあるかと質問された大統領は、仮説に基づく質問には答えないと述べ、明言を避けた。【4月30日 AFP】
*********************
アメリカはアフガニスタンのカルザイ政権も半ば見放しているところがありますが、アフガニスタンでもパキスタンでも現地政権の“ふがいなさ”に苛立ちを強めているようです。