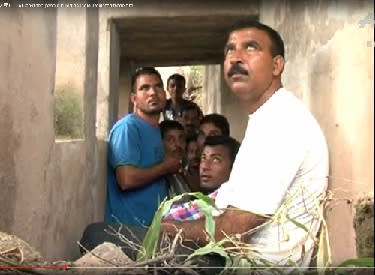(共和党候補者のなかでトップの支持率を誇るトランプ氏 【7月27日 Newsweek】 なお、「かつら疑惑」については否定、聴衆の女性をステージに上げて髪を触らせ、地毛であることを“証明”したとか。)
【感情に訴えるトランプ氏 「手に負えなくなる」おそれも】
「民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが」とはイギリスの元首相チャーチルの言葉ですが、“民主的な選挙によって代表・指導者を選ぶ政治形態”というものは“よりましな”“比較的安全な”“暴走への歯止めの効いた”形態であるにしても、“最悪”とは言わないまでも相当に問題も抱えています。
問題のひとつは、多数派の暴走を止める歯止めがないことですが、同時に、選挙で示される“民意”は往々にして、物事を単純化した“歯切れのいい”“明快で力強い”主張に引っ張られることがあります。
アメリカでは2016年11月8日に行われる次期大統領選挙に向けた超ロングラン選挙運動が始まっていますが、共和党候補をめぐる争いにおいて、過激な発言の言いたい放題で耳目を集める不動産王の大金持ちトランプ氏がレースのトップを走っています。
アメリカの選挙においてはヒスパニック票の行方が勝敗を分ける傾向になりつつあり、メキシコ系住民を敵に回すことは非常な不利になりますが、トランプ氏は6月の出馬表明の際に「メキシコは問題のある人間を(米国に)送り込んでいる。彼らは強姦犯だ」などと発言して、メキシコ移民を「麻薬や犯罪を持ち込んでくる」などと非難。
7月には、ベトナム戦争で長期間、捕虜になった共和党の重鎮・マケイン上院軍事委員長について「彼は捕らえられたから戦争英雄になった。私は捕虜にならなかった人が好きだ」と発言。
マケイン氏は「私は英雄ではない」と述べつつも、「トランプ氏は、戦争で犠牲になったり、従軍中に捕らわれたりした人々の家族に謝らなければならない」と批判。
8月の討論会では、「彼女の目から血が流れ出ていた。彼女のどこであれ血が出ていた」と、女性司会者が自分に厳しい態度だったのは生理中だったためとにおわす発言をして批判を浴び、共和党の集会への招待を取り消されたことも。
既成政治の常識を覆す発言を繰り返すトランプ氏が高い支持率を得ていることについて、当初は、選挙戦序盤に注目を集めるもののやがて消えていく“泡まつ候補”と見られていましたが、その高い支持はまだ続いており、「ひょっとすると、共和党候補になるの可能性も・・・」とも言われています。
****トランプ氏、勢い加速 対日強硬発言にも支持 米大統領選****
来年11月の米大統領選に名乗りをあげた共和党のドナルド・トランプ氏(69)の勢いが止まらない。今月上旬の世論調査では、有力視されるジェブ・ブッシュ元フロリダ州知事(62)の倍近い支持率を獲得。人気を下支えしているのが、日本を含む国々に対する強硬な発言だ。
「どこかの国が日本を攻撃したら我々は助けなければならない。だが、我々が攻撃されても日本は助ける必要がない。それがよい協定だと思えるか」
21日に米アラバマ州で行われたトランプ氏の支持者の集会で同氏がこう訴えると、会場からは一斉に「ノー」と罵声が飛んだ。
メキシコからの不法移民を「強姦(ごうかん)犯」などと決めつける過激な言動を繰り返し、強硬姿勢が保守派から支持を集めてきたトランプ氏。決まって同時にやり玉にあげるのが、中国と日本だ。
20日のテレビ番組でも「我々がすべきことは仕事を取り戻すこと。中国、日本、メキシコを止めなければいけない」と主張。「これまでで最大の船を見たが日本の車を積んでいた。だが、日本は我々が牛肉を売ろうとしても受け取ろうともしない」などと、強い不満も表明した。
オバマ政権が進める環太平洋経済連携協定(TPP)も「日本による通貨操作を止められない。あしき交渉だ」と反対する。対外関係や移民の受け入れに穏健な姿勢を示すブッシュ氏を「弱腰」と批判した。
出馬表明前の5月の世論調査ではわずか3%で本命でない候補とみられていたトランプ氏だが、CNNが8月中旬に実施した調査では、ブッシュ氏(13%)を引き離し、2倍近い24%の支持を集めて首位を独走している。【8月23日 朝日】
****************
当然ながらトランプ氏への批判は多々あります。
****ワシントン・ポスト(米国) 米国版プーチン、長く続かず****
米紙ワシントン・ポストは22日付の社説で、不法移民を侮辱するトランプ氏の言葉遣いを理性ではなく感情に訴えるもので、「手に負えなくなる」おそれがあるとした。
同紙は暴言によって高い支持率を維持している「トランプ旋風」に批判的な目を向けており、コラムニストの一人はそのポピュリストぶりをロシアのプーチン大統領になぞらえた。
社説はトランプ氏がメキシコからの不法移民を「強姦犯」と決めつけて侮辱したことを挙げて、こうした発言によって「政治的に有利になるよう意図的に世論の激情を刺激している」と指摘した。
その上で、トランプ氏の発言は大衆による不法移民への暴力をあおるものではないものの、「政治的な怒りを駆り立て、共和党予備選(での候補指名争い)に勝つことを意図するもの」であるとし、トランプ氏による「侮辱に満ちた誇張」には有権者の感情を刺激する問題があるとしている。
一方、ポスト紙のコラムニスト、デイビッド・イグネーシャス氏は19日付の論評で、トランプ氏を「米国版プーチン」と名付けて強く批判した。
トランプ、プーチン両氏の共通点として、具体的な計画を示すことなく国家の偉大さを復活すると約束していることや、短所を抱えているにもかかわらず非常に人気があることを挙げた。そして、「権力とショーマンシップが不可分のものであることを理解している」ことが2人に一致している点であるとした。
トランプ旋風については「遠慮のない発言が政治の曖昧な言葉遣いにうんざりしている国民に訴えている」と分析した。
ただ、プーチン氏のように、弱い者いじめをするような権威主義的な人格は米国では受け入れられてきていないと断言。「(トランプ氏が支持を維持した)この夏は例外だったが、長くは続かないであろうことは歴史が示唆している」と強調した。【8月31日 産経】
*******************
【文化的にも経済的にも疎外されている白人のブルーカラー労働者からの支持】
しかし、大統領候補になる可能性も出てきたとしてトランプ氏の発言を正面切って論評する記事も現れています。
****フィナンシャル・タイムズ(英国) 大統領候補あり得る****
米大統領選挙の共和党候補指名争いで、トランプ氏がリードしていることについて、23日付の英紙フィナンシャル・タイムズ(電子版)は、コラムニスト、エドワード・ルース氏の「ドナルド・トランプ(が米大統領候補になること)は、あり得ないことではない」と題する記事を掲載した。
同氏はまず、トランプ氏が不法移民の強制退去や、米国で生まれた子供に市民権を与えるとした法の廃止など、米国の「建国の精神」にも抵触する可能性がある問題にまで踏み込み、反発を呼んでいるとしながらも、「それでも彼は真剣に受け止められるべきだ」と論じた。
その理由として、▽今月の共和党の討論会の視聴者数が、2011年の前回討論会時の4倍以上の2400万に上り、記録的な数になっている▽数週間におよび共和党内での支持率がトップとなっている事実は一時的なものではない−などを挙げた。
さらに、「何を言うかわからない」トランプ氏は「意識的に不快に思われることで人気を得ている」とも分析。
共和党の大統領候補指名争いから「簡単に外れることもありうる」としながらも、「政治資金は豊富にある。強い自己もある。彼は暴言癖のある保守中道だといわれたりするが、選挙を戦いながら、自分自身をつくっている」と強調した。(後略)【同上】
**********************
経済政策面では、トランプ氏は「貿易協定で、アメリカが最後に中国に勝ったのはいつか? 私は常に中国をたたきのめしてきた」と、TPP推進の共和党にあって「反自由貿易」論を掲げていますが、これを支持しているのが白人ブルーカラー層であると指摘されています。
****「台風の目」トランプの意外な実力****
・・・・だがトランプが台風の目になる最大の理由は、共和党に訪れた大きな変化と関係がある。それは、共和党を支持する白人労働者層の急増だ。
アメリカでは製造業の雇用者数が減少し、白人のブルーカラー労働者に打撃を与えている。失業の危機に直面する彼らは、トランプが掲げる「反自由貿易」論に魅力を感じやすい。
白人ブルーカラー層の民主党離れは今に始まった話ではないが、近年その勢いは増している。
彼らが、従来の支持政党である民主党を見限り始めたのは60年代後半のこと。
80年代には、多くが共和党のロナルド・レーガン大統領支持に転じ、民主党との溝が広がった。90年代に民主党離れに歯止めがかかったのは、ビル・クリントン大統領が福祉改革や犯罪対策強化など、保守派寄りの政策を打ち出したおかげだ。
00年以降は、銃規制や石炭火力発電所への規制が引き金となり、民主党を見捨てる白人労働者層が増えている。
非大卒の白人有権者のうち、12年の大統領選でバラク・オバマを支持した人の割合はわずか33%、昨年の中間選挙で共和党候補者を支持した人は64%に上った。
「彼らは文化的にも経済的にも疎外されている存在だ」と、政治アナリストのロナルド・ブラウンスティーンは指摘する。
共和党支持に転じたブルーカラー層は、従来の共和党支持者よりも自由貿易に対して懐疑的だ。この事実が共和党を変化させている。
ピュー・リサーチセンターが5月に実施した調査によると、自由貿易協定は自分の雇用を奪うものだと考えている人は、民主党支持者よりも共和党支持者に多かった。これはトランプには好都合だ。共和党の主要候補は、おおむね自由貿易を支持しているからだ。(中略)
低学歴の白人ブルーカラー層は、当然ながらメディケア(高齢者医療保険制度)や公的年金の縮小に反対だ。この点でもトランプは、共和党支持者の多くと同じように、社会保障の縮小に反対する姿勢を示している。(中略)
アメリカでは92年に、やはり大富豪のロス・ペローが大統領選に出馬。保護貿易を唱え、大成功したビジネスマンとしてアメリカ経済を立て直すと主張したあたりは(選挙費用を自腹で負担したことも)、トランプにそっくりだ。
ペローは民主党でも共和党でもなく、いわゆる第3党の候補として出馬したが、11月の一般投票で約19%もの票を得た。
だとすれば、共和党に一定の支持基盤を築きつつあるトランプが、予備選でかなりの票を集めたとしてもおかしくない。事実、トランプは現在、ブッシュやウォーカーを抑えて断トツの支持率ナンバーワンにある。
たとえ大統領になれなくても、彼には痛くもかゆくもないだろう。自由貿易を攻撃して、共和党予備選に一波乱起こしたのだ、目立ちたがり屋のトランプは大満足に違いない。【8月19日 Newsweek】
*****************
アメリカの影響を大きく受ける世界の国々の国民としては、アメリカ大統領選挙が“目立ちたがり屋”に振り回されるようなことでは困るのですが・・・。
一方の民主党の話題(メール問題でのクリントン氏の人気低迷、バイデン副大統領への期待感など)は今回はパスして(“たかがメール問題ごとき”で大統領戦から排除されるというのも、困った話ですが)、イギリスの労働党の話。
【緊縮財政のしわ寄せを受ける人々に支持される「時代遅れの社会主義者」】
政権奪還を目指す最大野党・労働党の党首選挙で党内でも最左派のジェレミー・コービン氏が勝利する可能性が高まり、「強硬左派」「時代遅れの社会主義者」では政権は取れないとの危機感が右派などから上がっています。
****「強硬左派」党首濃厚=予想外のリードに危惧と期待―英労働党****
5月の総選挙で大敗した英最大野党・労働党の党首選が現在行われており、郵便などによる投票結果が9月12日に発表される。当初の予想を裏切り「強硬左派」のジェレミー・コービン氏(66)の勝利が濃厚で、党は危惧と期待が交錯する混乱状態にある。
コービン氏は1983年に下院議員初当選のベテランだが、党内では終始異端で、要職に就いたことがない。下院の議決でも、党の方針に従わなかったのは500回以上という。
緊縮財政の中止、鉄道の再国有化、英国の核戦力放棄などを掲げ、党内でも最左派と位置付けられる。
ところが、8月初めの世論調査では支持率53%と、本命視されていたバーナム「影の保健相」(45)ら他候補を30ポイント以上引き離した。
新党首は2020年の次回総選挙での政権奪還に向け、党を立て直す重責を担う。
今回の総選挙敗北をめぐっては、ブレア元首相らが長期政権を築いた右寄りの「ニューレーバー(新労働党)」路線をミリバンド前党首が放棄し、左傾化したことが原因だとの声が強かった。
それだけに「時代遅れの社会主義者」とみられていたコービン氏がトップに躍り出たことに、驚きは大きい。
右派には当然、危機感が強い。ブレア政権でメディア対策を取り仕切ったマンデルソン元民間企業相は、フィナンシャル・タイムズ紙上で「英労働党は最終章を迎えたのかもしれない」と悲観し、政権を取れない万年野党への転落を警告した。【8月29日 時事】
*******************
****英労働党、反緊縮に支持 党首選、最左派候補が人気 路線に逆行、重鎮反対****
・・・・「平等で民主的な社会を作っていきたい」とコービン氏が語ると、満場の聴衆が総立ちで拍手を送った。
党員のハンナ・クロフトさん(23)は「私たち若者や移民は、平等な社会がほしい。彼は画期的な社会の選択肢を示してくれた」と称賛した。(中略)
コービン氏は、労働組合出身。地方議員を経て1983年に下院議員に初当選した。身内の労働党政権下でも400回以上も造反したという「頑固さ」が売りの一方、政府や党の要職とは無縁だった。
訴えは80年代から変わらず、反緊縮や反戦、反核。自ら「コーベノミクス」と称する経済政策では、鉄道の再国有化や、高所得層への増税を掲げる。大学の学費を無料に戻すことや、核戦力の放棄も訴える。
コービン氏の主張が支持を広げる背景には、好調な経済の裏で、緊縮財政のしわ寄せが国民生活に及んでいることがありそうだ。
自治体予算の大幅削減で高齢者の福祉が減らされたり、若者が学費ローンを抱えて大学を卒業しても不安定な職しか見つからなかったりという実情がある。(中略)
ロンドン大学のティム・ベイル教授(政治学)は、「コービン氏の理想主義的な主張が、若者やニューレイバー路線に反発を覚える人々に希望を与えている」と分析した。【8月31日 朝日】
******************
“コービン氏の主張が支持を広げる背景には、好調な経済の裏で、緊縮財政のしわ寄せが国民生活に及んでいることがありそうだ”というのはわかりますが・・・。
不満を抱え、既成の政治から疎外されていると感じる国民は、ときに極端な主張、単純明快な主張に大きな期待を寄せがちです。
しかし、現実社会は白でも黒でもないグレーで、曖昧模糊として、あちらを立てればこちらが立たずというべきもので、その対応も必ずしも明快なものにはならないことが多いのですが。