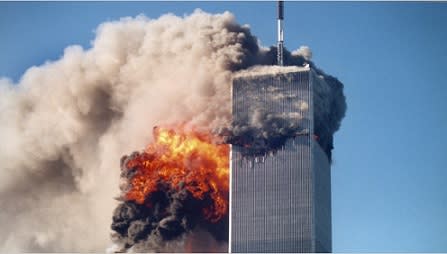(パキスタン・カラチから北東へ約220キロに位置するマットリで、地元当局によって助け出され、我が子を抱きしめる奴隷状態にあった女性たち 【2014年11月18日 AFP】)
【4500万人超が「現代の奴隷」状態に置かれている】
現代社会にあっても「奴隷労働」が広く存在しています。
******************
何者かの所有物として支配され、人間としての権利や自主性を認められずに搾取される奴隷は決して歴史上の用語ではなく、現代にも存在している社会問題と言えます。(中略)
奴隷的労働の実態は多岐にわたり、加工用の魚を捕る漁師(タイ)や、ダイヤモンドを掘る炭鉱作業員(コンゴ)、綿花摘み(ウズベキスタン)、サッカーボールを手縫いする仕事(インド)といったケースが見られるほか、戦闘行為にかり出される少年や売春行為の強要などが行われています。
国際労働機関(International Labour Organization:ILO)の推計によると、このような強制労働から生まれる利益は、年間1500億ドル(約17兆6000億円)にも上ると試算されています。(後略)【2014年11月20日 Gigazine “現代にも残る奴隷労働の実態をまとめた「Global Slavery Index 2014」”】
******************
上記調査の2016年版が発表されました。
****「現代の奴隷」人口、世界で4500万人超****
世界各地で「現代の奴隷」状態に置かれている人の数は、成人と子どもを合わせて4500万人を上回っていることが、31日に発表されたNGOの年次報告書で明らかになった。当初の予測よりはるかに多く、3分の2がアジア太平洋地域を占めている。
奴隷状態の撲滅を目指す団体「ウオーク・フリー・ファウンデーション(WFF)」が発表した報告書「グローバル・スレイバリー・インデックス2016(Global Slavery Index)」は167か国、4万2000人を対象に53言語で面談を行った情報に基づき、奴隷状態にある人々の割合と各国政府の対応を割り出している。データ収集と調査の方法を見直した結果、「奴隷」の数は2年前の推計よりもさらに28%増えているという。
国・地域別で「奴隷」の数が最も多かったのはインドだった(推計1835万人)。また全人口に占める奴隷状態の人の割合が最も多かったのは北朝鮮で、人口の4.37%が奴隷状態にあり、政府の対応も最も鈍かった。
「現代の奴隷」は、脅迫や暴力、強制、権力乱用、詐欺などによって立ち去る自由を奪われ、搾取されている状態を指す。場合によっては、借金の形に漁船で労働させられたり、強制的に家事や売春をさせられたりする例もある。【5月31日 AFP】
*******************
2014年版調査によれば、奴隷人口を全人口比で表した場合、全人口のうち実に4%もの人が奴隷的労働を強要されているというモーリタニアがトップ。次いで3.98%のウズベキスタン、2.30%のハイチ、1.36%のカタールなどが続きます。
カタールでは外国からの出稼ぎ労働者を雇用主が支配する「カファラ」という制度などが問題視されており、2022年に予定されるサッカーのワールドカップ(W杯)カタール大会の妥当性に疑問の声も出ています。
****カタール、W杯スタジアム改修で外国人労働者を酷使・・・・人権団体がFIFAに報告書を提出****
2022年のW杯開催が決まったカタールだが、スタジアム建設における労働者酷使が問題となっているようだ。英紙『テレグラフ』が報じた。
カタールは世界最大のスポーツイベントであるW杯開催に向け、準決勝開催が予定されているハリーファ国際スタジアムの改修工事を行っているが、労働者は過度な重労働に加えて賃金未払いが発生しているという。
この状況に国際人権NGO団体『アムネスティ・インターナショナル』が調査を開始し、50ページにも上る報告書をFIFAに提出した。
同団体のサリル・シェッティ代表は、「移住労働者の乱用は、サッカーの良心における汚点である。選手やファンにとってW杯のスタジアムは夢見る場所だが、労働者の中には悪夢を感じている人もいる」と、FIFAを非難した。
スタジアム建設、インフラ整備のために以前より外国人労働者の死亡事故も相次いでおり、犠牲者は今後も増え続けるとも指摘されている。【3月31日 フットボールチャンネル】
*******************
【最も多いのがインド 茶園での奴隷労働】
2014年版調査において、奴隷人口そのものでみると、1位がインドで1400万人、これに320万人の中国、210万人のパキスタン、120万人のウズベキスタンが続いています。
奴隷労働には、先祖代々続く奴隷身分と、経済的利益に基づく流動的な奴隷労働がありますが、インドなど南アジアでは前者が多いとされています。
インドで“先祖代々続く奴隷身分”と言えば、カースト制などの社会制度が先ず思い浮かびますが、奴隷労働を固定化させているのはそれだけではないようです。
****インド茶園の「奴隷」たち****
世界中で飲まれている有名産地の茶葉生産は、植民地時代そのままの劣悪な環境で働く労働者に支えられている
正午、午前の作業の終わりを告げるサイレンが茶畑に鳴り渡ると、ミナ・シヤルマ(45)は道具を片付け、粗末な服装をした汗だくの女性たちの長い列に並ぶ。収穫した茶葉の目方を量ってもらうためにだ。
それが済むと大急ぎで家に戻り、野菜だけの昼食を作る。安い賃金では、肉には手が出ない。90分後には、おんぼろの家を出て茶畑に戻る。1日の収穫のノルマは25キロ。午後の仕事がまだ残っている。
インド東部の西ベンガル州のドアーズ地方にあるモグルカタ茶園で働くシヤルマは、子供1人を育てるシングルマザー。地元の村の出身で、30歳のとき母親の後を継いでこの茶園の茶摘みの仕事を始めた。ほかの労働者もほとんどが女性だ。
賃金は、1日当たり米ドルにして2ドル足らず。50年以上前に茶葉生産会社から与えられた家に、両親と一緒に住んでいる。「一度も修理してもらっていない」と言い、シヤルマはさびたトタンの屋根に目をやる。「雨が降ると、家の中で傘を差さなくてはならない」
トイレはなく、近所で唯一の水道の蛇口は500人以上が共用している。熱病や下痢は珍しくなく、仕事を休んだ日は半額しか賃金が出ない。
インドは、中国に次ぐ世界第2位の茶葉生産国だ。世界の輸出に占めるシェアは14%。1500を超す茶園で350万人が働く。茶葉産業はインド屈指の重要産業だが、インドが独立して70年近くたった今も、茶園労働者たちは、イギリス統治時代と大して変わらない奴隷同然の待遇で働かされ続けている。
賃金があまりに低いだけではない。食料の配給、飲み水、医療施設、学校、電気を会社に頼っており、家も会社の所有なので、代々仕事を継いでいかなければ追い出されかねない。それに、会社が破産して茶園が閉鎖されれば、賃金も水も食料も一夜で失う。
トイレも飲み水もない
現地のNGOによれば、過去15年間で栄養不良により死亡した茶園労働者は2000人を超す。「私たちが飲む紅茶の陰では、多くの涙が流されている」と、インド屈指の茶葉生産地である西ベンガル州の茶園労働者支援団体「ドアーズ・ジャグロン」のリーダー、ビクトル・バスは非難する。
テライ、ドアーズ、ダージリンの3地区に276の茶園がある西ベンガル州は、茶園労働者の労働環境のひどさで有名だ。13年のインド政府の報告書によると、適切な飲用水施設がある茶園は61力所だけ。107ヵ所は病院がなく、44力所はトイレがない。会社が整備を義務付けられている施設であるにもかかわらず、だ。26万2000人の
労働者のうち9万6000人近くは、家も与えられていない。
「西ベンガルの茶園労働者は、最低中の最低レベルの施設も与えられていない」と、テライ地区で茶園労働者の労働組合を率いるアビジット・マズムダルは言う。「会社側は意図的に労働者をそういう状態に置いている。労働コストを抑えるためだ」(中略)
冒頭で紹介したシヤルマのような人たちにしてみれば、愛するわが子にはもっといい人生を送らせたいが、子供が自分を継いで茶園の仕事に就かなければ、家を失うことになる。家は、粗末とはいえ、彼女たちに保証されている数少ないものだ。
「若い世代はここに残りたがらない」と、不満げな声色でシヤルマは言う。「みんな出て行ってしまう」。シヤルマはおそらく、両親と同じようにここで老いていくのだろう。自分の後は、25歳の既婚の娘に茶摘みの仕事を継いでほしいと思っている。
何十年も過酷な生活に耐え茶園に人生をささげてきたシヤルマに与えられるたった1つの褒美は、子供時代からのすべての思い出が詰まった家で生き続けられることなのだ。ただし、その家を「私の家」と呼べる日は決して来ない。【4月26日号 Newsweek日本版】
*******************
上記の「茶園」労働が前出調査の対象となる「奴隷労働」に該当するのかどうかは知りませんが、極めて劣悪な労働環境にあることは間違いでしょう。
【先進国消費者も奴隷労働の受益者】
個人的には、この記事は少なからずショックでした。
これまでスリランカやインドネシア・ジャワ島などで、何も考えることなく茶園を“観光”してきたこともありますが、何より毎朝“激安紅茶”を飲んでおり、おそらくその“激安”を可能しているのは、上記のような「奴隷労働」ではないか・・・と思うからです。
前出の「Global Slavery Index 2014」では、日本でも23万人が奴隷労働に従事しているとされています。
****日本でも23万人が奴隷労働に従事****
この主な対象は、米国国務省が毎年発表する「人身売買報告書」でも指摘されている性風俗産業に関するものです。
また、今や農業や製造業現場では多くの「技能実習生」が事実上の外国人労働者として働き、日本の産業を下支えしていますが、この実習制度の現場でも、人権侵害が生じていると指摘されています。【3月1日 Business Journal 大谷 俊氏】
********************
もちろんこうした日本国内における「奴隷労働」も問題ですが、前出“激安紅茶”のように、知らず知らずのうちに消費者として、グローバル経済における奴隷労働の受益者となっているということも認識する必要があります。
ただ、消費者はどうしても安い商品に手が伸びてしまいます。私も前出“激安紅茶”を飲み続けています。
(もちろん、商品に「奴隷労働産品」といった表示でもあれば買いませんが・・・・)
2013年4月24日、バングラデシュの首都ダッカ北西約20kmにあるシャバールで、8階建ての商業ビル「ラナ・プラザ」が崩壊した事故は、死者1,127人、負傷者2,500人以上の大惨事になりました。
このビルには縫製工場が入っており、犠牲者の多くが、崩壊の危険のある建物にあっても労働を強制される劣悪な環境で働いていた女性労働者でした。
この事故を機に、労働条件・環境改善を求める声が大きくなりましたが、劣悪環境の縫製工場に発注していた先進国企業の責任も問われることになりました。そうした企業は母国で「激安商品」を供給し、最終的には消費者もその利益を享受する形となっていました。
【企業取引を規制する現代奴隷法の必要性】
上記のような事例を考えると、奴隷労働への関与を法的に企業レベルで食い止める対策が必要に思えますが、イギリスではそうした取り組みが始まっているようです。
****奴隷大国・日本の暗部、23万人も発覚・・・・日本企業、今後の海外展開の障害に****
英国で現代奴隷法(Modern Slavery Act)という法律が昨年、制定されたことをご存じでしょうか。
同法では人身売買、(家庭内含む)強制労働、借金のかたによる労働、性的搾取、強制結婚などの「現代の奴隷」に英国企業が加担することを抑止することを目的とするもので、英国で事業または事業の一部を行い、商品やサービスを提供している全世界での年間売上高が3600万ポンド以上の企業約1万2000社が対象とされています。英国に法人を置き、同規定に該当していれば日本企業も当然対象となります。
「奴隷」は昔の話ではないのかと思う方も多いと思いますが、現代でも奴隷に相当する労働に従事することを余儀なくされている人は少なくありません。
豪州のNGOであるウォークフリー財団が発表している「Global Slavery Index調査」では、世界で約3850万人もの人々がそうした労働環境下に置かれているとされています。(中略)
同法では、自社事業の関わるすべてのサプライチェーン、すなわち英国内外、直接・間接問わず、世界中すべての企業との取引において、現代の奴隷に加担していないことを確認するために企業が取っている方策を毎年公表する義務が課せられることになります。(中略)
同法が制定された背景には、グローバルに広がる企業取引において、そのサプライチェーンの下流にある企業の調達行動を制限することで、上流企業が引き起こす社会・環境・人権等の問題を予防する「CSR(企業の社会的責任)調達」「サステナブル調達」がグローバル企業を中心として、一般化していることが挙げられます。多くのグローバル企業が取引先に対し、調達基準を示し、それを遵守することが取引条件となっています。(後略)【3月1日 Business Journal 大谷 俊氏】
*************************
もちろん、規制があれば直ちに「奴隷労働」がなくなる訳ではないでしょう。
現在でも多くの先進国大手企業は、途上国などの発注先について、不当労働などが行われていないか、一定に視察・監視しているところが多いと思われます。
しかし、実際にはまともな「視察用工場」が存在して、生産の多くは劣悪な「裏工場」で行われていたり、視察する側もそうした事情を薄々知りながらも敢えて問題にせず、形式的に「視察用工場」だけを見てよしとする・・・そうしたことも行われているように聞きます。
抜け道はいくらでもあるのでしょう。そうであるにしても、イギリスの現代奴隷法(Modern Slavery Act)のような規制がかけられることで、企業に対する一定の圧力にはなるでしょう。もし何かトラブルが発覚すれば、「知らなかった」では済まされない企業責任が問われることにもなりますので。
【フェアトレード】
なお、現在でも「フェア・トレード」の仕組みがあります。
****フェアトレードとは****
コーヒーや紅茶、バナナやチョコレート。日常を彩るたくさんの食べ物が世界の国々から私たちの手に届けられています。それらを生産している国、人々のことを考えてみたことはありますか?
日本では途上国で生産された日用品や食料品が、驚くほど安い価格で販売されていることがあります。一方生産国ではその安さを生み出すため、正当な対価が生産者に支払われなかったり、生産性を上げるために必要以上の農薬が使用され環境が破壊されたりする事態が起こっています。
生産者が美味しくて品質の良いものを作り続けていくためには、生産者の労働環境や生活水準が保証され、また自然環境にもやさしい配慮がなされる持続可能な取引のサイクルを作っていくことが重要です。
フェアトレードとは直訳すると「公平な貿易」。つまり、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいいます。
フェアトレード・ラベル運動とは
フェアトレードの明確な基準を設定し、それを守った製品にラベルを貼付して分かりやすく伝え、フェアトレードを広めていこう、というのがフェアトレード・ラベル運動です。
国際フェアトレード認証ラベルは、その原料が生産されてから、輸出入、加工、製造工程を経て「フェアトレード認証製品」として完成品となるまでの全過程で、国際フェアトレードラベル機構(FLO)が定めた国際フェアトレード基準が守られている事を証明しています。【FAIRTRADE JAPAN】
********************