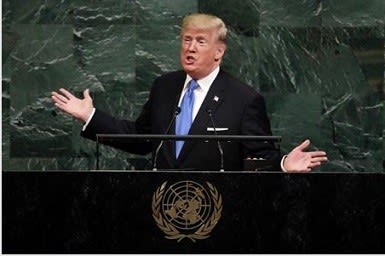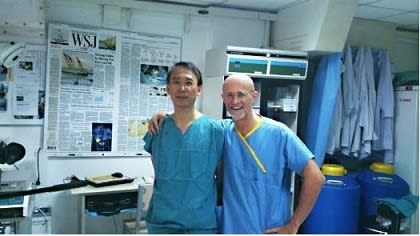(サハラ砂漠の拡大を防止する“万里の緑の壁”計画に参加する11か国【2016年9月17日 環境金融研究機構HP】)
【依然として続く命がけの旅】
ひと頃の混乱状態ほどではなくなったこともあって、メディア等への露出は減っていますが、アフリカから欧州を目指す難民・移民は依然として絶えません。
“年初以降、対岸のリビアからイタリアを目指した移民は10万人近くに上る。この経路では2242人が命を落としたと(国連の国際移住機関)IOMは指摘する。”【8月17日 BBC】
最近の傾向としては、リビア当局が密航業者の取締りを強化したことなどから、イタリアに到着する人の数は減少傾向にありますが、かわって、モロッコからジブラルタル海峡などを渡ってスペインに向かう人々が増えていることで、IMOによれば、8月中旬時点でスペインには今年8000人以上が到着しており、去年の同じ時期の3倍以上に増えているとのことです。海上で遭難し命を落とした者も120人以上。
悲惨な事故・事件も相変わらずです。
“移民船難破、100人超不明=リビア沖”【9月21日 時事】
“密航業者が移民を海に投げ出す、イエメン沖で29人死亡 摘発恐れ”【8月10日 AFP】
危険は海上だけでなく、リビアやモロッコに行くためにサハラ砂漠を横断する危険な旅を選択する人々もあとをたちません。
“国連のIOM=国際移住機関は、8日、北アフリカのニジェールのサハラ砂漠で、ことし4月以降、合わせておよそ1000人の難民や移民を保護したと発表しました。
先月下旬には、西アフリカのガンビアやセネガル出身の23人が砂漠の中に置き去りにされて救助され、中には7歳の女の子もいたということです。”【8月10日 AFP】
やっとリビアにたどり着いても悲惨です。
****難民の旅の悲惨な終着点リビア****
・・・・内政の混乱が続くリビアを支配するのは民兵組織の寄せ集め。彼らは密航業者の人身売買に加担し、移民・難民への虐待や人権侵害を行っているとされる。
首都トリポリでは密航を待つ大勢の男女や子供が隠れ家などから追い立てられ、移民・難民収容所に送り込まれていく。
シッカ通りの施設では、不衛生な倉庫に男性約1500人が閉じ込められている。トイレもシャワーもなく、用を足すのは空のペットボトルかビニール袋だ。(後略)【8月30日 Newsweek】
******************
【『ヨーロッパ要塞化』】
こうした命がけの危険な旅でサハラ砂漠・地中海を超えても、たどり着いた欧州で幸せが手に入る訳でもありません。
****EU:難民受け入れ合意 履行はわずか3分の1****
EU(欧州連合)加盟国は、ギリシャとイタリアにいる庇護希望者を受け入れることに合意しているが、その履行期限が9月26日に迫っているにもかかわらず、約束した人数の受け入れには、ほど遠い状況である。
同計画の合意から2年、ほとんどの国が約束を果たしていないため、このままでは数千人の難民と庇護希望者が、イタリアとギリシャに取り残され、見捨てられかねない。
国別にみると、ポーランドとハンガリーは、これまで受け入れをことごとく拒み、受け入れ数はいまだにゼロだ。同計画への異議を欧州裁判所に申し立てをしたスロバキアは、割り当てられた受け入れ枠902人のうち16人を受け入れただけで、チェコの受け入れは、同2,691人のうち、わずか12人である。(後略)【9月27日 アムネスティ国際ニュース】
******************
受け入れ先でも、多くが施設に収容するだけの中途半端な状態に置かれています。しかも各国の反移民・難民感情は高まっており、ますます“厄介者”扱いが進みます。
****難民100万人以上が欧州で放置状態****
ヨーロッパに渡った220万人の難民白の約半数が忘れ去られている
米調査機関ビュー・リサーチセンターの9月20日の発表によると、15~16年にヨーロッパで難民申請した人々のう
ち、滞在許可を得だのは約40%のみ。残りは収容施設で中ぶらりんの状態に置かれている。多くの国では難民申請から少なくとも数力月は就労も許されない。
放置された難民たちは、人道上の問題を抱えるだけではない。難民が政府の寛大な支援に寄生しているという見方が、欧州各国の反難民感情をあおっている。
難民受け入れで先頭に立ってきたドイツでは、9月24日の総選挙で極右政党「ドイツのための選択肢(AfD)」が国政初の議席を獲得し、第3党に躍進するとみられている。反移民を訴えるAfDの成功は、欧州各国で連鎖反応を呼ぶ恐れもある。
EUの難民政策は、「リビアのキャンプに難民たちを追い返す『ヨーロッパ要塞化』の方向へ進んでいる」と、バーミンガム大学の研究員ヨセフィン・グレーフは言う。「地中海で命を落とす難民を救うことはますます困難になっている」【10月3日号 Newsweek日本語版】
**********************
欧州・EU側も何も対策をとっていない訳ではなく、地中海での救助活動、国境警備・強制送還に加え、リビアでの出国を防ぐような海上防御活動も行っています。
しかし、欧州に来させない『ヨーロッパ要塞化』だけを進めても、命がけの旅に出る人々にはそうせざるを得ない事情が出身国にあり、その根本を改善しないかぎり欧州への難民圧力はなくなりません。
仮に、『ヨーロッパ要塞化』が功を奏して欧州への難民・移民流入を防ぐことができたとしても、壁に守られて恵まれた生活を送る人々がいる一方で、壁の外側では多くの人々が貧困・紛争に苦しむ・・・・という状況が、人道的にみて容認できる状態とも思いません。
また、壁の内側の人々への憎しみは、テロを必然的に生みます。
すると、更に壁を高くして・・・人間性が問われます。
もっとも、こうした人道・人間性の話をすれば、昨今は鼻先で嗤われるだけの風潮ではありますが・・・。
【「地中海で多くの人が死んでいるのはみんな知っているが、それでもリスクを冒さずにいられない」】
EUでも、そうしたアフリカ各国の状況を改善して、移民・難民の動機をなくすための対策は行っています。
****不法移民を元から断つEUの「太陽政策」****
増え続ける不法入国を阻止するため、密航の危険性を伝える啓発プロジェクトを推進
ヨーロッパを目指すのは危険です・・・・ナイジェリア南部エド州の農村イルケンにある学校で、プレシャス・オーウェンズは生徒たちにそう説く。外国にいい仕事があるという誘いは、大抵は嘘。密航業者に搾取・監禁されるケースが多く、ボートで地中海を渡るのは命懸けで、多くの場合は売春婦などとして働くことを強制される、と。
オーウェンズはエド州の住民を対象に啓発活動を行う非政府組織のスタッフ。密入国のリスクを教える彼らの活動は、実はEUの支援を受けている。(中略)
EUは国境警備や強制送還などの強硬策を取ってきたが、焼け石に水。そこで最近は密入国希望者を減らすための「太陽政策」に巨額を投じている。「移民・難民問題はEU外交政策の最優先課題だ」と、オックスフォード大学難民研究センターのジェフークリスプ研究員は言う。(中略)
人道問題に絡む懸念も
1年前と比べて、地中海を渡って欧州に入った難民・移民の数自体は減少している。ただし国際移住機関(IOM)によれば、密航船の質の低下などで死亡者の割合は増加。EUは、密入国の危険性を啓発するとともに、不法移民の母国の経済や治安を改善させ、密航せずに済む環境をつくろうとしている。
EUは15年、アフリカのための緊急信託基金(EUTF)を創設し、アフリカ3地域の26力国に29億ユーロを拠出する方針を決定。8月下旬時点で計117のプロジェクトに約19億ユーロを拠出することが承認されている。
もっとも一部のプロジェクトについては、人道犯罪が指摘されるエリトリアやスーダンの政府を利する可能性があると懸念する声が上がる。(中略)
別の懸念もある。オックスフォード大学のクリスプらに言わせれば、開発によって自国でよりよい教育や仕事にアクセスしやすくなると、欧州への移住を考える人はむしろ増える傾向がある。そのための手段や資金が手に入るからだ。
一方、ロンドン大学東洋アフリカ学院開発学部の責任者で、EUの支援下でエリトリアやソマリアなどアフリカ大陸東端の国々の移民問題を調査するローラ・ハモンドは、自国でよりよい仕事があれば移住を思いとどまるはずだと言う。「最低限の生活ができる賃金を自国内で得るか、外国を目指して危険な旅をするか。選択肢があるなら、多くは前者を選ぶだろう」
だがイルケン村では、選択肢などないに等しい。大半の生徒の家庭には、3ヵ月分の学費500ナイラ(約1.4ドル)を支払う余裕もないと、教師のケスター・エヒコーは話す。
外国に仕事があると家族の誰かが誘われれば、仕送り欲しさに飛び付いてしまう。「地中海で多くの人が死んでいるのはみんな知っているが、それでもリスクを冒さずにいられない」【9月19日号 Newsweek日本語版】
*******************
現実政治の世界にあっては、こうしたアフリカ各国への支援は、アフリカの経済成長を促し、各国における国民生活を改善させるにとどまらず、支援する側の欧州に将来的な巨大な市場を提供する“囲い込み”的な側面もあると思われます。そのたりが政策選択のインセンティブにもなるのでしょう。
【生活を破壊するサハラ砂漠の拡大 大陸横断8000kmの植林帯で防止】
上記の緊急信託基金(EUTF)のプロジェクトに関連しているかどうかは知りませんが、サハラ砂漠南縁(サヘル地域)を脅かす砂漠化を植林事業で防止して国民生活を守ろうとする“壮大な”取り組み“万里の緑の壁”プロジェクトがあることは随分以前に数回取り上げたことがあります。
2008年11月4日ブログ“砂漠化防止対策 “数百年後”のセネガルの「緑の壁」完成を待つだけではなく・・・”では、今のペースで本当に実現できるのだろうか?という疑問も。
2010年6月26日ブログ“貧困に苦しむサブサハラ サハラ砂漠に「緑の壁」”では、先進国の支援の必要性を。
2013年5月26日ブログ“ニジェール イスラム過激派が仏ウラン加工施設攻撃 拡散するテロ組織の背景に砂漠化進行と食糧難”では、テロ活動の根底に砂漠化による生活破壊があることなどを取り上げてきました。
****砂漠化がテロを生む 消える村、流れる若者****
(中略)
■信仰じゃない、食べるために
サヘルの若者が武装勢力に加わっているというのは、本当なのか。取材を重ねていると、国際テロ組織アルカイダ系のイスラム武装組織「MUJAO(西アフリカ統一聖戦運動)」の元メンバーら2人に会うことができた。(中略)
「メンバーには食うのに困った農民や牧畜民がたくさんいた。近年の大干ばつで多くの人が家畜や生活の糧を失った。大半が宗教心から加わったわけではなく、家族を養うためだ」。2人はそう証言した。(中略)
(2人のうちの1人)イドリサさんが言う。「畑に砂が積もる故郷で、何ができるのだ。政府は助けてくれない。貧困と社会不平等がなくならない限り、また新たな組織ができるだろう。食べるものがなくて、戦えばくれると言われれば、死ぬかもしれなくても参加するだろう」(中略)
■緑の壁、自立の芽育む
国際社会がサヘルの問題を見過ごしていたわけではない。
前回2008年の第4回アフリカ開発会議(TICAD4)でも取り上げられ、日本は国連開発計画(UNDP)を通じ、砂漠化を含めた気候変動の脅威への対応に9210万ドルの拠出を表明。さらに6月の第5回会議を控え、サヘル地域などの平和と安定のため、5・5億ドルの支援を明らかにしている。
東はジブチから西はセネガルまで、全長約8千キロにわたって植樹するという「アフリカ緑の壁プロジェクト」構想も持ち上がっている。
ニジェール南東部では10年から緑地帯の周りにヤシの樹皮を何重にも張り巡らせ、砂漠の拡大を食い止める試みが続いている。農地を失った地元住民らが作業に当たり、賃金が支払われている。
メイネ・ソロア県と周辺では計3600ヘクタール分の囲いを作り、120万本を植林したという。ニジェール政府の担当者は「小さな活動だが住民が参加することで持続可能な土地の利用を促すことができる」と話す。
ただ、サヘル地域の治安の悪化によって活動の停止に追い込まれている場所も少なくない。マリでは国際NGOなどによる100以上のプロジェクトがあったが、昨年からの紛争によって北部ではほぼすべて活動が停止しているという。
それでもマリ政府の環境衛生省のスーマナ・タンボ局長補佐は「砂漠化によってコントロールができなくなる地域が増えることは過激派の活動を助長する。さらに生活の糧を失った人々が過激派の提示する金になびく可能性がある」と緑化事業継続の必要性を訴えた。
ブルキナファソなどで20年以上、環境活動をしている日本のNGO「緑のサヘル」(岡本敏樹代表)は、植林に加え果樹栽培や養蜂技術の支援などで地域住民が現金収入を得られるよう、自立のための活動も展開している。【2013年5月26日 朝日】
**********************
“壮大な”緑化プロジェクトは、この10年で全体計画の15%が達成されいるそうです。(完了までに“数百年”もは必要ないようです。)
****アフリカに築かれる「緑の万里の長城(Great Green Wall)」。サハラ砂漠の拡大防止で大陸横断の植林帯。計画から10年で15%を達成****
地球温暖化の進行で、砂漠化が一段と進むアフリカ。生態系と地域社会の荒廃に待ったをかけようと、アフリカの11か国が共同で、サハラ砂漠の南端に植林による「緑の壁」 を築く構想がスタートして今年で10年目。7000kmに及ぶ目標の「壁」の約15%分が、現在までに植えられたという。
このプロジェクトは「Sahara and Sahel Great Green Wall Initiative(SSGGWI)」と呼ばれる。2007年に、アフリカ連合(AU)の主導によって、アフリカ西岸のセネガルから東岸のジブチの沿岸部までの約7000kmを植林帯でつなぐことを目指して始まった壮大な計画だ。
計画に参加している11カ国は、サハラ砂漠の南縁部に広がる半乾燥地帯のサヘル地域に点在する諸国。ジブチ、エリトリア、エチオピア、スーダン、チャド、ニジェール、ナイジェリア、マリ、ブルキナファソ、モーリタニア、セネガルである。
温暖化による砂漠化の拡大と、人口増加と経済発展による森林・草原等の減少、生態系の改変等は、地域の食糧供給を不安定にし、社会の悪化からテロリズムの温床や、欧州への移民の供給源などの社会問題をも引き起こしている。このため大規模植林計画は、単なる緑化という目的だけでなく、住民を守り、テロ等のグローバル脅威を絶つ狙いもある。(中略)
植林される樹木は、アフリカに多いアカシア科。気象条件が厳しい地域でも育つためだ。またアラビア・ゴムの原料にもなる。同ゴムは接着剤の原料になるほか、食料添加物や薬剤などにも利用され、経済的利益を地元にもたらす。
計画スタートから10年経過した本年で、「緑の壁」は約15%分の植林が進んだという。植林プロジェクトを実施する11カ国を支援するのはAUだが、欧州連合(EU)、世界銀行、欧州諸国などが「緑の壁のサポーター」になっている。(後略)【2016年9月17日 環境金融研究機構HP】
********************
この“万里の緑の壁”プロジェクトが一番進んでいるのは2008年11月4日ブログでも取り上げたセネガルです。
そのセネガルの状況について、http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51217にBBCの動画が掲載されています。
動画内容は、以下のようなものです。
****アフリカに巨大な緑の壁 地元経済再生へ****
プロジェクトは11か国、全長8000km、幅15km 最も進んでいるのがセネガルで1100万本を植樹した。
村長:緑の壁が砂漠化に対抗しています。木がなかったときは風で土壌が侵食されていました。今は前より土壌が守られています。落ち葉で腐葉土ができ、枝で覆われた場所の湿度が増し、日陰もできるのでそれほどたくさん水やりをしなくて済みます。
このプロジェクトでは干ばつに耐性のあるアカシアの木を植えている。木の根が土中の水分を保持する。そのため枯れていた井戸にも水がたっぷりもどってきた。
村長:かつてはここには干ばつと飢えがはびこっていました。それから植樹がはじまり、女性たちが作物を育てるための庭ができました 。
壁によってまったく新しい経済の仕組みができたという
村長:本当に大きな助けになっています。今や女性200人がこの仕事についています。賃金にも恵まれています。
砂漠化が原因で大勢が故郷から離れざるを得なかった。
村長:これまでみんなよそに移住していました。しかし今では仕事のため緑の壁沿いに集まっています。もうよそには出ていきません。
プロジェクト参加女性:これまで仕事は何もありませんでした。今は仕事があって経済的にも楽になりました。万里の緑の壁はとても役に立ちます。野菜をたくさん育てられるし、農産物をもっと安く買えるようになりました。(中略)
このプロジェクトは2007年に始まった。総額は推定80億ドル(約8900億円) 緑の壁の完成にはまだ時間がかかる。それでも世界銀行、国際連合、アフリカ連合、それに英国の王立植物園は寄付を約束した。植樹を続けるために。【9月29日 BBCより】
*****************
成果とされるものが、緑化の結果によるものなのか、公共事業としての緑化事業の雇用創出によるものなのか判然としない部分はありますが、効果が上がっているのなら非常に喜ばしいことです。
サヘル地域の砂漠化に対し、80億ドルで一定の効果が期待できるな、国際社会としては“安いもの”ではないでしょうか?