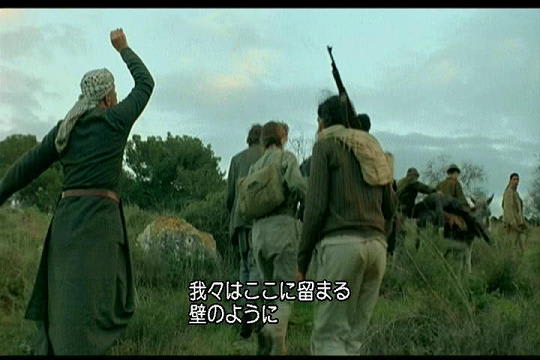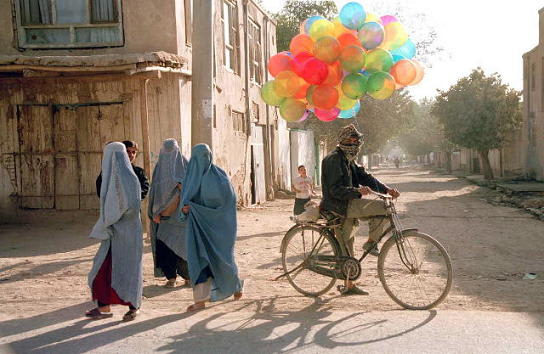(ボリビアの街角 先住民の母子 “flickr”より By PJFurlong06)
南米の中央部内陸に位置するボリビア。
個人的には、ボリビアに関する情報といえば、19世紀ラテンアメリカ世界のスペインからの独立を実現した英雄シモン・ボリバルにちなんだ国名であること(ボリビア現地で活動したシモン・ボリバルの部下でありパートナーであったアントニオ・ホセ・デ・スクレが初代大統領で、首都スクレは彼の名前にちなんだもの)、今世紀稀代の革命家チェ・ゲバラがこの地で革命を目指すも捕らえられ処刑されたこと・・・そのぐらいです。
それと昨年1月、アンデス先住民(インディオ)であるアイマラ出身のモラレス大統領が左派政権を実現したことも、南米全体の左傾化の文脈で目にすることがあります。
シモン・ボリバル、チェ・ゲバラ、モラレス・・・革命に縁のある土地柄のようです。
それはまた、その対象となる旧勢力が強い支配力を持っているということでもあるでしょう。
*****南米に初の東西横断道路、2009年の完成めざし合意******
ボリビア、ブラジル、チリの首脳は12月16日、ボリビア・ラパスで会談し、ブラジルの大西洋岸からボリビアを抜けてチリの太平洋岸までをつなぐ南米初の東西横断道路の建設で合意した。
ブラジルのダシルバ大統領は、南米横断道路の完成は2009年を予定していると説明、3か国間のみならず国際物流のスピード促進につながるとして、経済効果に期待を寄せた。
地元の企業関係者は、アジアに輸出を行っているブラジル企業やブラジル市場を狙うアジア企業に大きなビジネスチャンスをもたらすとしている。また内陸のボリビアは、国内の輸出の70%を新道が担うとみている。
横断道路は全長4700キロ。ブラジルが1億6200万ドル(約183億円)、チリが9200万ドル(約104億円)を拠出するという【12月17日 AFP】
************************
ボリビアの一人当たり国内総生産(GDP)はラテンアメリカで最低クラスの3623ドル(2006年 世界銀行調査)。
一方、西隣のチリはラテンアメリカ最高の12277ドル、東隣のブラジルはいまやBRICsとして世界の中心に躍り出る勢いで8608ドル。
天然ガス・鉄・マグネシウムなど豊富な資源にもかかわらず貧しいボリビアは、かつて「黄金の玉座に座る乞食」と揶揄されていたこともあります。
そのボリビアのネックは内陸国で海をもたないこと。
“海へ出たい”というのはボリビアの長年の悲願でもありますが、太平洋・大西洋の両方に出口が開ける今回の南米東西横断道路は、ボリビアの物流には大きな影響をもたらすと思われます。
ブラジルは太平洋を越えてアジア向け輸出のため、チリは大西洋を越えて欧州向け輸出のための物流の拡大に期待を寄せており、ボリビアを含め三者の思惑が一致した結果の横断道路のようです。
しかし、ちょっと調べるとこの三者の関係は微妙なものがあります。
まず、ボリビアとチリは“不倶戴天の敵”といった険悪な関係が続いており、78年には外交が途絶え、今でも正式な外交関係はありません。
両者の確執のおおもとは19世紀末の“太平洋戦争”にあります。
詳しいことは割愛しますが、当時ボリビアは海岸線を保有していました。
しかし、ボリビア・ペルー連合軍対チリの戦争が起こり、ボリビアは敗北。
チリに海岸線領土を割譲し内陸国になってしまいます。
以来、“チリ憎し”“海を返せ”はボリビアの怨念となり、いまでもチリとは“海の問題”で対立しています。
チリの方は比較的余裕の対応で、フォクスレー外相はボリビアとの外交関係について、「ラパス(ボリビア最大都市)の決断次第だ」と、ボリビアとの外交関係の再開に期待を示しているそうです。
ブラジルの国営石油企業Petrobrasはボリビアの天然ガスに既に15億ドル投資を行っています。
Petrobrasのビジネス活動は、ボリビア国内総生産の24%を占め、ボリビア天然ガス備蓄の46%の権利を取得しています。
また、ブラジルの市場開放策により1999年には2300万ドルであったブラジルにおけるボリビア製品輸入が9億9000万ドルに増加しました。(Petrobras建設のパイプラインによる天然ガス輸入が中心。)【5月20日 IPS】
その緊密なボリビア・ブラジルの経済関係に大きな波紋をおこしているのが、ボリビア・モラレス大統領の資源国有化政策です。
ボリビアの天然ガス埋蔵量は南米で2番目に多い量であると推定されています。
この採掘のため、ブラジル、イギリス、スペインなどの外国資本が参入しています。
しかし、国民には「ガスの輸出は、17世紀の金銀に始まって20世紀の錫に至るまで何世紀にもわたって外国企業によって搾取され続けてきたボリビアの天然資源の問題をそのまま繰り返す事になる」「ボリビア国内にガス精製所を作り、輸出するよりも前に国内25万世帯にガスを供給するべきだ」との主張が先住民や労働団体に強く、国内諸問題と相まって“ボリビアガス紛争”とも呼ばれる政治的混乱を引き起こしてきました。
武装治安部隊の反対運動鎮圧、反対勢力によるラパス包囲・道路封鎖といった混乱で、03年にはロサダ大統領が、06年にはメサ大統領も辞任に追い込まれています。【ウィキペディアより抜粋】
ボリビアの石油産業は過去2回、最近では69年に国有化されたことがあります。
しかし、90年代の世界経済の潮流の変化のなかで経済的新自由主義の方向に転換し、ボリビアは「資本化政策」といわれる新しい型の民営化を先駆けて行っています。
この資本化政策で、外国企業は国営企業の株式の半分を取得し経営権を握り、残りの株式は年金生活者のために投資に回されました。
結果的には、この経済自由化の成果は乏しく、一連の“ボリビアガス紛争”の混乱及びモラレス大統領の登場は、経済自由化政策への幻滅と外国企業に対する反感の高まりを反映していると言えます。
また、南米全体で見ると、世界第5位の石油経済国であるベネズエラのチャベス大統領が05年に行った「主要投資企業がベネズエラで操業を続けたいのなら、新しい契約を結べなければならない」との宣言に見られる、資源の国家管理の流れがあります。
大雑把に分類すると南米は現在、ボリビア、ベネズエラを中心とする反米・左派勢力、米国との自由貿易策を打ち出しているコロンビア、ペルーのグループ、そしてブラジル、アルゼンチンの「中道」社会民主主義政府の3グループに分かれています。
モラレス大統領は就任以来、ベネズエラのチャベス大統領、更にはキューバのカストロ議長と緊密な連携を保っています。
モラレス大統領は就任100日目に当たる06年5月1日(メーデーの日)、油田とガス・パイプラインに軍隊を送り込んで、国有財産であると宣言しました。
この宣言では、「ボリビアにある外国企業は180日以内に撤退するか、新しい契約を結ばなくてはならない。」としています。
ボリビア政府はまた、少なくとも2つのガス田について、課税を大幅に引き上げると発表しました。
政府は主だった外国投資企業はボリビアに残るであろうと予測し、撤退した会社の代わりには中国の会社が入ってくるであろうと予想していたとも言われます。
ここでも中国の資源外交が展開されています。
結果的には、撤退企業は1社もなく、06年10月末、全企業がモラレス政権の提示条件をのみました。
これによりエネルギー産業からの国庫収入は、2.5億ドルから10億ドルに増大し、同時期に成立したアルゼンチン向け天然ガス輸出を併せると20億ドルにのぼるそうです。【06年11月10日 IPS】
モラレス大統領は「誰一人追放することも、なにひとつ財産を没収することも、一切の補償金を支払うこともなく国有化が実現された」と評しています。
当然、このような措置に対するブラジル世論の反発はありますが、ブラジル政府の反応は比較的抑制されたもので、従来の「非干渉」「良い隣人」の原則に沿ったものであるようです。
今月16日、ブラジルのルラ大統領はボリビアを訪問してモラレス大統領と会談、相互のエネルギー開発などで合意しています。
資源の魅力には勝てないようです。
なお、資源問題だけでなく、ボリビアにはおよそ3万人の越境したブラジル人地主がいるそうで、モラレス大統領は、国境沿い50キロ以内の非農耕地および違法所有地の没収を発表しています。
このようなボリビア政府の農地改革に対する反対もブラジルにはあります。【06年5月20日 IPS】
ボリビア国内に目を転じると、天然ガスの問題にも絡みますが、憲法改正を進めようとするモラレス大統領に対し、今月15日東部4県が徴税権など独立色の強い“自治”を宣言してモラレス大統領と激しく対立、厳戒態勢のなかで分裂の危機を迎えています。
モラレス政権は今月9日、新自由主義、寡頭支配との決別を掲げて、先住民の権利拡充や「連帯的な混合経済」などをうたった新憲法草案を、主要野党が出席を拒否する制憲会議で採択しました。
モラレス大統領は憲法を改正し、自身の権限拡大、および富裕な東部の県の財産を貧しいアンデス山地の西部の県に再分配しようとしていると言われています。
東部のサンタクルス、タリハ、ベニおよびパンドの富裕な4県は、国内総生産の3分の2、人口850万の3分の1を占めており、鉱山企業や大農園が集中しています。
東部4県は天然ガスなどの資源に富み、その利権を新たに地域づくりに生かすことを求めています。
また東部住民には先住民と白人の混血が多いのに対し、モラレス大統領の出身地である西部山間部は先住民が多数を占めています。
両者の対立は、天然ガス国有化を進めるモラレス大統領による経済活動の国家管理の懸念、資源利益の東部から西部への移転という経済面に加え、人種的対立の側面も含んでいます。
東部4県の宣言は今後県民の投票に付されますが、世論調査では東部住民の過半数がこれを支持しているようです。
これに対し、モラレス大統領は、自身の信任を問う国民投票を実施する方針を発表しています。
また、モラレス大統領は14日、自治が宣言されれば軍事介入すると警告していましたが、国防相は非常事態の宣言の可能性については否定しており、現在ところはそのような事態には至っていません。
アルゼンチンやブラジルなど中南米九カ国の首脳は、民主的に選出された政府の安定性を損なう動きに反対し、反政府派に対話を促す文書を明らかにしており、EU、米州機構も仲介に入るとも言われています。【12月17日 しんぶん赤旗】
現在モラレス政権と東部4県の対立は拮抗していますが、今後の動向としては、来年に行われる新憲法の国民投票の結果が注目されます。
また、仮に新憲法が国民投票で信任されても、選挙後に「憲法法廷」での争いに突入する可能性が高いとも観測されています。