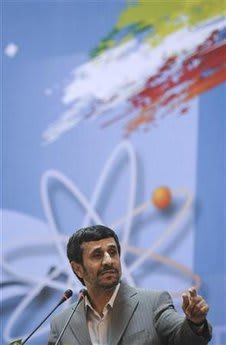(南シナ海を巡航するアメリカ艦隊 中国艦隊の進出で南シナ海の波が今後高まることが予想されます。
“flickr”より By Official U.S. Navy Gallery
http://www.flickr.com/photos/usnavynvns/4379219449/)
【鄭和で「平和外交」アピール】
ヴァスコ・ダ・ガマが喜望峰を回り、ヨーロッパ人として初めてインドのカリカットに到着したのが1498年ですが、このヨーロッパの大航海時代に先だって1405年7月11日、中国・明の宦官である鄭和が永楽帝の命により第1次航海へと出ました。
“『明史』によれば長さ44丈(約137m)、幅18丈(約56m)という巨艦であり、船団は62隻、総乗組員は2万7800名余りに登る。”【ウィキペディア】という、巨艦・大船団です。
鄭和の遠征は、永楽帝死後の1431年まで7回行われ、東南アジア、インド、アラビア半島を経てアフリカ東海岸に至っています。
中国が、その鄭和の偉業を「平和外交」の象徴として、中国とアフリカの歴史的交流をアピールしています。
****中国明代・鄭和艦隊の難破船、ケニア沖に 「平和外交」の象徴、共同研究*****
15世紀初めにアフリカまで航海したといわれる中国・明代の武将、鄭和(ていわ)の大艦隊のうち、磁器などを積み込んだ1隻が東アフリカのケニア沖に沈没している可能性が高いとして、中国とケニア両国が共同研究に乗り出した。中国はいま、近代的な外洋海軍の整備を着々と進めており、約600年前にインド洋を横断して東アフリカまで到達した鄭和を“平和外交”の象徴として強調することで、国際社会の懸念を和らげる狙いがあるとみられている。(中略)
経済成長に必要な資源などを獲得するため、アフリカで独裁政権を支援し欧米の批判を招くことも少なくない中国だが、最近、鄭和が交易を中心とした“平和外交”を推進したと主張。その後、アフリカに到達した欧州諸国が武力を行使し、奴隷貿易まで行った負の歴史との違いを強調している。
中国側には、航海から600周年に当たる2018年までに中国とアフリカの歴史的交流を証明し、国際社会に中国とアフリカ関係の長さをアピールする狙いがあるようだ。(後略)【7月30日 産経】
*****************************
鄭和の遠征が“平和外交”だったかどうかについてはよくわかりませんが、【ウィキペディア】によれば、自衛、あるいは現地要請によるとされる武力行使もあるにはあったようです。
“(第3次遠征)帰路のセイロンで現地の王が鄭和の船に積んである宝を強奪しようと攻撃してきたので鄭和は反撃して王とその家族を虜にして本国へと連れ帰り、1411年7月に帰国した。”
“(第4次遠征)帰路の途中、スマトラで現地の王の要請で兵を使って反逆者を討ち、1415年7月に帰国した。”
一方、“鄭和が寄港した各地の港でも鄭和の評判は非常に高く、ジャワ・スマトラ・タイには三宝廟が建立されて祀られている”とも。
鄭和の遠征の目的については、“中国艦隊が南シナ海やインド洋における海上覇権を樹立することによって諸国の朝貢を促し、宮廷で使用される海外の奢侈品を入手するのが主目的だったと考えられる”という経済目的が重視されていますが、当然ながら、中華思想を背景にした国威発揚、周辺国を威圧することでの中国を中心とした世界秩序の構築という政治的な思惑もあったと想像されます。
「62隻、総乗組員2万7800名」という大船団を目にして、周辺国は朝貢を余儀なくされたことでしょう。
【「核心的利益」】
時代は下って現代の中国。急成長する経済活動を支えるため中東・アフリカから石油などの資源・エネルギーを海上交通路(シーレーン)で安定輸入する目的で近年、官民挙げてインド洋沿岸諸国の港湾整備を積極支援しています。その拠点は、パキスタンのグワダル、スリランカのハンバントタ、バングラデシュのチッタゴン、ベンガル湾のココ諸島などで、「真珠の首飾り」と呼ばれています。
また、中国は海軍力を急速に強化し外洋艦隊へと成長させています。
それに合わせて、南沙諸島や西沙諸島の領有権で東南アジア各国との軋轢がある「南シナ海」を、台湾やチベット、新疆ウイグル両自治区などと並ぶ「核心的利益」と位置付け、今後更にこの地域へのプレゼンスを強める意志を明確に示しています。
****中国:南シナ海で海軍が大規模演習 米国けん制が狙いか*****
30日付の中国軍機関紙・解放軍報によると、中国海軍は26日、南シナ海で艦艇多数が参加した実弾演習を実施した。中国は、南沙(スプラトリー)諸島など周辺国と領有権紛争を抱える南シナ海に米国が介入することを警戒しており、演習には米国をけん制する狙いがありそうだ。
演習には、中国海軍の北海、東海、南海各艦隊の主力艦や潜水艦、戦闘機などが参加。(中略)
現場では、陳炳徳総参謀長(中央軍事委員会委員)が「情勢変化に注目し、着実に軍事闘争を準備しなければならない」と強調した。軍首脳の軍事委委員が演習に現場で参加することは珍しく、今回の演習を重視していることがうかがえる。
南シナ海を巡っては、クリントン米国務長官が23日にハノイで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム(ARF)で多国間協議を支持。当事国2国間での係争解決を主張する中国側と鋭く対立している。【7月30日 毎日】
****************************
南シナ海問題では、上記記事にもあるように、23日のASEAN地域フォーラム(ARF)で、いつになく激しい議論が中国と関係国の間で交わされたばかりです。
****ASEAN、南シナ海問題で拘束力ある枠組み主張*****
ハノイで23日に開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラム(ARF)では、ASEAN―中国間で緊張が高まっている南シナ海の領有権を巡る問題も大きな焦点となった。
ASEAN側は、平和解決に向けて拘束力のある枠組み作りの必要性を主張し、今後結束して対処すると表明。これに対し、中国は対話には応じつつ、主権が絡む妥協は拒否する構えを崩さなかった。
「南シナ海問題で中国側とこれほど論議したのは久しぶりだ」とASEAN筋が語る。会議では、この問題が北朝鮮問題に次いで議論され、中国の楊外相発言のほとんどは、南シナ海を巡るものだった。
スプラトリー(南沙)諸島などの領有権争いを巡り2002年にASEAN、中国が署名した「行動宣言」は、法的拘束力がない。ASEAN側はこれまで、信頼醸成などでの具体的行動を明記し、法的拘束力を持たせた「行動規範」の策定を働きかけてきたが、中国側に拒否されてきた。
今会議でASEANは、「行動宣言」の影響が及ぶのは「海域の権利主張国」と限定していた従来の主張を変え、ASEAN全体の利害にかかわる問題だと強調した上で、「『行動宣言』の完全履行に加え、『行動規範』策定に向け、努力を促す」ことを声明に盛り込むよう求めた。【7月24日 読売】
*******************************
この問題は議長声明では、平和解決を盛り込んだ「行動宣言」の重要性などを再確認するにとどまりました。
南シナ海の現代の鄭和は相当にこわもてです。
****中国:武装艦で威嚇「拿捕の漁船解放せよ」 一触即発の海*****
青く、穏やかな南シナ海に緊張が走った。6月23日、インドネシア領ナトゥナ諸島のラウト島から北西57カイリ(約105キロ)。現場海域からの立ち退きを命じるインドネシア海軍艦船に対し、(軍艦を改造した)中国の白い大型漁業監視船が、「拿捕(だほ)した中国漁船を解放しなければ攻撃する」と警告。大口径の機銃が銃口を向け、インドネシア海軍艦も応戦準備に入った--。
「洋上対決」は前日、同じ海域で10隻以上の中国漁船団が操業したのが発端だ。インドネシア警備艇がうち1隻を拿捕した。「排他的経済水域(EEZ)内であり、他国は勝手に操業できない」(当局者)ためだ。だが約30分後、2隻の白い中国の漁業監視船が現れ、「インドネシアのEEZとは認めていない」と無線で主張し、解放を要求してきた。(中略)
警備艇はいったん、漁船を放したが翌朝、応援のインドネシア海軍艦船の到着を待って再び拿捕した。だが中国側は、海軍艦の登場にもひるまなかった。ファイバー製の警備艇は被弾すればひとたまりもない。やむなく漁船を解放したという。中国監視船は5月15日にも拿捕漁船を解放させていた。「武装護衛艦付きの違法操業はこれが初めて」(インドネシア政府当局者)だった。(後略)【7月26日 毎日】
毎日新聞 2010年7月26日 23時41分(最終更新 7月26日 23時49分)
*****************************
【激しさを増す米中の海上覇権争い】
ARFでは、クリントン米国務長官が冒頭発言の3分の1を「南シナ海問題」の説明に充て、(1)南シナ海の「航行の自由」が米国の国益(2)領有権問題の外交解決(3)武力行使や威嚇に反対--を主張。
これに対し中国外務省は25日、「中国を攻撃するものだ」、「(東南アジア諸国を)脅迫している」と、反ばくする楊外相の談話を発表しています。
単に中国と東南アジア各国の間の問題ではなく、中国とアメリカの海上覇権をめぐる争いの様相も呈しています。
****転換期の安保2010:海をゆく巨龍 大国間、揺れるフィリピン*****
南シナ海の領有権を巡り、東南アジア諸国は中国と衝突してきた。うちフィリピンは、同盟国・米国と新たな地域大国・中国の板ばさみとなった。冷戦時代にアジア最大の米海軍基地を抱え、後に撤退させた事情もあり、東南アジアでもとりわけ2大国のはざまでジレンマに悩んでいる。
「すみやかな艦船の撤去を求める」--。5月、任期満了が迫ったフィリピンのアロヨ政権は中国政府から抗議文を受けた。「艦船」とは、南沙諸島の浅瀬に座礁した元米海軍の戦車揚陸艦だ。約10キロ先で中国に占拠されたミスチーフ環礁を監視する前線基地として使ってきた。
フィリピン国防大のロンメル元教授によると、同環礁の中国軍施設は3階建てビルやヘリ発着所、運動場を持ち、南沙諸島にある中国軍の拠点7カ所で最大。フィリピン海軍幹部は「中国の(撤去)主張に我々は抗議できない」と弱気だ。(中略)
中国は、アキノ新大統領が就任して3日後の7月2日、南沙諸島で軍事訓練を行った。フィリピン・デラサール大のデカストロ教授(国際関係論)は、「米国の同盟国がどう反応するか試している」と話す。アキノ政権は演習についてコメントしていない。
中国は南シナ海問題への米国の介入や、実施中の米韓合同演習などを通じた中国周辺への米国の影響力伸長に警戒感を強めている。米中外相同士による非難合戦は、南シナ海を舞台にした両大国の覇権争いを印象付けた。【7月27日 毎日】
****************************
日本もこうした流れのなかで対応をみせています。
“自衛隊もこれまでの枠組みを広げ、外洋に出ている。海自は今年、米ハワイ沖で行われている「環太平洋合同演習」(リムパック2010)で、軍事行動以外の海賊対処訓練などに限り、各国海軍の合同部隊による多国間訓練にも初参加。歴代政府が「集団的自衛権」にかかわるとして80年代から一貫して避けてきた「封印」を解くためのステップをひとつ上った。”【7月29日 毎日】