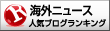(写真はセネガルの聖地トゥーバ マラブーとその信者(多分・・・)
“flickr”より By restoux)
セネガルはサハラ砂漠西南端に位置し大西洋に面する西アフリカの国。
旧フランス植民地で、首都は“パリ・ダカール・ラリー”の終着点として知られているダカールです。
ダカールはかつて、大西洋を渡って送られる奴隷貿易における世界最大の“積出港”でした。
昨日の報道でセネガルに関する以下のようなニュースを見ました。

バイオ燃料の熱心な推進者のひとりであるセネガルのアブドゥラエ・ワッド大統領は、世界でも代表的なバイオエタノール供給国である外遊先のブラジルで、「バイオ燃料がアフリカに“新しい革命”を起こそうとしている」「アフリカ大陸はバイオ燃料の巨大な生産地となる」と語ったそうです。
セネガルではバイオディーゼル生産に向けた菜種栽培の実験を開始し、また、国内の製糖企業1社がバイオエタノール抽出のための蒸留を行っています。
更に、ワッド大統領はバイオ燃料と再生可能エネルギーに関する政策に特化した省を新設。
同国は石油を産出せず、発電の大半をディーゼルに依存していることから、バイオ燃料の生産開始を強く望んでいると言われています。
このような動きに対し、仏語系の西アフリカ諸国8か国による西アフリカ経済通貨同盟は「バイオ燃料は石油を補完するものにすぎず、エネルギー問題の解決策にならない。」「バイオ燃料では大量生産として必要な生産量に達するのは不可能」と警告を出したそうです。
また国連食糧農業機関も批判的で、「バイオ燃料の生産拡大により、アフリカがすでに直面している食糧不足に拍車をかける事態に陥りかねない」と危機感を示しているそうです。
(以上、2007年07月30日 21:40 AFP 発信地:ダカール/セネガル)
西アフリカ経済通貨同盟の警告の背後に何か地域事情があるのかどうかはわかりません。
国連食糧農業機関の危機感は食糧不足のアフリカにあって、もっともと思えます。
セネガルはイスラム教徒が大部分を占める国ですが、特にイスラム教スーフィズムの流れを汲むムリッド教団が急速に拡大しており、人口1000万人のこの国で信者は300万人を超えると言われています。
また、ワッド大統領自身がムリッドの熱心な信者です。
以下、「アフリカ21世紀」(NHK「アフリカ」プロジェクト)より、ムリッド教団について紹介します。
スーフィズムはイスラムスンニ派の系統に属する神秘主義的なイスラム哲学で、厳しい修行と禁欲を重視し、ひたすらクルクルまわる回旋舞踏による神との一体化などの特徴があります。ギリシャ哲学やヒンドゥー教的な異端の要素も含んでいるそうです。
その中でもムリッド教団は19世紀末、教祖バンバによりセネガルで広められた教えです。
1895年フランス軍に捕らえられ流刑される際、船上で祈ることを禁じられたバンバは、海上に敷物を投げその上で1日5回の礼拝をしたそうです。
この奇跡がムリッド教団の原点ともなっており、今も人々の信仰を集めているそうです。
大勢いる開祖バンバの血縁者達が“マラブー”と呼ばれる“奇跡の血”を受け継ぐ宗教的な指導者として崇拝されており、信者はおのおの自分のマラブーを決めて付き従います。
ムリッドの特徴は、「働くことは祈ること」というその教義です。
バンバは「労働は祈りのひとつの形である。私のために働きなさい。そうすれば私があなた方に代わって祈ってあげましょう。」と語ったそうです。
農民達に暴力による抵抗を禁じ、「働き祈る心の中までフランス植民地主義は入ってこられない」とひたすら働くことを説いたバンバは、フランスにとっても利用価値があり、後年両者は協調路線をとるようになりました。
フランス植民地政府はムリッド教団に土地を与え、そこでフランスが持ち込んだ落花生をムリッド信者が生産、フランスの建てた加工場で食用油を絞るという関係です。
セネガル独立後も、政府と教団のこのような協調関係は引き継がれたそうです。
信者30万人ぐらいが暮らす教団の本拠地トゥーパは、政府のコントロールから独立した、教義に基づく独自の運営がなされているそうです。
住民サービス、水や土地などの供給を国家に代わって教団が無料で行います。
これに対し信者は献金を行います。
「自分ができるときできる分だけを教団に寄付し、困ったときは生きるのに必要なものを無償で教団が提供する」という、法律や罰則によらない“相互扶助”の精神で成り立つ関係、「権利と義務」とか社会契約という概念とは異なる関係が存在しているそうです。
また、そこには公立学校はなく、子供の教育はコーラン学校で行われます。
通いのコーラン学校では卒業生などが子供達の両親から食事の寄付を受けて、コーランを教えます。
マラブーが運営する寄宿制のコーラン学校もあります。
公立学校が一応存在するトゥーパ以外の街でも、コーラン学校がさかんだそうです。
西洋式の公立学校では膨大な子供数に対応できないそうです。
(不十分な公教育から溢れた貧しい人達がイスラム宗教学校に流れる構図は、「赤いモスク事件」で揺れたパキスタンでも見られました。
マラブーの寄宿制コーラン学校では大勢の子供達が、中庭の砂の上で折り重なるように寝起きするような環境で暮しています。
子供達はコーランを朗読するほか、街へ出て食べ物・お金の施しを集めます。
集められた食材・お金はマラブーに届けられ、マラブーの妻が料理をつくり子供達に与えます。
また、子供達は交代でマラブーの落花生農場で働きます。
「働くことは祈ること」ですから、皆熱心にはたらきます。炎天下でも夜でも。
子供達は卒業後もマラブーの農場ではたらき、畑を広げます。やがて独立を許され、土地を分け与えられます。
やがて子供が生まれると、マラブーの学校に預けて・・・。
このようなムリッドのマラブーと子供達の関係は西欧的には奇異に思える部分があります。
個人的にも、新興宗教をイメージさせるものがありますし、結局バンバの血縁者であるマラブーと呼ばれる特権集団に奉仕しているだけのようにも見えます。
ただ、それが信仰なんだと言われればそうなのでしょうが・・・。
ユニセフは報告書の中で「宗教学校は資金不足で子供達を長時間路上に送り出し、食事とお金を物乞いするよう強制している。」「子供がその生活条件を受け入れ、抵抗しないように教え込まれている点で、強制労働である。」と批判しています。
ユニセフの批判も頑なに西洋的な感じはします。
ムリッドからすれば、物乞いではなく一種の托鉢でしょうし、労働は宗教的行為ということになります。
ただ、視野が宗教的な面に限定され、現状に無批判な人間が宗教学校で育てられる点には危惧の念を感じます。(どこの社会でも同じじゃないか・・・と言われればそうですが。)
宗教の外にいる人間には、判断しかねるものがあります。
このムリッド教団が急速に拡大したのは、教団を中心とした相互扶助システムが実際に干ばつによる飢饉のときに、“都市部に出ていた信者が献金する、農村の親は子供をコーラン学校に預けて都市に出て援助物資をもらう”といった形で、信者達の命を支えるべく有効に機能したことがあります。
現在は、ムリッド信者の相互扶助ネットワークはセネガル経済を左右するほど大きくなっており、更に海外に出稼ぎに出る信者によって、海外にもネットワークが広がっているそうです。
最初の話題に戻ると、熱心なムリッド信者でもあるワッド大統領は恐らく菜種栽培・バイオエタノール生産を、ムリッド教団の農場に持ち込もうと考えているのではないでしょうか。
経済の発展にとって、その社会を構成する人々の“勤勉精神”が非常に重要であることは言うまでもありません。
先ほども述べたように、外の人間には若干奇異に思える部分はありますが、ムリッドという宗教に支えられた「働くことは祈ること」という勤勉精神がセネガル経済を豊かにしてくれるのであれば、そしてその相互扶助システムが社会のセーフティーネットとして機能し、社会を安定化させるのであれば、それはそれでいいのかな・・・と思います。
もちろん、教団以外の国民の権利が十分に守られていることが前提ですが。
ワッド大統領は次のように発言しています。
「ムリッドにとって仕事は神に到達する方法です。西洋人は金を稼ぐために、家族を養うために働きますが、ムリッドが働くのはそれが神の啓示だからです。働けば働くほど天国への道に近づく。働くために働かねばならないのです。だから、ムリッドはエネルギーと動員力のある宗教なのです。」