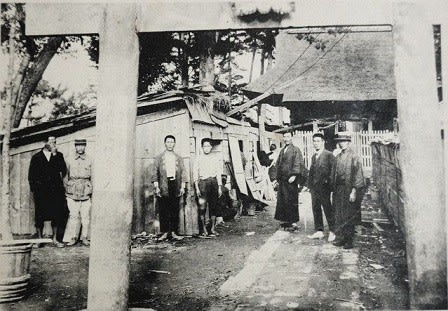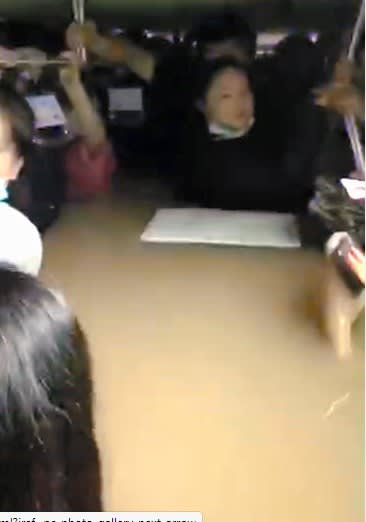(【8月28日 BBC】)
【国土の3分の1が冠水】
8月末から報じられているパキスタンの洪水は甚大な被害をもたらしています。
****パキスタン、洪水で国土の3分の1冠水 死者1100人超・人口の15%被災****
パキスタンのレーマン気候変動相は、モンスーン期の豪雨と大規模な洪水によって、国土の3分の1が冠水したと明らかにした。死者はこれまでに1100人を超え、シャリフ首相によると、子ども380人が含まれる。
6─8月の降雨量は30年間平均を約190%上回り、全人口の15%に当たる3300万人が被災した。
国連は「前例のない気候の大惨事」とし、グテレス事務総長はビデオメッセージで1億6000万ドルの支援を各国に呼びかけた。報道官によると、グテレス事務総長は来週被災地を訪問するという。【8月31日 ロイター】
******************
国土の3分の1が冠水・・・・俄かには信じがたい数字です。
日本で言えば、北海道と九州の全域が冠水したような数字で、ほとんど「日本沈没」クラスの災害です。
人的被害の1100人(続報では1290人とも)は、災害規模を考慮すれば、よくぞそのレベルにとどまっているという感も。
経済的被害は・・・想像できません。
****パキスタン洪水、雨量は平年の10倍 インダス川が「湖」に****
パキスタンで深刻な被害をもたらしている洪水について、欧州宇宙機関は1日、平年の10倍の降雨量が原因となったとの見解を示すとともに、インダス川の氾濫によって生じた広大な「湖」の衛星画像を公開した。
同国では、6月から続くモンスーン(雨期)の豪雨が引き起こした洪水で、これまでに少なくとも1190人が死亡。広範囲の農地が水没し、家屋100万戸以上が損壊した。
ESAは、救助活動を支援するため、地球環境モニタリング計画「コペルニクス」の衛星データを使用して宇宙から洪水の規模を測定したと発表。6月中旬以降の降雨量は「通常の10倍」であり、これが国土の3分の1を水没させる洪水を引き起こしたと説明した。
ESAはさらに、南部ラルカナとデラムラードジャマリの間で、氾濫したインダス川が「幅数十キロの長い湖を事実上形成」している地域の衛星写真を公開した。
パキスタン当局によると、同国の7人に1人に当たる3300万人以上が被災しており、復興には100億ドル(約1兆4000億円)以上を要する見通し。
国連のアントニオ・グテレス事務総長は「気候大災害」だとして、1億6000万ドル(約224億円)の緊急支援を各国に呼び掛けている。 【9月2日 AFP】AFPBB News
****************
パキスタンのレーマン気候変動担当大臣は「モンスーンは毎年来るが、こんな“怪物”は見たことない」と。
また、同氏は北部の氷河が解けているとする専門家の見解に言及し、洪水の主な原因は「気候変動だ」とも述べています。
【気候変動との関連】
そのたりの気候変動との関連について、気象予報士の千種ゆり子氏は以下のようにも。
****【解説】パキスタンの洪水被害。地球温暖化の影響は?2つのポイントから分析****
(中略)
1300人近くが亡くなったとされるパキスタンの洪水被害は、過去最悪と言われた2010年の洪水に迫る被害となってきています。パキスタンのシェリー・レーマン気候変動相によれば、国土の1/3が冠水したといいます。
地球温暖化が進むと極端な気象が増えると言われている中で、今回のパキスタンの洪水と地球温暖化はどのように関係しているのでしょうか。ポイントとなる降水量や、春先の熱波による氷河の融解から考えます。
一年で降る雨がわずか一日で…
まずは、降水量を見てみましょう。
被害の大きかった地区の一つ、シンド州の都市ナワーブシャー。年間の降水量は約150mmですが、今年の8月24日には、たった一日で222mmの雨が降りました。
平年であれば一年で降る量の雨が、わずか一日で降ってしまったことになります。18日、25日にも似たような大雨が降っていたのですから、レーマン気候変動相が「モンスターモンスーン」と表現していたのも頷けます。
パキスタンは「水不足」が深刻な社会問題になることもある、雨の少ない国です。大雨に慣れていない土地柄であるために、被害が拡大したと思われます。
温暖化の影響は?2つのポイントから分析
今回の洪水被害に関して、地球温暖化による影響は、いくつかに分けて論じることができます。
1.地球温暖化が、今回の降水量に与えた影響。
2.地球温暖化が、氷河の融解に与えた影響。
1.大雨そのものに地球温暖化が与えた影響
現在地球は、産業革命前に比べて、約1℃気温が上昇しています。気温が1℃上がると空気が含むことが出来る水蒸気量は7%増えます。
今回の場合は水蒸気量がどれくらい増えていたのか、詳しい分析は研究者による解析を待つ必要がありますが、日本を対象にした研究では、1℃気温が上昇した時の水蒸気量の増加率は、7%をはるかに上回り、11~14%にものぼることがわかっています。
一般的には、空気中の水蒸気量が多くなると、積乱雲がより発達しやすくなり、雨が降る所ではより顕著な大雨になりやすい傾向が存在していて、これは「Wet-gets-wetter,dry-gets-drier」メカニズムとして広く受け入れられています。
雨のもととなる水蒸気量が増えているわけですから、地球温暖化の影響を受けて多少なりとも降水量が増えている可能性は高いと思います。
2.氷河の融解に地球温暖化が与えた影響
今回の洪水について、パキスタンのレーマン気候変動相は「4~5月の熱波で氷河が融解しインダス川の水量が多くなっていた所に大雨が降ったため洪水の被害が拡大した」と、専門家の見解を引用しながら述べています。
パキスタンに貴重な水資源を供給しているのが、パキスタンの北にあるカラコルム山脈やヒマラヤ山脈の積雪・氷河です。
実際にインダス川の流量がどれだけ増えていたかはわかりませんが、4~5月にパキスタンが異常高温だったことは確かで、パキスタンの月平均気温は、4月としては1961年以降で最も高かったと報告されています(パキスタン気象局)。
世界気象機関は、今年の春先の熱波についても、地球温暖化の影響で、1℃分の底上げ効果があったとの発表をしています。
ヒマラヤやカラコルム山脈をはじめとするアジアの氷河の融解がすでに進んでいることは、IPCCによって2019年に発表された海洋・雪氷圏特別報告書でも「確信度が非常に高い」と結論づけられています。
地球温暖化の影響で、インダス川の流量が増えていた可能性は高いと思います。
気象災害とSDGsを繋げて考えてみよう
被害をさらに大きくする要因が「貧困」です。
地球温暖化が進むと気象現象が極端になると言われますが、気象災害はどうしても、貧しい人が一番被害を受けやすくなる傾向にあります。
インフラの整備で防げる被害も、貧しければ防げません。被害を受けた後の復興にも時間がかかります。気象災害によって職を失い、さらに貧困が加速する、という負の循環もあります。
パキスタンのシャバズ・シャリフ首相はパキスタンが出している二酸化炭素は全体の1%以下だとTwitterで述べています。つまり、ほとんど温室効果ガスを出していないのに、地球温暖化によって激甚化した災害の被害を受けてしまったのだ、不公平である、ということで、「気候正義」という概念を念頭に発言したものと思われます。
地球の気温は産業革命前に比べて約1.1℃上昇しており、この上昇のほとんどが、人間活動による温室効果ガスの影響であることに疑う余地がないということは、すでにIPCCで報告されています。この温室効果ガスの多くを排出したのは、先進国です。これまで豊かさを享受した先進国は、その責任を果たすべきだ、という考え方が、気候正義です。
「持続可能な開発目標」、いわゆるSDGsでは17の項目があげられていますが、項目1であげられている「貧困をなくそう」は、気候変動による被害を小さくすることにも繋がります。今回の洪水で被害を受けたパキスタンの方々が一日も早く平穏な暮らしを取り戻せるように、日本からは何ができるのか、SDGsの視点も含めて、考えるべきです。
もちろん、今回の洪水被害に対して募金をする、というのも1つの選択肢。カーボンニュートラルを一刻も早く実現するために行動することは、今後の被害を減らすという観点での、1つの選択肢になると思います。【9月6日 気象予報士・千種ゆり子氏 HUFFPOST】
********************
【貧困者にとりわけ重い負担】
災害の犠牲者の悲しみ・痛みは、パキスタンでも日本でも、また、洪水でも地震・台風でも同じです痛ましいものがあります。
上記記事にもあるように、その悲しみは貧困者に襲い掛かります。
****パキスタン、洪水で1290人死亡 「国土の3分の1」が浸水****
(中略)
被害が大きかった地域の一つの北西部カイバル・パクトゥンクワ州のカブール川近くの集落を毎日新聞助手が9月2日に訪ねた。多くの家屋が損傷し、水圧によって壁にヒビが入った家も多く見られた。
住民によると、8月末に近くの川のダムが決壊し、決壊から約1週間がたった今も一部の家や集落を通る道は冠水したままだという。住民のアルシャドさん(35)は「夜、寝ているうちに川が決壊して水が家の中まで入ってきた。避難して自分の命は助かったが、家財道具はすべて失ってしまった」と途方に暮れていた。
パキスタンでは、かねて食料品などの物価上昇が深刻で、洪水被害は庶民の生活苦に追い打ちをかけている。
政府が用意した避難所に身を寄せるタジーム・ビビさん(36)は「借金をして2カ月前に牛を買って牛乳を売って生活していたのに、牛は洪水で流され、家も損壊した。どうやって家を修理しろと言うのでしょうか」と訴えた。
同じく避難中のディルシャド・ベグムさん(70)も「私たちは貧しく、家を建て直すお金はありません。政府に被害を補償してほしい」と語った。
パキスタン災害当局によると、6月中旬以降に住宅約146万軒が全壊または部分的に損傷した。また、国連人道問題調整事務所は、5000キロ以上の道路と243の橋が被害を受けたとしている。
国連のグテレス事務総長は9月9日にパキスタンの首都イスラマバードに到着した後、被災地を訪ねる予定で、ビデオメッセージで「(現地の)ニーズの規模は洪水のように拡大している」と支援を呼びかけた。【9月4日 毎日】
****************
****コツコツためた持参金が洪水で駄目に…結婚も中止 パキスタン****
パキスタンのトラック運転手で、7人の子どもがいるムリード・フセインさんは、10月に娘を結婚させようとしていた。しかし、自宅が洪水の被害に遭い、後ろ側の壁だけではなくコツコツ貯めた娘のための持参金「ダウリ」も流されてしまった。
フセインさんは、4部屋の家に兄弟家族と住んでいる。「娘の持参金は3年近くかけて準備していた」とAFPに語った。
パキスタンでは6月以降、記録的なモンスーン(雨期)による洪水が全土で発生。これまでに1200人以上が亡くなった。国土のほぼ3分の1が水に漬かり、3300万人の生活に影響が出ている。
最も影響を受けているのは農村部の貧困層だ。家屋や所持品、これまでにためてきた資産、穀物が押し流された。
フセインさんが住むパンジャブ州の村もひどい状況になっている。洪水により倒壊したり、破損したりした建物も多い。
フセインさんの娘ノウシーンさんの結婚も流れてしまった。
フセインさんは、トラック運転手として稼ぐ月収1万7000パキスタン・ルピー(約1万1000円)から、毎月数千ルピーを娘のダウリー用にためていた。
家父長制のパキスタンでは、娘が結婚する際に多大な持参金を持たせる習慣がある。多くの地域で、親は娘が生まれたその日から持参金をためることになっている。多額の持参金を要求することは法律で禁止されているものの、未だこの習慣を行っている人は多い。
新郎の家族は将来の花嫁の家を頻繁に訪れ、家具や家電、衣料品などほしいものが書かれた膨大なリストを渡す。裕福な家庭は、自動車や住宅を要求することさえある。
リストに上げられたものを用意できないことは恥だとされ、十分な持参金を渡せない場合には、娘が義理の家族からひどい扱いを受けることも多い。
フセインさんは「ノウシーンの後に、娘2人と残っている息子1人を結婚させたかった」と語った。「少しずつためればできると思っていた」
自宅が洪水になると、フセインさんは、妻と子どもたちと一緒に、高台にある近所の駅に避難した。
一家は2日前、泥をかき分けながら自宅に戻った。家のひどいありさまを見て、妻と娘は泣き出したという。
フセインさんの妻スグラ・ビービーさんは、家の状態と娘の持参金のことを思うと涙が出てくる。
長い年月をかけて特注のベッドセット、鏡台、ジューサー、洗濯機、アイロン、シーツ、キルトなどを買い集めてきた。しかし、すべてが洪水で駄目になってしまった。
「汚れてしまった。これを見たらみんな、私たちが娘に中古品を持たせたと思うだろう」とスグラさん。
結婚は中止になったが、ノウシーンさんは気丈に振る舞っている。
「家族にとって幸せな時となるはずだった、私もとても楽しみにしていた」とノウシーンさんはAFPに語った。
「私のために持参金をためるのがどんなに大変だったか、両親の苦労を目にしてきた。父と母はこれを一からやり直さなければならないなんて」
フセインさんは「自宅を再建すべきか、小麦をまくべきか、子どもたちを結婚させるべきか? 私たちにとっては、どれもとても重要なことだ」と述べた。 【9月12日 毎日】
******************
【国連事務総長「明日はあなたの国かもしれない」】
洪水自体の復旧には長い時間が必要とされるようです。その後の被災者の生活再建となると・・・
****冠水解消まで半年も パキスタン洪水で州首相****
大雨による洪水の被害が深刻化しているパキスタン南部シンド州のアリシャー州首相は、被災地で冠水が解消するまでに「3カ月から半年かかる」との見方を示した。地元メディアが13日までに報じた。
シンド州では、国内最大級のマンチャール湖の氾濫で近くの人口密集地が洪水に遭うのを避けようと、当局が堤防を一部破壊して人口が少ない地域に水を流した。このため周辺の村で新たに冠水が広がっている。
アリシャー氏は、冠水が深さ3メートルに及ぶ場所もあると指摘。「水が引いている場所でも、住民が戻れる状況ではない」と説明した。排水設備の整備を急いでいるという。【9月13日 共同】
*********************
各記事にもあるように国連も支援に動いています。
****パキスタン洪水、国連総長が国際支援呼びかけ 「世界的危機」****
国連のグテレス事務総長は10日、大規模な洪水被害に見舞われたパキスタンの被災地を視察し、国際社会に資金援助の強化を呼びかけた。
モンスーンによる豪雨や北部山岳地帯の氷河溶解を受けた今回の洪水では1391人以上が死亡、住宅や道路、橋、家畜などが流され、パキスタンは被害額を300億ドルと試算している。
グテレス氏は記者会見で「きょうはパキスタンだが、明日はあなたの国かもしれない。これは世界的な危機であり、世界的な対応が必要だ」と述べた。
また「世界中で多くの災害を見てきたが、これほどの気候被害は目にしたことがない」とし、国際社会は気候変動の影響が最も深刻な国々への支援を強化する必要があると訴えた。
具体的には、復興や気候変動への適応を支援する資金提供に加え、20カ国・地域(G20)各国は自国の排出削減目標を毎年引き上げるべきだと指摘。
また、パキスタンのように気候変動の影響を受けやすい国に対する新たな債務救済の仕組みが必要だとし、債務国が対外債務の返済を続ける代わりに自国の気候プロジェクトに資金を振り向ける債務交換を提案した。【9月12日 ロイター】
*********************
こうした災害を教訓として、今まで以上の取り組みが・・・ということであれば、唯一の救いにもなりますが、残念ながらそうしたこともないようです。
今後、現地では感染症拡大の心配もありますし、食料品価格高騰は必至でしょう。
貧しい国が裕福な国の工業化の影響を受けて気候変動災害に苦しむことについて“ラホール経営科学大学の社会学教授であるニダ・キルマニ氏は、「洪水に関するいかなる救済も『援助』としてではなく、過去数世紀にわたって蓄積された不正に対する賠償としてとらえられるべきである」と述べている”【8月31日 東洋経済ONLINE】