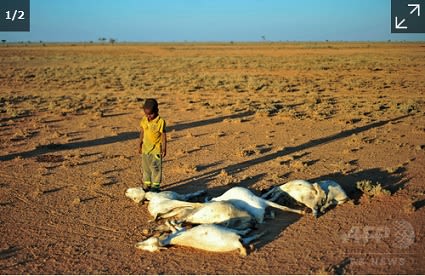(軍用装備品店「ミリタリスト」で、同店オリジナルのウクライナ製戦闘ベスト(左)とイギリス製のものを見せる店長のアレクサンドルさん【1月6日 朝日】)
【昨年末から戦闘激化】
ウクライナ東部における政府軍と親ロシア派と戦闘は、2015年2月にベラルーシのミンスクで、ウクライナのポロシェンコ大統領、ロシアのプーチン大統領、ドイツのメルケル首相、フランスのオランド大統領の間で「ミンスク合意」が調印され、一応は停戦状態にはありますが、完全に戦闘が止んだ訳でもなく、ときおり戦闘が激化することがあります。
昨年夏にも戦闘が再燃し、2016年8月4日ブログ“ウクライナ東部 戦闘・犠牲者が増加 欧米・ロシアも停戦合意順守を求めているものの・・・”http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20160804でも取り上げました。
その後はしばらく落ち着いていましたが、昨年12月中旬から、また戦闘が激しくなっているようです。
****ウクライナ東部で戦闘激化、政府軍と親ロシア派****
ウクライナ東部で1月29日から30日にかけて政府軍と親ロシア派の間で戦闘が起き、これまでに兵士計7人が死亡した。
ウクライナでは2014年、分離独立を目指す親ロシア派とこれを阻止しようとする政府軍が正面から衝突、ウクライナ内戦が発生した。
内戦は2015年、ドイツなどの仲介でミンスク和平合意が成立。停戦が続いていたが、昨年12月中旬に戦闘が再開され、年を越して激化の様相を呈していた。
事態を重く見たウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は30日、ベルリンでアンゲラ・メルケル独首相と会談した。【1月31日 ロイター】
******************
****東部で戦闘、兵士7人死亡=ウクライナ****
ウクライナ東部で29日から30日にかけ、政府軍と親ロシア派の戦闘が起き、政府軍によると、これまでに兵士計7人が死亡した。一方、親ロ派のメディアは30日、政府軍の攻撃で市民2人が死亡したと伝えた。
ドネツク州アウデエフカで激しい戦闘が起きているもようだ。政府軍は30日、フェイスブックに「アウデエフカ周辺は緊迫している。敵は30日朝も迫撃砲などで攻撃を続けていた」と書き込んだ。
一方、親ロ派のメディアは、政府軍が停戦合意に違反して攻撃していると非難した。【1月31日 時事】
********************
互いに相手の停戦合意違反を非難するのはシリアなどと同様で、どちらに責任があるのかは定かではありません。
【一方で親ロシア派支配地域との“密売”も】
上記のようにウクライナ東部では戦闘が断続的に続いていますが、親ロシア派とウクライナ側の間の“密売”も行われているようです。
****ウクライナ政府支持派、親ロシア派支配地域への線路を封鎖****
ウクライナで27日、政府を支持する活動家らが、ウクライナ東部の分離独立を求める親ロシア派との交易に抗議し、親ロシア派支配地域に通じる線路を封鎖した。政府支持派の報道担当者が明らかにした。
同報道担当者によると、元政府側民兵数十人と議員らが、親ロシア派が支配する東部ルガンスク州に通じる主要な線路を封鎖した。数日内に道路も封鎖する計画だという。
2014年に東部ドンバス地方で政府軍と親ロシア派の戦闘が始まって以来、双方で合わせて1万人近くが命を落としている。昨年12月末に「無期限」の停戦が宣言されたが戦闘は完全には収まっていない。
ウクライナ政府は2015年に親ロシア派支配地域との交易をほぼ全面的に禁止したが密売が横行。同地域からの石炭の購入だけは合法とした。
ルガンスク州知事によると、政府支持派は石炭をウクライナ政府支配地域に運ぶ予定だった列車を止めたという。
同知事は、冬の盛りにこのような行動を取ることは「この国のエネルギー安全保障をおびやかす」「燃料供給が再開されなければ、ウクライナ中部と西部の火力発電所の燃料が切れるだろう」と警鐘を鳴らした。【1月28日 AFP】
******************
ウクライナの腐敗・汚職の深刻さはかねてより指摘されているところですから、親ロシア派支配地域との間の“密売”が横行しているというの想像に難くないところです。
ただ、列車を止めた“元政府側民兵数十人と議員”というのも、単なる“義憤”ではなく、おそらくなんらかの政治的思惑があってのことではないかとも推測されます。
ウクライナの政治情勢については、親ロシア派が分離し、結果的に親欧米派でまとまりやすくなったことや、戦闘によって求心力も高まったことで“以前と比べて大きな落ち着きを見せている”との評価もあるようです。【1月10日「ウクライナなう!」http://ukrainenow.net/ukraine-politics/ より】
“以前と比べて”というのは、“オレンジ革命”の時期や、ヤヌコビッチ大統領が亡命を余儀なくされたような激しい対立があった時期に比べれば・・・・の話でしょう。ポロシェンコ政権が順調に統治を進めている・・・という話は聞きません。ジョージア(グルジア)前大統領で、ウクライナ南部オデッサ州の知事を務めるサーカシビリ氏が腐敗・汚職の蔓延を理由に辞意を表明するなどの混乱の話なら聞きますが・・・・。
「ウクライナなう!」も、“以前と比べて大きな落ち着きを見せています”としつつも、“しかしながら、現在行われている様々な改革がうまくいかず、経済の低迷が続いたり、EUやNATOへの加盟プロセスが滞ったとすると、再び国内に混乱が生まれる恐れがあります。”とも。
【EUにはウクライナ支援への倦怠感も】
そのEU加盟について停滞感が強まっていることは、昨年8月4日ブログでも取り上げたところです。
****ウクライナのEU統合、英離脱で暗雲 域内に倦怠感 「遠心力」抑えるのに手一杯****
英国が国民投票で欧州連合(EU)からの離脱を決めたあおりを受け、ウクライナのポロシェンコ政権が旗印としてきたEUとの統合路線に暗雲が立ちこめてきた。
EU内にウクライナを支援することへの倦(けん)怠(たい)感が出ていたのに加え、EUが今や内部の「遠心力」を抑えるのに手一杯のためだ。
EUのウクライナに対するビザ(査証)廃止の見通しは遠のき、ウクライナ国民自身にもEU統合路線への失望が芽生えつつある。
ウクライナ政界では英国の投票を受け、最高会議(議会)の欧州統合問題副委員長が「展望のなさ」を理由に職を辞するなど、波紋が広がった。ポロシェンコ政権にとって英国の離脱決定は、オランダの国民投票で4月、EUとウクライナの自由貿易を柱とする「連合協定」の批准に「ノー」が突きつけられたのに続く打撃となった。
英国の投票後、EU首脳会議に合わせて行われたポロシェンコ大統領とEU首脳の会合は成果に乏しく、「象徴的成果」になると期待されていたビザ廃止に関する合意も見送られた。
ウクライナの政治学者、スピリドノフ氏は「貧しいウクライナを統合すれば、(労働移民の問題などで)EUの社会状況がさらに悪化する。ただでさえEU統合路線は幻想的だったが、英国の投票後は、EUの役人がいっそうウクライナを警戒している」と話す。
ウクライナで2014年、大規模デモによる親露派政権の崩壊を受けて発足したポロシェンコ政権にとって、EU統合路線は最大の公約であり、よりどころだった。EUも、ウクライナ東部に軍事介入したロシアに経済制裁を発動し、ポロシェンコ政権を後押しした。
しかし、EUでは、ウクライナ東部紛争をめぐる15年2月の和平合意が履行されないことへのいらだちが出ている。ロシア側もさることながら、ウクライナが合意に盛られた改憲などを実行していないことに厳しい視線が向けられつつある。
ウクライナの国内総生産(GDP)は14年の前年比6・6%減に続いて15年も同9・9%減で、EUとの連合協定の恩恵は見えてこない。
前出のスピリドノフ氏は「国民は欧州統合の話題に疲れている」とし、一部の親欧派政党が方向転換を図る可能性があると語る。東部紛争の政権側元義勇兵など、民族派勢力が力を増している現状もある。【2016年7月11日 産経】
*****************
オランダの国民投票で昨年4月、EUとウクライナの自由貿易を柱とする「連合協定」の批准が否決されたことを受けて、EUはウクライナに対する財政的・軍事的防衛義務を負わないことを明確化することで合意しています。
【厳しい財政・経済状況 兵士の装備も自前や支援者寄付で】
ウクライナ経済に関しては、下記のようなニュースも。
****ウクライナ、最大手銀行を国有化 不良債権問題の拡大回避****
ウクライナ政府は17日、深刻な不良債権問題が取り沙汰されていた同国最大の銀行プリバトバンクを国有化すると発表した。問題が広がって金融システムが崩壊するのを回避する狙いだ。(中略)
国際通貨基金(IMF)はウクライナに対して、持続的な成長のために不透明な金融部門の整理と安定化を求めており、今回の措置はそれに合致したものとなった。
プリバトバンクは政治的に強い影響力を持つ富豪のイーゴリ・コロモイスキー氏が保有。ペトロ・ポロシェンコ大統領は汚職との闘いで同氏を早い段階から標的としていた。【12月19日 AFP】
******************
ウクライナ財政が破たん寸前状態にあることは以前も取り上げたことがありますが、上記のような最大手銀行(ウクライナの預金残高の3分の1を保有)国有化が話題になるところを見ると、相変わらずの“綱渡り”状態にあるように思えます。政治絡みの面もあるようにも。
そんなウクライナ政府には親ロシア派との戦闘を維持する資金的余裕もなく、政府軍兵士の装備や医薬品は“自己負担”あるいは“支援組織からの寄付”で調達する・・・という状況のようです。
****前線部隊、装備買わないと ウクライナ****
2014年に始まったウクライナと親ロシア派武装勢力の紛争は、いまも続く忘れられた「戦争」だ。
ウクライナ東部ドネツク州ボルナバハ近郊。ミンスク合意によって戦闘はやんでいるが、ウクライナ陸軍第30機械化旅団はなお、約800メートル先の親ロシア派部隊とにらみ合っている。
前線にある旅団の地下作戦室を訪れた。そこには5人の下士官がいた。気になったのは彼らの足元。バラバラの色のブーツだった。
「俺のはウクライナ製だが、あいつのはカナダ。ほかのやつはドイツかな」
下士官はそういった。さらに部屋の中を見渡すと、5台のパソコンもどれも違うメーカーだった。
「実は、パソコンも、冷蔵庫も、ここにあるのは何でも、民間の支援者や団体に寄付してもらったものばかりなんだよ」
作戦室の隣の医務室に入った。女性看護兵が医薬品の棚を指さし、「7割が民間の寄付。政府からは3割だけ」と冷たく言う。
実戦の真っ最中にもかかわらず、ウクライナ政府は前線部隊に十分な装備や物資を提供できていない。この戦線を支えているのは民間からの支援だった。
*
首都キエフの支援者の一人、カテリナ・ビコレンコバさん(37)は「14年以来、戦闘服、質のいいブーツ、応急医療セット、医薬品などを旅団に提供してきた」と振り返る。支援総額は日本円ですでに300万円以上。
ソーシャルメディアなどを通じて寄付を呼びかけ、街の小売店などから様々な物資を少量ずつ買い、前線の兵士たちの要望に応じて直接届ける。
前線の兵士たちを支援する動きは企業などにも広がっている。
キエフのスーパーマーケットに、軍用装備品チェーン店「ミリタリスト」があった。アレクサンドル店長(26)によると、05年の創業以来、警備員や治安機関員らが主な顧客だった。ところが、14年にロシアがウクライナ南部のクリミア半島を併合すると一変した。
志願兵や支援者らが前線の兵士のために物資を大量に購入し始めた。売り上げは一気に倍増し、その後も高止まりしているという。アレクサンドルさんは「軍から支給される装備は質が悪い」と理由を挙げる。
この需要に目をつけたこのチェーンは衣料を中心に自社生産を開始した。
「これが、自社工場のウクライナ製、隣は英国製」と兵士用ベストを見せてくれた。丁寧な仕立てで品質に違いはなさそうだった。ベスト腹部のポケットに防弾プレートを入れれば、防弾チョッキになる基本機能は同じ。だが、ウクライナ製はメッシュ構造を採用し、夏の猛暑の中でも戦えるよう工夫されている。
■ベンチャー参入、密輸も横行
この「戦争」は、皮肉にも起業を生んでいる。キエフの「愛国者の武器庫」もその一つ。古びた倉庫の扉を開けて中に入ると、ここで製造された防弾チョッキが山積みになっていた。(中略)
仲間とこの事業を本格的に立ち上げたのは、ロシアによるクリミア併合後の14年6月。前年末からヤヌコビッチ大統領打倒の運動を支持するうちに、安価な防弾チョッキが必要だと気づいた。ネットで製造方法を調べ、材料を買い集め、アパートで仲間と製造を始めた。(中略)
ウクライナ東部で戦闘が激化するにつれ需要は増え、現在の倉庫に移転。最盛期には、約20人が1日20時間働いた。装甲車にも使われるスウェーデン製の特殊鋼板を切断し、特殊ゴムなどを貼りつけて防弾プレートを製造。狙撃されたときの衝撃を散らすためのクッション材を中にいれたチョッキを、200ドル超で販売したら即完売した。14年夏には1日に約1千着売れたことも。
「武器庫」前には購入希望者が何時間も並び続け、「毎日100件以上」の問い合わせの電話があった。
電話の主は、東部の戦場に息子を送り出す母親や志願兵ら。政府が招集した6万人から12万人ともいわれる新兵に十分な装備を提供できないことは国民の間ですぐに常識になった。
兵士を支援する団体の関係者は「米国から戦闘服やブーツを輸入するときに、暗視スコープなどの物資を紛れ込ませている」と明かした。暗視スコープは3千ドルから4千ドルはする。これらの物資が正規の税関手続きを経ずに戦場へ大量に流入している。
米ロ対立まで生んだウクライナ危機の前線はこうした闇市のような軍用装備品市場に支えられていた。【1月6日 朝日】
*******************
なんとも興味深い話ではありますが、支援組織からの寄付や、民兵に依存していることは、戦闘に関して政府がコントロールできない状況をも生みます。
【ロシアとの関係改善に前のめりなトランプ政権誕生で】
昨年12月にEUは「ウクライナ東部の停戦合意が依然として順守されていない」として対ロシア制裁を延長、アメリカ・オバマ政権はロシア制裁を強化しました。
ウクライナ情勢の今後については、親ロシア的なトランプ政権の対応が注目されます。ウクライナ・ポロシェンコ政権は、これまでのようにアメリカの支援をあてにできない情勢にもなりつつあります。
トランプ米大統領は就任直前に、ロシアに対する制裁解除と引き換えに、核兵器の削減協定を結ぶ可能性を示唆したことが話題になりました。
そのほかにも、トランプ氏が関与した話ではありませんが、クリミアとコソボの“取引”といった話も出ているとか。
****ロシアはコソボと引き換えにクリミアを獲得するか?****
西側メディアのコラムニストで討論クラブ「ヴァルダイ」のメンバーでもあるメリー・デジェフスキー氏は、ロシアは米国との新たな関係を構築する文脈でコソボの独立を承認することができるはずだと考えている。(中略)
専門家らも「米国はロシアのクリミアを承認し、ロシアはコソボの独立に同意する」というシナリオを議論している。
ロシア戦略研究所所長顧問のイーゴリ・プシェニチニコフ氏は「スプートニク」のインタビューで、ロシアがコソボを承認するのは不可能だと述べ、少なくともプーチン大統領のもとでは不可能だとし、「ロシアにはクリミアがロシアであるために米国の支持は必要ない」と語った。(中略)
クリミアは住民投票の結果、自主的にロシアの一部となった。一方コソボは米国やEUの支援を受けて一方的にセルビアから分離した。【1月26日 SPUTNIK】
*****************
最後の一文は、ロシア側メディアらしい、ロシア側の“建前”です。
まあ、そんなに簡単にはいかないでしょうが、こういう話が出ることは、ロシアとの関係を重視し、“取引”が大好きなトランプ大統領誕生ならでは・・・という感も。