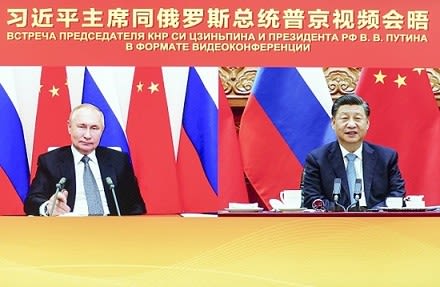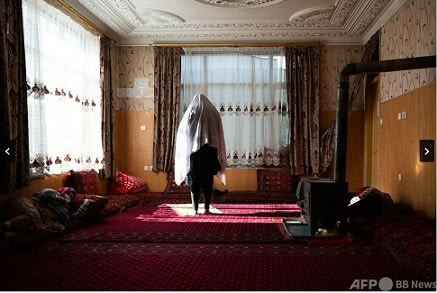(リトアニア首都ビリニュスの台湾代表機関で20日撮影【1月26日 ロイター】)
【小国リトアニアの叛乱に苛立つ中国】
バルト三国のリトアニアが大使館に相当する「台湾代表処」の設置を決めたことを受けて、強烈に反発する中国が外交関係見直しに加え、事実上の貿易制限を行うなど「小国」リトアニアに強い圧力をかけているのは周知のところです。
****中国とリトアニアをめぐる動き****
<2021年7月> リトアニアが「台湾代表処」の設置を許可
<8月> 中国が駐リトアニア大使を召還
<9月> リトアニア外相が訪米、米側は支持表明
<11月> 中国がリトアニアとの外交関係を「代理大使級」に格下げ
<〃> リトアニアなどバルト3国の国会議員団が台湾を訪問
<12月> 中国がリトアニア製品の輸入を停止?
<〃> 中国が在中国リトアニア大使館員に身分証更新要求、全員帰国
<2022年1月> 台湾が中東欧向け投資基金設立を発表【下記 朝日】
*************************
これまでも取り上げてきたように、リトアニアが中国の反発が想定されるなかで今回措置に踏み込んだのは、かつてソ連に抑圧された自国歴史と台湾の現状が重なるところがあり、シンパシーを感じるためとされています。
また、中国との取引がさほど多くないため、中国の経済的圧力を軽視していたこともあるのかも。
しかし、中国の圧力はリトアニアとの直接取引だけでなく、リトアニア製品を使用する欧州企業にも及んでおり、リトアニアは想定以上の圧力にさらされていると推測されます。
****リトアニア×中国、続く対立 自由・人権重視×「主権侵害」訴え 台湾が「大使館」、欧米巻き込む****
バルト3国の一つ、リトアニアと中国の関係悪化が深刻になっている。自由や人権を重んじて台湾への接近を図るリトアニアに対し、中国は主権の侵害を訴えて外交的・経済的な圧力を強める。対立は欧米を巻き込む事態に発展し、先行きは不透明だ。
対立が激しくなったきっかけは昨年7月、リトアニアが大使館に相当する「台湾代表処」の設置を決めたことだ。中国は駐リトアニア大使を召還し、外交関係を「代理大使級」へ格下げ。一方のリトアニアは12月、在中国大使館員を全員帰国させた。身分証を返還するよう「脅し」を受けたとするリトアニアに対し、中国は「外交関係の格下げに伴う更新手続きだ」と主張している。
影響は経済にも波及した。リトアニア産業界は昨年12月から「自国製品が中国の税関を通らない」と訴え始めた。対象はリトアニア製の部品を含むEU製品にも拡大しているとみられ、ロイター通信は独自動車部品大手「コンチネンタル」が、中国からリトアニア製部品の使用をやめるよう圧力を受けたと報じた。こうした動きのなか、台湾は今月、リトアニアを含む中東欧に対し半導体産業などに投資する2億ドル(約230億円)の基金設立を発表した。
リトアニアには、ロシア帝国やソ連の侵攻や支配を受けてきた歴史があり、人権侵害や覇権主義的な動きへの問題意識が高い。中国にも、経済関係の強化を目指す一方、安全保障の脅威として警戒を強めてきた。
2019年には、首都ビリニュスで開かれた香港民主派への連帯を示す集会に、中国国旗を持った中国人が乱入する騒ぎが起き、国民の対中感情が悪化。リトアニア外務省は、中国大使館の職員が関与したとして抗議し、翌年の政権交代後には、中国と中東欧との経済協力枠組み「17+1」から離脱するなど、対中政策が厳しさを増している。
人口270万人の小国リトアニアが中国との正面衝突も辞さない姿勢を示す背景には、常にロシアの脅威にさらされる自国や東欧地域に米国や欧州の関心を引く思惑もありそうだ。
リトアニアの輸出額に占める中国の割合は約1%と小さく、同国の巨大経済圏構想「一帯一路」の主要投資国ではないなど経済的な結びつきが薄いことも、リトアニアがこうした姿勢をとれる要因になっているようだ。
■譲れぬ中国、軟化待つ
一方、中国にとってリトアニアの言動は、中台関係において決して譲れない「一つの中国」原則への挑戦に映る。リトアニアを追い詰める姿勢からは、小国に振り回されることへのいら立ちも透けて見える。
外務省報道官は「最後は歴史のゴミ箱に投げ込まれる」と批判し、共産党機関紙・人民日報系の環球時報も「ゾウの足の裏にいるネズミかノミにすぎない」とののしった。
中国にはジレンマもある。昨年末、ニカラグアとの国交が回復し、台湾と外交関係を持つ国は過去最少の14カ国まで減った。リトアニアとの関係がどれほど悪化しても外交戦略上、断交は選択しづらい。対中警戒はスロバキアやチェコなどにも広がっている。リトアニアへの過剰な圧力が、10年間かけて築いた中東欧との経済協力枠組みからのさらなる離脱を招く不安もある。
中国は当面、対抗措置を維持しつつリトアニアの軟化を待つ構えだ。4日、ナウセーダ大統領が代表処の名称に「台北」ではなく中国が反発する「台湾」を用いた判断を「過ちだった」と表明すると、中国外務省の汪文斌副報道局長は翌日の会見で「誤りを認識するのは正しい一歩。より重要なのは行動だ」と求めた。【1月12日 朝日】
*****************
【中国の圧力でリトアニア内部にも不協和音】
中国の圧力が強まるなかで、上記記事のナウセーダ大統領発言に見られるように、リトアニア内部の政治的対立も表面化しています。
****リトアニア、親台湾政策めぐり大統領と外相が対立****
バルト三国の一つ、リトアニアの政府内で親台湾外交をめぐる対立が起きている。
ナウセーダ大統領は4日、昨年11月に国内に設置された台湾当局の代表機関に「台湾代表処」の名称を認めたのは「過ちだった。私は関与しなかった」と主張。ランズベルギス外相は「すべて大統領とともに決めた」と反論した。内政バトルに中国と米国が「参戦」し、場外戦に発展している。
一連の発言は、リトアニア公共放送LRTなどが報じた。ナウセーダ大統領は、代表機関の設置自体は正しいとしながら、「名前が問題。対中関係に大きな打撃を与えた」と発言し、ランズベルギス外相に打開策を示すよう求めた。
これに対し、同外相は「リトアニアは悪いことをしていない。価値観に基づいて方針を決めたため、罰を受けている」と述べ、中国がリトアニアに「報復」として経済圧力を加えていることこそが問題と主張している。
大統領と外相の対立について、ビリニュス大のコンスタンチナス・アンドリヤウスカス准教授は「2人がライバル関係にあるのが原因」と指摘する。ナウセーダ大統領は、中央銀行の元理事で経済専門家。ランズベルギス外相は2020年の議会選で勝利した中道右派政党の党首で、かつて大統領選でナウセーダ氏の対立候補だったシモニテ現首相を擁立し、新政権を発足させた。
ナウセーダ大統領の発言を受け、中国外務省報道官は5日、「誤りを正すのは正しい方向への一歩。重要なのは行動だ」と述べ、台湾代表処の名称変更を促した。
これに対し、米通商代表部(USTR)のタイ代表はランズベルギス外相と電話で会談し、支持を表明。ツイッターで「リトアニアは中国の経済的威圧に直面している」と指摘した。
中国は台湾代表処の開設は「一つの中国」政策に反すると批判。リトアニアからの出荷品の通関を差し止める報復に出ている。中国は実施を認めていないが、欧州連合(EU)に影響が広がっており、欧州委員会は世界貿易機関(WTO)への提訴も辞さない構えを示している。
リトアニアは1990年、民主化運動の末にソ連から独立回復を宣言した歴史があり、中国の圧力を受ける台湾を支援してきた。昨年11月にはナウセーダ大統領が、バイデン米大統領と訪英中に会い、親台政策で「支持を得た」とも述べていた。
しかし、隣国ロシアの脅威が増す中、国内には対中関係悪化への不安も強く、最近の世論調査では41%が政府の政策に不支持を表明していた。【1月7日 産経】
*********************
この名称問題、今も継続中です。
****リトアニア、「台湾」名称の変更検討 中国との対立回避=関係筋****
バルト3国の一つであるリトアニア政府は、昨年首都ビリニュスに開設した台湾の代表機関について、中国との対立を回避するため中国語の名称を変更するよう台湾に要請すべきか議論している。2人の関係者がロイターに語った。
リトアニアは、台湾の事実上の大使館となる代表機関を昨年11月に開設した。名称も欧州に置く代表機関で初めて「台北」ではなく「台湾」の表記の採用を認めた。
これに対して、台湾を自国領土の一部と主張する中国は猛反発し、リトアニアとの外交関係を格下げするなど、中国とリトアニアの関係は冷え込んでいる。
関係筋によると、リトアニアのランズベルギス外相は先週、ナウセーダ大統領に対して、中国との関係を修復する手段として代表機関の中国語表記を「台湾」から「台湾人」に変更することを提案した。この変更には台湾の同意が必要になる。
リトアニア大統領府はコメントを差し控えている。外務省はコメントの要請に応じていない。
シンクタンク、ビリニュス東欧研究センターの代表、リナス・コヤラ氏は、リトアニアがどんな行為を示したとしても中国の態度を変えることは不可能だと指摘した。
その上で「リトアニア政府はおそらく、代表機関が政治的実体としての台湾を代表しているのではく、リトアニアが文化や経済面での関係構築を望む台湾の人々を代表しているということを強調しようとしている」と説明した。
中国国営メディア「環球時報」は22日に掲載した論説で、リトアニアが中国との関係を修復するには、代表機関の名称変更だけでは不十分だとの見方を伝えた。【1月26日 ロイター】
リトアニアは、台湾の事実上の大使館となる代表機関を昨年11月に開設した。名称も欧州に置く代表機関で初めて「台北」ではなく「台湾」の表記の採用を認めた。
これに対して、台湾を自国領土の一部と主張する中国は猛反発し、リトアニアとの外交関係を格下げするなど、中国とリトアニアの関係は冷え込んでいる。
関係筋によると、リトアニアのランズベルギス外相は先週、ナウセーダ大統領に対して、中国との関係を修復する手段として代表機関の中国語表記を「台湾」から「台湾人」に変更することを提案した。この変更には台湾の同意が必要になる。
リトアニア大統領府はコメントを差し控えている。外務省はコメントの要請に応じていない。
シンクタンク、ビリニュス東欧研究センターの代表、リナス・コヤラ氏は、リトアニアがどんな行為を示したとしても中国の態度を変えることは不可能だと指摘した。
その上で「リトアニア政府はおそらく、代表機関が政治的実体としての台湾を代表しているのではく、リトアニアが文化や経済面での関係構築を望む台湾の人々を代表しているということを強調しようとしている」と説明した。
中国国営メディア「環球時報」は22日に掲載した論説で、リトアニアが中国との関係を修復するには、代表機関の名称変更だけでは不十分だとの見方を伝えた。【1月26日 ロイター】
*******************
“政治的実体としての台湾”と“台湾の人々”の違い・・・微妙ですね。
まあ、「一つの中国」自体が極めて微妙ですから。
****リトアニア大統領が「台湾代表処」の名称変更を督促、中国外交部が反応****
2022年1月28日、環球時報は、リトアニアのナウセダ大統領が「台湾代表処」の変更を呼びかけたことについて、中国外交部のコメントを報じた。
記事は、中国本土から強い反発が出ているリトアニアの「台湾代表処」の名称問題について、26日に欧米メディアからリトアニア政府が名称変更を台湾側に要請するかどうかの議論を行っているとの報道が出たことに対し、リトアニア外務省と台湾外交部がそろって変更を否定したと伝えた。
一方で、ナウセダ大統領が27日にリトアニアの国営ラジオ局のインタビューに対し、英語やリトアニア語では「台湾人」となっている代表処の名称が、中国語では「台湾」と表記されていることについて「もしその名称が言語によっていささか異なれば、本来全く必要のない問題を引き起こすことになる」とし、名称問題がが中国本土との衝突を生む大きな要因になっているとの見方を示した上で、「リトアニア政府は名称決定の際に事前に協議をせず、政府も中国本土の反応を十分に評価しなかった。現在最も重要なのは、中国本土との関係の正常化であり、リトアニア企業が損失を受けないようにすることだ」と述べたことを紹介した。
そして、中国外交部の趙立堅(ジャオ・リージエン)報道官が28日の定例記者会見でこの件について質問を受けた際、「わが国は既にこの問題の本質について再三言明しており、リトアニアは問題の根本的な原因をよく分かっている。リトアニアが本当に中国との緊張を緩和したいのであれば、誠意を示し、実際の行動にて誤りを正し、一つの中国を堅持するという正しい軌道に戻すことだ。文字遊びによってうやむやのうちにやり過ごすことは許されない」とコメントしたことを伝えた。【1月31日 レコードチャイナ】
*******************
“文字遊びによってうやむやのうちにやり過ごすことは許されない”というのは、“台湾人”に変更するだけではダメだということでしょうか。
【リトアニアを支援するEUだが、何ができるか・・・】
EUはリトアニアを支援する姿勢です。
****EU、3月末に中国と首脳会談=リトアニアへの圧力非難****
欧州連合(EU)のボレル外交安全保障上級代表(外相)は14日、フランス西部ブレストで行われたEUの外相会議終了後に記者会見し、「3月末に中国とEUの首脳会談が開催される」と明らかにした。外相会議は13日から2日間行われ、台湾の代表機関開設を認めたリトアニアに対して中国が貿易面で圧力を強めている問題の対応を協議した。
欧州連合(EU)のボレル外交安全保障上級代表(外相)は14日、フランス西部ブレストで行われたEUの外相会議終了後に記者会見し、「3月末に中国とEUの首脳会談が開催される」と明らかにした。外相会議は13日から2日間行われ、台湾の代表機関開設を認めたリトアニアに対して中国が貿易面で圧力を強めている問題の対応を協議した。
台湾は昨年11月、リトアニアの首都ビリニュスに、大使館に相当する「台湾代表処」を開設した。「一つの中国」原則を掲げる中国はこれに猛反発。リトアニアからの輸出品が中国の税関を通らなくなり、他のEU加盟国から中国への輸出にも影響が出ているとされる。
ボレル氏は、EU各国の外相が「域内市場への影響と、どのように緊張を緩和するかを話し合った」と説明。共同で記者会見したEU議長国フランスのルドリアン外相も「リトアニアへの完全な連帯を確認し、中国の威圧的な行動を非難した」と述べた。【1月15日 時事】
*********************
ただ、支援するとは言っても、中国の激しい怒りを前にしてEUに何ができるのか・・・難しいところです。
****EUの限界が試されるウクライナ危機とリトアニア問題****
1月17日付の英フィナンシャル・タイムズ紙(FT)で、同紙外交問題コメンテーターのギデオン・ラックマンが、ウクライナ危機とリトアニアに対する中国の抑圧的な貿易措置が欧州連合(EU)の地政学上の力の限界をテストしていると論じている。(中略)
リトアニアの問題は性格を異にする。この一件にEUが外部の大国に小突き回される命運にあることの証左を見ようとするのは大袈裟に過ぎると思うが、ともかく、EUは結束してリトアニアを守らねばならない。しかし、これといった名案は見出し難い。
リトアニアが「台湾代表事務所」の開設を認めたことに憤激する中国はリトアニアとの間の直通の貨物列車の運行を停止し、両国間の貿易を停止した――リトアニアに工場を有するドイツの自動車部品大手Continentalの製品も対象となる。
更に、EUの他の加盟国企業がリトアニアでの投資と部品調達を控えるよう警告し、これら企業の中国でのオペレーションに報復することがあり得ることを警告したとも伝えられる。これはEU加盟国間に楔を打つ中国が得意とする手法と言い得よう。
EUは、12月8日に欧州委員会が提案した反抑圧法制(Anti-Coercion Instrument)を早期に実現し、その対象とすることによって中国に対抗することを考えるのかも知れないが、恐らく間に合わない。中国への対抗措置を講じ得たとしても、中国の抑圧が止むことは考えられず、その効果如何という問題がある。
問題はリトアニアがどれだけ耐えられるか
台湾はリトアニアを支援する意向を表明している――中国税関に拒否されたリトアニアの貨物を出来るだけ多く引き受け(2万4000本のラム酒を引き受けた)、2億ドルの基金を設けてリトアニアに投資するとしている。EUとしても、リトアニアの支援の方が有効であり、これを検討すべきではないかと思われる。
いずれにせよ、リトアニアが何時まで耐えられるかの問題がある。1月4日、リトアニアの大統領ギターナス・ナウセーダは台湾の代表事務所の開設自体ではないがその名称に(台北ではなく)「台湾」を使ったことは間違いだった、名称については自分に協議がなかったと述べた。
彼は「台湾」の名称の撤回までも求めた様子はないが、政府内部における本件のその後の取り扱いは詳らかにしない。
EUおよび加盟国にも名称の問題での騒動を不必要な騒動だと迷惑に思う向きがあるに違いない。かといって、中国に屈服する形になることは甚だしく望ましくない。
どうなるのか分からないが、FTの論説が指摘するような、リトアニア危機が「世界の場でその利益を守るEUの能力の飛躍を導くこともあり得る」ことにはなりそうにない。【1月31日 WEDGE Infinity】
**********************
EUに何ができるか・・・というより、どこまで(大きな影響力を有する貿易・投資相手国である)中国相手に争う覚悟があるか・・・という問題でしょう。
別に揶揄する訳でなく、日本も中国との間で同様問題をかかえるところで、現実的対応は難しい問題です。