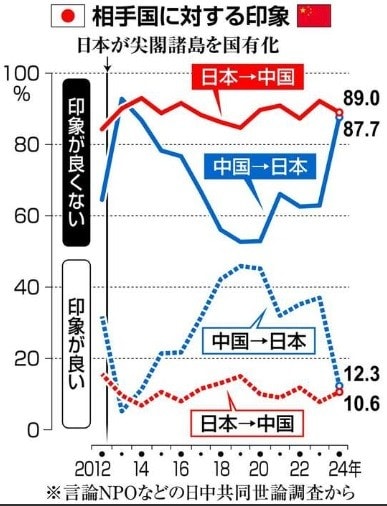(内モンゴルの民族団結を促すスローガン【2月8日 TBS NEWS DIG】)
【習近平主席指導で進められる同化政策 20~21年には激しい抵抗運動も】
「アジア」という地域でイメージするのは(私の場合)、中国・韓国・北朝鮮・台湾など東アジア、ASEAN諸国の東南アジア、インド・ネパール・スリランカ更にはパキスタン・バングラデシュなどの南アジアの国々。
中央アジア・イラン・アフガニスタンとなると「地理的にはアジアなんだろうけど・・・」という異質な感じも。
そうした「アジア」のイメージで抜け落ちがちなのがモンゴル。(相撲ファンはそうでもないでしょうが)
そうした背景もあってか、モンゴルに関する相撲以外の日本語報道は非常に少ないのが現実です。
周知のように、独立国家としてのモンゴル以外に、中国には内モンゴル自治区も存在します。
歴史的に見ると、日本は満州国を作った当時、内モンゴルにも侵攻しておりこの地域に深く関与しています。
このあたりの経緯を簡単にまとめると、以下のようにも。
****二つのモンゴル、その歴史的経緯 日本が作った「蒙古聯盟自治政府」*****
清王朝は約300年の栄華を極めたが、1911年、孫文が「漢民族の国家を再興する」という旗印を掲げて辛亥革命を起こし、清王朝を崩壊させた。
1915年、ソ連は中華民国・北京政府に提案して「キャフタ条約」を結び、独立を望んでいたモンゴル人の意思を無視して、モンゴルを二つに分けた。
ソ連に隣接する外モンゴル(北モンゴル)に自治を認める代わりに、中国に隣接する内モンゴル(南モンゴル)を中華民国領に編入したのである。1924年、外モンゴルはソ連の影響を受けて社会主義国となり、モンゴル人民共和国として独立した。
(中略)(日本は)ロシア革命を経てソビエト連邦となっていた同国を中国・東北部から追い出し、そこに退位した清朝皇帝・溥儀をいただいて「満州国」(1932年)を樹立した。それと同時に、ソ連に対する“防共”戦線の最前線とみなす内モンゴルに進攻して占領。日本に協力する「蒙古聯盟自治政府」を樹立した。
(中略)だが1945年、日本は第二次世界大戦に負けて、満州や内モンゴルから退去した。
4年後の1949年、中国共産党が支配する中華人民共和国が誕生し、清朝政府の後継者を公言して、内モンゴルを自国領として引き継いだ。内モンゴルにとっては、また新たな試練に晒されることになった。試練は21世紀の今日になってもなお続いている。いや、前にも増して過酷になった。(後略)【2021年5月8日 譚 璐美氏(作家) JBpress】
********************
国際ニュースであまり多くは登場しないモンゴルに注目が集まったのが2020年~2021年、中国による同化政策、それに対する住民の抵抗が大きく取り上げられました。それが上記記事最後にある“前にも増して過酷になった”という件です。
習近平指導部による同化政策強化の一環として、内モンゴルの小中学校ではモンゴル語による授業が大幅に減らされ、漢語による授業が大幅に増やされました。
****習主席、同化政策を強化 内モンゴルで標準中国語の推進を指示****
中国の習近平国家主席は5日、同化政策の強化を指示し、内モンゴル自治区当局は「民族問題を解決」して標準中国語の使用を推し進めていくべきだと述べた。
同地区では昨年、モンゴル語に代わって標準中国語で教育が義務化されることに反対する住民らが激しい抗議活動を行った。
中国政府は、少数民族を多数派の漢民族に同化させる政策の一環として、標準中国語による教育の義務化を全国的に推し進めているが、内モンゴル自治区では昨年、モンゴル語の代わりに標準中国語で教育を行うようカリキュラムが変更されたことを受け、数万人が抗議デモや授業のボイコットを行った。
同自治区での抗議活動はまれだが、過去数十年で国内最大規模となった抗議デモを受け、政府は取り締まりを開始し、装甲車両で複数の学校を包囲し、警察当局はデモを主導した数十人を拘束。
さらに当局は、子どもに学校をボイコットさせた親に対して、解雇や罰金、子どもの退学という脅しをちらつかせ、地域によっては、同級生らを説得して登校させた子どもに金銭の提供を申し出ていた。
内モンゴル自治区での弾圧は、同様の同化政策を実施している新疆ウイグル自治区やチベット自治区における中国政府の動きに呼応する。
国営メディアによると、習氏は5日、全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で、内モンゴル自治区での文化や民族についての「誤った認識」を正すため、地元当局は「全国共通の教材の使用をしっかりと推進」すべきだとの考えを示した。
習氏は内モンゴル自治区での抗議活動について、地元当局に「中国の特色で民族問題を解決するという正しい道を歩み続けるべきだ」と求め、内モンゴル自治区の住民らは「漢民族は少数民族から切り離せず、少数民族も漢民族からは切り離せないことを覚えておくべきだ」と述べた。 【2021年3月6日 AFP】
********************
当時、内モンゴルにおける「文化的弾圧」に対し、(外)モンゴルの反応はあまり大きなものはありませんでした。
****草原の民・モンゴル族、「内」と「外」の微妙な関係****
中国政府が内モンゴル自治区の少数民族モンゴル族に強めている同化政策は、国際社会に懸念を広げつつある。その同胞による独立国家で「外モンゴル」とも呼ばれるモンゴル国の動きは鈍い。それでも、中国はその動向が気にかかる。
(中略)9月12日には、「母語を救おう」をスローガンとした抗議デモが、東京、大阪、名古屋のほか、米国、ドイツなどで行われた。中国の少数民族問題に敏感な米国では議員らも関心を示す。
モンゴル国政府は公式の反応は示していないが、やむを得ない部分もある。長年にわたり、石炭や銅など輸出総額の9割前後を中国が占める。直接投資を受ける外国企業の約5割も中国企業だ。国内経済の生命線は中国に握られている。
エルベグドルジ元大統領は昨年9月、個人の立場で「母語の尊重」を呼びかけ、今年3月には国内に支援組織を発足させた。それでも支援は民間レベルにとどまり、同胞の危機に積極的に動いているように見えない。
背景には、モンゴル族が、長年にわたり共存してきた漢族と「融合した」と見下すモンゴル国の「純血主義」も指摘される。モンゴル国民の歴史的な強い嫌中感が、内モンゴルの同胞に対する複雑な感情につながったものだ。
中国は、モンゴル国の事情を見越しているはずだ。それなのに、王毅ワンイー国務委員兼外相は昨年9月、ウランバートルに出向き、「国内問題に干渉するな」とわざわざクギを刺した。(後略)【2021年10月12日 読売】
********************
モンゴル国の動きが鈍いのは、「純血主義」も指摘されていますが、一番は中国を刺激したくないというところでしょう。
【教育現場で消えるモンゴル語 「僕は少しは話せます」 (外)モンゴル国ではモンゴル文字復活の動き】
中国の同化政策は今も続いています。
****中国による「同化政策」…言葉をめぐって揺れる「2つのモンゴル」【報道特集】****
中国では今、少数民族の言葉が存続の危機に陥っています。内モンゴル自治区で何が起きているのか。一方で隣のモンゴル国は今年、長年使われていなかったモンゴル文字の復活を決めました。言葉をめぐって揺れる2つのモンゴルを取材しました。
旭鷲山「モンゴル人として残念」
大相撲の元小結・旭鷲山。1991年にモンゴルから来日し、史上初のモンゴル出身力士として多彩な技で人気を集めた。(中略)
引退後、故郷のモンゴル国に戻り、国会議員などを務めたが、今「あること」が心配だという。
「モンゴルの言葉を話してはいけない、モンゴル文字は学校で教えてはいけない。これは本当に残念ですね。特に僕らは同じモンゴル人なので大変残念です」
「2つのモンゴル」で起きていること
それはモンゴルの隣の国、中国で起きていた。中国北部にある内モンゴル自治区は、人口約2400万人。そのうちの2割、約400万人がモンゴルの人々だ。
「各民族はザクロのように固く団結しよう」 いたるところで目につくのは、民族団結を促すスローガン。実がギュッと詰まったザクロは、民族団結の象徴とされている。
中国では、多数派を占める漢族のほか、55の少数民族が暮らしている。モンゴル族も、ここでは少数民族の一つに数えられている。(中略)
これまで公用語である中国語とともにモンゴル語を学び、使うことが許されていた。しかし5年前、事態は一変する。
中国「同化政策」に広がる抗議
(中略)モンゴル族の親たちが、学校の前に集まり抗議の声を上げた。きっかけは2020年、中国政府が「国語」や「歴史」といった一部のモンゴル語の教科書を中国語に切り替えるなど、モンゴル語による授業を大幅に減らす方針を打ち出したことだ。 ここ数年、中国政府は少数民族に対し、中国語教育を強化するなど漢族への同化政策を進めている。
「モンゴルの言葉が失われてしまう」
危機感を抱いた生徒や親による抗議活動は瞬く間に拡大した。授業をボイコットする動きも広がったが、中国政府は抗議活動の参加者を次々と拘束。徹底的に抑え込んだ。アメリカを拠点とする人権団体によると、約1万人が当局に拘束されたという。
国際的な非難にさらされた中国政府は、こう主張した。
中国外務省・華春瑩報道官 「モンゴル語の授業時間も、使用教材も、授業で使う言語も変わりません。中国語とモンゴル語を使うことに変わりはありません」
しかし、2023年には習近平国家主席自ら内モンゴル自治区を視察。中国語の使用を徹底するよう指示を出すなど、方針は強化されている。
抗議活動から5年。現地はどうなっているのだろうか?
「モンゴル語が話せない」親の懸念
内モンゴル自治区・西部にあるオルドス市には、モンゴルの子どもたちが多く通う民族学校がある。
中国の国歌が流れる校庭で、敬礼する子どもたち。校舎には「中国語を話そう」というスローガンが掲げられていた。
抗議活動に参加したという人に話を聞いた。
モンゴル族の親 「この学校はまだましで、子どもたちはモンゴル語で勉強していますが、他の学校ではもうできません」 モンゴル語による授業はここ数年で大幅に削減されたという。
モンゴル族の親 「今は自分たちが家で言葉を教えるしかありません。モンゴル語による授業を受けられないから、子どもは幼稚なモンゴル語しか話せなくなっています」 この男性もまた、モンゴル語が失われてしまうという危機感を抱いていた。
モンゴル族の親 「(モンゴル語による)授業は禁止されました。子どもは幼稚園に通う歳ですが、モンゴル語で教える幼稚園も無くなりました。当時、激しく抵抗したけれど最後は中国共産党の勝ちですよ」
モンゴル語による授業削減という中国政府の方針に抗議して辞職した教師もいたという。
モンゴル族の親 「子どもが民族の言葉を学べなくなれば民族は消えてしまうでしょう。私の同級生の子どもたちの多くはモンゴル語が話せなくなっています。深刻な問題です」
モンゴル族の子どもが通う民族学校の教師は、授業の変化をこう証言した。
民族学校の教師(漢族) 「小学1年生は全部中国語です。今は全部中国語ですよ。モンゴル語の授業は少しはあるけれど、他は全部中国語で教えています」
(中略)
Q.モンゴル族の子どもたちはモンゴル語を話せるの? 「僕は少しは話せます」
Q.中国語とモンゴル語どっちが話しやすい? 「中国語です。 モンゴル族の子どもも中国語で授業を受けるので」
変化が起きていたのは、学校だけではなかった。
消されていくモンゴル文字
街中では、これまでモンゴル族の文化を保護するため併記されていた「モンゴル文字」の表記が少なくなり漢字のみの看板が並んでいた。(中略)
中国で消えるモンゴル語。失われゆく、モンゴルのアイデンティティー。危機感を抱いたのはとなりの国、モンゴル国で暮らす人々だ。
80年ぶりのモンゴル文字復活
2020年、中国国内での抗議活動に呼応するようにモンゴル国でも「モンゴル語を守ろう」というキャンペーンが展開され、瞬く間に世界各地に広がった。キャンペーンを主催したNGOは、中国政府の弾圧から逃れてくる内モンゴル自治区の人たちを助ける活動も行ったという。
NGO「言語を守ろう」 バーサンジャルガルさん(33)
「モンゴルでは『命より名誉が大事。名誉とは言葉や文化を守り抜くこと』です。命をかけてモンゴル語を守ります」
「モンゴルでは『命より名誉が大事。名誉とは言葉や文化を守り抜くこと』です。命をかけてモンゴル語を守ります」
市民たちも、中国の状況に胸を痛めていた。
モンゴルの市民 「民族を絶滅させるためには、まず言葉に手をつけてくるのです。とても残念です」(中略)
実は、モンゴル国で暮らす人々の多くは「モンゴル文字」が読めない。長らく旧ソ連の強い影響下にあったため、1940年代「モンゴル文字」にかわりロシアで使われている「キリル文字」を導入したからだ。(中略)
中国国内で進む急速な「モンゴル語消滅」の動きは、モンゴル政府のある決断を後押しすることになった。それは…
言語政策国家委員会 ナランゲレル事務局長(36) 「2025年1月1日からモンゴル文字とキリル文字で公文書を作成すると決めました」(中略)
モンゴル国で暮らすモンゴル人は約330万人。一方、内モンゴル自治区には400万人が暮らしている。もし、内モンゴルからモンゴル文字が消えてしまったら。危機感は強い。
モンゴル政府は今後、公文書だけでなく、道路標識や看板などにも徐々にモンゴル文字を広げていく方針だ。
80年ぶりの「モンゴル文字」復活の動きは、教育現場でも広がっている。
この学校では小学校6年生から高校3年生が週2回、モンゴル文字を学んでいる。先生の悩みは、日常生活の中でモンゴル文字に触れる機会が少なく、生徒がすぐに忘れてしまうことだ。それでも生徒たちは、自らの民族の歴史と文化を再確認するように、積極的に学んでいる。(中略)
モンゴルで始まった「モンゴル文字」復活の動きは、一度失った言葉を取り戻すには長い年月がかかることを教えてくれる。(後略)【2月8日 TBS NEWS DIG】
*******************
【高度な自治の実現などを訴えてきたハダ氏 体調悪化 連絡が取れない状況】
中国政府による同化政策が進められる内モンゴルにあって、モンゴル族の人権の擁護や、モンゴル語の保護、高度な自治の実現などを訴えてきたのが南モンゴル民主連盟代表のハダ氏。
ハダ氏は1995年に「国家分裂罪」などで懲役15年の判決を受けていました。同氏の体調悪化が報じられています。
****中国軟禁下の南モンゴル人権活動家、緊急搬送 日本の国会議員がノーベル平和賞候補推薦も****
米国に拠点を置く人権団体「南モンゴル人権情報センター」は1月30日、中国内モンゴル自治区で高度な自治実現を目指し、公安当局に軟禁されている南モンゴル民主連盟代表のハダ氏(69)について区都フフホトの病院に緊急搬送されたと発表した。ハダ氏は日本の国会議員の推薦で今年のノーベル平和賞候補となっている。
多臓器不全の疑い
同センターは30日、酸素マスクを付けて集中治療室に横たわるハダ氏とみられる姿や太ももの写真も合わせて公開した。ハダ氏の妻から入手したといい、太ももには打撲傷とみられる紫色のあざが映っている。
妻によれば、中国の保健当局は25日にハダ氏が危篤状態にあることを伝え、妻は病院の集中治療室で意識をほとんど失った状態のハダ氏と面会したという。多臓器不全の疑いがあるといい、原因については明かされなかった。
ハダ氏は1980年代から中国の憲法で保障されている南モンゴルの民族自決権の回復を言論活動を通して主張し、95年に逮捕された。刑期を終えた後も中国当局が管理するアパートで軟禁されているという。
無償で治療し解放を
30年間自由を奪われても平和的に抵抗活動を続けるハダ氏は「南モンゴルのネルソン・マンデラ」と呼ばれ、自民党の山田宏参院議員ら4人の与野党議員はノーベル平和賞候補に推薦し、1月26日にノルウェーのノーベル委員会に受理された。
中国の弾圧政策に抗議する民族団体「南モンゴルクリルタイ」(世界南モンゴル会議)は今月1日、中国政府に対する抗議声明を出し、ハダ氏に適切な治療を無償で施した上で、軟禁状態を解くことを求めた。【2月3日 産経】
*******************
その後「行方不明」報道も。
****中国・内モンゴル自治区の民主活動家が行方不明か 中国政府に自治区の高度な自治訴え****
(中略)容体が一時的に回復したとして家族はハダ代表との面会が許されたということですが、再び集中治療室に運ばれてからは接触できず、家族の問い合わせに対して、病院側はハダ代表の容態や居場所について回答を拒否しているということで、行方不明になっていると報じています。(後略)【2月10日 TBS NEWS DIG】
*********************
*********************