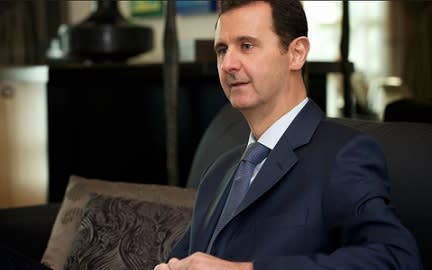(ナイジェリア政治の「変革」を訴える大統領選挙候補ブハリ氏の選挙キャンペーン 本文でも触れているようにブハリ氏の“実績”を考えると、彼にも「変革」が必要に思えます。 “flickr”より By Heinrich-Böll-Stiftung https://www.flickr.com/photos/boellstiftung/16215951040/in/photolist-qGWZhL-qXdmus-q3HAXn-q3vb4j-pXUkUV-qDDxc1-qW42cP-pZ4eUA-qW1q5u-qW4rnM-qW8gaS-qVUy34-qVYQty-pZd97V-qDyVDx-qDq3HS-qDxfRB-pZiuMx-qDEihH-qW4rBp-qDwCQu-qW8gHA-qBsSwM-qDrjoQ-qVV59N-qTL4cM-qDCgSd-qDCgZs-qDMbJP-qBsRUe-qBkCCs-pWUXp9-qTV1Fa-qTyZRw-qTL2zP-qW8gxA-qDCgD7-pZqkY6-qDxzzg-qVPo7T-qF86Mu-qYMN9X-qXCm3c-qWdBiN-qDksKk-pYGaE5-qC52jq-qStygd-qDZvgC-pYuwxG)
【面的支配、カメルーンへの拡大、女性・子供の拉致、人間爆弾・・・・エスカレートする「ボコ・ハラム」】
世界の注目を集める「イスラム国」(“ISIL”と呼んだ方がいいのでしょうか)ですが、それと同等、あるいはそれ以上の残虐行為を繰り返している西アフリカ・ナイジェリアのイスラム過激派「ボコ・ハラム」にはナイジェリア政府・軍も有効に対処できておらず、国際的にも放置された状態にあります。
そのことについては、1月15日ブログ“ナイジェリア 「ボコ・ハラム」による虐殺に無力な政府・国際社会”(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20150115)でも取り上げたところです。
「ボコ・ハラム」は、共鳴する「イスラム国」にならって、面的な支配地域拡大を狙っています。
活動範囲もナイジェリアだけでなく、隣国カメルーン北部にも拡大し、殺戮・暴行の他、女性や子供の拉致も繰り返しています。
拉致した女性や子供を「奴隷」として扱い、戦闘員との結婚を強要したり、少年兵として戦闘に参加させたりしていますが、当局から疑われにくい女性や子供を「人間爆弾」として利用する非道な自爆テロも行っているとも指摘されています。
****ボコ・ハラム襲撃、200人超死亡 ナイジェリア州都で政府軍と戦闘****
ナイジェリアからの報道によると、同国北東部ボルノ州の州都マイドゥグリなどで25日、イスラム過激派ボコ・ハラムとみられる武装集団と政府軍の激しい戦闘があり、200人以上が死亡した。武装集団はマイドゥグリから撤退したが、マイドゥグリとほぼ同時に襲撃された同州の別の町モングノは武装集団に制圧された。
ボコ・ハラムは北東部を中心に襲撃やテロ、誘拐などを繰り返しているが、今回の攻勢では都市部を支配下に置くことを狙った可能性がある。ロイター通信によると政府軍はモングノへ空爆を実施したもようだ。
ナイジェリアでは2月に大統領選が予定されており、政治混乱が広がればボコ・ハラムを利する恐れがある。
25日に同国の最大都市ラゴスを訪問したケリー米国務長官はジョナサン大統領らと会談し、平和的に選挙を行うよう求めた。【1月27日 産経】
******************
****子供ら80人拉致、うち24人を保護 ボコ・ハラム、女性や子供「奴隷」扱い****
カメルーン北部で18日、隣国ナイジェリアを拠点とするイスラム過激派「ボコ・ハラム」とみられる武装集団が複数の村を襲撃し、住民約80人を連れ去った。10~15歳の子供約50人が含まれるという。ロイター通信が報じた。
カメルーン軍は19日、ナイジェリアに戻ろうとする武装グループを追跡する中、被害者のうち24人を保護したと明らかにした。
ボコ・ハラムは昨年4月、ナイジェリア北東部で女子生徒200人以上を拉致。今月中旬にはナイジェリア北東部の2都市で、ボコ・ハラムに送り込まれたとみられる10歳前後の女児が、市場で自爆する連続テロが発生した。(後略)【1月20日 産経】
*********************
「ボコ・ハラム」の度重なる襲撃で難民が増大、地域の不安定化が進んでいます。
【「アフリカ全体が連帯してボコ・ハラムの脅威と戦わなければならない」】
こうした状況で、カメルーン政府の支援要請に応じる形で、戦闘経験が豊富と見られている隣国のチャドが18日までに軍の部隊をカメルーンに派遣しました。
国連安全保障理事会もチャドの介入を歓迎し、周辺国の軍による支援介入を認めています。
****ボコ・ハラム、チャド軍派遣部隊を攻撃 双方で126人死亡****
チャド軍は30日、国営テレビで声明を発表し、ナイジェリアのイスラム過激派組織「ボコ・ハラム)」に対抗するため派遣していた部隊が29日と30日に隣国カメルーンの北部の町フォトコルでボコ・ハラムの攻撃を受け、チャド兵3人が死亡、12人が負傷し、ボコ・ハラム側の123人が死亡したと明らかにした。
死亡したチャド兵はボコ・ハラムが使用した手製爆弾で命を落としたという。
ボコ・ハラムがナイジェリアの周辺国に与える脅威が増大していることを受けてチャド政府は今月17日、カメルーンに軍の部隊と軍用車両を派遣していた。(中略)
チャドはボコ・ハラムとの戦いで近隣各国に広範な連携を呼び掛けており、ナイジェリアとの国境周辺に自国軍を展開しているほか、カメルーンにも増派しようとしている。【1月31日 AFP】
*******************
チャドのデビ大統領は部隊の派遣に先立って、「アフリカ全体が連帯してボコ・ハラムの脅威と戦わなければならない」と述べ、アフリカ各国にも軍事支援を呼びかけました。
もはやナイジェリア一国に任せておけない状況下で、アフリカ連合の取り組みも報じられています。
****アフリカ連合、ボコ・ハラム対策で7500人の部隊結成へ****
アフリカ連合(AU)は30日、ナイジェリアのイスラム過激派組織「ボコ・ハラム」の恐るべき台頭を打破するため、周辺5か国の軍で構成する計7500人の部隊の結成を呼びかけた。
AUの執行機関にあたるAU委員会のヌコサザナ・ドラミニ・ズマ委員長が明らかにした。
「ボコ・ハラムの残虐な行為、言語を絶する残酷さ、徹底的な人命無視、財産の理不尽な破壊は比類ないもの」と同委員長は、30日のAU首脳会議に先立って前日に行われた「平和安全保障委員会」会議後に声明で述べた。
ボコ・ハラムの勢力拡大は周辺地域の危機となっており、これまでに直接被害を受けたカメルーン、チャド、ニジェール、ナイジェリアの4か国はベナンとともに、ボコ・ハラムの脅威を封じ込め、多国籍統合機動部隊を結成するため協力を強化することで合意した。【1月30日 AFP】
******************
【ナイジェリアに内在する問題】
ただ、これまでもスーダン・ダルフールでのアフリカ連合の軍事的取り組みは、資金不足などもあって十分な成果をおさめていない現実があります。
なによりも、地元ナイジェリアの確固たる対応が求められます。
****不運なナイジェリア****
・・・・このような脅威に対処するためのより協調的なアプローチが出てくる一時的な兆しはある。国連安保理は1月19日、地域の国々にイスラム主義勢力に対する取り組みで力を合わせるよう要請した。その翌日、西アフリカ諸国の高官らはニジェールで会合を開き、多国間の特別部隊の創設について話し合った。
そうした動きは心強いが、ナイジェリアが自国の問題に立ち向かう覚悟を決めない限り、統合軍は効果的ではないだろう。
決意を固めたナイジェリア政府にできることはたくさんある。第一に、ナイジェリアは十分な資金と装備を持つ、より順法精神の高い治安部隊を必要としている。
ナイジェリアは年間60億ドルを防衛と治安維持に費やしているが、上官が装具用資金をかすめ取ったり、下級兵の賃金を着服したりすることもあって、兵士は反抗したり、脱走したりすることがよくある。多くの市民は、ボコ・ハラムとほとんど同じくらい、規律のない軍や警察を恐れている。
組織的な汚職や悪政は、貧しい北部から連邦石油収入の取り分を奪ったり、北部の発展を妨げたりといった形でも、イスラム主義の急進化や民族対立を助長している。
ジョナサン氏か同氏の後継者が反乱とその原因に対処し始めなければ、政府は自分たちが統治すべき国がないことに気づくかもしれない。【英エコノミスト誌 2015年1月24日号 JP Pressより】
********************
「ボコ・ハラム」の活動がおさえきれない背景には、腐敗・汚職が蔓延するナイジェリア軍の装備不足・士気低下、もっと基本的には、「ボコ・ハラム」が活動する北部イスラム圏が経済成長の恩恵にあずかっておらず、貧困が解消しないという政治的問題があります。
また、「ボコ・ハラム」同様に、ナイジェリア軍の残虐行為も住民から恐れられており、住民の支持を得ていないという問題もあります。
【2月に大統領選挙 ナイジェリア再建の契機となるか?あるいは一層の混乱か?】
ナイジェリアでは2月14日に大統領選挙が行われます。
南部・キリスト教圏を地盤とする現職ジョナサン大統領と、北部出身元最高軍事評議会議長、ムハンマド・ブハリ氏の争いとなっています。
**************
・・・・皮肉なことに、ボコ・ハラムの成功はジョナサン氏の再選の可能性を高める。大統領の政治基盤は主にキリスト教徒の多い南部で、北部の反乱に悩まされずに好景気を享受しているためだ。
一方、ジョナサン氏の主要対立候補である北部出身の屈強な元最高軍事評議会議長、ムハンマド・ブハリ氏の勝算は、ボコ・ハラムが同氏の潜在的支持者の多くを追い出したことで打撃を受けている。【同上】
***************
経済成長を謳歌する南部にとって、連日報じられる北部辺境地域での虐殺・拉致事件は他人事なのでしょうか。
もっとも、選挙戦に見通しについては、原油価格下落の影響など異なる見方もあるようで、ふたを開けてみないとわからないところでもあります。
****ナイジェリアの大統領選:原油安ショックで接戦に?****
落選し続けたブハリ氏に追い風か
ナイジェリアが民政に移行した1999年以降、ブハリ氏は権力の奪回を目指して大統領選挙に3度出馬し、落選している。
だが、この2003年、2007年、2011年の選挙はいずれも、世界の石油価格が急回復しつつあるかピークに近づいている状況下で行われたものだった。
今回は違う。アフリカ最大の経済大国・ナイジェリアは輸出の90%以上、および国家の歳入の70%を石油に頼っているため今年の見通しは厳しく、今回の大統領選はこれまでよりもはるかに拮抗した争いになる公算がある。
銀行業やサービス業、消費関連産業などが好況に沸き、経済が6~7%というペースで安定的に成長していた時期には、ブハリ氏の禁欲主義的だという評価や、無駄遣いと汚職を一掃しようという主張は票につながらなかった。
今回は景気が下り坂であるため、政治家という階層の行き過ぎに歯止めをかけるべきだという主張――72歳の痩身の候補者ブハリ氏は今回、この点を訴えの中心に据えている――には、急を要することだという印象が以前よりも強く感じられる。
投票結果にはこれ以外に民族、宗教、当選者が選挙後に支持者に配分する恩恵といった要因が大きく影響するとしても、だ。
選挙管理委員会は、有権者証の配布が遅れているものの、投票は予定通り2月14日に実施できるとしている。
また、ブハリ氏は軍を建て直し、同国北部で勢力を伸ばしているテロ集団「ボコ・ハラム」に対抗すると公約しているが、こちらも急を要することであるように聞こえる。
「自分の懐に打撃が及ぶと、人はそれまでよりも合理的になり、感情を抑えて決断するようになる。石油価格の下落は政府を、企業を、そして個人を直撃している。今の状況はブハリ氏に有利に作用する」。ナイジェリアの大都市ラゴスの投資会社、ファイナンシャル・デリバティブズのビスマルク・ルウェイン最高経営責任者(CEO)はこう指摘する。
現職のグッドラック・ジョナサン大統領にはこれと正反対のことが当てはまる、とルウェイン氏は言う。現職としての優位性は通貨ナイラの急落とともに衰えている。ナイラは先週月曜日、1ドル=190.45ナイラという史上最安値を付けた。
同氏はまた、ナイラ安はブハリ氏の地盤である貧しい北部だけでなく、ジョナサン氏にとって最も頼りになる南東部の支持者の一部にも影響を及ぼすと述べている。南東部の支持者には商業で生計を立てている人が多い。
「(ジョナサン大統領が)原油価格を引き下げたわけではない。彼は原油安の犠牲者であり、これについて彼にできることはあまりない。政府はこれまでの上昇局面で浪費をした。下降局面から身を守るためのものはあまり残していない」とルウェイン氏は言う。(後略)【1月26日付 英フィナンシャル・タイムズ紙 JB Pressより】
*********************
これまで石油収入を“浪費”してきたナイジェリアでは、原油価格下落によって、連邦政府や地方政府は、公務員に予定通り給与を支給するのに苦労している状況にあります。
原油安の影響は、これまでの無駄を切り詰めて、財政引き締めに転じる好機となるという意味で、ナイジェリアにとって長期的にはプラスに作用するという見方もあるようです。
もっとも、それは財政問題や「ボコ・ハラム」による治安問題を真摯に受け止める、まともな政府が樹立されればの話です。
現在のジョナサン大統領の統治にも問題がありますが、対立候補のブハリ氏はかつて軍を背景にクーデターで権力を掌握し、綱紀粛正の名のもとに報道の自由を弾圧し、緊縮財政によって経済悪化を招いた“実績”もあります。
いずれにしても、まずは大統領選挙を平和裏に行うことです。選挙による混乱が生じれば、ケリー米国務長官も懸念するように、「ボコ・ハラム」の活動はますます拡大するばかりになります。
前回大統領選挙でブハリ候補がジョナサン現大統領に敗れた際には、開票結果が発表された後、ブハリ支持者の多い北部を中心に暴動が勃発し、500人以上が死亡したとのことです。